【2025年版】不倫慰謝料・養育費の相場と増額のポイント
「不倫の慰謝料、実際のところ、いくら請求できるの?」
「離婚後の養育費、どうやって金額が決まるんだろう…」
不倫や離婚という問題に直面したとき、お金の話は避けて通れません。
結論から言うと、不倫慰謝料の相場は50万~300万円、養育費は裁判所の「養育費算定表」で決まるのが基本です。しかし、どちらも個別の事情によって金額は大きく変動します。
この記事では、不倫慰謝料と養育費の相場や金額の決まり方、そして実際に請求を増額させるためのポイントについて、実際の判例を交えながら専門的に解説します。正しい知識を身につけ、ご自身の状況で最善の判断を下すためにお役立てください。
不倫慰謝料の相場はいくら?金額が決まる仕組み
不倫慰謝料とは、不貞行為という裏切りによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。金額はケースバイケースですが、一定の相場が存在します。
【離婚の有無で変わる】不倫慰謝料の相場は50万~300万円
慰謝料額を左右する最大の要因は、不倫によって夫婦関係がどうなったか、です。
-
不倫が原因で離婚・別居した場合
- 相場:100万円~300万円
- 夫婦関係が破綻したと見なされ、精神的苦痛が大きいと判断されるため、慰謝料は高額になる傾向があります。
-
離婚せず、婚姻関係を継続する場合
- 相場:50万円~150万円
- 夫婦関係が修復可能、または修復の途中と見なされ、離婚した場合よりは精神的苦痛が小さいと評価されるため、慰謝料は比較的低額になります。
なお、慰謝料は不倫した配偶者とその不倫相手の両方に請求できますが、合計で相場額以上を受け取る「二重取り」はできません。
慰謝料が増額・減額される10の要因
相場はあくまで目安です。実際の金額は、以下のような様々な事情を考慮して決定されます。
【慰謝料が増額されやすい要因】
- 婚姻期間が長い
- 不倫の期間が長く、頻度も多い
- 未成年の子どもがいる
- 不倫によってうつ病などを発症した
- 不倫相手が妊娠・出産した
- 不倫発覚後も反省の態度がない
【慰謝料が減額されやすい要因】
- 婚姻期間が短い
- 不倫前から夫婦関係が破綻していた
- 不倫の期間が短い、一度きりの関係
- 不倫した側が深く反省している
【判例で見る】慰謝料300万円が認められた悪質なケースとは?
実際の裁判では、不倫の態様が悪質であるほど高額な慰謝料が認められています。例えば、長期間の不倫関係の末に不倫相手が妊娠・出産し、離婚に至ったケースや、被害者から再三関係の中止を求められたにもかかわらず同居を始めたようなケースでは、300万円という高額な慰謝料が認められています(東京地裁平成28年2月21日判決など)。
養育費の相場と計算方法|令和最新の「算定表」を解説
養育費は、子どもが自立するまでに必要な生活費や教育費です。離婚しても親であることに変わりはなく、子どもと離れて暮らす親にも支払う義務があります。
養育費は父母の年収と子の数で決まるのが基本
養育費の金額は、当事者間の話し合いで決めるのが原則ですが、その際の基準となるのが、裁判所が公表している「養育費算定表」です。これは、調停や裁判でも広く使われている公平な基準であり、2019年(令和元年)に改定されたものが最新版となります(2025年9月現在)。
この算定表は、主に以下の情報から標準的な月額を算出します。
- 支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)のそれぞれの年収
- 子どもの人数と年齢(0~14歳/15歳以上)
【年収・子の数別】あなたの養育費の相場は?簡単シミュレーション
ここでは、母親(権利者)の年収が120万円(給与所得者)と仮定し、「養育費算定表」に基づいた月額の相場を見てみましょう。
父親(義務者)の年収が400万円(給与所得者)の場合
- 子ども1人(0~14歳):月額2~4万円
- 子ども2人(全員0~14歳):月額4~6万円
父親(義務者)の年収が700万円(給与所得者)の場合
- 子ども1人(0~14歳):月額6~8万円
- 子ども2人(全員0~14歳):月額10~12万円
※これはあくまで標準的な目安です。裁判所のウェブサイトで公開されている算定表で、ご自身の状況に合った詳細な金額を確認できます。
算定表の金額が変わる「特別な事情」とは?(私立の学費など)
算定表はあくまで標準的な生活費を想定しています。そのため、以下のような「特別な事情」がある場合は、算定表の金額に上乗せ(または減額)されることがあります。
【養育費が増額されやすい事情】
- 子どもが私立学校や大学に通っており、高額な学費がかかる
- 子どもに持病や障害があり、高額な医療費が継続的に必要
- 留学費用など、特別な教育費がかかる
【養育費が減額されやすい事情】
- 支払う側がリストラや病気で大幅に収入が減った
- 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
- 子どもが受け取る側の再婚相手と養子縁組をした
これらの事情がある場合は、その事実を証明する資料(学費の請求書や診断書など)をもとに、金額を交渉・請求することになります。
慰謝料・養育費請求で後悔しないための3つの重要ポイント
慰謝料や養育費の問題を有利に進めるためには、感情的にならず、冷静に準備を進めることが重要です。
ポイント1:客観的な証拠を集める
特に不倫慰謝料の請求には、不貞行為があったことを示す客観的な証拠が不可欠です。メールやSNSのやり取り、写真、探偵の調査報告書などが有効です。養育費の増額を求める際も、学費の請求書など主張を裏付ける証拠を揃えましょう。
ポイント2:まずは話し合い、まとまらなければ調停へ
まずは当事者間での話し合い(協議)から始めます。直接話すのが難しい場合は、弁護士を代理人に立てることも可能です。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立て、調停委員を交えて解決を目指します。
ポイント3:必ず弁護士に相談する(公正証書の作成も)
慰謝料や養育費の問題は、法的な知識が結果を大きく左右します。できるだけ早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すれば、交渉や法的手続きをすべて任せることができ、精神的な負担も軽減されます。
また、話し合いで合意した内容は、必ず「公正証書」として書面に残すことが極めて重要です。公正証書にしておくことで、将来支払いが滞った場合に、裁判を起こさなくても強制的に給与などを差し押さえることが可能になります。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家である弁護士に相談を
不倫慰謝料や養育費の相場は、あくまで一般的な目安に過ぎません。あなたの状況でいくら請求できるのか、どうすれば有利に進められるのかは、個別の事情によって全く異なります。
もし今あなたがこれらの問題で悩んでいるなら、一人で抱え込まず、まずは法律の専門家である弁護士に相談してください。専門家の力を借りることが、あなたの正当な権利を守り、新たな一歩を踏み出すための最も確実な方法です。

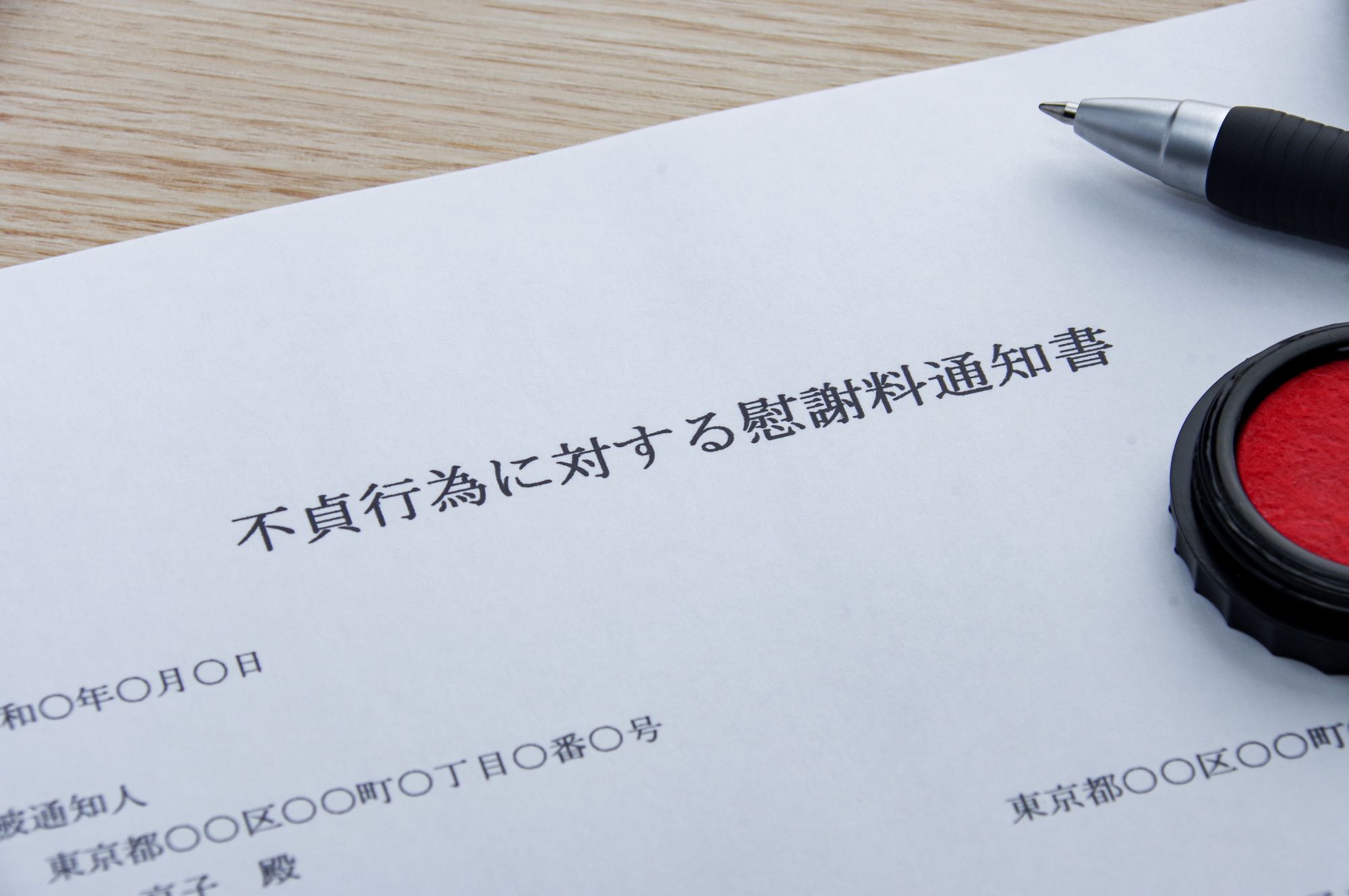




まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。