「男の生きづらさ」の正体とは?女性活躍が社会を変える理由
「男だから稼ぐべき」「男は弱音を吐くな」——多くの男性が、こうした社会的な役割や自己責任というプレッシャーを無意識のうちに感じています。個人の努力で乗り越えようと奮闘する一方で、その背景には根深い社会構造が存在します。
しかし、この構造を理解し、見直すことは、男性自身の生きやすさだけでなく、現代日本の大きな課題である「女性が直面するジェンダーギャップ」の問題解決にも繋がります。
この記事では、男性の生きづらさと女性の活躍がどう結びつくのか、そして性別に関わらず誰もが能力を発揮できる社会をどう作るか、そのヒントを解説します。
なぜ男性は「自己責任」のプレッシャーを感じるのか?
多くの男性が抱える「生きづらさ」やプレッシャーは、個人だけでなく社会が長年作り上げてきた「男性の役割」意識と深く関わっています。
社会が期待する「稼ぎ手」「リーダー」という役割
歴史的に、男性には「一家の大黒柱として家族を養う」という経済的な役割が強く期待されてきました。この意識は、パートナーの働き方に関わらず、多くの男性が自負として内面化している傾向があります。
また、「仕事で成功し、リーダーシップを発揮する」ことも、男性に求められてきた価値観です。内閣府の調査でも、こうした経済的・社会的な役割は伝統的に「男の役割」と認識されており、「男は仕事ができて当たり前」という観念が、一部の男性にとってプレッシャーの原因となっていることが示されています。
「男は弱音を吐くな」という無言の規範
困難に直面したとき、「男は感情的になるべきではない」「他人に頼らず自力で解決すべきだ」といった考え方も根強く存在します。
このような規範は、問題解決への責任をすべて個人に帰結させ、「自己責任」という感覚を強めます。目標を達成した際の誇りの源泉となる一方で、うまくいかない時には一人で抱え込み、孤立を深める原因にもなりかねません。
私たちが向き合うべき「ジェンダーギャップ」という現実
男性がこうした役割意識と向き合う一方で、社会全体として直視すべき課題が、依然として存在するジェンダーギャップです。
世界118位。日本のジェンダー平等の現在地
世界経済フォーラムが発表した2024年のジェンダーギャップ指数で、日本は146ヶ国中118位と、先進国の中で著しく低い順位にあります。特に、政治や経済分野での格差が大きく、社会の意思決定の場への女性の参画が遅れているのが現状です。
- 国会議員に占める女性の割合:約1割
- 企業の女性管理職(部長相当)の比率:7.9%(2023年)
これらのデータは、社会の重要なポジションが依然として男性中心であることを示しています。
女性のキャリアを阻む「見えない壁」とは
この構造的な格差は、女性のキャリア形成に大きな影響を与えています。
- 固定的な役割分担:「総合職は男性、一般職は女性」といった意識
- キャリアの中断:出産や育児による離職や働き方の変更
- 家事・育児負担の偏り:家庭内での無償労働が女性に偏る傾向
- 健康課題への無理解:月経や更年期など、女性特有の健康問題が仕事のパフォーマンスに影響することへの理解不足
これらの「見えない壁」は、女性が能力を十分に発揮する機会を奪い、社会全体の成長の機会損失にも繋がっています。
なぜ女性への支援が、男性の生きやすさにも繋がるのか?
一見すると別々の問題に見える「男性の生きづらさ」と「女性の働きにくさ」。しかし、女性が直面する課題を解決することは、結果的に男性を含む社会全体の利益に繋がります。
女性が働きやすい職場は、結果的に誰もが働きやすい
女性活躍を推進するために企業が導入する制度は、性別を問わず全ての従業員にメリットをもたらします。
- 柔軟な働き方の導入:時短勤務やリモートワークは、育児中の女性だけでなく、介護をする男性や、自身の時間を大切にしたい若手社員にも恩恵があります。
- ハラスメント対策の徹底:誰もが安心して働ける職場環境が整備されます。
- 長時間労働の是正:性別に関わらず、ワークライフバランスの改善に繋がります。
「男だから長時間働くべき」といった古い価値観から解放され、男性も家庭や個人の時間を大切にできる。そんな社会への転換点となるのです。
企業の成長と社会全体の活力になる
女性の能力を最大限に活かすことは、企業の生産性向上やイノベーション創出に直結します。多様な視点が取り入れられることで、組織はより強靭になります。これは、ESG投資やSDGsといった世界的な潮流とも合致しており、企業価値を高める上でも不可欠な戦略です。
新しい時代へ。共感から始める私たちの一歩
男性がこれまで担ってきた役割と責任感は、社会を支える力となってきました。その努力を否定するのではなく、その力を新しい方向に向ける時が来ています。
それは、女性が直面している困難や課題に共感し、具体的な支援へと行動を広げることです。社会に存在する「配慮不足」という課題に真摯に向き合うことが、男性にとっても新たな社会貢献の形となります。
まとめ:古い「役割」を脱ぎ捨て、共に歩む社会へ
「男だから」「女だから」という古い役割意識は、男性には「自己責任」のプレッシャーを、女性には「見えない壁」という制約を与えてきました。
しかし、時代は変わり、私たちは新しい地図を共に描くべき岐路に立っています。
男性が自らの課題と向き合いながら、同時に女性への共感と支援の輪を広げていくこと。それこそが、性別に関わらず誰もが自分らしく能力を発揮できる、より豊かでしなやかな社会を築くための鍵となるのです。



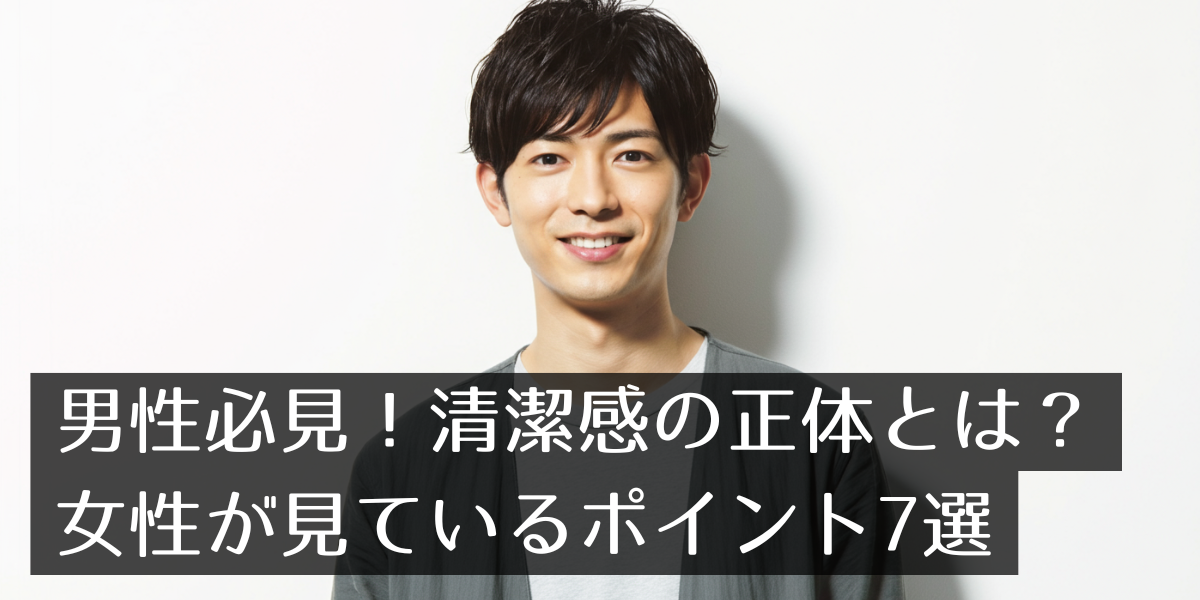


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。