『名もなき家事』は誰の仕事?令和の夫婦に求められる【公平な役割分担】
家庭生活において、「料理」「洗濯」「掃除」といった明確な名前を持つ家事は誰もが認識しやすいものです。しかし、日々の暮らしには、その存在すら意識されにくい無数の細かな作業が存在します。これらは「名もなき家事」あるいは「見えない家事」と呼ばれ、令和の夫婦関係において、その負担の偏りが大きな課題となっています。
「名もなき家事」とは、具体的には洗剤の補充やストック管理、夕飯の献立を考えることなどが挙げられます 。裏返しに脱いだ服をひっくり返す作業や、なくなったシャンプーの補充なども典型的な例です 。さらに、子どもの数や年齢に応じて、それぞれの月齢に合わせたメニューや分量を用意するといった、より複雑なタスクも含まれます 。夫が食器を洗った後、シンクに残った水滴を拭いたり、食器を拭いて所定の場所に戻したりする作業も、「名もなき家事」として妻の負担を増大させる一因です 。冷蔵庫の掃除、ゴミ出しの計画、友人や家族の誕生日の祝い、動物病院の予約、旅行の計画といった、「誰かが言わなければ誰もやらないこと」も、この「名もなき家事」の範疇に含まれ、その多くが一方に集中している現状が指摘されています 。
これらの家事が見過ごされがちな背景には、いくつかの要因があります。第一に、「主婦ならやって当たり前」という根強い意識が社会や家庭内に存在することです。夫が家事を「主婦が当然やるもの」と捉えている場合、妻は家事のつらさを素直に打ち明けられず、結果として一人で抱え込み、精神的・肉体的なダメージが蓄積しやすくなります 。第二に、夫婦間で家事のタスクに対する認識にズレがあることです。細かい家事は、そもそもパートナーにその存在が認識されていないことが少なくありません。これにより、家事を代わってもらえず、夫婦の一方だけにストレスが溜まる状況が生まれます 。第三に、家事をする側が「些細なことだから、わざわざお願いするまでもない」「なんとなく自分が当たり前にこなしている」と捉えてしまうケースも多く、自ら負担を抱え込んでしまう傾向が見られます 。
これらの「名もなき家事」は、単なる物理的な作業に留まらず、「献立を考える」「ストックを管理する」といった計画、管理、予測といった知的作業を伴います。例えば、シャンプーの補充という一見些細な作業も、その前には「シャンプーが減っていることに気づく」「新しいシャンプーの在庫を確認する」「在庫がなければ買い物リストに入れる」「買い物に行く」「補充する」という一連の思考と行動が含まれます。これらの「気づき」「計画」「実行」のプロセス全体が「名もなき家事」であり、そのほとんどが一方に集中している現状があります。これは、物理的な家事よりも精神的な疲労に直結し、パートナー間の認識のズレを深める根本的な原因となっています。
特に子育て世帯においては、「名もなき家事」の負担が加速する傾向にあります。子どもの数や年齢によって家事のタスクが飛躍的に増加し、一つ一つの作業に時間がかかるようになることも、労力が理解されにくい理由です 。例えば、兄弟・姉妹で食べる量や内容が違うため、それぞれの月齢に合わせたメニューや分量を用意するといった作業は、時間と労力を要します 。ある調査では、「家の中の雑務」や「料理の準備」にかかる時間について、「子どものいる」男性が最も短い一方で、これらの「見えない家事」に最も長い時間を費やしているのは「子どものいる」女性であることが明確なデータとして示されています 。子どもが生まれると、家事の量は単純に増えるだけでなく、その質も変化します。離乳食の準備、子どもの服の管理、持ち物の準備、病気の際の対応など、予測不可能なタスクや、時間的制約の厳しいタスクが増加します。これらの多くが「名もなき家事」の範疇に入ります。男性がこれらの「見えない家事」への関与を減らす一方で、女性の負担が劇的に増大しているという事実は、子育て世帯における家事分担の不均衡が、特に「見えない部分」で深刻化していることを示唆しています。
あなたの家庭にも潜む「見えない家事」の具体例
以下に、あなたの家庭にも潜んでいるかもしれない「名もなき家事」の具体例をリストアップしました。これらを見て、「うちにもある!」と共感する方も多いのではないでしょうか。
「計画・管理」に分類される家事としては、夕食の献立を考えること 、食材のストックを管理すること 、子どもの持ち物(着替え、学用品など)を準備すること 、家族の誕生日や記念日を管理し、プレゼントを手配すること 、旅行の計画を立てること 、病院や習い事の予約をすること 、家計の管理や支払い計画を立てること などが挙げられます。
「補充・整備」に関する家事には、洗剤やトイレットペーパーの補充・買い足し 、シャンプーや石鹸の交換・補充 、ゴミ袋のセットやゴミ出しの準備 、電球や電池の交換などがあります。
「細かな手直し」としては、裏返しに脱いだ服をひっくり返すこと 、夫が洗った後のシンクの空拭きや食器拭き 、洗濯物の干し方や畳み方の修正 、散らかったものを元の場所に戻すこと 、ホコリ取りやちょっとした拭き掃除 などが該当します。
「子育て関連」では、子どもの月齢や食べる量に合わせたメニュー・分量を用意すること 、子どもの安全確認をしながら家事をすること 、子どもの急な体調不良への対応などが含まれます。
その他にも、使用後の調理器具や食器の予洗い、郵便物の開封・仕分け、家電製品の簡単なメンテナンスなども「名もなき家事」として存在します。
このリストは、抽象的な「名もなき家事」という概念を、読者が具体的にイメージできるようにすることで、問題の具体化を促します。また、読者、特に家事負担を感じている側が「自分だけじゃない」と共感し、パートナー側が「こんなにたくさんあるのか」と認識を改めるきっかけを提供します。このリストは、後述する「家事の見える化」の最初のステップとして、夫婦間の話し合いの具体的な叩き台となるでしょう。
令和の夫婦が直面する家事分担の現状と課題
共働き世帯が多数を占める現代において、家事分担は夫婦間の重要な課題であり続けています。理想と現実の間には大きなギャップが存在し、その不均衡が夫婦関係に影を落とすことも少なくありません。
理想と現実のギャップ:なぜ妻に負担が偏るのか
共働き家庭が増加しているにもかかわらず、家事分担の現状は依然として女性に大きく偏っています。ある調査では、女性の約68%が家事の7割以上を担当していることが明らかになっています。これに対し、男性は「3〜4割」という回答が最も多く、39.8%にとどまっています 。別の調査では、20代・30代の共働き夫婦において、「主に妻」が家事を担当している割合が53%に上る一方で、「主に夫」は15%、「夫婦平等に分担」は25%にとどまるという結果も出ています 。さらに、理想的な家事分担として「妻5:夫5」を挙げる夫婦が多いにもかかわらず、実際にその割合を実現できている家庭はわずか6.4%であり、半数以上の家庭で妻が家事の大部分を担っている実態が浮き彫りになっています 。年間で見ると、6歳未満の子どもを持つ共働き夫婦の家事時間は夫婦合計で2,883時間にもなりますが、その多くが女性に偏っているのが実情です 。
家事分担の理想の割合は男女ともに「5:5」が1位であるにもかかわらず、女性の半数以上は「自身が多めの方が理想」と回答しているという、一見矛盾したデータが存在します 。これは、理想としての「5:5」は共有されつつも、女性側が現実的な妥協点として「自身が多め」を許容している可能性を示唆しています。しかし、この妥協点すら達成されていない現状が、女性の不満の大きな原因となっています。一方で、男性の約86%が家事分担に満足しているのに対し、女性は約54%にまで満足度が下がります 。男性側は「もっと自分が担当すべき」という意識は持ちつつも 、実際の行動に移せていないか、あるいは自身の「3〜4割」という分担で「満足」してしまっている可能性があります。この認識のズレが、女性の「言わないとやらない」という不満 や「手伝い」意識 に繋がっているのです。
男性と女性で異なる家事認識と満足度
家事に対する認識や、パートナーへの満足度には男女間で大きな隔たりがあります。主に担当している家事を見ると、女性は「料理」「買い物」「キッチンの掃除」が上位を占めるのに対し、男性は「ゴミ出し」「食器洗い」「食器の片づけ」が上位にランクインしています 。
配偶者の家事に点数をつけるとしたら、男性の約7割が80点以上と高評価である一方、女性は80点以上が約3割にとどまり、約4割が40点以下と低評価という結果が出ています 。さらに、女性が配偶者にもっと担当してもらいたい家事の1位は「トイレの掃除」であるにもかかわらず、男性が配偶者にもっと担当してもらいたい家事は「特にない」が最多という、対照的な結果が出ています 。
男性が主に担当する家事(ゴミ出し、食器洗い、片付け)は、比較的「単発的」で「終わりが見えやすい」作業が多い傾向にあります。一方、女性が主に担当する家事(料理、買い物、キッチンの掃除)は、「献立を考える」「食材のストックを管理する」「調理後の片付け全体を計画する」といった「名もなき家事」と密接に結びついており、継続的な計画性や管理能力が求められます 。男性がパートナーの家事に高得点をつける一方で、女性が低評価を下すのは、男性が目に見える「作業」の完了度で評価しているのに対し、女性は「名もなき家事」を含む全体的な負担や精神的負荷、そして当事者意識の有無で評価しているためと考えられます。男性が「特にない」と回答する一方で、女性が具体的な家事(トイレ掃除)を挙げるのは、男性が自身の家事負担の少なさに気づいていないか、あるいは女性が抱える「名もなき家事」の存在自体を認識していないことを示唆します。この認識のズレが、女性の「私の負担が多い」「見えない家事はほぼ私」 という不満に直結しているのです。
「言わないとやらない」夫と「手伝い」意識の壁
女性が抱える不満の多くは、パートナーの家事に対する姿勢、特に「当事者意識の薄さ」に起因しています。女性が配偶者の家事に低い点数を付けた理由の1位は「言わないとやらない」で60%に上ります 。共働き夫婦の家事分担での不満ランキングでも「言わないとやらない」が上位にランクインし、「夫は自分から積極的には家事はしてくれない」という声も聞かれます 。
女性の最も多い不満は「家事を『手伝うもの』と思っていること」(43%)です 。妻は夫に指示を待つ「お手伝い」ではなく、自発的に動く「当事者」になってほしいと強く願っています 。夫が家事を担当しても、その結果に満足できないケースも多く、「夫が洗った食器の汚れが落ちていない」「片付ける場所が違う」「洗濯物の干し方、畳み方が違う」といった不満が挙げられます 。これにより、結局妻がやり直すことになり、新たな「名もなき家事」が発生することもあります 。
「言わないとやらない」という不満は、夫が家事を「自分の責任」ではなく「妻の指示に従う手伝い」と捉えていることに起因します。この「お手伝い」意識があると、妻は夫に家事を依頼する際に、タスクの特定、指示、進捗確認、場合によってはやり直しの指示まで、一連の「管理業務」を担うことになります。「夫に何か頼めばやってくれるんだけど、メンタルロードは私にかかってるんだよね」というユーザーの声は 、この「指示出し」自体が新たな「名もなき家事」であり、精神的負担であることを明確に示しています。夫が「言わないとやらない」状態が続くと、妻は「どうせ言わないとやらないなら、自分でやった方が早い」という諦めや、「言っても完璧にやってくれないなら、自分でやり直す方が確実」という思考に陥り、結果的にワンオペ状態が固定化されることがあります 。これは、夫の当事者意識が育つ機会を奪い、悪循環を生むのです。
「名もなき家事」が夫婦関係と心身に与える影響
「名もなき家事」の負担は、目に見えない形で蓄積し、やがて夫婦関係にひび割れを生じさせ、個人の心身の健康にも悪影響を及ぼします。
蓄積するストレスと不満:見えない負担の重さ
家事の不均衡は、「これって不平等じゃない?」「そんなことする時間あるならもっとやってよ!」といった不満につながります 。具体的には、「人が忙しく家事をしているときに自分はお酒を飲みながらテレビを見てガハガハと笑っている姿を見ると本当に腹が立つ」 といった、強い不満や怒りが蓄積されることがあります。また、「仕事が休みの日も家事は休みではない。私の家事プラス仕事の時間を計算したら、1週間の夫の勤務時間をはるかに超えていた」 と感じるほどの過重労働に陥る人もいます。
このような状況が続くと、「家事したくない」という心理状態に陥りやすくなります。無理して家事を続けると、体調面や精神面に負担がかかり、精神的に無理をするとうつ病などの精神的な不調につながる可能性も指摘されています 。ストレス性疲労のある女性は、休日の家事時間が「3時間以上」の割合が高い傾向にあり、趣味やセルフケアの時間が「ほとんどない」と回答する割合も高くなっています 。
「名もなき家事」は認識されにくいため、その負担は表面化しにくいものです。しかし、その負担が蓄積し、パートナーの無関心や「お手伝い」意識 を目の当たりにすることで、「不公平感」が「怒り」へとエスカレートします。この怒りは、直接的に夫婦喧嘩の原因となるだけでなく 、関係性の悪化、コミュニケーションの停止 、「夫に期待するだけ無駄と思うようになった」 といった諦めへと繋がる可能性があります。怒りや不満を抱えた状態での家事は、さらに精神的負担を増大させ、負のスパイラルを生むでしょう。
「メンタルロード」の正体と夫婦喧嘩の原因
家事の物理的な作業だけでなく、その背後にある「考える」「計画する」「管理する」といった精神的な負担、すなわち「メンタルロード」が、夫婦間の衝突の大きな原因となっています。家事の負担を軽減するために、献立や片付けの順番など、あれやこれやと頭の中で常に考えている状態は、「メンタルロード」の典型です 。あるRedditユーザーは、「夫に何か頼めばやってくれるんだけど、メンタルロードは私にかかってるんだよね。冷蔵庫の掃除、ゴミ出し、予定が合わなくて友達との約束をキャンセルしたり、プレゼントの手配、友達や家族の誕生日の祝い、動物病院の予約、旅行の計画、ホコリ取り、掃除機、片付けとか。いつも全部考えてるのは私で、彼は私が言うことをやるだけだから、それが原因で喧嘩になることもあるんだよね」と具体的に訴えています 。実際に、家事分担は、20代・30代共働き夫婦の言い争いの原因の15.4%を占めるほど、夫婦間の意見の相違点となっています 。
「メンタルロード」は、物理的な家事の実行以前に発生する「認知」「計画」「管理」のプロセスです。このプロセスは目に見えないため、パートナーにはその存在自体が認識されにくいという特徴があります。「彼が私が言うことをやるだけだから、それが原因で喧嘩になることもあるんだよね」 と述べられているように、夫は「言われたことはやっている」と認識していても、妻は「なぜ私ばかりが常に考え、指示しなければならないのか」という根本的な不満を抱えるのです。メンタルロードが一方に集中すると、その人は常に「家庭のCEO」のような役割を担うことになり、精神的な余裕がなくなります。パートナーが「言われたことしかやらない」状態では、その負担は軽減されず、むしろ「指示を出す」という新たなタスクが加わります。この「見えない負荷」に対する認識のズレが、表面的な家事分担の不満を超え、夫婦間の深い部分での対立や不信感を生み出す原因となるのです。
家事負担が引き起こす心身の不調
過度な家事負担は、身体的な疲労だけでなく、精神的な健康にも深刻な影響を及ぼします。無理して家事を続けると、体調面や精神面に負担がかかり、精神的に無理をするとうつ病などになる可能性も指摘されています 。ストレス性疲労のある女性は、休日の家事時間が長く、「趣味時間」や美容・健康に関する「セルフケア時間」が「ほとんどない」と回答する割合が高い傾向にあります 。部屋の乱れが心の乱れに繋がるように、ストレスを感じる家事の1位は「部屋の片付け・整理」、2位は「掃除」がランクインしています 。また、家事をやらないと洗い物が溜まり、部屋が汚くなることで、さらにやる気がなくなり、水回りの掃除を怠るとカビが生え、身体に炎症が起こる可能性もあります 。
「良い妻、良い夫、良いママ、良いパパでありたいと思うことはとても良いことだと思います。ですが、つい頑張り過ぎて疲れてしまうこともありますよね」 とあるように、「家事したくないけど自分がやらないと」 という心理が、多くの女性に過度な負担を強いる一因となっています。社会的な期待や自己の理想像(「良い妻/母」であること)が、女性に過度な家事負担を強いる一因となっていることがあります。この「ねばならない」という心理は、自身の心身の限界を超えても家事を継続させ、結果的に慢性的な疲労やストレス、ひいてはうつ病などの精神疾患に繋がりかねません。
公平な役割分担を実現するための実践的ステップ
「名もなき家事」の負担を軽減し、令和の夫婦が公平な役割分担を実現するためには、具体的なステップを踏むことが不可欠です。
ステップ1:家事の「見える化」で全体像を把握する
見えない家事を見えるようにすることが、公平な分担への第一歩です。家事リストを作成することには、多くのメリットがあります。まず、「うっかりさん」を卒業し、やり忘れを防ぐことができます 。家事はマルチタスクの頂点とも言えるほど同時進行でこなすことが多く、すべてを完璧にこなすのは困難だからです 。リスト化により、やるべき家事が整理され、見落としがなくなります 。次に、家事の偉大さを家族で共有し、ストレスや不満を減らすことができます 。項目を書き出してみると、その数の多さに家族はきっと驚くことでしょう。その大変さを家族で共有し理解してもらうだけでも、不満やストレスは減らせるのです 。さらに、「できない夫」を「できる夫」に変えるきっかけにもなります。家事のやり方にはそれぞれのルールがあるため、「何をすればいいか分からない」状態の夫も少なくありません。家事リストを作り一覧化することで、一つひとつの家事の作業が細分化され、どのようなルールや段取りで作業を進めているのかが分かり、お互いに納得のいくルールで統一できます 。これにより、自分の出番さえ分かれば家事をする夫に変わる可能性が見えてきます 。また、子どものお手伝い意識を高める効果も期待でき 、最終的には夫婦それぞれのリフレッシュタイムの誕生にも繋がります 。
具体的な方法としては、まず「家事の棚卸し」を行います。日々の家事を全て書き出し、リスト化します。毎日の家事量、タイミング、所要時間、どの程度できているかなど、詳細に洗い出すのが重要です 。この際、シャンプーの詰め替え、献立決め、子どもの持ち物準備など、普段意識しない細かな「名もなき家事」も全てリストに加えることが重要です 。リストを基に、誰が何を担当するか、着手前・着手済がわかるように可視化する「家事分担表」を作成しましょう 。スマートフォンアプリの活用も有効な手段です 。
「夫はほんの一部しかやっていないのに、大半をやっていると勘違いしている」 という妻の不満があるように、家事の負担には男女間で大きな認識のズレがあります。家事の「見える化」は、この「勘違い」という認知バイアスを是正する強力なツールとなります。リスト化することで、これまで「当たり前」と見過ごされてきた「名もなき家事」の量と質が明確になり、夫婦間で家事に関する「共通言語」が生まれます。これにより、「言わないとやらない」という一方的な指示出しの構造から、「これだけの家事があるから、どう分担しようか」という対等な話し合いの土台が築かれるのです。
ステップ2:夫婦で「当事者意識」を育むコミュニケーション術
見える化した家事を基に、夫婦が共に家庭の運営者であるという「当事者意識」を持つことが重要です。家事の分担には、労働状況や健康状態、家事スキルなど多くの要因が影響するため、唯一の「正解」は存在しません。状況は日々変化するため、一度きりではなく、月に1回など定期的に話し合いの機会を設けることが大切です 。これにより、言いたいことを言い合える関係を築き、我慢の限界を迎える前に冷静に意見交換ができるようになります 。
具体的なコミュニケーションのコツとしては、まず相手の家事への貢献に対して、具体的に感謝の気持ちを伝えることが挙げられます。「今日の夕食、美味しかったよ。ありがとう」 のように、具体的に伝えることで相手のモチベーションを高めることができます。たとえ不満があった場合でも、まずは感謝を伝えた上で、「こうしてほしい」とお願いする姿勢が大切です 。次に、お互いのストレスレベルを数値化して伝え合う方法も有効です。0(ストレスなし)から10(極度のストレス)までの数値で自分の状況を伝え、「今週は仕事が忙しくて、ストレスレベルが8なので、家事負担を少し減らしたいです」 のように、具体的な数値とその理由、そして必要なサポートを言葉にして伝えることで、お互いの状況をより理解しやすくなります 。
また、「できない」を解決するための方法を夫婦で模索することも重要です 。夫が家事を担当しても、その結果に満足できない場合があるのは、やり方やこだわりが異なるためです 。このような場合、「○○は自分の仕事」「△△はこういう風にやってほしい」という意識を共有できれば、不満は軽減されます 。特に、こだわりが強い家事は、そのこだわりを持つ相手に任せるのが基本です 。無理に相手に押し付けると、小さなミスや意識のズレに毎回ストレスを感じ、相手も「やっているのに不満を抱かれている」とフラストレーションが溜まりがちになります 。お互いの精神衛生のためにも、それぞれの持ち場を決めるルールが大切です 。
完璧を求めすぎないことも、円滑な家事分担には不可欠です 。自分が頑張っていると感じる分、パートナーのやり方が気になったり、不満が大きくなったりする可能性もあります 。夫婦二人でこなせない家事は、家事代行サービスを利用するなど、外部のサポートを取り入れることも有効な手段です 。
夫が家事を「手伝うもの」と捉える「お手伝い」意識から、「家庭の運営者」としての「当事者意識」を持つことへの転換は、公平な分担の鍵となります 。この転換には、夫が自ら家事をする姿勢を見せること 、そして妻側も夫に細かい指示を出すのではなく、家事全体を任せて必要最低限のこと以外は口を出さないことで、夫の当事者意識が育ちやすくなるという側面があります 。
ステップ3:効率化と外部サポートの活用
家事の負担を物理的・精神的に軽減するためには、効率化と外部サポートの活用も有効な手段です。
時短テクニックの導入としては、料理の効率化が挙げられます。献立作りは生成AIにサポートしてもらうと楽になります 。冷蔵庫の食材から献立を作成したり、手間をかけずに数日分の献立と買い物リストを作成したりできます 。また、段取りを考えてから調理に取り掛かる 、火を使わない副菜を取り入れる 、電子レンジをフル活用する 、一食分を多めに作って翌日のランチに回す 、冷凍食品やレトルトを常備する、カット野菜を活用して下ごしらえの手間を省く などが挙げられます。片付け・掃除の効率化では、すぐ掃除できるよう机の近くに掃除道具を置く 、キッチン掃除は汚れを溜めない工夫をする(カビ汚れ防止マスキングテープ、油跳ねガードなど) 、使ったついでに掃除する習慣をつける(風呂から出た後、レンジ使用後など) といった工夫があります。洗濯物の効率化として、その日に使うものはたたまない など、手間を省く方法も有効です。
便利家電の活用も有効です。家事の負担を少なくするために購入した便利家電としては、ロボット掃除機、食器洗い乾燥機、電気ケトルが上位に挙げられています 。これらの家電は、日々の家事時間を大幅に削減し、精神的な負担も軽減します。
家事代行サービスの検討も視野に入れましょう。夫婦二人でこなせない家事は、家事代行サービスを利用することも有効な選択肢です 。料理の作り置きや水回りの掃除など、苦手な家事や時間のかかる家事をプロに任せることで、日々の負担を軽減し、夫婦の時間や自分の時間を確保することができます 。特に、男性はベビーシッターや家事代行の利用意向が高い傾向にあります 。
ステップ4:感謝と労いを忘れずに、柔軟な関係を築く
家事分担において何よりも大切なのは、相手への「思いやり」です 。仕事・家事・育児で精神的にイライラが溜まったときにこそ、相手への感謝を思い出すことが重要です 。自分だけ、相手だけではなく、お互いに支え合い頑張っているという認識が何より重要です 。
相手の家事への貢献に対して、「今日の夕食、美味しかったよ。ありがとう」 のように具体的に感謝を伝えることは、相手のモチベーション維持に繋がります。また、体調や仕事の忙しさなどを加味しつつ、時には柔軟にルールを変更させていく余裕を持つことも大切です 。形骸化したルールを押し付けてしまうと、不満が蓄積する原因となります。
「完璧主義」から脱却し、自分自身を追い詰めすぎないことも重要です 。良い妻、良い夫、良いママ、良いパパでありたいという気持ちは素晴らしいですが、それが行き過ぎて疲弊してしまっては本末転倒です 。時には手抜きをしたり、外部のサポートに頼ったりする勇気も必要です 。
夫婦円満の秘訣は、何よりもコミュニケーションと相互理解にあります 。腹を割ったコミュニケーションを通じて、お互いの得意・不得意分野やこだわり、出勤・勤務時間などの情報をシェアし合い、無理のない分担について話し合いましょう 。ルールに基づいた生活を続けつつ、少しずつ調整をしていくなかで、二人ならではの暮らしが形成されていくのです 。
まとめ:令和の夫婦が目指す「共創」の家庭
「名もなき家事」という見えない負担は、令和の夫婦関係において、多くの不満や心身の不調の根源となっています。女性に偏りがちな家事負担、特にその背景にある「メンタルロード」の存在を認識し、夫婦間で共有することが、公平な役割分担を実現するための第一歩です。



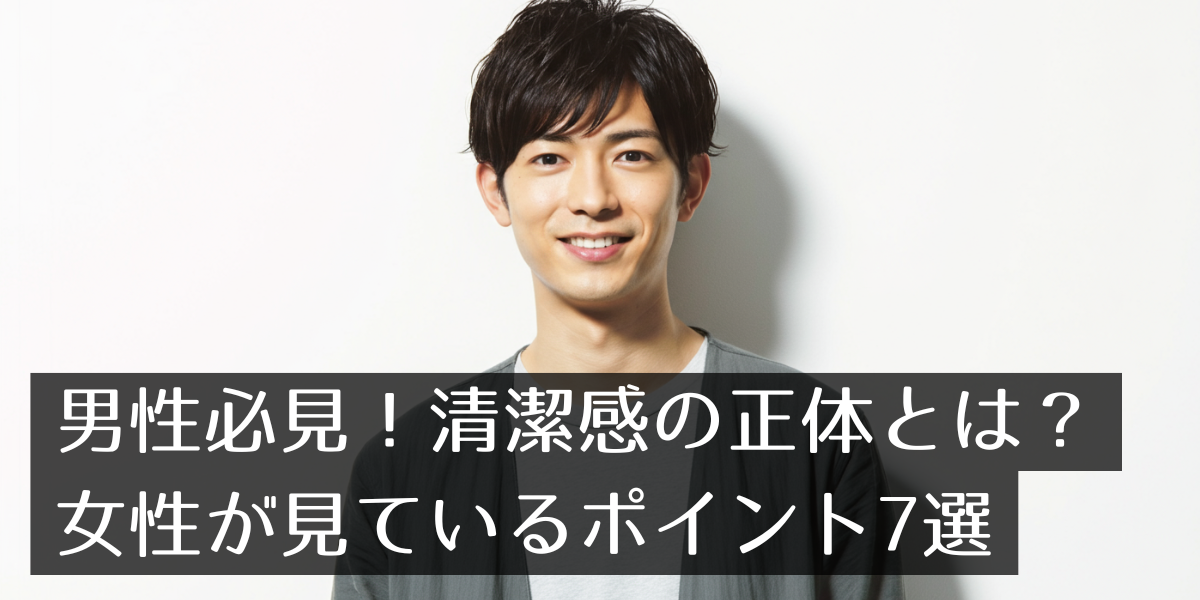


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。