【2026年義務化】カスハラ対策|企業が今すぐすべき4つのこと
2026年中にカスハラ対策が義務化されます。もはや従業員個人の対応に任せる時代は終わり、企業が組織的に取り組むことが法的に求められます。企業が今すぐ取り組むべきは、①方針の明確化、②相談体制の整備、③事後対応フローの確立、④研修の実施という「4つの柱」の構築です。本記事では、義務化のポイントと、具体的な対策・事例を徹底解説します。
2026年施行!カスハラ対策の義務化とは?
これまで「努力義務」とされてきたカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が、改正労働施策総合推進法により、パワーハラスメントと同様に事業主の「義務」となります。2026年中の施行が見込まれており、企業は待ったなしの状況です。
なぜ今、義務化されるのか?企業が負うリスク
義務化の背景には、従業員のメンタルヘルス悪化や離職率の増加といった深刻な問題があります。企業が対策を怠った場合、従業員を守る「安全配慮義務違反」を問われ、損害賠償請求に発展するリスクが格段に高まります。さらに、SNSでの悪評拡散による企業イメージの低下や、採用活動への悪影響など、経営へのダメージは計り知れません。
そもそも「カスハラ」とは?正当なクレームとの違い
効果的な対策のためには、まずカスハラとは何かを正しく理解することが重要です。厚生労働省は、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。
- 顧客などからの要求であること
- 要求内容や手段・態様が社会通念上、不相当であること
- 従業員の就業環境が害されること
商品やサービスへの正当なクレームは企業の成長に繋がる貴重な意見ですが、カスハラは要求の妥当性に関わらず、その手段や態様が問題となります。
- 正当なクレーム: 商品の不具合に対する交換要求
-
カスハラに該当しうる行為:
- 大声での暴言、人格否定、脅迫
- 土下座の強要、長時間の拘束
- SNSでの誹謗中傷
- 社会通念を超える過剰な金銭要求
これらの行為は、暴行罪や脅迫罪などの犯罪に該当する可能性もあります。
義務化に対応!企業が取り組むべき4つの柱
厚生労働省の指針に基づき、企業が構築すべきカスハラ対策の「4つの柱」を具体的に解説します。
柱1:方針の明確化と社内外への周知
- トップメッセージの発信: 経営トップが「カスハラを容認しない」という強い姿勢を表明します。
- 就業規則への明記: カスハラの定義や禁止行為を就業規則に具体的に規定します。
- 社内への周知徹底: 研修やポスター、イントラネットを通じて全従業員に方針を浸透させます。
- 顧客への意思表示: 店舗やウェブサイトで、迷惑行為には毅然と対応する旨を明示し、未然に防止します。
柱2:相談体制の整備とプライバシー保護
- 相談窓口の設置: 従業員が安心して相談できる窓口を設置し、広く周知します。外部の専門機関への委託も有効です。
- プライバシーの保護: 相談者の秘密を厳守し、相談したことによる不利益な扱いを禁止するルールを明確にします。
- メンタルヘルスケア: 産業医やカウンセラーと連携し、被害を受けた従業員の心のケアを行う体制を整えます。
柱3:事案発生時の迅速・毅然とした対応
- 証拠の記録: 通話録音や防犯カメラの映像など、客観的な証拠を確保します。
- 組織での対応: 従業員一人に対応を任せず、上司や専門部署が連携して対応するフローを確立します。
- 毅然とした態度: 不当な要求には応じず、悪質な場合はサービス提供の拒否や退去要求、警察への通報をためらわない姿勢が重要です。
- 外部機関との連携: 必要に応じて、弁護士や警察と連携し、法的措置も辞さない構えを示します。
柱4:実効性のある研修とマニュアル作成
- カスハラ対応マニュアルの作成: カスハラの具体例、対応フロー、証拠の記録方法などを盛り込んだ実践的なマニュアルを作成します。
- 定期的な研修の実施: 全従業員を対象に、マニュアルに基づいた研修を定期的に行います。特に、具体的な場面を想定したロールプレイングは対応スキル向上に極めて有効です。
- 管理職研修: 管理職には、従業員保護の重要性や、事案発生時の適切な対応手順に関する研修が不可欠です。
成功事例から学ぶ!効果的なカスハラ対策
他社のカスハラ対策事例から、実践的なヒントを学びましょう。
裁判事例から見る企業の安全配慮義務
過去の裁判では、企業が具体的な対策を講じ、それが「実効性をもって運用されているか」が厳しく問われています。
- まいばすけっと事件: 深夜の複数人配置や緊急ボタン設置、従業員の解雇要求に応じないなどの具体的な対策が評価され、会社の安全配慮義務違反が否定されました。
- NHKサービスセンター事件: 悪質電話に対する転送・切断ルールの運用や、カウンセリング制度の整備が評価され、同様に会社の責任が否定されました。
これらの事例は、ルール作りだけでなく、従業員を守る仕組みが実際に機能していることの重要性を示しています。
ICT活用と補助金制度の紹介
テクノロジーや国の支援を活用することで、対策をより効果的に進められます。
- ICTツールの活用: IVR(自動音声応答)の導入で「この通話は録音されています」とアナウンスするだけで、カスハラ行為の抑制効果が期待できます。実際に従業員の離職率が低下した事例も報告されています。
- 補助金の活用: 国や自治体は、カスハラ マニュアルの作成や研修の実施、録音・録画設備の導入などに取り組む企業に対し、助成金を支給する制度を設けています。積極的に情報を収集し、活用しましょう。
まとめ:カスハラ対策を経営の重要課題に
2026年のカスハラ対策義務化は、単なる法改正への対応ではありません。従業員が安心して働ける環境を整え、企業価値を高めるための絶好の機会です。
本記事で解説した「4つの柱」を軸に、自社の状況に合わせた対策を計画・実行することが急務です。経営トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸となってカスハラを許さない企業文化を醸成し、持続可能な事業運営を目指しましょう。



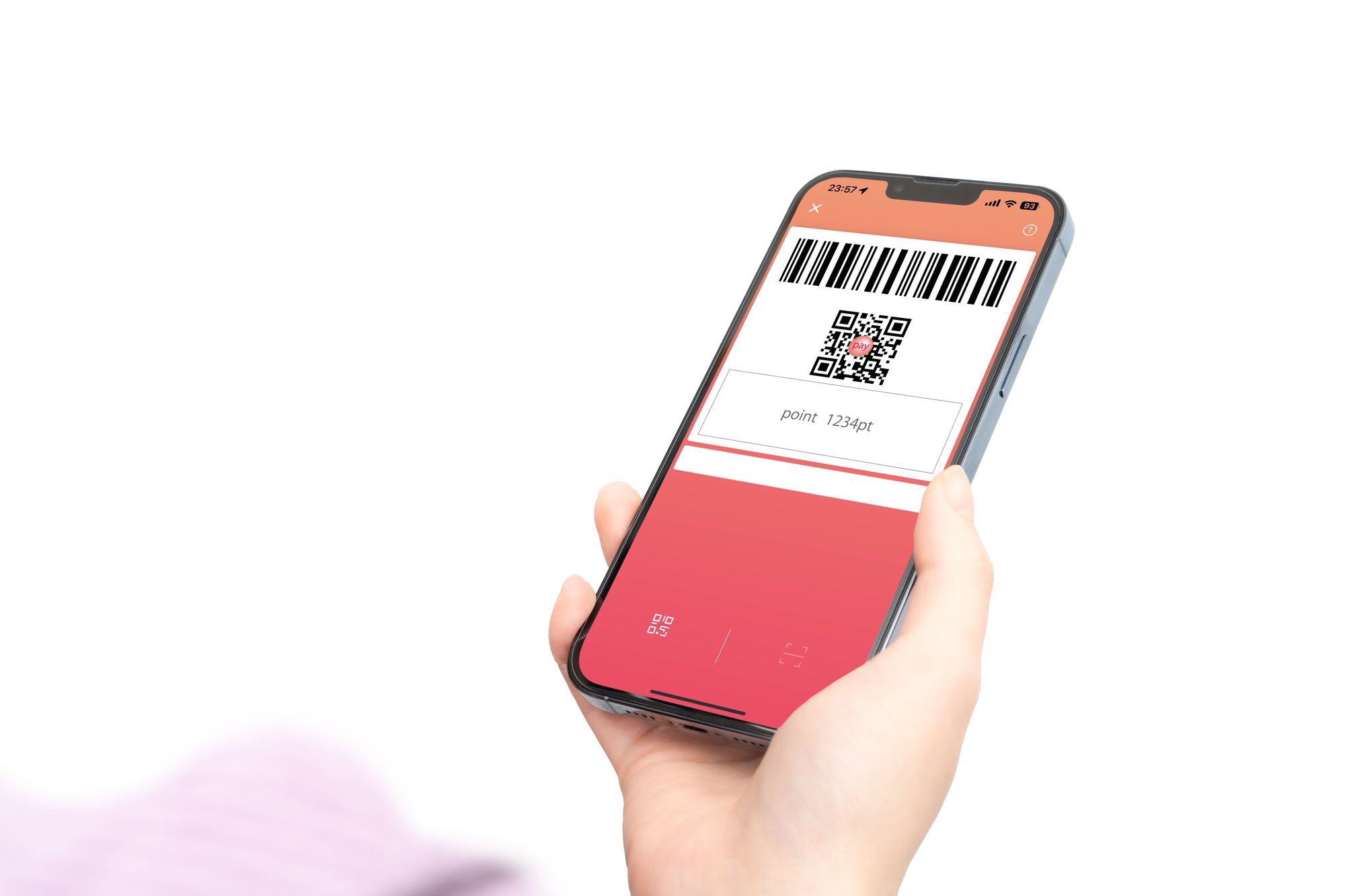


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。