『デジタル弱者』を生み出さない社会の実現に向けて
現代社会は、デジタル技術の急速な進化と普及により、かつてないほどの利便性を享受しています。行政サービスのオンライン化、キャッシュレス決済の浸透、そして情報への容易なアクセスは、私たちの日常生活に不可欠な要素となりつつあります。このデジタル化の波は、社会全体の効率性を高め、新たな価値創造の機会を提供しています。
しかし、この進化の恩恵を全ての国民が等しく享受できるわけではないという懸念も同時に高まっています。高齢者、障害を持つ人々、経済的に困難な状況にある人々、あるいはデジタルリテラシーが不足している人々は、デジタル社会の進展から取り残され、「デジタル弱者」となるリスクを抱えています。このような情報格差、あるいは利用格差は、社会の分断を深め、公平性の原則を揺るがす可能性を秘めています。
本稿では、このような重要な社会課題意識を起点とし、特に「iPhoneマイナンバーカード対応」という具体的な政策・技術動向に焦点を当て、その多面的な影響を深く掘り下げていきます。この新たな対応は、行政サービスの利便性向上やデジタル化推進に大きな「光」を当てる一方で、既存のデジタルデバイドを拡大させたり、新たな課題を生み出す「影」の部分も持ち合わせています。技術導入の是非に留まらず、真に「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現に向けた多角的な視点から議論を展開し、技術、政策、そして人々の支援がどのように連携すべきかを探求します。
第1章:iPhoneマイナンバーカード対応が照らす「光」
待望のサービス開始:利便性向上の大きな一歩
2025年6月24日より、マイナンバーカードのiPhoneでの利用を可能にする「iPhoneのマイナンバーカード」の提供が開始されました 。この画期的な対応により、利用者は実物のマイナンバーカードを取り出したり、専用のカードリーダーにかざしたりすることなく、自身のiPhoneを通じて多様な行政サービスにアクセスできるようになります。具体的には、マイナポータルへのログインが可能となり、薬や医療費、年金情報の確認、引越し手続き(転出届の提出や来庁予定日の予約)といった手続きをオンラインで完結できます。さらに、コンビニエンスストア等での住民票の写しや印鑑登録証明書の取得も、iPhoneをかざすだけで可能となります 。
認証プロセスにおいては、Face IDやTouch IDといった生体認証技術が採用されており、パスワードの入力や忘れによるストレスを解消し、簡単かつ安全な利用体験を提供します 。これは、物理的なカードの携帯や紛失のリスクを軽減するだけでなく、スマートフォン一つで多様な行政サービスにアクセスできるという点で、ユーザーの利便性を飛躍的に向上させるものと評価できます。デジタル庁は、今後、マイナ保険証としての利用や、民間サービスにおける本人確認、年齢確認、住所確認での利用拡大も順次予定していると発表しており、マイナンバーカードがデジタルIDとして社会の様々な場面で活用される基盤が強化される見込みです 。
日本特有のiPhone普及率がもたらす影響
日本のスマートフォンOSシェアは、約6割をiOS(iPhone)が占めており、AndroidとiPhoneの比率は約6:4という、世界的に見てもiPhoneのシェアが非常に高い特異な市場構造となっています 。これは、Androidがトップである世界の傾向とは逆行する日本独自の現象です 。
この高いiPhone普及率は、iPhoneマイナンバーカード対応が多くの国民にとって直接的な利便性向上に繋がることを意味します。日本市場においてiPhoneが圧倒的なシェアを占めているという前提に立つと、この対応は多数のiPhoneユーザーに直接的な利便性向上をもたらします。多くの利用者が日常的に使い慣れたiPhoneで行政サービスにアクセスできるようになるため、デジタルサービスへの心理的および物理的障壁が大幅に低減し、その利用頻度が増加する可能性が高いと考えられます。デジタルサービスの利用促進は、行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)推進という政府の政策目標達成に大きく貢献する要素です。このように、特定の技術(iPhone対応)が国民の広範な行動変容を促し、結果としてデジタル社会への移行を加速させるという好循環が生まれることが期待されます。
第2章:デジタル包摂への「影」:残された課題と潜在的リスク
依然として存在するデジタルデバイドの実態
高齢者のデジタル利用状況の二面性
2023年のシニア層(60~79歳)のモバイル端末所有率は94.5%に達し、そのうちスマートフォンをメインで利用する割合は91.9%と、非常に高い普及率を示しています 。この数値は2022年から2.9ポイント増加しており、シニア層におけるスマートフォンの利用が着実に進んでいることを示唆しています 。さらに、2025年1月時点の調査でも、関東在住の60代と70代のスマートフォン所有率は89%に達し、80代前半でも3人に2人が所有するなど、全体的にスマホ利用が続伸していることが確認されています 。
これらのデータは、一見すると高齢者のデジタルデバイドが解消されつつあるかのように見えます。しかし、依然として約5.0%のフィーチャーフォン利用者が存在し、そのうち38.2%がスマートフォンへの乗り換え意向を示しているものの、61.8%は乗り換えを検討していないと回答しています 。また、フィーチャーフォン利用者の約8割が月間データ容量1GB以下であり、これは限定的な利用に留まっている可能性を示唆します 。この状況は、表面的な普及率だけでは測れない、より深い「質的デジタルデバイド」の存在を明らかにしています。単にデバイスを持っているだけでなく、iPhoneマイナンバーカード機能のような高度なデジタルサービスを使いこなすためのリテラシーや意欲が不足している可能性が強く示唆されます。スマートフォンの普及率が高まっていることは喜ばしいものの、その利用実態には大きな幅があり、単に電話や簡単なメッセージアプリを使うだけでなく、行政手続きのような複雑なサービスを使いこなすには、より高いデジタルリテラシーが求められます。フィーチャーフォンからの乗り換え意向がない層や、データ利用量が極端に少ない層は、iPhoneマイナンバーカードのようなサービスから取り残されるリスクが高いと言えます。これは、デジタルデバイドがデバイスの有無だけでなく、利用スキル、利用目的、そして利用意欲といった多面的な要素によって構成されていることを示唆しています。
Androidユーザーへの配慮の必要性
日本ではiPhoneのシェアが高いものの、Androidのシェアも約4割近くを占め、2023年から2024年にかけて約8%上昇し、ここ10年間で過去最高を記録するなど、近年は上昇傾向にあります 。特に価格を理由にiPhoneからAndroidへ乗り換えるユーザーも増えており、操作性の違い(例:電話の出方、LINEの既読表示)に戸惑う事例も報告されています 。
iPhoneマイナンバーカード対応は大きな一歩ですが、約4割を占めるAndroidユーザーへの同等かつ円滑な対応が不可欠です。もしAndroid版の機能や利便性がiPhone版に比べて劣る場合、新たなデジタルデバイドを生む可能性があります。日本のスマートフォン市場ではAndroidも約4割のシェアを持ち、その比率は上昇傾向にあるという市場の現実があります。もしAndroid版の機能や提供時期が遅れる場合、この約4割のユーザーがデジタルサービスの恩恵を享受しにくくなり、新たなデジタルデバイドが生じる懸念があります。政策は市場の多様性に対応し、Androidユーザーへの同等な機能提供と利便性確保を迅速に進める必要があります。特に、価格を理由にAndroidへ移行する層は、経済的側面からもデジタルデバイドに陥りやすい可能性があるため、Android版の機能拡充と利便性向上は喫緊の課題となります。異なるOS間でのユーザー体験の均質化が、真に包括的なデジタル社会を実現する上で重要な課題となります。
物理的なカードリーダーの課題と次期モデルへの期待
現行の顔認証付きカードリーダーには複数の課題が指摘されています。具体的には、今後搭載予定のスマートフォン用電子証明書の読み取りには一部機種しか対応しておらず、外付けの汎用カードリーダーが必要な場合があること 。また、視覚障害者が一人でカードリーダー上の操作(顔認証、暗証番号入力等)を行うことが困難である点や、端末によって画面(特に同意ボタン)がバラバラで操作しづらく、高齢者にとっては文字が判読しづらいといった問題も挙げられています 。
iPhoneマイナンバーカード対応により、スマートフォンでのデジタルサービス利用が促進される一方で、行政窓口や医療機関に設置されている既存の物理カードリーダーには、スマートフォンとの互換性やアクセシビリティ(特に視覚障害者や高齢者向け)に課題があります。このハードウェア側の課題が、せっかく向上したスマートフォンでの利便性を相殺し、結果的にデジタルサービスの円滑な利用を妨げるボトルネックとなる可能性があります。デジタルサービスの普及には、個人のデバイスだけでなく、その周辺機器や公共インフラ全体のアクセシビリティが不可欠です。
これらの課題解決を目指し、2026年夏頃から販売開始見込みの次期顔認証付きカードリーダーの開発が進められています 。次期モデルでは、物理的なマイナンバーカードとスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの読み取り口を同一とすることが望ましいとされています 。次期モデルでの改善は期待されるものの、その普及と既存機器の置き換えには時間を要するため、過渡期の課題として認識し、対策を講じる必要があります。
デジタルリテラシー格差がもたらす利用障壁
スマートフォンを所有しているだけでは、iPhoneマイナンバーカード機能を十分に使いこなすことはできません。アプリのインストール、初期設定、オンラインでの手続き方法の理解、セキュリティ意識の保持など、一定のデジタルリテラシーが求められます。特に、高齢者やデジタル機器に不慣れな層は、こうした複雑な操作や概念につまずきやすく、結果としてサービスの利用を諦めてしまう可能性があります。
スマートフォンそのものの普及率は高まっているものの 、iPhoneマイナンバーカード対応のように、デジタルサービスはより高度化し、多機能化しています 。これらの高度なサービスを安全かつ効果的に利用するには、単なるデバイス操作を超えた、より深いデジタルリテラシーが必要となります。デジタルデバイドは、単にインターネットに接続できるか、スマートフォンを持っているか、という「アクセス格差」だけではありません。より深くは、デジタルサービスを「使いこなせるか」「活用できるか」という「利用格差」や「リテラシー格差」にあります 。リテラシー不足が、デバイスを持っていてもサービスを利用できない「利用格差」を生み出し、「デジタル弱者」の定義を広げています。iPhoneマイナンバーカードのような高度なサービスが普及するほど、このリテラシー格差が顕在化し、新たな「デジタル弱者」を生み出すリスクが高まるため、政府や自治体は、このリテラシー格差の解消に重点を置く必要があります。
第3章:『デジタル弱者』を生み出さない社会へ:多角的なアプローチと今後の展望
国のデジタル活用支援推進事業と官民連携の取り組み
総務省は令和3年度から「デジタル活用支援推進事業」を実施しており、高齢者等が携帯ショップなど身近な場所でデジタル活用を学べる講習会を推進しています 。これらの講習会の費用は国が負担し、標準教材も提供されています 。この取り組みは、デジタルデバイド解消に向けた政府の明確な意思と、実践的な支援策を示しています。特に「身近な場所で身近な人から」学ぶというアプローチは、デジタルに抵抗感を持つ層にとって心理的ハードルを下げ、効果的な学習機会を提供しています 。
さらに、2025年1月には総務省がプラットフォーム事業者や通信事業者、IT関連企業・団体と連携し、官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」を発足しました 。このプロジェクトは、インターネットやSNSにおける偽・誤情報や詐欺広告、誹謗中傷といった問題に対処し、利用者のICTリテラシー向上を目的としています 。デジタルデバイドが、デバイスの有無だけでなく、リテラシー、利用意欲、情報の真偽判断能力など、多岐にわたる側面を持つという認識に基づき、政府は初期のデバイス操作支援から、より高度な情報リテラシー教育まで、多段階の支援策を展開しています。この多層的かつ連携型の支援体制は、「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現に向けた包括的なアプローチであり、デジタル化の進展に伴う新たな課題にも柔軟に対応しようとする姿勢を示しています。
また、総務省は「地域デジタル社会推進交付金」や「高齢者向けデジタル活用支援事業」を通じて、地方自治体のデジタル化やデジタルデバイド対策への財政支援を行っています 。さらに、通信インフラの整備も進められており、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」では、光ファイバの世帯カバー率を令和9年度末までに99.9%に、5G人口カバー率を令和12年度末までに全国・各都道府県で99%にすることを目指しています 。これらの取り組みは、デジタルサービスへのアクセス格差を解消するための基盤を強化するものです。
地方自治体における先進的なデジタル包摂事例
地方自治体は、地域の実情に応じたきめ細やかなデジタル包摂の取り組みを推進しており、その先進事例は全国的な政策形成に貴重な示唆を与えています。
高知県日高村:「村まるごとデジタル化」の挑戦
高知県日高村は、2021年6月に「スマートフォン普及率100%を目指す村宣言」を掲げ、「村まるごとデジタル化事業」をスタートさせました 。村内には「よろず相談所」が開設され、自治会と連携した住民向けの説明会や個別相談会をきめ細かく展開することで、村民の様々な不安解消に繋げています。特に高齢者へは、防災、情報、健康といった関心の高い領域からスマホ利用を促しました 。日高村の取り組みは、地方におけるデジタルデバイド解消の成功モデルとして非常に示唆に富みます。住民一人ひとりに寄り添う「伴走型支援」と、地域の実情に合わせた「ちょうどいい技術」の導入が成功の鍵となっています。彼らは「フルコースよりお茶漬け」という哲学で「不釣り合いな先進技術ではなく、ちょうどいい技術でコストも低く味変できる」ことを重視しています 。また、この事業を通じて培ったデジタルデバイド解消のノウハウを社会に還元するため、一般社団法人「まるごとデジタル」を設立し、2025年3月1日時点で全国から19の地方公共団体が賛助会員として参画しています 。このノウハウの全国展開は、地方自治体間の連携による課題解決の可能性を示しています。
渋谷区:高齢者向けスマホ無料貸与と伴走型支援
KDDIと渋谷区は、2021年9月から2023年8月までの2年間、65歳以上でスマートフォンを所有していない約1,700人の渋谷区民を対象に、スマートフォンを無償で貸与し、デジタルデバイド解消の実証実験を行いました 。この実証実験では、専用コールセンターが用意され、遠隔で参加高齢者のスマートフォンを操作しながら利用方法を伝えることで、操作を教えてもらう機会が少ないという課題の解決を狙いました 。渋谷区の事例は、デバイス提供だけでなく、継続的なサポート体制がいかに重要であるかを実証しています。特に、遠隔操作によるサポートは、高齢者が自宅にいながらにして不明点を解消できる点で画期的であり、心理的負担を軽減する効果が高いことが示されました。結果として、多くの参加者がインターネット検索やLINEなどを積極的に利用し、8割以上が「スマホの利用で生活に良い影響があった」と回答しています 。
AIチャットボット導入事例:行政サービスのアクセシビリティ向上
富山県魚津市立図書館では、2025年4月からAIコンシェルジュが導入され、利用者が探している本を音声やタッチ操作で自由に伝えるだけで、AIが意向に沿った本をピックアップして紹介する実証実験が開始されました 。富山県庁も職員の生産性向上のため、AI議事録、RPA、AIチャットボットといった最新のデジタル技術を導入しています 。佐賀市では、2023年11月に子育て支援部保育幼稚園課への来訪者を対象に、生成AIを活用したチャットボットの実証実験が行われ、利用者の質問を的確に解釈し適切な回答を生成できることが確認されました 。唐津市は2024年12月から公式ホームページとLINE公式アカウントでAIチャットボットの利用を開始し、市役所の手続きに関する質問に24時間いつでも対応しています 。栃木県那須塩原市では、総務省とデジタル庁が連携する「国・地方共通相談チャットボット(Govbot)」が導入され、「税」や「子育て」など住民からの問い合わせニーズが多い分野に対応しています 。また、那須塩原市役所にはAI接客システム「AIさくらさん」も導入され、人手不足解消とDX推進に貢献しています 。
AIチャットボットは、行政窓口の混雑緩和や24時間対応を可能にし、住民がいつでもどこでも情報を得られる環境を整備します。これにより、デジタルに不慣れな層でも、対話形式で気軽に質問できるため、行政サービスへのアクセス性が向上します。LINEのような身近なプラットフォームでの導入は、利用の敷居をさらに下げ、より多くの人々にデジタルサービスの恩恵を届ける可能性を秘めています。これらの地方自治体の事例は、中央政府の政策を補完し、時には先行する形で、デジタルデバイド解消の具体的な道筋を示しています。特に、日高村の「ちょうどいい技術」や渋谷区の「伴走型支援」は、技術導入だけでなく、人間的なサポートや地域コミュニティの役割が不可欠であることを強調します。AIチャットボットの導入は、効率化とアクセシビリティ向上を両立させる手段として注目され、人的リソースの制約がある地方自治体にとって特に有効な解決策となり得ます。これらの成功事例は、デジタル包摂政策の設計において、多様なアプローチと地域の実情に合わせた柔軟な対応が重要であることを示唆しています。
ユニバーサルデザインとアクセシビリティの重要性
Webアクセシビリティは「全ての人がWebで提供される情報を利用できること」を指し、ユーザーの障害の有無や度合い、年齢、利用環境に関わらず、あらゆる人々がWebサイトのサービスを利用できることを目指します 。これには、知覚可能(Perceivable)、操作可能(Operable)、理解可能(Understandable)、堅牢(Robust)という4つの原則と、視覚、聴覚、身体・運動機能、認知への配慮(例:画像の代替テキスト、音声のテキスト表示、キーボード操作、シンプルな画面設計)が求められます 。
特に重要なのは、2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、これまで民間企業にとって努力義務だった「合理的配慮」が義務化されたことです 。ウェブアクセシビリティの国際基準であるWCAG2.2や、国内標準であるJIS X 8341-3:2016といったガイドラインが存在します 。デジタルサービスの設計段階からユニバーサルデザインとアクセシビリティを考慮することは、後からの修正よりもはるかに効率的で、結果的に「デジタル弱者」を生み出さないための根本的な解決策となります。この法的義務は、デジタルサービス提供者に対し、開発の初期段階からユニバーサルデザインとアクセシビリティを組み込むことを強く促します。これは、単に障害者だけでなく、高齢者や一時的な状況にある人々も含め、あらゆるユーザーがデジタルサービスを円滑に利用できるようなデザインを最初から組み込むべきだという強いメッセージです。これにより、デジタルサービス開発のパラダイムが「一部の人向け」から「全ての人向け」へとシフトし、結果的にデジタルデバイドの根本的な解消に繋がる可能性を秘めています。法的義務化は、企業や行政機関がこの原則を遵守する強力なインセンティブとなり、デジタルサービス全体のエコシステムをより包括的なものへと変革を促します。
国際事例から学ぶデジタル政府の教訓
エストニアは「e-Estonia(イーエストニア)」として知られ、15歳以上の国民全員にデジタルIDカードが発行されており、これを利用することで教育、医療、選挙まで、ほぼ全ての行政手続きがインターネットで完結します 。この包括的なデジタルIDシステムと、それを基盤とした行政サービスの徹底的なオンライン化は、国民の利便性をいかに高めるかを示しています。
さらに、外国人向けの電子居住者(e-Residency)制度も導入されており、国外にいながらにして法人の設立や銀行口座の開設などが可能となっています 。e-Residencyは、デジタルIDが物理的な国境を超えて経済活動を可能にする新たな可能性を提示します。また、エストニアは「データ大使館」構想を進めており、政府のデータと行政サービスのシステムを世界中の大使館内のサーバーに分散することで、サイバー攻撃や万が一の領土侵略時にも国家の機能を維持できるような安全保障上の戦略を透けさせています 。データ大使館の構想は、デジタル化におけるセキュリティとレジリエンスの重要性を浮き彫りにし、国家レベルでのデジタル戦略の深さを示しています。エストニアの事例は、デジタルIDが単なる本人確認ツールに留まらず、国家の基盤インフラとして機能し、行政の効率化、国民の利便性向上、さらには国家の安全保障にまで貢献し得ることを示しています。特に「データ大使館」という概念は、デジタル化が進む現代において、物理的な領土に依存しない国家機能の維持という、極めて先進的な視点を提供しています。日本がマイナンバーカードのデジタル化を進める上で、単なる利便性だけでなく、このような国家的なレジリエンス強化の視点も取り入れるべきであるという示唆を得られます。
おわりに:真に「誰一人取り残さない」デジタル社会の実現に向けて
iPhoneマイナンバーカード対応は、日本のデジタル化を加速させる強力な推進力となる一方で、その恩恵を全ての国民が享受できるよう、引き続き「デジタル弱者」問題に真摯に向き合う必要があることを強調します。技術の進化(iPhone対応、AI導入)だけでは不十分であり、それを支える人的支援(講習会、伴走型サポート)、そして包括的な政策設計(デジタル活用支援事業、アクセシビリティ義務化、インフラ整備)が不可欠です。国、地方自治体、民間企業、そして地域コミュニティがそれぞれの役割を果たし、連携を強化することが、持続可能なデジタル包摂社会を築く上での鍵となります。

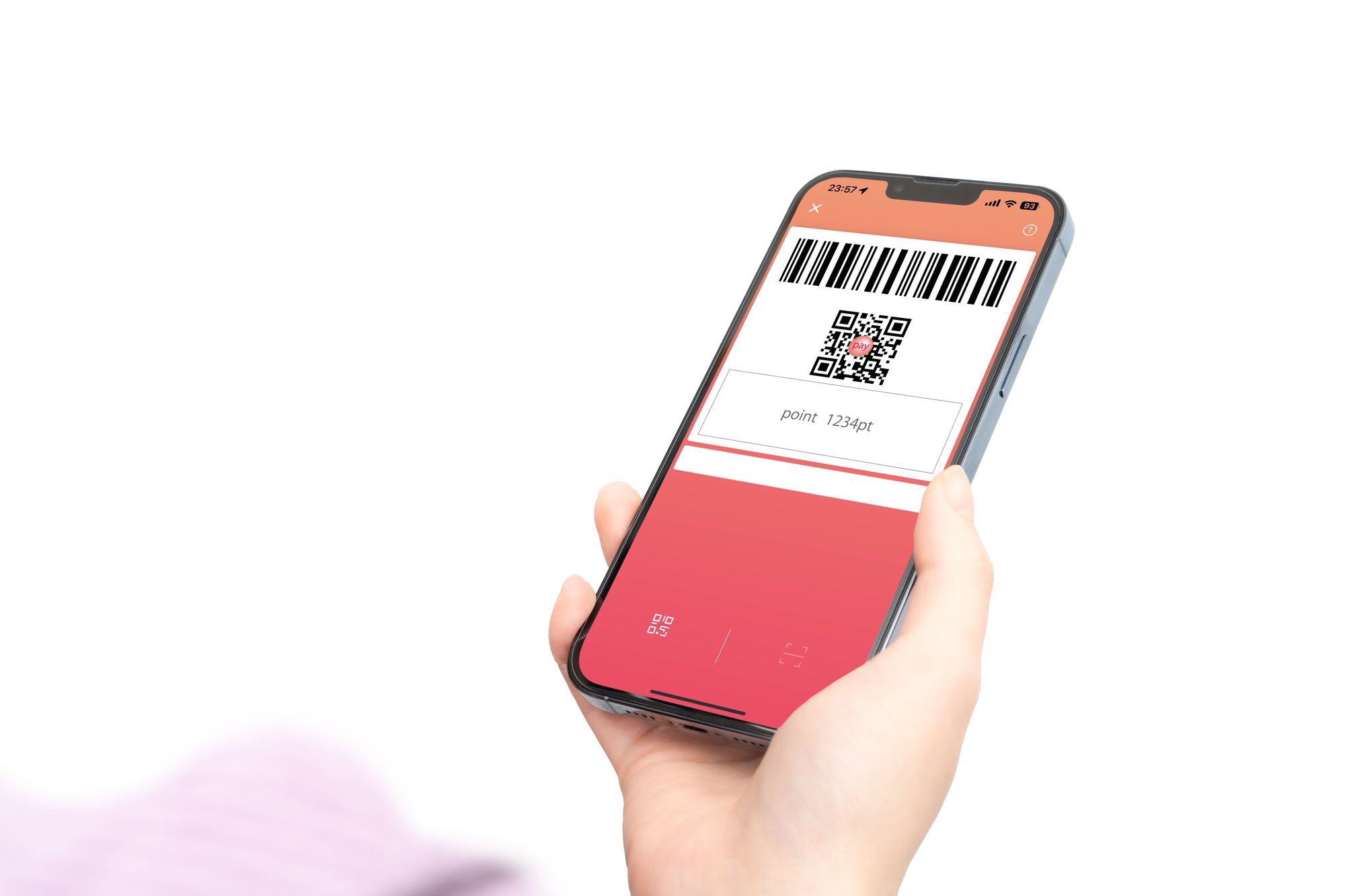




まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。