「ご褒美」という名の搾取、レンズに映ることのない私たち
週末の居酒屋は、どうしてこうも暴力的な音量で満たされているんでしょうね。
隣の席の怒声に近い笑い声、店員の張り上げた声、安っぽい唐揚げの油の匂い。
そして目の前で繰り広げられる、ありふれた「強者の無邪気さ」。
私たちの部署の後輩、まだ20代半ばの彼が、テーブルの上に真新しいiPhoneを置きました。
最新モデル。鈍く光る質感。
彼は悪びれもせず、まるでそれが世界の理であるかのように、こう言ったんです。
「いやー、最近プロジェクトも終わったし、頑張った自分へのご褒美っすね」
その瞬間、私のグラスを持つ手がわずかに止まりました。
ご褒美。なんて甘美で、そして残酷な響き。
私は温くなったサワーを揺らしながら、あくまで軽い調子を装って、けれど正確に彼の急所を狙って口を開きました。
「新しいの買ったんだ。…ところでさ、彼女にも買ってあげたの?」
彼は一瞬、何を言われたのか分からないという顔で瞬きをしました。
きょとんとしたその表情。まるで宇宙人と遭遇したかのような、純粋な困惑。
「え? なんでですか? 俺の金ですよ?」とでも言いたげなその沈黙に、私はあえて不思議そうに首をかしげて続けました。
「普通さ、彼女にも同じの買ってあげない? ほしいのはわかるけど、自分のだけってのはなくない? 彼女さんへの配慮、足りなくない?」
場の空気が、少しだけ凍ったのが分かりました。
彼は引きつった愛想笑いで「いやいや、さすがに二台は無理っすよ」と誤魔化そうとしましたけれど。
ああ、やっぱり。
この徒労感。
彼は本気で理解していないのです。
自分が手にしているその「ご褒美」が、一体誰の犠牲の上に成り立っているのかを。
言わなきゃ分からない「当然」の作法
別にね、法律で決まっているわけじゃありません。
「男は女に貢げ」なんて、野暮なことを言うつもりもない。
でも、考えてもみてください。
彼が今日まで、誰のおかげで心身ともに健康で、仕事に打ち込めたと思っているんでしょう。
彼が疲れて帰った時、誰がそのメンタルをケアしたの?
彼が万全の状態で社会という戦場に出られるように、生活の端々で、見えない気遣いというインフラを整備しているのは誰?
パートナーというものは、そういう「下支え」があって初めて成立している関係のはずです。
ならば、そこで生まれた果実——彼が手にした給与や成功——の分配において、その土台を支えた人間が「先」に配慮されるのは、重力に従って水が下に落ちるのと同じくらい、自然な理(ことわり)ではありませんか?
それを「自分へのご褒美」と言って、真っ先に自分の欲だけを満たす。
美味しいケーキをホールで買ってきて、切り分けもせず、支えてくれた人の目の前で自分だけがかぶりつく。
それを「おかしい」と思わない感性。
別にいいんですよ、自分の稼ぎをどう使おうと。
ただ、あまりにも「美しくない」。
パートナーを一番に喜ばせようという発想が抜け落ちているその姿は、大人の男性として、致命的にダサいのです。
最新機種を持つ、旧式の感性
私が一番、深い絶望を感じたのは、彼がまだ20代だという事実です。
これが昭和の頑固親父ならまだしも、彼はジェンダーだの多様性だのが叫ばれる時代に育った若者です。
それなのに、インストールされているOSは、化石のような旧世代のまま。
「自分の欲求が満たされて、余りがあれば女にやる」
無意識でしょうが、彼の行動はそう語っています。
彼にとって彼女は、同じ目線で生きる人間ではなく、自分の人生の付属品(オプション)なのでしょう。
だって、対等な人間だと思っていたら、自分が最新の機能を体験するときに「彼女にもこの体験をさせてあげたい」と想像力が働くはずですから。
彼女だって、綺麗な写真を撮りたいはず。サクサク動く画面で動画を見たいはず。
そんな当たり前の「彼女の意思」や「人権」が、彼の脳内では、自分の物欲の前で完全に透明化されている。
「Sakura.さん、考えすぎですよ」
周りの男性社員が苦笑いでフォローに入ります。
そうやって、男同士で「まあまあ」と傷を舐め合う。
その温ぬるい空気こそが、彼らをいつまでも「少年のまま」にしている元凶なのに。
映らないレンズ
「ま、彼女さんがそれでいいなら、いいんじゃない?」
私はそう言って、会話を打ち切りました。
これ以上言っても、言葉の通じない相手にマナーを説くようなものですから。
ただ、彼がその新しいカメラで何を撮ろうと、そこには決して「真実」は映らないということだけは、確信しています。
そのレンズの向こう側には、彼に尽くし、後回しにされ続け、それでも「私のことはいいから」と笑顔を作ることを強要されている女性の、静かな諦めがあるだけ。
自分が優先されることが「当然」だと信じて疑わない彼。
そして、優先されるべき女性が後回しにされている現状に、何の違和感も抱かない社会。
彼が無邪気に画面をスワイプするたび、私たちの尊厳がまたひとつ、指先で弾かれて消えていく気がして。
私は残ったサワーを、苦い薬のように飲み下すしかありませんでした。
最新のiPhone、ね。
そんなもので世界と繋がる前に、一番近くにいる人の「心」と繋がる努力をしたらどうなの、なんて。
…まあ、言っても無駄か。

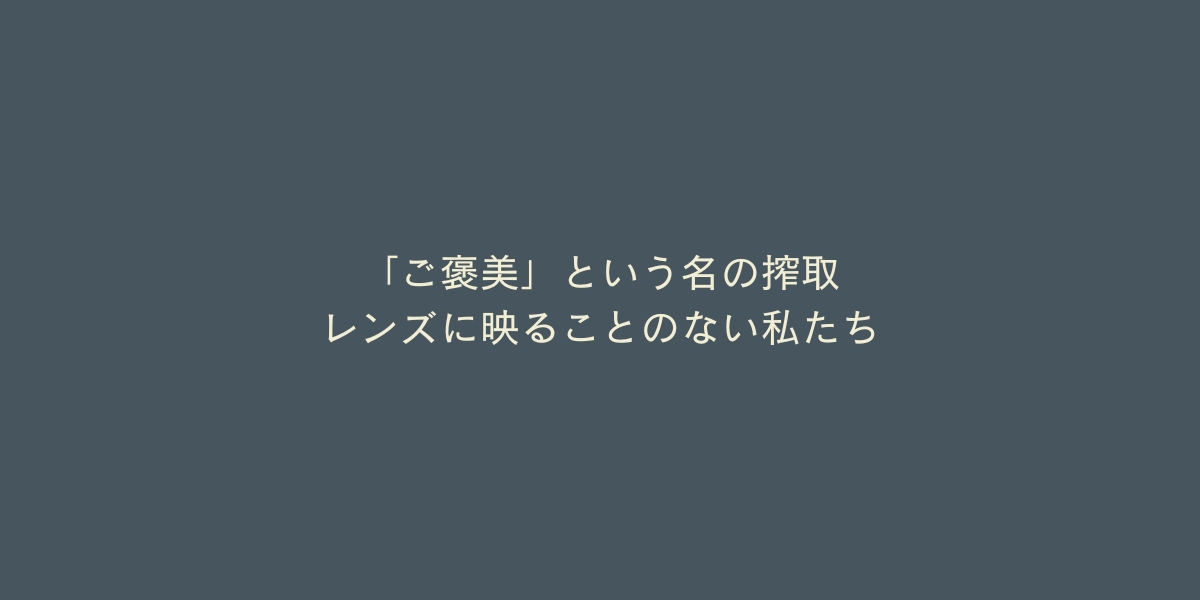

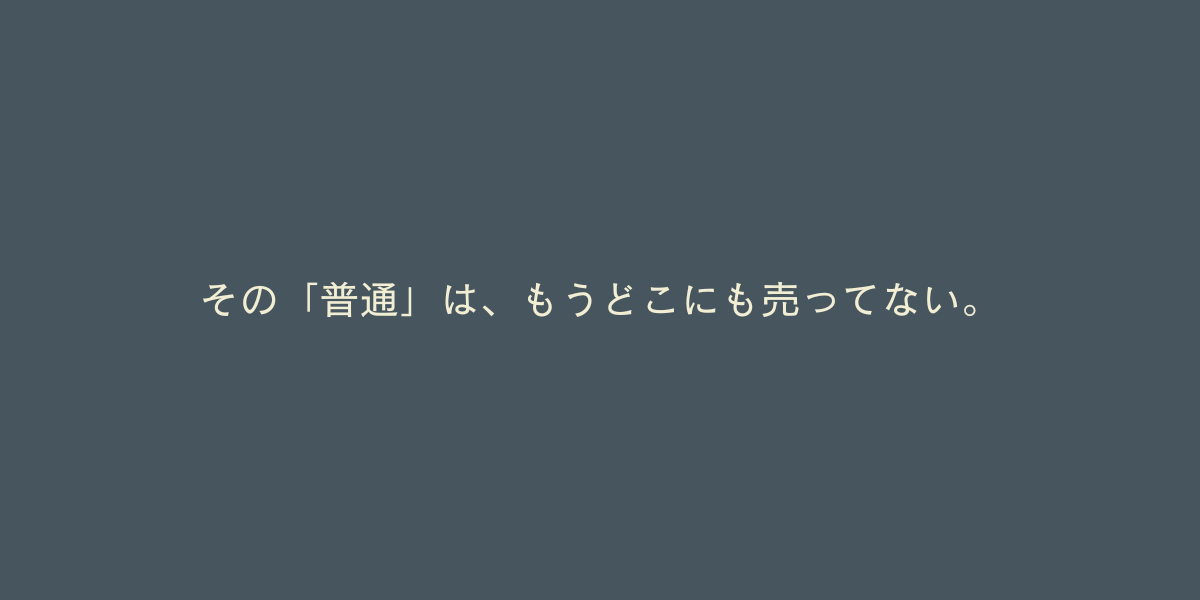
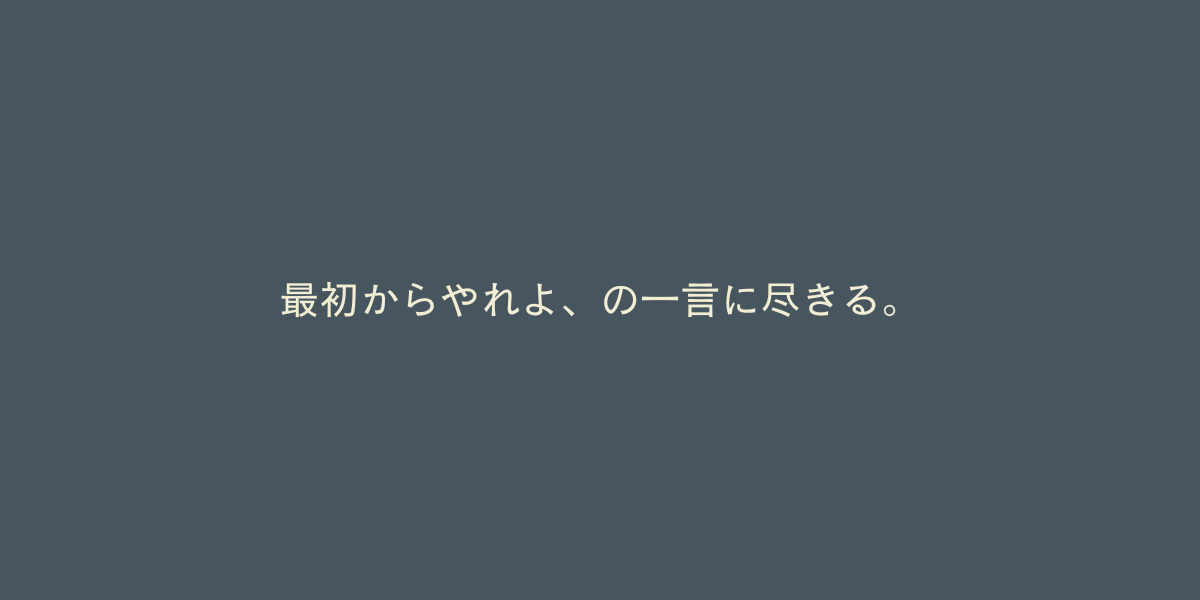
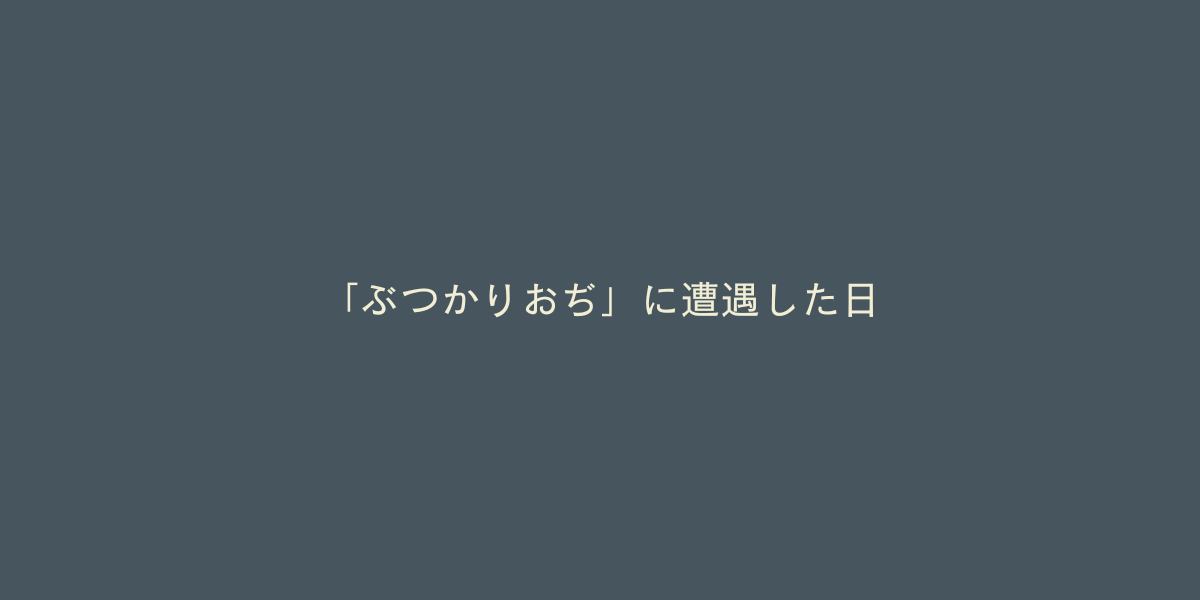
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。