相続税ゼロでも手続きは必須!放置の危険と全手順
「うちは財産が少ないから相続税はかからない。だから手続きは不要のはず」――そう考えていませんか?
実は、相続税がゼロであっても、亡くなった方の財産を引き継ぐための法的な手続きは必ず必要です。特に、2024年4月からは不動産の相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性も出てきました。
この記事では、相続税がかからない場合でも手続きが必要な理由から、ご自身でできる手続きの具体的なステップ、そして専門家の力を借りるべきタイミングまで、分かりやすく解説します。後々のトラブルを避け、円満な相続を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ?相続税がかからなくても手続きが必要な理由
「相続税の申告が不要」なことと、「相続手続きが一切不要」なことは全く意味が異なります。たとえ相続税なしの場合でも、以下の理由から手続きは必須です。
理由1:財産の名義変更をしないと凍結・売却できない
亡くなった方(被相続人)名義の財産は、法的な手続きを踏まなければ相続人が自由に使うことができません。
- 預貯金口座:被相続人名義の口座は金融機関によって凍結され、入出金や解約ができなくなります。
- 不動産:名義変更(相続登記)をしないと、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
- 自動車など:名義変更をしなければ、売却や廃車手続きが進められません。
これらの手続きを放置すると、相続関係が複雑化するリスクもあります。例えば、手続きをしないうちに相続人が亡くなると、次の世代(孫など)がさらに複雑で面倒な手続きを強いられることになります。
理由2:【義務化】不動産の相続登記をしないと罰則も
これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。これは、所有者不明の土地が増えて社会問題化していることを受けた法改正です。
- 期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 罰則:正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 過去の相続も対象:この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。この場合、2027年(令和9年)3月31日までに登記を済ませる必要があります。
この法改正により、「相続税なし」のケースであっても、不動産を相続した場合は必ず手続き(相続登記)が必要不可欠となりました。
【初心者向け】自分でできる相続手続き5つの基本ステップ
事案がシンプルであれば、ご自身で相続手続きを進めることも可能です。ここでは、一般的な流れを5つのステップで解説します。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
まず、被相続人が遺言書を残していないか確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
- 自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用していなければ、家庭裁判所での「検認」が必要です。
ステップ2:誰が相続人か戸籍で確定させる
次に、法的な相続人を確定させます。これには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をすべて集める必要があります。令和6年3月からは戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
ステップ3:財産と借金を調査し「財産目録」を作る
被相続人が遺したプラスの財産(不動産、預貯金、株式など)と、マイナスの財産(借金など)をすべて調査します。調査結果は、後々の手続きで必要となる「財産目録」という一覧表にまとめておきましょう。
ステップ4:相続人全員で遺産の分け方を決める(遺産分割協議)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
- 協議には相続人全員の参加が必須で、一人でも欠けると無効になります。
- 合意した内容は<b>「遺産分割協議書」</b>という書面にまとめ、全員が署名し、実印を押印します。この書類は、不動産や預貯金の名義変更手続きで重要な役割を果たします。
ステップ5:不動産や預貯金の名義を変更する
遺産分割協議書または遺言書に基づき、各種財産の名義変更を行います。
- 不動産:法務局で相続登記を申請します。
- 預貯金:各金融機関の窓口で解約・名義変更の手続きをします。
- 自動車:運輸支局などで名義変更の手続きをします。
要注意!相続手続きの主な期限
相続手続きには、法律で定められた期限があるものが多くあります。特に注意が必要なものを覚えておきましょう。
- 死亡届の提出:死亡を知った日から7日以内
- 相続放棄・限定承認:相続の開始を知った時から3ヶ月以内
- 所得税の準確定申告:死亡の翌日から4ヶ月以内
- 相続税の申告・納付:相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 不動産の相続登記:相続を知った日から3年以内
こんな時は専門家へ!相談すべきケースと頼れる専門家
ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合は、専門家の力を借りるのが賢明です。
専門家への相談を検討すべきケースとは?
- 相続人の関係が複雑(前婚の子がいる、連絡が取れない相続人がいるなど)
- 相続人同士で意見が対立している、またはその可能性がある
- 仕事などが忙しく、手続きに時間を割けない
- 財産の種類が多い、または評価が難しい財産(非上場株式など)がある
- 借金が多く、相続放棄を検討している(3ヶ月の期限に注意)
- 特例(配偶者の税額軽減など)を利用して相続税をゼロにするための申告が必要
- 何代にもわたって相続登記がされていない不動産がある
誰に何を頼める?【司法書士・弁護士・税理士・行政書士】
相続に関する専門家と、それぞれの主な役割は以下の通りです。
- 司法書士:不動産の相続登記の専門家。遺産分割協議書の作成や戸籍収集なども依頼できます。相続トラブルがなく、登記がメインの場合の第一相談先として適しています。
- 弁護士:相続人間のトラブル解決の専門家。遺産分割協議の代理交渉や調停・審判を依頼できます。紛争が発生している、または発生しそうな場合に頼りになります。
- 税理士:相続税申告の専門家。相続税がかかる場合や、特例を使って納税額をゼロにするための申告が必要な場合に依頼します。
- 行政書士:遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更など、書類作成の専門家。ただし、登記申請の代理や紛争解決はできません。
専門家費用の目安
費用は依頼内容や財産額によって大きく異なりますが、一般的な目安です。
- 司法書士:相続登記のみで5万円~15万円程度。遺産整理業務全体では25万円~。
- 弁護士:着手金として10万円~(紛争性があれば更に高額)。成功報酬は得られた経済的利益に応じます。
- 税理士:相続税申告で遺産総額の0.5%~1.0%程度が目安。
- 行政書士:遺産分割協議書作成などで5万円~が目安。
まとめ:相続手続きは放置せず早めの対応が重要
相続税がかからない場合でも、財産を引き継ぐための法的な手続きは避けて通れません。特に不動産の相続登記は義務化され、社会的な要請としてもその重要性は増しています。
手続きを放置すればするほど、関係者が増えて状況は複雑になり、家族間のトラブルに発展する可能性も高まります。各種手続きには期限も設けられているため、できるだけ早く着手することが、後悔しない相続への第一歩です。
何から手をつけて良いか分からない、一人で進めるのは不安だという場合は、まずはお近くの司法書士や自治体の無料法律相談などを利用してみることをお勧めします。この記事が、円満な相続手続きを進めるための一助となれば幸いです。




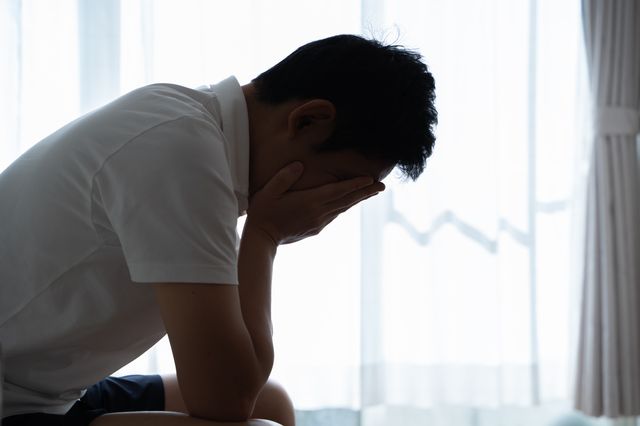

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。