【老後のお金】今さら聞けない…!年金の基本のキからやさしく解説
「年金って、なんだか難しそう…」「将来ちゃんともらえるの?」そんな不安や疑問を抱えていませんか? 大丈夫です!この記事を読めば、年金の基本的な仕組みがスッキリわかります。未来の自分のために、今からできることを一緒に考えていきましょう。
年金って、そもそも何のため?
年金は、私たちの生活を支えるための大切な社会保険制度です。主に3つの役割があります。
- 老後の生活のため(老齢年金): 年をとって働くことが難しくなった時の生活を支えます。
- 病気やケガで障害が残った時のため(障害年金): 万が一、病気やケガで障害を負ってしまった場合の生活を支えます 。
- 一家の働き手が亡くなった時のため(遺族年金): 家族を支えていた方が亡くなった場合に、残された家族の生活を支えます 。
日本では「国民皆年金」といって、原則として20歳から60歳未満のすべての人がいずれかの公的年金に加入することになっています 。
日本の年金は「3階建て」
よく「年金は3階建て」と例えられます。これは、年金の仕組みが3つの層で構成されているからです 。
- 1階:国民年金(基礎年金) これは年金制度の土台となる部分で、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します 。自営業者、会社員、学生、無職の人など、立場に関わらず共通の年金です。
- 2階:厚生年金 主に会社員や公務員が加入する年金です 。国民年金に上乗せされる形で、より手厚い保障が受けられます。
- 3階:私的年金など 1階・2階の公的年金だけでは不安な場合や、より豊かな老後を送りたい場合に、自分で準備する年金です 。iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業年金、個人年金保険などがこれにあたります。
1階部分:国民年金(基礎年金)のキホン
まずは、年金制度の土台である国民年金について見ていきましょう。
誰が加入するの?3つのタイプ
国民年金の加入者は、働き方などによって主に3つのタイプに分けられます 。
- 第1号被保険者: 自営業者、農業従事者、学生、無職の人などです。保険料は自分で納めます 。
- 第2号被保険者: 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人です。国民年金の保険料は、厚生年金の保険料に含まれています 。
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫)で、一定の収入未満の人です。自分で保険料を納める必要はありません 。
保険料はいくら?どうやって納めるの?
第1号被保険者の場合、国民年金の保険料は収入にかかわらず一律です。令和6年度(2024年4月~2025年3月)の保険料は、月額16,980円です 。この金額は毎年見直されます。納付書を使って金融機関やコンビニで支払うほか、口座振替やクレジットカード、スマホ決済なども利用できます 。
困ったときのサポート制度(免除・猶予)
経済的な理由で保険料を納めるのが難しい場合には、申請によって保険料の支払いが免除されたり、猶予されたりする制度があります 。学生向けの「学生納付特例制度」もその一つです 。ただし、免除や猶予を受けた期間は、将来もらえる年金額が減ってしまうことがあるので注意が必要です。後から保険料を納める「追納」も可能です 。
どんな時に、いくらくらいもらえるの?
国民年金からは、主に以下の3種類の年金が受け取れます。
- 老齢基礎年金: 原則として65歳から受け取れる、老後の生活のための年金です 。20歳から60歳までの40年間、きちんと保険料を納めた場合、令和6年度・7年度の満額は年額816,000円(月額68,000円)です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。納めた期間が短いと、その分もらえる額も少なくなります。
- 障害基礎年金: 病気やケガで法令に定められた障害の状態になった場合に受け取れます 。年金額は障害の程度などによって決まります。例えば令和7年度では、2級障害で子なしの場合、年額831,700円です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。
- 遺族基礎年金: 国民年金の加入者などが亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます 。例えば令和7年度では、子1人の配偶者が受け取る場合、年額1,071,000円(831,700円+子の加算239,300円)です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。
2階部分:厚生年金のキホンをチェック!
次に、会社員や公務員などが加入する厚生年金です。
誰が加入するの?
会社や役所などに勤めている人が加入します 。厚生年金に加入すると、自動的に国民年金の第2号被保険者にもなります 。
保険料はどうやって決まるの?
厚生年金の保険料は、毎月の給与やボーナス(賞与)の額に応じて決まります 。保険料率は現在18.3%で固定されており、これを会社(事業主)と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。本人の負担分は、給与や賞与から天引きされるのが一般的です 。この保険料には国民年金の保険料も含まれています 。
どんな時に、いくらくらいもらえるの?
厚生年金からも、国民年金と同様に老齢・障害・遺族の3つのケースで年金が支給されますが、これらは国民年金の基礎年金に上乗せされる形になります 。
- 老齢厚生年金: 原則65歳から、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。年金額は、厚生年金に加入していた期間や、その間の給与・賞与の額(これを「報酬」といいます)によって計算される「報酬比例部分」が中心です 。つまり、長く勤めてお給料が高かった人ほど、もらえる年金額が多くなる傾向があります。
- 障害厚生年金: 厚生年金加入中に初診日がある病気やケガで障害の状態になった場合に、障害基礎年金に上乗せして支給されます 。障害の等級(1級~3級)や報酬額によって年金額が決まります。
- 遺族厚生年金: 厚生年金の加入者などが亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母など優先順位あり)に支給されます 。原則として、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安となります 。
3階部分:もっと手厚く!自分で備える年金
公的年金だけではちょっと心配…という方や、もっとゆとりのある老後を送りたいという方は、3階部分にあたる私的年金などを活用できます。
- iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金): 自分で掛金を積み立て、自分で運用方法を選んで将来の年金を作る制度です 。最大の魅力は税制優遇! 掛金が所得控除になったり、運用益が非課税になったりします 。原則60歳から受け取れます 。
- 企業年金(企業型DCなど): 会社が従業員のために用意してくれる年金制度です 。企業型確定拠出年金(企業型DC)では、会社が掛金を出し、従業員自身が運用方法を選びます 。退職金の一部として導入している会社もあります。
- 国民年金基金: 自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者のための上乗せ年金制度です 。厚生年金のない第1号被保険者にとって、老齢基礎年金にプラスできる心強い味方です。掛金は全額所得控除の対象になります 。
- 個人年金保険: 生命保険会社などが扱っている貯蓄型の保険商品です 。毎月コツコツ保険料を払い込み、将来年金として受け取ります。将来受け取る金額が決まっている「定額型」や、運用実績によって金額が変わる「変額型」など、様々なタイプがあります 。一定の条件を満たせば、生命保険料控除(個人年金保険料控除)の対象になり、税金の負担が軽くなることもあります 。
年金をもらう時のポイント
いざ年金をもらう年齢になったとき、知っておきたいポイントがあります。
いつからもらう?繰上げ・繰下げ受給
老齢年金は原則65歳からですが、希望すれば受け取り開始時期を早めたり(繰上げ受給)、遅らせたり(繰下げ受給)することができます 。
- 繰上げ受給: 60歳から64歳の間に早めてもらうことができます。早くからもらえるメリットがありますが、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%減額され、その減額率は一生続きます(昭和37年4月2日以後生まれの方)。
- 繰下げ受給: 66歳から75歳の間で遅らせてからもらうことができます 。遅らせるメリットとして、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、その増額率も一生続きます 。
どちらが良いかは、ご自身の健康状態やライフプランによって異なりますので、慎重に検討しましょう。
自分の年金情報をチェック!「ねんきんネット」
「ねんきんネット」は、日本年金機構が提供しているインターネットサービスです 。これまでの年金加入記録や、将来もらえる年金の見込み額などを、スマートフォンやパソコンでいつでも確認できます 。登録も簡単なので、ぜひ一度アクセスしてみてください。
年金制度のこれから
日本の年金制度は、少子高齢化という大きな課題に直面しています 。年金を支える現役世代が減り、年金を受け取る高齢者が増えているため、制度を持続可能なものにするための見直しが続けられています。
最近でも、パートタイムで働く人が厚生年金に加入しやすくなったり(適用拡大)、働きながら年金をもらう場合のルールが見直されたり(在職老齢年金制度の見直し)、年金の受け取り開始時期の選択肢が広がったり(繰下げ受給の上限年齢引き上げ) といった改正が行われています。
おわりに:未来の自分のために、今できること
年金制度は、私たちの長い人生を支える大切な仕組みです。少し複雑に感じるかもしれませんが、まずは関心を持つことが第一歩。そして、ご自身の年金記録を確認したり、将来設計を考えたりする中で、iDeCoや個人年金保険といった私的年金の活用も検討してみましょう。
この記事が、皆さんの年金に対する「?」を少しでも「!」に変えるお手伝いができれば幸いです。詳しいことや個別の相談は、お近くの年金事務所や「ねんきんネット」で確認してみてくださいね。




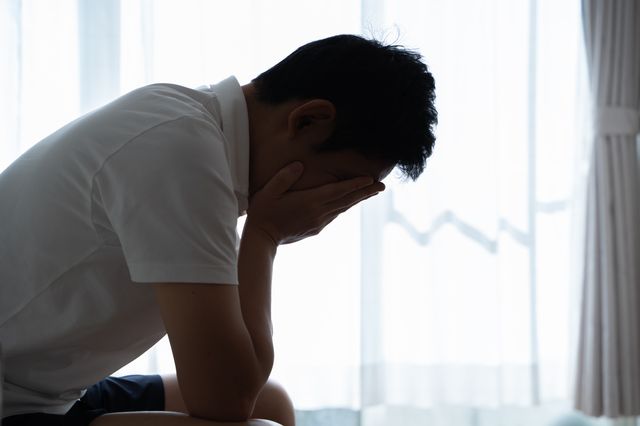

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。