男性の産後うつ支援はなぜここまで紛糾するのか?SNSで交錯する賛否の深層
男性の産後うつが火種に
2025年3月、男性の「産後うつ」支援をめぐる議論がSNS、特にXで盛り上がっています。きっかけは、こども家庭庁の研究班が発表した「父親支援マニュアル」や、父親のメンタルヘルスを扱った報道が拡散されたことです。賛成する人からは「男性も支援が必要です」との声が上がり、反対する人からは「名称がおかしいです」「甘えじゃないですか?」と批判が飛び出しています。コメント欄は感情的なやりとりで埋まり、議論は落ち着く気配がありません。なぜ、これほどまでに紛糾しているのでしょうか。その背景を探ってみます。
名称論争:「産後うつ」は男性に当てはまるのか
「産後うつ」という言葉そのものが、まず話題の火種になっています。Xでは「産んでないのに産後うつって何ですか?」「育児うつと呼べばいいじゃないですか」との投稿が相次ぎ、名称への違和感が反発を呼んでいます。確かに、「産後」は出産直後の時期を指し、女性のホルモン変化や身体的負担と結びついてきた歴史があります。この言葉を男性に使うことで、女性の経験が軽く見られていると感じる人が少なくありません。また、「うつ」という深刻なイメージが、男性の育児ストレスを大げさに扱っているとの印象を与え、笑いものや反感の対象にもなっています。言葉の持つニュアンスの違いが、感情的な対立を大きくしているのです。
性別間の不公平感:女性の経験との比較が波紋を呼ぶ
女性の産後うつとの比較が、さらに議論をややこしくしています。研究では「父親の産後うつリスクは母親と同程度」とされていますが、これが「女性の方が大変なのに同等扱いはおかしいです」との反発を招いています。女性の産後うつは、出産による身体的ダメージや社会的な孤立感が背景にあり、長年支援が求められてきた課題です。一方、男性のそれは認知も支援も遅れていて、急に注目されたことで「今さら男性を優先するんですか?」との不公平感が生まれています。SNSでは「母親の支援が先でしょう」「男性の話を持ち出すのはズレてます」との声が飛び交い、性別間の経験の違いをめぐる感情がぶつかっています。
支援の正当性をめぐる分断:必要か、甘えか
支援の必要性そのものが、意見の分かれ目になっています。育児参加が進む今、男性も仕事と家庭の両立やパートナーとの関係変化でストレスを抱え、うつ症状に陥るケースが増えています。「男性の支援は家族全体のためです」と訴える声がある一方、「我慢できないなら育児しないでください」「自己責任じゃないですか」と切り捨てる意見も根強いです。Xでは、父親としての苦悩を吐露する投稿に共感が集まる一方、「そんなことで弱音を吐かないでください」との反応もあります。背景には、男性に「強くあるべき」と求める昔ながらの考え方と、育児に積極的に関わる新しい父親像とのギャップがあります。この価値観のズレが、支援をめぐる議論を感情的なものにしているのです。
社会の認知不足とタイミングの悪さ:議論が収まらない背景
男性の産後うつが注目されるタイミングも、紛糾の理由の一つになっています。女性の産後うつ支援が少しずつ進んでいるものの、まだ十分とは言えない状況です。そんな中で「男性の問題」が浮上したことで、「まだ女性の課題が解決してないのに」との苛立ちが広がっています。また、男性のメンタルヘルスがこれまであまり認知されてこなかった歴史もあり、「今さら取り上げるのは遅すぎます」との皮肉や、「新手の流行りものですか」と疑う声も出ています。課題の認知度や解決の優先順位のズレが、議論をさらに熱くしているのです。
結論:紛糾の根底にあるものと今後の課題
男性の産後うつ支援をめぐる紛糾は、単なる言葉や支援の賛否を超えた深い問題を映し出しています。性別役割が大きく変わる中で、男性も女性も新しいストレスに直面し、それをどう受け止め支援するかの社会的な合意がまだできていません。また、メンタルヘルスの理解が広がる一方で、誰をどう優先するかの認識の違いが対立を生んでいます。この議論を落ち着かせるには、名称や支援の形にこだわるよりも、個々の経験を尊重しつつ家族全体の幸せを考える視点が必要です。対立を超えて、誰もが支えられる社会への一歩が、今求められているのではないでしょうか。

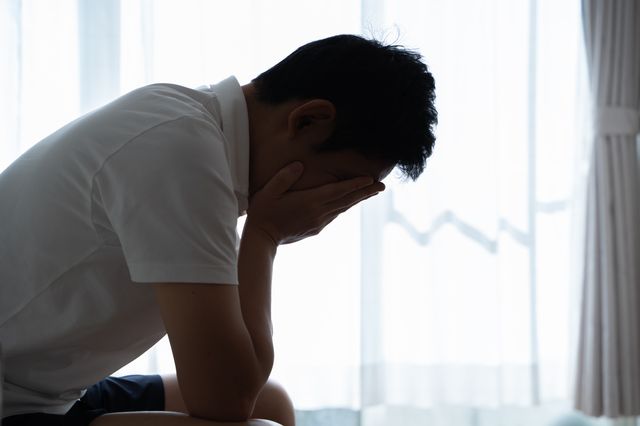



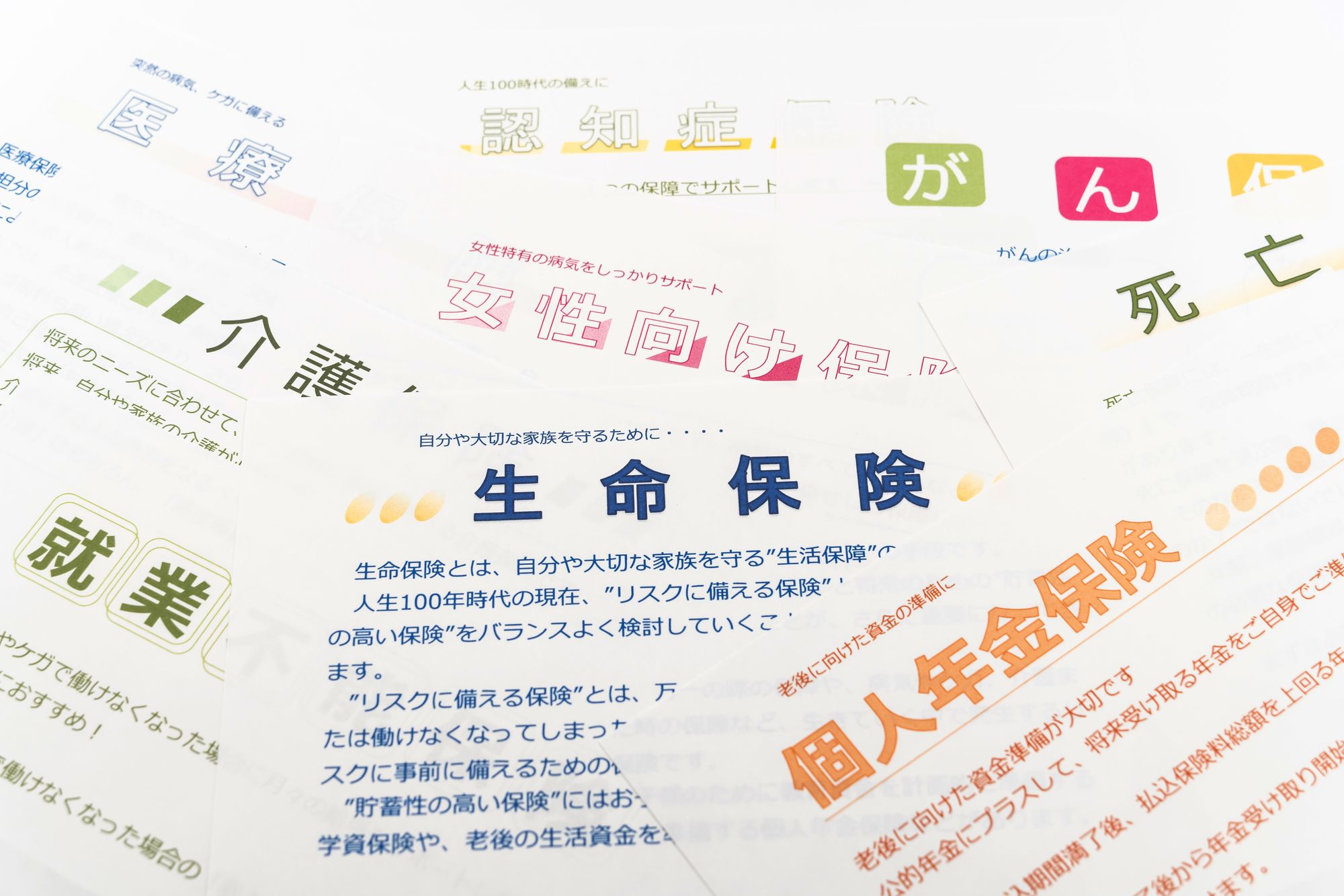
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。