2025年「106万円の壁」撤廃でパート・アルバイトの働き方はどう変わる?社会保険の新常識
長年の課題「106万円の壁」とは?なぜ見直しが必要とされたのか
長年にわたり、パートやアルバイトとして働く短時間労働者が、年収を一定額以下に抑えようとする「働き控え」は、日本の社会における構造的な課題でした。この背景には、年収が特定の基準を超えると、社会保険料の負担が発生し、結果として手取り収入が減少するという「年収の壁」の存在があります 。特に「106万円の壁」は、特定の勤務条件を満たす短時間労働者が、厚生年金や健康保険の加入義務を負うボーダーラインとして、共働き世帯の家計や働き方に大きな影響を与えてきました 。
この「働き控え」は、社会全体に複数の深刻な影響をもたらしています。多くの労働者が「手取りが減る」ことを避けるために意図的に年収を106万円未満に抑えるため、本来は供給できるはずの労働時間やスキルが活用されていませんでした 。また、近年では最低賃金の引き上げによって、短時間勤務でもこの壁を容易に超えてしまう地域が増え、問題はさらに顕著になっています 。労働者側の就業調整は企業側の人手不足を深刻化させる一因にもなっており、今回の制度改正はこれらの課題を解消することを目的としています 。
「年収の壁」から「時間の壁」へ:変わる社会保険の加入基準
今回の年金制度改革は、単に「106万円の壁」を撤廃するだけではありません。少子高齢化が進む現代の労働市場に適応し、持続可能な社会保障制度を再構築するという広範な目的を持っています 。その具体的なステップとして、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用要件が大きく見直されます。
まず、最も大きな変更は、2026年10月に予定されている「月額8.8万円以上」または「年収106万円以上」という賃金要件の撤廃です 。これにより、短時間労働者の社会保険加入条件から年収基準がなくなり、これまでの「106万円の壁」という概念は実質的に消滅します。
賃金要件の撤廃に続き、企業の規模要件も段階的に見直されます。現在の社会保険の適用対象は原則として「従業員数51人以上」の企業に限定されていますが 、これも将来的には撤廃される方針です 。
- 2027年10月: 企業規模要件も撤廃される方向で検討されています 。
- 2035年10月: 最終的には、企業規模を問わず、すべての企業で短時間労働者の社会保険加入が義務化される見込みです 。
このように段階的に制度が拡大されることで、将来的に社会保険加入の主な基準は、「週20時間以上」という労働時間要件に集約されることになります 。これは、これまでの「年収の壁」に代わり、「時間の壁」が新たな就業調整の指標になることを意味します。例えば、時給1,300円で週19.5時間働く場合、月収は約10万9,000円となり、年収106万円の壁は超えますが、「週20時間以上」の要件を満たしていないため、社会保険未加入のままとなります 。逆に、時給1,000円で週20時間働く場合は、月収が8.8万円未満でも強制加入の対象となります 。
混同しやすい「年収の壁」を徹底解説
「106万円の壁」の撤廃は、働く人々が意識すべき複数の「年収の壁」のごく一部の変更に過ぎません 。今回の制度変更後も、働き方を考える際には、税制や扶養制度に関わる他の基準を正確に把握しておくことが不可欠です。
それぞれの「壁」がどのように私たちの家計に影響するかを整理してみましょう。
- 住民税の壁(約100万円): この年収を超えると、本人の住民税が課税され始めます。地域によって基準額は多少異なりますが、年収100万円を超えると均等割と所得割が課税されます 。
- 所得税の壁(103万円): 本人の年収が103万円を超えると、所得税が課税され始めます。また、以前は配偶者控除の基準でもありましたが、制度改正によりその役割は薄れています 。
- 社会保険の壁(106万円): 今回撤廃される対象です。これまでは賃金・企業規模・労働時間の条件を満たすと社会保険への加入義務が発生し、保険料は労使折半で負担していました 。
- 社会保険の壁(130万円): 106万円の壁の条件に該当しない場合でも、この年収を超えると配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、年間30万円前後の負担が発生する可能性があります 。
- 配偶者特別控除の壁(150万円): 妻の年収が150万円を超えると、夫が受けられる配偶者特別控除の控除額が段階的に減額され始めます。控除額は年収201.6万円まで減少します 。
このように、「106万円の壁」の撤廃は社会保険加入の条件を「年収」から「労働時間」に変えるものであり、税制や配偶者控除の「壁」は引き続き存在します。
手取りは一時的に減る?新制度での収支シミュレーション
社会保険に新たに加入することになった場合、最も気になるのが「手取り収入の減少」でしょう 。これまで配偶者の扶養内で働いていた人は、給与から厚生年金保険料と健康保険料が天引きされるため、年収が同じでも手取りが減るという事態が発生します 。
例えば、年収106万円で社会保険に加入した場合、年間でおよそ15万円の保険料負担が発生すると試算されています 。この影響は大きく、年収が129万円から130万円になった途端に手取りが約17万円も減る「逆転現象」にも似たインパクトをもたらす可能性があります 。
このような手取り減少のショックを緩和するため、政府は時限的な措置として、導入から3年間は本人の保険料負担を軽減する「年収の壁・支援強化パッケージ」などの支援策を講じています 。
あくまで概算ですが、年収ごとの手取りの変化を見てみましょう。現行制度(社会保険未加入)での年収106万円の手取りが約103万円、年収110万円の手取りが約107万円、年収120万円の手取りが約117万円、年収130万円の手取りが約127万円だったとします 。社会保険に新たに加入すると、手取りは一時的に減少します。年収106万円で加入した場合、手取りは約93万円となり、約10万円の減少が見込まれます。年収120万円では手取りが約102万円となり、約15万円の減少が見込まれます 。
見過ごせない長期的なメリットとキャリアの再設計
短期的な手取り減少というデメリットがある一方で、社会保険に加入することには、それを補って余りある長期的なメリットがあります 。
まず、将来の年金が増額されます。国民年金に加えて厚生年金に加入することで、将来受け取る老齢年金が手厚くなります。厚生年金は生涯にわたる保険料の納付額に応じて年金額が計算されるため、加入期間が長くなるほど、将来の年金受給額も増加します 。これは、個人の老後生活の安定に直結する大きなメリットです。
次に、手厚い社会保障を受けられるようになります。厚生年金に加入することで、病気やケガで休業した場合の傷病手当金や、出産手当金、障害年金、遺族年金など、国民健康保険や国民年金だけでは得られない充実した保障が受けられます 。これらの保障は、万が一の事態に備える上で非常に重要です。
さらに、働き方の自由度も向上します。年収の壁を意識して労働時間を調整する必要がなくなるため、自身の希望に応じてより長く働いたり、キャリアアップを目指したりすることが可能になります 。
今回の制度変更は、従来の「扶養内」という単一の働き方モデルから、個々の労働者が自律的に自身のライフプランを設計する、という新しい働き方への移行を促しています。手取り減少を避けつつ、柔軟に働くための選択肢の一つとして、複数の勤務先で働く「ダブルワーク」を選ぶ人も増えるかもしれません 。ただし、ダブルワークの場合、社会保険の加入条件を両方の勤務先で満たすと、それぞれの給与を合算して社会保険料が計算されるため、手続きが複雑化する点には注意が必要です 。
企業が直面する課題と政府の支援策
「106万円の壁」撤廃は、企業側にも大きな影響を与えます。これまで社会保険に未加入だった従業員が新たに加入することで、企業は従業員と同額の社会保険料(労使折半分)を負担する必要が生じ、人件費コストが増加します 。また、労務管理も複雑化し、パートやアルバイトのシフト変動に合わせて加入対象者を正確に把握し、手続きを行う体制の再構築が求められます 。
こうした課題に対し、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」のような支援策を用意しています。これは、手取り減少を補う取り組みを行う企業に対し、助成金を支給する時限的な支援策です 。しかし、この支援策は恒久的な解決策ではなく、企業が保険料を肩代わりする仕組みも労使合意が前提となるなど、課題も指摘されています 。
企業は、政府の支援策を最大限に活用しつつも、従業員への丁寧な説明や個別面談を通じて、制度変更への理解を促し、優秀な人材の定着・確保に努めることが、今後の競争力を左右する重要な要素となるでしょう 。
まとめ
2026年10月に予定されている「106万円の壁」撤廃は、パート・アルバイトで働く人々の働き方を根本から見直す大きな転機となります。この制度改正は、短期的な手取り減少というデメリットと、長期的な年金増額や手厚い社会保障というメリットの二律背反を個人に突きつけます。
この新しい時代においては、目先の収入だけでなく、将来のライフプランやキャリア設計などを総合的に考慮し、自身の価値観に合った働き方を自ら選択することが求められます。




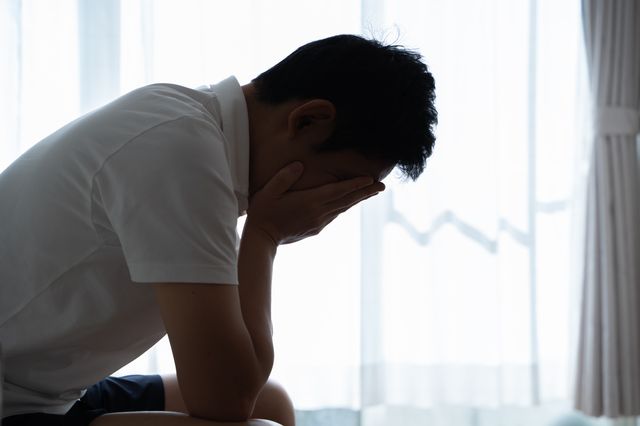

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。