身内が亡くなったら?もしもの時に慌てないための準備と手続き
身内が亡くなったらまず何をする?【結論】事前の準備が重要です
大切な身内が亡くなったら、深い悲しみの中で、多くの手続きや決断に迫られます。しかし、事前に「病院 死亡後 流れ」や準備すべきことを知っておけば、いざという時に冷静に対応でき、故人との最期の時間を大切に過ごすことが可能です。この記事では、ご逝去直後の対応から葬儀の準備、死亡後の手続きまでを、順を追って分かりやすく解説します。
病院で亡くなった後の流れ【逝去直後から搬送まで】
身内が病院で亡くなられた場合、限られた時間の中で迅速な対応が求められます。一般的な病院 死亡後 流れを把握しておきましょう。
医師による死亡確認とエンゼルケア
ご逝去後、まずは医師による死亡確認が行われ、「死亡診断書」が作成されます。その後、看護師によって故人のお体を清め、身なりを整える「エンゼルケア」が施されます。病院によっては、故人の唇を水で湿らせる「末期の水」の儀式を行うこともあります。
霊安室への安置とタイムリミット
エンゼルケアが終わると、ご遺体は病院内の霊安室へ移されます。しかし、病院の霊安室はあくまで一時的な安置場所であり、利用できる時間は数時間から長くても1日程度が一般的です。そのため、ご家族は速やかにご遺体の搬送先を決めなければなりません。
葬儀社への連絡と搬送依頼
霊安室の利用時間に限りがあるため、速やかに葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送を依頼する必要があります。事前に葬儀社を決めておくと、この段階で慌てることなくスムーズに依頼できます。病院から葬儀社を紹介されることもありますが、ご自身の希望に合うとは限らないため、可能であれば事前に調べておくことが望ましいです。
死亡診断書の受け取りとコピーの保管
医師から「死亡診断書」を必ず受け取ります。この書類は、死亡届の提出や火葬許可の申請など、あらゆる死亡後の手続きに必要となる非常に重要なものです。原本は役所に提出すると返却されないため、必ず事前に複数枚コピーを取っておきましょう。生命保険の請求や年金手続きなどで必要になります。
いざという時に備える7つの事前準備
もしもの時に冷静に対応するため、元気なうちから準備できることがあります。
1. 信頼できる葬儀社の選定(事前相談の活用)
葬儀は短時間で多くの決断を迫られます。そのため、事前に信頼できる葬儀社を見つけておくことが最も重要な準備の一つです。「葬儀社 事前相談」のサービスを活用し、複数の会社から資料請求や見積もり取得を行いましょう。費用やサービス内容、スタッフの対応などを比較検討することで、納得のいく葬儀社を選ぶことができます。
2. 葬儀費用の目安と資金計画
葬儀にはまとまった費用が必要です。葬儀の形式や規模によって費用は大きく変動しますが、近年の調査では家族葬で100万円前後が一つの目安とされています。生命保険や預貯金を確認し、費用をどのように捻出するか考えておきましょう。また、国民健康保険などから「葬祭費」として補助金が支給される制度もあるため、お住まいの自治体の情報を確認しておくことをお勧めします。
3. 故人の意思の確認(エンディングノートなど)
可能であれば、延命治療の希望、葬儀の形式、納骨の方法などについて、ご本人の意思を事前に確認しておきましょう。エンディングノートに記されている場合は、その内容を尊重することで、ご家族の迷いや負担を軽減できます。
4. 親族・関係者の連絡先リスト作成
訃報を知らせるべき親族や友人、関係者の連絡先をリスト化しておくと、いざという時にスムーズに連絡できます。氏名、電話番号、関係性などをまとめておき、連絡の優先順位も決めておくと良いでしょう。
5. 遺影写真の候補選び
葬儀で使用する遺影写真は、故人らしい表情の写真を選びたいものです。慌てて探すことがないよう、元気なうちに写りの良い写真をいくつか候補として選んでおくと安心です。
6. 宗教・宗派の確認
葬儀の儀式は宗教・宗派によって大きく異なります。故人の信仰や、菩提寺(お付き合いのあるお寺)の有無を事前に確認しておくことは非常に重要です。不明な場合は、親族に確認しておきましょう。
7. 喪服や持ち物のチェック
ご自身の喪服や数珠、黒い靴、バッグなどが揃っているかを確認しておきましょう。事前に準備しておくことで、直前に慌てて買いに走る必要がなくなります。
葬儀社との打ち合わせで確認すべき必須ポイント
葬儀社が決まったら、具体的な内容について打ち合わせを行います。後悔しないために、以下の点は必ず確認しましょう。
葬儀プランと費用の詳細見積もり
プランに含まれるサービス内容(祭壇、棺、人件費など)と、含まれないもの(飲食費、返礼品、宗教者へのお礼など)を明確にしましょう。必ず総額だけでなく、項目ごとの詳細な見積書をもらい、不明な点は全て質問してください。
葬儀の日程と場所の決定
火葬場の空き状況や宗教者の都合、遠方の親族の移動時間などを考慮して、通夜や葬儀・告別式の日程を決定します。場所についても、葬儀社の斎場、公営斎場、寺院など、参列人数やアクセスを元に最適な場所を選びます。
供花・供物・返礼品の手配
参列者へのお礼となる返礼品や、香典返しについて打ち合わせます。近年では、香典をいただいた額に応じて後日品物を送る「後返し」が一般的です。どのような品物があるのか、カタログなどを見せてもらいましょう。
火葬と納骨に関する相談
火葬の日時や、火葬後の遺骨をどうするのか(お墓への納骨、納骨堂、散骨など)についても相談します。故人の希望や家族の意向に沿って、最適な方法を検討しましょう。
葬儀後に必要な手続き一覧
葬儀が終わった後も、様々な手続きが待っています。期限が設けられているものも多いため、計画的に進めましょう。
役所への各種届出(死亡届など)
身内が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を役所に提出する必要があります。その他、健康保険証の返納や年金の受給停止手続きなど、様々な死亡後の手続きが発生します。
相続に関する手続きの開始
遺言書の有無を確認し、相続人を確定させ、遺産分割協議を進めます。預貯金の名義変更や不動産の登記など、専門的な知識が必要になる場合も多いため、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
悲しみと向き合う心のケア
大切な人を失った悲しみは、すぐに癒えるものではありません。無理に気持ちを抑えず、家族や友人と故人の思い出を語り合うなど、ご自身のペースで悲しみと向き合う時間を持つことが大切です。一人で抱え込まず、時には専門のカウンセリングなどを頼ることも選択肢の一つです。
まとめ:事前の備えで、心穏やかなお見送りを
予期せぬ別れは、誰にとっても辛く悲しいものです。しかし、「身内が亡くなったらどう動けばいいのか」を事前に少しでも知っておくことで、精神的な負担は大きく軽減されます。
葬儀社 事前相談などを活用して情報を集め、必要な準備をしておくことで、いざという時にも冷静に対応でき、故人様とのお別れの時間を心穏やかに過ごすことができるでしょう。この記事が、もしもの時のための「備え」の一助となれば幸いです。



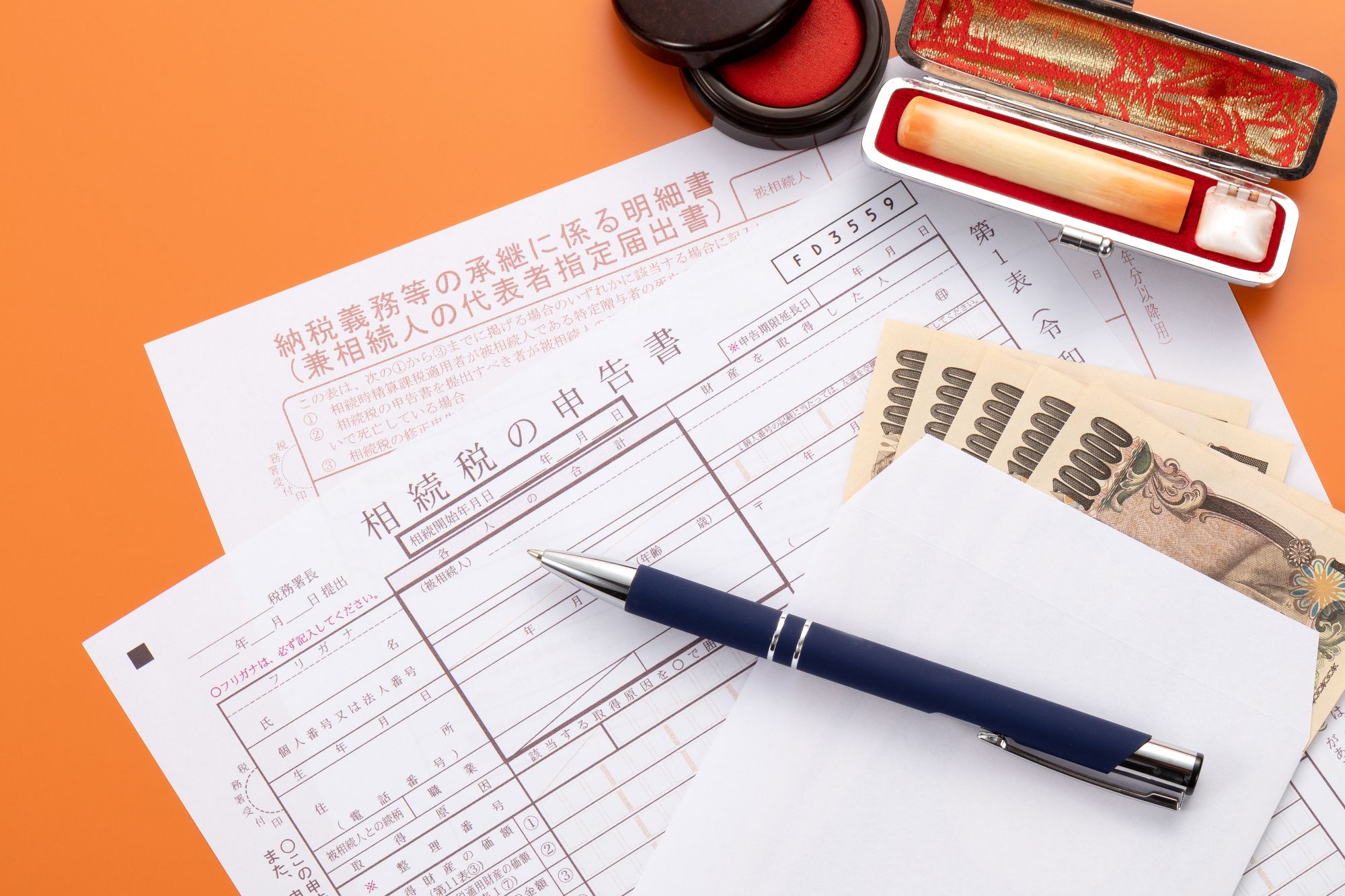


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。