相続税はいくらから?払う人・払わない人の境界線と計算方法
「親の遺産を相続することになったけど、相続税って結局いくらから払うの?」「自分は対象になるんだろうか?」と不安に思っていませんか?
結論から言うと、相続税を支払う必要があるのは、遺産の総額が「基礎控除額」という一定のラインを超えた場合のみです。実際、相続税の申告が必要になるのは亡くなった方のうち1割未満で、9割以上の人は相続税を払う必要がありません。
この記事では、あなたが相続税を「払う人」なのか「払わない人」なのかを判断するための境界線(基礎控除)の計算方法から、税金の負担を軽くする特例、専門家への相談の目安まで、分かりやすく解説します。
結論:相続税を払うのは約1割!課税の分かれ目「基礎控除」とは
相続税がかかるかどうかの最初の、そして最大の関門が**「基礎控除」**です。相続する財産の合計額が、この基礎控除額より少なければ、相続税は1円もかからず、税務署への申告も原則不要です。
すぐわかる!基礎控除額の計算式
基礎控除額は、以下のシンプルな式で計算できます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この式の通り、基礎控除額は誰にでも一律に適用される「3,000万円」の部分と、法定相続人の数に応じて変動する「600万円 × 人数」の部分で構成されています。つまり、相続人が多いほど非課税枠が大きくなり、相続税がかかりにくくなります。
【計算例】
-
相続人が妻と子1人(計2人)の場合
- 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
- → 遺産総額が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
-
相続人が子2人のみ(計2人)の場合
- 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
- → 遺産総額が4,200万円以下なら相続税はかかりません。
【重要】法定相続人の数え方と注意点
基礎控除の計算で最も重要なのが「法定相続人の数」を正確に把握することです。法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことで、以下のルールがあります。
- 配偶者:常に法定相続人になります。
- 子(第一順位):子が最も優先されます。子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わって相続人になります(代襲相続)。
- 父母(第二順位):子がいない場合に相続人になります。
- 兄弟姉妹(第三順位):子も父母もいない場合に相続人になります。
【数え方のポイント】
- 相続放棄した人:相続を放棄した人がいても、その人を含めて基礎控除の人数を計算します。
- 養子:被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
あなたは払う?払わない?相続税3ステップで簡単セルフチェック
ご自身が相続税の対象になるか、以下の3ステップで大まかに確認してみましょう。
ステップ1:プラスの財産とマイナスの財産を把握する
まず、亡くなった方が遺した財産をすべてリストアップします。相続税の対象となる財産には、プラスの財産だけでなく、みなし相続財産も含まれます。
- プラスの財産:預貯金、不動産(土地・家屋)、株式、自動車、貴金属など
- みなし相続財産:生命保険金、死亡退職金など
- マイナスの財産:借金、未払いの税金や医療費など
- 葬式費用:これもマイナスの財産として差し引けます。
ステップ2:課税対象になる財産の総額を出す
次に、課税対象となる遺産の正味価額を計算します。
(プラスの財産 + みなし相続財産) - (マイナスの財産 + 葬式費用) = 課税対象の遺産総額
※生命保険金や死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、その金額を差し引いてから加算します。
ステップ3:基礎控除額と比べて判断する
最後に、ステップ2で算出した「課税対象の遺産総額」と、ご自身のケースの「基礎控除額」を比べます。
- 遺産総額 ≦ 基礎控除額 → 相続税はかからない(申告も原則不要)
- 遺産総額 > 基礎控除額 → 相続税がかかる可能性がある(申告が必要)
この時点で基礎控除額を超えたとしても、すぐに納税額が決まるわけではありません。さまざまな特例や控除を適用することで、税額がゼロになるケースも多くあります。
知らないと損!相続税の負担を軽くする主な特例と控除
基礎控除額を遺産が超えてしまった場合でも、税額を大幅に軽減できる制度があります。ここでは特に影響の大きいものを紹介します。
【影響大】配偶者の税額軽減
配偶者が遺産を相続する場合に使える非常に強力な制度です。以下のいずれか多い金額まで、配偶者が相続した財産には相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
この特例を使えば、ほとんどのケースで配偶者の相続税はゼロになります。ただし、この特例の適用を受けるには、税額がゼロでも相続税の申告が必要です。
【不動産があるなら】小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地を相続した場合、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。自宅の土地の評価額を大幅に下げられるため、相続税額に絶大な効果があります。こちらも適用には相続税の申告が必要です。
【生命保険金】非課税枠の活用
亡くなった方が受け取るはずだった生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、以下の非課税枠があります。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば相続人が3人なら、1,500万円までの生命保険金は非課税となり、課税対象の財産から除外できます。
相続税の計算・申告で迷ったら?専門家(税理士)に相談する目安
相続税の計算や財産評価は非常に複雑です。特に以下のようなケースでは、ご自身で判断せずに相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
- 遺産総額が基礎控除額を明らかに超えそうな場合
- 土地や非上場株式など、評価が難しい財産がある場合
- 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使いたい場合
- 相続人の間で意見がまとまらない可能性がある場合
相続税の申告のうち、約86%は税理士が関与しています。専門家に依頼すれば、正確な申告はもちろん、利用できる特例を漏れなく適用し、最適な遺産分割のアドバイスも受けられます。
まとめ:まずは「基礎控除」を計算し、ご自身の状況を把握しよう
相続税がかかるかどうかは、遺産総額が「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算される基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
まずは法定相続人が何人いるかを確認し、ご自身のケースの基礎控除額を計算してみましょう。そして、大まかな遺産総額と比較することで、相続税を払う必要があるのか、その可能性が見えてきます。
もし基礎控除を超えそうで不安な場合や、手続きが複雑で分からない場合は、決して一人で抱え込まず、早めに専門家である税理士に相談することが、円満で安心な相続への近道です。

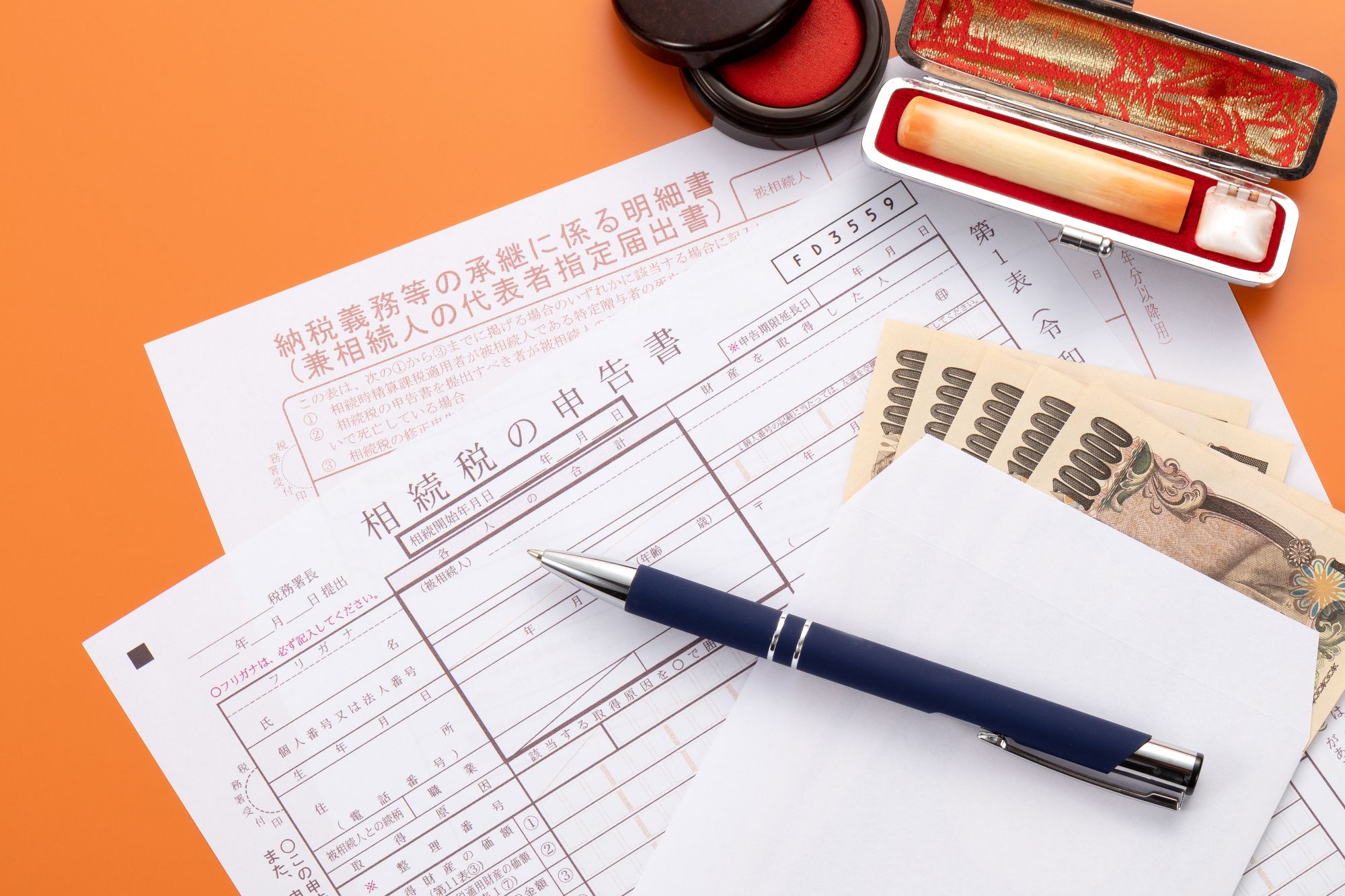




まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。