「日本って凄いでしょ?」と外国人に言わせる日本人。その「ナルシシズム」が気持ち悪い
テレビをつければ、外国人観光客を捕まえて「日本のココがすごい!」と言わせる番組。YouTubeを開けば、「日本に来て人生が変わった!」と涙ながらに語るサムネイル。
正直、見ていて「気恥ずかしい」を通り越し、「背筋が寒くなるような気味の悪さ」を感じることはないでしょうか?
それは、褒められているから照れているのではありません。いい大人が、他人に「ねえ、僕のこと好き? すごいと思ってくれてる?」と執拗に確認して回るような、未熟で哀れな姿を、公共の電波やネットで見せつけられているから感じる嫌悪感です。
この記事では、その「気持ち悪さ」の正体を解剖します。私たちが陥っているのは、他国を見下す愛国心ですらなく、ただひたすらに自信を失った国がすがる「自己慰撫(セルフ・コンフォート)」の病理です。
1. 外国人は「ホメてくれるペット」ではない
この手のコンテンツが放つ独特の「気持ち悪さ」。その最大の要因は、そこに登場する外国人が、対等な人間として扱われていないことにあります。
彼らは「日本を称賛する」という役割を期待された、単なる「舞台装置」や「都合のいい人形」に過ぎません。「日本のトイレは魔法だ!」「日本人は神様みたいに優しい!」……そう言わせるためにマイクを向け、期待通りの言葉が出れば「ほら見ろ」と満足げに頷く。
そこにあるのは、異文化への敬意ではありません。あるのは、「外国人にひれ伏される自分たち」を見て悦に入る、歪んだ優越感です。外国人を、自分たちの自尊心を満たすための道具(あるいはペット)のように扱っている傲慢さが透けて見えるからこそ、心ある視聴者は直感的に「グロテスクだ」と感じるのです。
2. 「凄い」のハードルが下がりきっている哀れさ
さらに痛々しいのは、私たちが誇っている内容の変化です。
かつて日本が世界を席巻していた頃、技術力や経済力といった「実力」で評価されていました。しかし今はどうでしょうか。「四季がある」「水道水が飲める」「店員の愛想がいい」「治安がいい」。
もちろんそれは素晴らしいことですが、これらは「先人が築いた遺産」や「環境」であって、今を生きる私たちの功績ではありません。
世界をリードする産業も、革新的なイノベーションも生み出せなくなった今、私たちは「当たり前のインフラ」や「マナー」といった、誰でも誇れる低いハードルにすがりつき、「まだ日本は凄い」と自分に言い聞かせているのです。
それはまるで、テストの点数が落ち続けているのに、「でも僕は挨拶ができるから凄いんだ」と必死に言い訳をしているようで、見ていて痛々しいものがあります。
3. 「ニッポン・スゴイ」という麻薬中毒
はっきり言いましょう。今の日本社会に蔓延しているのは、自信のなさの裏返しとしての「承認乞食」です。
経済は停滞し、給料は上がらず、かつて見下していたかもしれない近隣諸国に、技術でもエンタメでも追い抜かれつつある。そんな直視したくない現実(没落)から目を逸らすために、「日本スゴイ」という強力な麻薬を打ち続けている状態です。
画面の中で外国人が日本を褒めちぎるたび、私たちは一瞬だけ、現実の閉塞感を忘れ、全能感に浸ることができます。しかし、その「気持ちよさ」に溺れている間も、世界は残酷なまでに先へと進んでいます。
まとめ:鏡を見るのをやめ、現実を見よ
私たちが感じる「気持ち悪さ」の正体。それは、沈みゆく船の上で、必死に鏡に向かって「私は美しい」と唱え続けている集団の異常さです。
外国人からの称賛を乞うのは、もうやめにしませんか。「日本はまだ凄い」と自分を慰めるそのエネルギーがあるのなら、それを「なぜ日本は競争力を失ったのか」「どうすればこの泥沼から抜け出せるのか」という、血の滲むような自己批判と改革に向けるべきです。
「気持ち悪い」と感じるその感覚こそが、まだあなたが正常である証拠です。その違和感を大切にし、甘い称賛の麻薬を拒絶することからしか、日本の再生は始まらないのです。




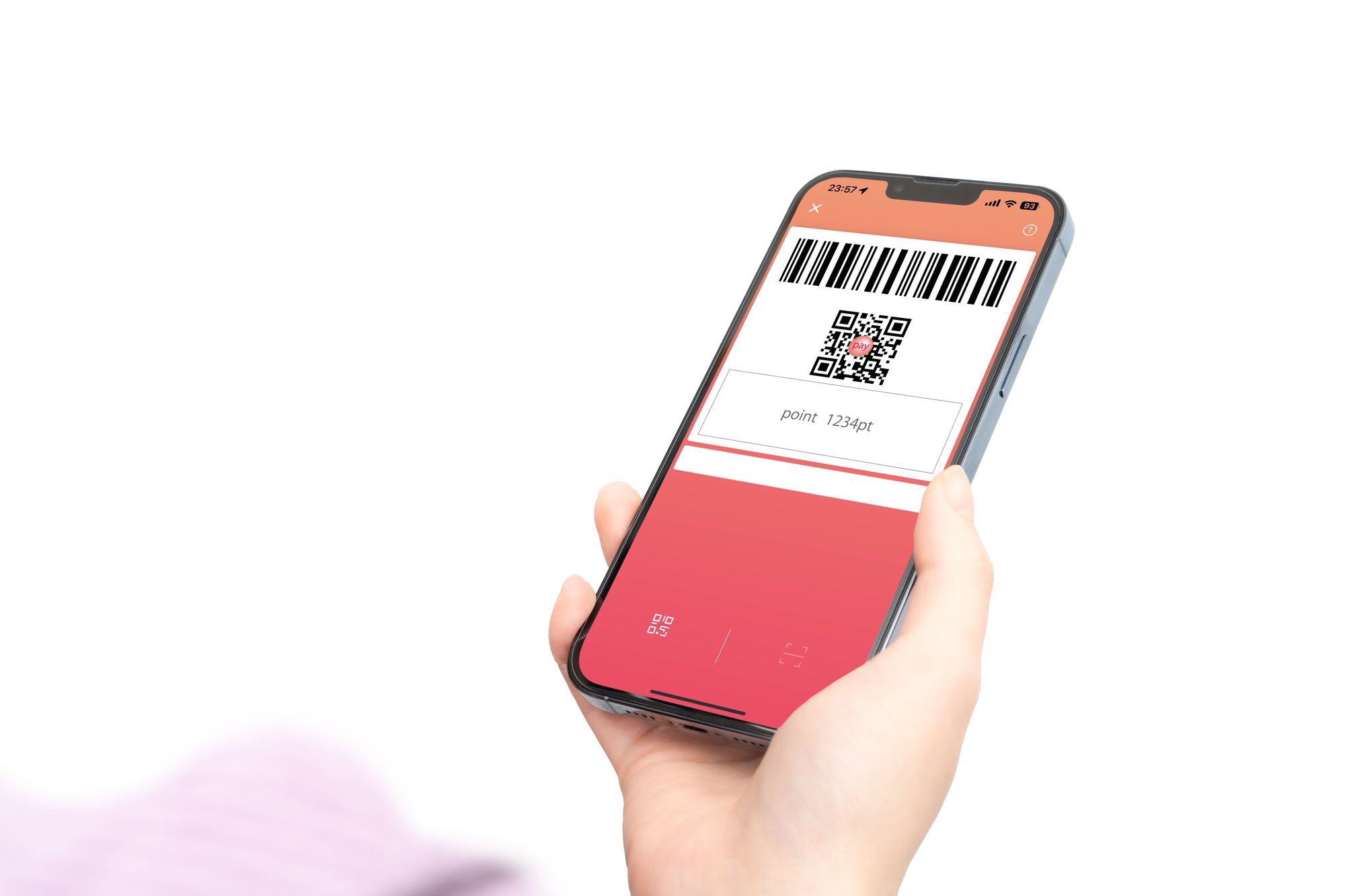

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。