逆境こそ、輝きの源泉。南場智子流「不格好」な挑戦が教えてくれる、自分らしい道の拓き方
「輝く女性」と聞いて、どんな姿を思い浮かべますか? 華やかな経歴、揺るぎない自信、そして圧倒的な成功…。しかし、もしその輝きが、数々の「不格好」な挑戦と、人間味あふれる葛藤の中から生まれてきたものだとしたら?
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の創業者であり、現在は代表取締役会長を務める南場智子さん 。彼女はまた、日本プロ野球界初の女性オーナーとして横浜DeNAベイスターズを率い、女性初の経団連副会長も務めるなど、数々の「女性初」を成し遂げてきたパイオニアです 。しかし、その華々しい肩書の裏には、失敗を恐れず、泥臭く、そしてどこまでも誠実に「コト」に向き合い続けてきた一人の女性の姿があります。彼女の生き様は、私たち、特に変化の多い現代を生きる女性たちにとって、自分らしいキャリアを築き、人生を切り拓いていく上で、大きな勇気とヒントを与えてくれます。
「不格好」こそ強さの源泉:常識を疑い、自分の道を切り拓く
南場さんのキャリアは、まさに挑戦の連続です。津田塾大学を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社 。その後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得し、マッキンゼーでは日本人女性として3人目となるパートナー(役員)にまで上り詰めました 。誰もが羨むようなキャリアパス。しかし彼女は、その安定を自ら手放し、1999年にDeNAを設立します 。当時まだ黎明期だったインターネット業界への、まさにゼロからの挑戦でした。
その原動力は、「一度でいいから、当事者として事業を最後までやり遂げてみたい」という強い想い 。コンサルタントとして数々の企業にアドバイスを送る中で芽生えた、自らが主体となって価値を創造したいという渇望が、彼女を新たなステージへと突き動かしたのです。
しかし、その船出は決して順風満帆ではありませんでした。南場さん自身、著書『不格好経営』の中で、DeNAの創業期を「なにもそこまでフルコースで全部やらかさなくても、と思うような失敗の連続」だったと赤裸々に語っています 。例えば、起業のきっかけとなったオークションサービスでは、外部に委託していたシステム開発が全く進まず、競合に大きく遅れをとるという苦渋を味わいました 。
「マッキンゼーのコンサルタントとして経営者にアドバイスをしていた自分が、これほどすったもんだの苦労をするとは……。経営とは、こんなにも不格好なものなのか」。この言葉には、理想と現実のギャップに直面した彼女の驚きと、それでも前に進もうとする決意が滲んでいます。
重要なのは、「正しい選択をすることと同等以上に、その選択を正しいものにすることが重要だ」という彼女の哲学 。最初に完璧な道を選ぶことよりも、選んだ道を信じて努力し、困難を乗り越えていく過程にこそ価値がある。この「不格好経営」の思想は、完璧主義に陥りがちな私たちに、失敗を恐れず挑戦する勇気を与えてくれます。それは、特に高い基準を求められがちな女性にとって、肩の力を抜き、ありのままの自分でいることへの許可とも言えるでしょう。
試練を乗り越えるしなやかさ:公私の危機と誠実な対応
南場さんの強さは、ビジネスの舞台だけで発揮されたわけではありません。2011年、DeNAが成長の軌道に乗っていたまさにその時、彼女は夫の看病に専念するため、代表取締役CEOを退任するという大きな決断をします 。キャリアの頂点にいながら、家族のために一時的に身を引くという選択は、多くの働く女性が直面するであろう葛藤を映し出しています。しかし、それは決してキャリアの終焉ではありませんでした。後に彼女はDeNAの経営に復帰し、再びリーダーシップを発揮します 。この経験は、彼女の人間的な深みと、優先順位を見極めるしなやかな強さを物語っています。
また、2016年から2017年にかけて、DeNAはキュレーションメディア事業において、著作権侵害や不正確な情報掲載といった問題で社会的な批判を浴びました 。この危機に対し、南場さんは2017年3月に代表取締役会長として復帰し、問題の解決に陣頭指揮を執ります 。記者会見では深々と頭を下げ、「ゼロから会社を作り直す気持ち」で再建に取り組むことを表明しました 。この一連の対応は、リーダーとしての説明責任と、失敗を真正面から受け止め、信頼回復に努める勇気を示しています。
ビジネス上の失敗、個人的な危機、そして企業倫理に関わる問題。これら異なる種類の困難に直面しながらも、常に問題から逃げずに立ち向かい、適応し、前進してきた南場さんの姿は、私たちに困難への向き合い方を教えてくれます。
人を惹きつけ、共に成長するリーダーシップ:「コトに向かう」力
南場さんのリーダーシップの核となるのが、「人や自分に向かわずに、コトに向かう」という哲学です 。個人の感情や評価、社内の人間関係といった雑音に惑わされず、目の前の課題解決や目標達成に集中することの重要性を示唆しています。
そして、その「コト」を成し遂げるために不可欠なのが、多様なメンバーで構成されたチームです。「チームは多様なメンバーから組成されていた方がうんと強い」と彼女は断言します 。DeNAでは、「球体型組織」という考え方のもと、若手社員にも積極的に責任ある仕事を任せています 。社員一人ひとりがDeNAを代表するという意識を持ち、能力ギリギリの仕事(ストレッチャーサイン)に挑戦することで、飛躍的な成長を促すのです 。
南場さんは、自らの経験を踏まえ、女性がライフイベントとキャリアを両立できる、より柔軟で支援的な職場環境の実現にも力を注いでいます。DeNAでは、若手女性社員がキャリアプランについて考えるイベント「DeNA Women's Night」を開催 。そこで彼女は、「仕事がうまくいかない時、理由を『女だから』に求めない」「制度を堂々と活用する」「コトに向かう」といった具体的なアドバイスを送っています 。DeNAでは、結婚や出産を理由に退職した女性社員は「1人もいない」といいます 。
「ライフイベントや個々の事情に応じた柔軟な働き方を全力で後押ししたい」。この言葉には、自身の家族の看病という経験から得た、深い共感と決意が込められています 。
あなた自身が輝くために:南場智子からのエール
南場さんの言葉には、迷いながらも前に進もうとする私たちを力強く後押ししてくれる、普遍的な知恵が詰まっています。
「“優等生”をやめる時がきている」。他人からの評価や社会的な「偏差値」に縛られず、自分自身の尺度で人生を選択することの重要性を教えてくれます。「そろそろ自分の尺度で生き始めましょう。もっとわがままになっていいと、私は思います」。会社名やブランドといった表面的なものではなく、「実際に何をするか」「自分が成長できる場所か」を問いかけること 。それは、周りに流されず、自分の内なる声に従ってキャリアを築くための、最初の一歩となるでしょう。
そして、失敗を恐れないこと。「うまくいくことだけが全てではない」。目標達成にこだわる一方で、南場さんは挑戦のプロセスそのものに価値があると言います。「たとえ目標は未達成でも、本気で挑んだのなら、そのプロセスは決して無意味なものではない」。この言葉は、結果が出ないかもしれないという不安から一歩を踏み出せないでいる私たちに、挑戦すること自体の尊さを教えてくれます。
人間には「貢献本能」があると南場さんは語ります。「何かに貢献することが、奥深いところから湧き上がる喜びにつながります」。短期的な利益や評価だけでなく、社会や誰かの役に立っているという実感こそが、仕事を続ける上での持続的なモチベーションになる。
南場智子さんの歩みは、一直線の成功物語ではありません。それは、数々の挑戦、予期せぬ困難、そして人間的な葛藤を経て、しなやかに進化し続けてきた「本物の成長物語」です。彼女が「不格好」な瞬間や個人的な苦悩を臆せずに語る姿は、私たちにとって、他に類を見ないほど共感しやすく、力強いロールモデルとなっています。
彼女の生き方は、私たち一人ひとりが、自分自身の「不格好」な旅路を愛し、「コトに向かう」情熱を胸に、大胆に未来を切り拓いていくための、力強いエールなのです。




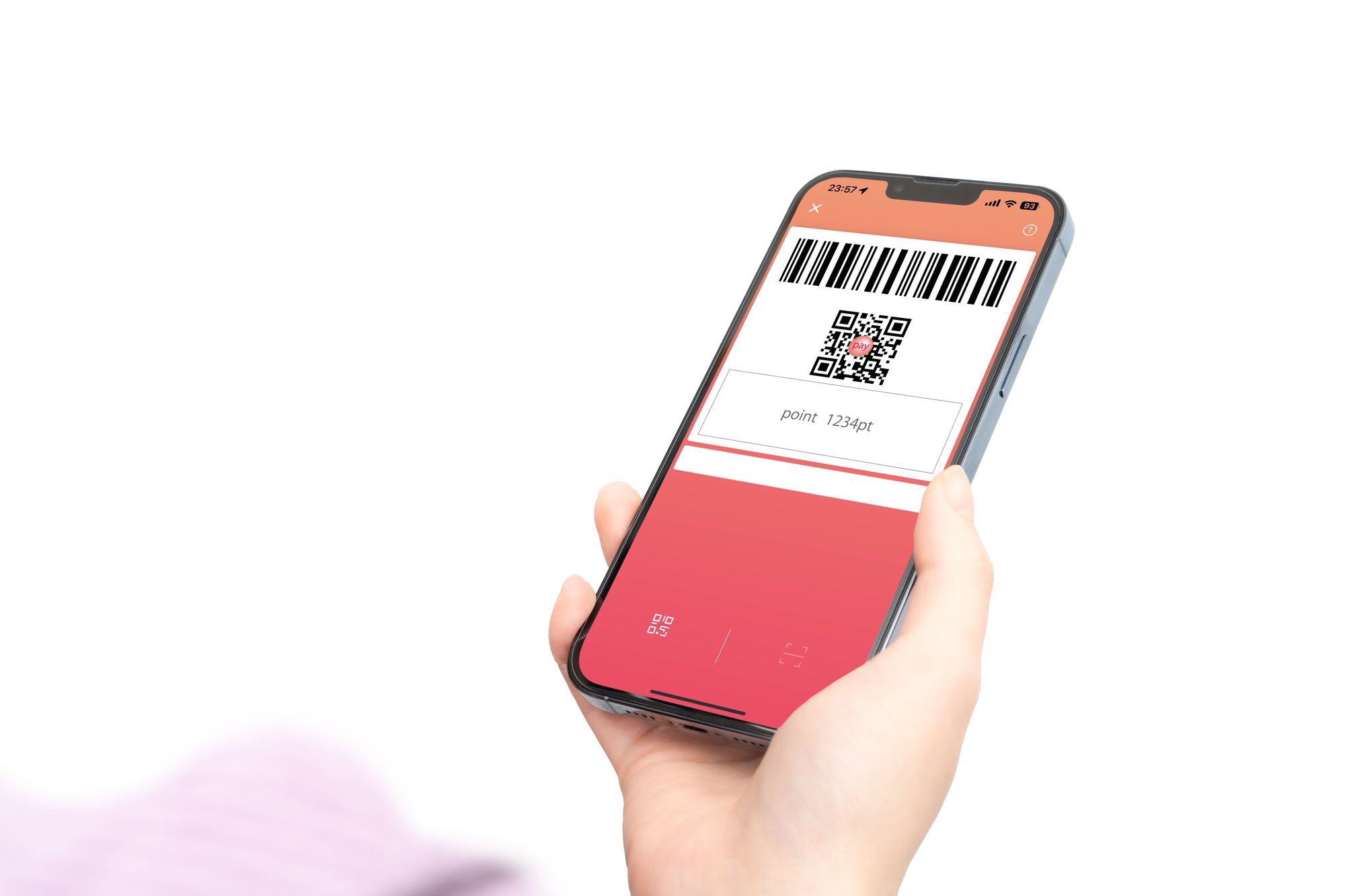

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。