SNS誹謗中傷に負けない!今日からできる対策と法的ステップ
はじめに:一人で抱え込まないで、あなたの心を守るために
SNSは私たちの生活に欠かせないツールとなりましたが、残念ながら誹謗中傷という負の側面も存在します。心ない言葉の暴力は、時に私たちの心に深い傷を残し、うつ病やパニック障害、さらには心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった深刻な影響を引き起こすこともあります 。自己嫌悪や人間不信に陥ってしまうケースも少なくありません 。
しかし、忘れないでください。あなたを攻撃しているのは、ごく一部の悪意あるユーザーに過ぎません。「炎上」と呼ばれる現象も、実際に攻撃に加わるのは限られた人たちであることが研究で示されています 。この事実を知るだけでも、孤立感や絶望感が和らぐはずです。
このブログ記事では、SNSでの誹謗中傷に直面した際に、今日からできる具体的な対策から、法的な措置、そして何よりも大切な心のケアまで、多角的な視点から解説します。一人で悩まず、適切な対処法を知ることで、被害を最小限に抑え、前向きな一歩を踏み出しましょう。
まずは心の健康を守る!初期対策とセルフケア
誹謗中傷の被害に遭ったとき、最も大切なのは、あなたの心の健康を守ることです。初期段階での適切な対応が、精神的なダメージの拡大を防ぐ鍵となります。
SNSの機能を賢く活用しよう
誹謗中傷の投稿に直接反応したり、SNS上で言い争ったりすることは、状況を悪化させる可能性があります 。まずは冷静に対応し、SNSプラットフォームが提供する機能を活用して、不快な情報や相手を「見えなくする」ことを強くお勧めします 。
具体的には、「ミュート機能」が有効です。これは相手に知られることなく、そのアカウントからの投稿を自分のタイムラインに表示させなくする機能で、不快な情報が視界に入らないようにすることで精神的な負担を軽減します 。
さらに強力なのが「ブロック機能」です。これは誹謗中傷をしてくる相手とのつながり自体を断ち、自分の投稿を見せなくしたり、相手からの返信やメッセージの送信を不可能にしたりする機能です 。これは相手からの直接的な接触を遮断する最も直接的な方法であり、デジタル空間での安全を確保するための重要な手段となります。
多くのSNSサービスでは、投稿への返信やコンタクトができる相手を制限するプライバシー設定機能も提供されています 。これらの機能の名称や操作方法はSNSアプリによって異なりますので、ご自身の利用環境に合わせて確認し、積極的に活用して、不必要なストレスから身を守りましょう 。
信頼できる人への相談とセルフケアの重要性
誹謗中傷の辛さを一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族に相談することは非常に重要です 。身近な人々は、あなたの気持ちに寄り添い、感情的なサポートを提供するだけでなく、具体的な対策を一緒に考えたり、必要に応じて専門家や相談窓口を紹介したりすることで、不安を軽減する手助けとなることがあります 。
また、自身の心の健康を積極的にケアする「セルフケア」も、回復には不可欠です。科学的にも効果が示されているいくつかのセルフケア方法を試すことで、精神的な負担を軽減し、心の回復を促進できます 。
- マインドフルネス瞑想: 今この瞬間に意識を集中させることで、過去への後悔や未来への不安からくるストレスを軽減します。ストレス軽減や不安緩和に効果があることが科学的に示されています 。
- 感情日記: 日々の感情の変化を記録することは、自分の気持ちを客観的に見つめ直し、心の整理に役立ちます。感情のパターンを理解することで、より効果的なセルフケアに繋がります 。
- 運動: ウォーキング、ヨガ、ジョギング、水泳などの有酸素運動は、セロトニンやエンドルフィンといった脳内物質の分泌を促進し、気分を改善する効果があります 。
- リラックス法: 深呼吸や漸進的筋弛緩法など、自分に合ったリラックス法を見つけて実践することで、心を落ち着かせることができます 。
- 趣味や創作活動: 好きなことや楽しいことに没頭する時間を持つことは、気分転換を図り、心の回復を促す上で有効です 。
これらのセルフケア方法は、一つずつ試してみて、自分に合った方法を見つけていくことが大切です 。
誹謗中傷の心理的影響と専門家による心のケア
SNSでの誹謗中傷は、抑うつ、自尊心の低下、対人不安といった不適応症状を引き起こし、長期的な精神的ストレスからうつ病やパニック障害、さらには心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった後遺症につながる可能性も指摘されています 。特にPTSDは、人間不信や情緒不安定を招き、日常生活に深刻な支障をきたすことがあります 。
これらの精神的な後遺症は、一人で克服することが非常に難しい性質を持っています。そのため、精神的な後遺症を発症した、あるいはその可能性が少しでもある場合には、医療機関や専門家の指導の下での治療が不可欠です 。心のケアは、自身の気持ちや時間を大切にし、必要に応じて外部の専門的なサポートを積極的に求めることで行われます 。専門家の支援を受けることで、被害者は自身の感情を整理し、適切な対処法を学び、回復への道を歩むことができるでしょう。
法的措置への第一歩:証拠保全の重要性と具体的な方法
誹謗中傷の被害に遭った際、その後の法的措置(投稿削除依頼、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴など)を効果的に進めるためには、まず何よりも最優先で証拠を確保することが極めて重要です 。この証拠保全は、すべての法的対応の基盤となります。
なぜ証拠保全が重要なのか?
インターネット上の誹謗中傷は、物理的な証拠とは異なり、非常に脆弱です。加害者自身が投稿を削除したり、SNS事業者やインターネット接続事業者(プロバイダ)が保有するアクセスログ(投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなど)が一定期間(一般的に3ヶ月から半年程度)で自動的に消去されたりするリスクが存在します 。
このアクセスログが失われてしまうと、匿名で投稿された誹謗中傷の発信者を特定することが極めて困難になります。その結果、損害賠償請求や刑事告訴といった、加害者の責任を追及するための重要な法的措置を進めることが不可能になる場合があります 。このため、誹謗中傷の被害に気づいたら、迅速に証拠を保全することが、将来的な法的救済の可能性を確保する上で決定的に重要となります。ログの保存期間という物理的な制約が、被害者が行動を起こす上での事実上のタイムリミットとなるため、迅速な対応が求められるのです 。
また、デジタル証拠は、物理的な証拠に比べて容易に改ざんや削除が可能であるという特性を持っています。そのため、その証拠能力を法廷で維持するためには、厳格な手順での取得と保存が求められます 。例えば、単にファイルを開いたり編集したりするだけでも、そのファイルの「最終更新日時」が書き換えられるなど、意図しない改ざんにつながる可能性があるため、細心の注意が必要です 。適切に取得・保全されたデジタル証拠は、裁判において強力な証拠として採用される可能性が高まります 。
スクリーンショット、動画、公証役場での保全方法
誹謗中傷の証拠を保全する方法には、いくつかの段階と選択肢があります。
-
基本的な証拠保全:
- スクリーンショット: 誹謗中傷の投稿画面をスクリーンショットで保存することが最も手軽な方法です。この際、投稿内容、投稿日時、投稿のURLやアドレス、アカウント名が明確にわかるように記録することが必須となります 。URLや日時が確認しやすいパソコンでのスクリーンショットが推奨されます 。
- 動画での保存: スクロールが必要なWebページや動画コンテンツで誹謗中傷を受けた場合、パソコンに搭載されている画面収録機能(Windowsでは「Windowsキー + G」、Macでは「Command + Shift + 5」)を使って動画で保存することも有効です。これにより、ページ全体や動画の連続した内容を証拠データとして残すことができます 。
- 被害状況の記録: 精神的・社会的な被害(体調不良、通院記録、医療費の領収書、日記など)も具体的に記録しておきましょう。これらの記録は、損害賠償請求を行う際に、被害の具体的な証拠として有用となります 。
-
より強固な証拠保全:公証役場での事実実験公正証書
- より高い証拠能力を求める場合、公証役場で「事実実験公正証書」を作成する方法があります 。これは、公務員である公証人が被害状況を直接見聞し、その内容を公正証書として作成するものです。公証人によって作成された公文書は、極めて高い証明力を持ち、将来的な訴訟において証拠の改ざんを疑われるリスクを大幅に低減し、強力な証拠として機能します 。
- 費用: 事実実験公正証書の作成手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間に応じて算定されます。目安として、1時間までごとに11,000円が相場とされています 。事実実験が休日や午後7時以降に行われた場合は、手数料の10分の5が加算されることがあります 。
これらの証拠保全方法は、被害の状況や今後の法的措置の選択肢に応じて使い分けることが重要です。
SNSプラットフォームへの削除依頼と通報の手順
誹謗中傷の投稿を発見した場合、最初の対応としてSNS事業者に削除依頼を出すことが一般的です 。多くのSNSプラットフォームには、利用規約やコミュニティガイドラインに違反する投稿を報告するための機能が備わっています。
削除依頼の基本的な流れとSNS事業者の対応
SNS事業者への削除依頼は、以下の基本的な手順で行われます。
- 証拠の記録: 該当する投稿のURLやアドレス、画面(スクリーンショット)や動画を必ずメモ・保存します。これは、削除依頼の際に具体的な情報として提供するだけでなく、万が一削除されなかった場合の法的措置の証拠としても不可欠です 。
- 報告機能の利用: 利用しているSNS内の「通報」「報告」「お問い合わせ」などの削除依頼ができるページやメニューを探します 。
- 情報入力と送信: フォームの指示に従って必要な選択・入力を行い、漏れがないか内容を確認して送信します 。
SNS事業者は、報告された内容を自社のコミュニティ規定や利用規約に照らして審査し、問題があると判断されれば、投稿の非表示化や削除、アカウント制限などの対応を行います 。報告は基本的に匿名で行われるため、相手に誰が報告したかが知らされることはありません 。
しかし、SNS事業者への報告だけでは、必ずしも誹謗中傷の投稿が削除されるとは限りません 。SNSのガイドラインに違反しないと判断された場合など、削除依頼が認められないケースも存在します。このような場合、被害者はより強力な法的手段を検討する必要が生じます。プラットフォームの対応には限界があることを理解し、必要に応じて次の段階へ移行する準備をしておくことが重要です。また、加害者への直接的な連絡は、かえって事態を悪化させるリスクがあるため、避けるべきです 。
主要SNSごとの報告・削除手順
各SNSプラットフォームには、不適切な投稿やアカウントを報告するための独自の機能が備わっています。報告は基本的に匿名で行われ、相手に誰が報告したかは知らされません 。
- X (旧Twitter): 問題の投稿上部にある「…」(三点リーダー)をタップし、「ポストを報告」を選択します。その後、ツイートの問題点を報告する理由を選択します 。Xのヘルプセンターにあるお問い合わせフォームから、報告する問題に最も当てはまるトピックを選択し、違反投稿の情報を報告することも可能です 。
- Instagram: 報告したい投稿の右上にある「…」をタップし、「報告する」を選択。「嫌がらせやいじめ」など、該当する報告理由を選びます 。コメント一覧を開き、報告したいコメントを左にスワイプすると表示される「!」アイコンをタップし、「このコメントを報告」を選択して理由を選びます 。アカウントの報告は、相手のプロフィール画面右上の「…」から「報告する」を選択し、「アカウントを報告」を選び、理由を報告します 。アプリ内のプロフィール画面右上の「≡」から「ヘルプ」→「ヘルプセンター」または「問題を報告」からもアクセス可能です 。
- Facebook: 報告したい投稿の右上にある「…」を選択し、メニューから「投稿を報告」を選択します。報告する理由を選び、報告を完了します 。アカウントの報告は、報告したいアカウントのトップページを開き、「…」ボタンをタップ。メニューから「サポートを依頼またはプロフィールを報告」を選択し、理由を選び報告を完了します 。
- TikTok: 該当動画を長押しし、「報告」を選択。報告する内容(トピック)と詳細を記載して送信します 。コメントの報告は、報告したいコメントを長押しし、「報告する」を選択。理由を選び送信します。スパムコメントなど、複数のコメントが投稿されている場合は、最大100件まで一括で報告することも可能です 。ユーザーの報告は、誹謗中傷を行っているユーザーのプロフィールに移動し、画面右上に表示される3点リーダーをタップ。「アカウントを報告する」を選択し、報告理由を選び送信します 。ダイレクトメッセージ、LIVE動画、LIVEコメント、ハッシュタグについても同様に報告機能が提供されています 。
削除されない場合の追加対応
SNS事業者への報告だけでは投稿が削除されない場合、追加の対応を検討する必要があります 。
- 再通報・追加証拠の提示: 運営会社が一度「ガイドライン違反なし」と判断したとしても、別の視点から問題点を指摘したり、被害の具体的な状況を示す追加のスクリーンショットや証拠を提示したりすることで、再審査を促せる場合があります 。
- 弁護士を通じた「送信防止措置依頼書」の送付: プロバイダ責任制限法に基づき、弁護士からSNS事業者に「送信防止措置依頼書」(テレコムサービス協会ガイドライン書式、通称テレサ書式)を郵送する方法があります 。これは法的根拠に基づいた削除請求であり、個人での依頼よりも削除がスムーズに進む可能性が高まります。書式の作成は専門的知識を要するため、弁護士に依頼することが推奨されます 。
- 裁判所への「削除の仮処分」申立て: SNS事業者が任意での削除や送信防止措置依頼に応じない場合、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てることができます。これは正式な判決を待たずに暫定的な削除命令を求める民事保全手続きであり、緊急性を要する事案に対して迅速な対応が期待できます 。裁判所が仮処分命令を発令すれば、通常は問題の投稿が削除されます 。この手続きも、ネットトラブルに詳しい弁護士を通じて行うのが確実です 。
加害者を特定し、責任を追及する法的措置
匿名の誹謗中傷投稿者に対して損害賠償請求や刑事告訴を行うためには、原則として投稿者を特定する必要があります 。この特定手続きが「発信者情報開示請求」です。
発信者情報開示請求とは?(プロバイダ責任制限法改正のポイント)
発信者情報開示請求は、インターネット上で誹謗中傷を行った匿名投稿者の氏名や住所などの個人情報を、インターネット接続事業者やSNS運営事業者(プロバイダ)に開示を求める手続きです 。
この手続きは、令和4年(2022年)10月1日より施行された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の改正により、より簡易かつ迅速に行えるようになりました 。特に、大規模プラットフォーム事業者に対しては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化が義務付けられ、被害者が投稿者を特定しやすくなる環境整備が進められています 。
手続きの流れと期間の目安:
発信者情報開示請求は、通常、以下の二段階で進められます。
- 証拠保管: まず、誹謗中傷の投稿のスクリーンショット、URL、日時などの証拠を確実に保存します。これは開示請求の要件であり、相手が投稿を削除する可能性もあるため、最優先で行う必要があります 。
- コンテンツプロバイダへの開示請求: 誹謗中傷が投稿されたSNSや掲示板の運営会社(コンテンツプロバイダ)に対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。これは通常、裁判所への仮処分申立てによって行われます 。SNS側が任意で開示に応じる可能性はほとんどありません 。
- 経由プロバイダの特定: 開示されたIPアドレスとタイムスタンプから、投稿者がインターネット接続に利用したプロバイダ(経由プロバイダ、例:NTT、KDDIなど)を特定します 。
- 経由プロバイダへの開示請求: 特定した経由プロバイダに対し、投稿者の氏名や住所といった個人情報の開示を求めます。これも通常、裁判所への訴訟(発信者情報開示請求訴訟)によって行われます 。
発信者情報開示請求にかかる期間は、おおむね3ヶ月から10ヶ月程度が目安とされています 。訴訟の結果が出るまでには10ヶ月前後かかることもあります 。プロバイダが保有するログの保存期間は3ヶ月から半年程度であるため、非常にスピーディーな対応が求められます 。この期間内に適切な手続きを行わないと、重要な証拠が失われ、加害者の特定が不可能になるリスクがあります 。
弁護士に依頼するメリットと費用相場:
弁護士は、法的に有効な形で告訴状や申立書を作成し、証拠の整理・要点の明文化をサポートします 。複雑な二段階の手続きをスムーズに進め、ログの保存期間が過ぎる前に迅速に行動できます 。また、警察や検察への対応も同行・代行が可能です 。
弁護士費用は、相談料が30分あたり5,000円~10,000円が相場ですが、多くの法律事務所では初回無料相談を受け付けています 。着手金は、発信者情報開示請求訴訟の場合、20万円~40万円程度が目安です 。任意開示を求める場合は10万円~20万円程度です 。成功報酬は、申立てが認められた場合などに発生する費用で、10万円~30万円程度が目安です 。裁判所に支払う申立手数料(約2万円)、郵便切手代のほか、仮処分申立てには担保金(10万円~30万円程度)の供託が必要です。この担保金は、申立人の請求が正当と認められれば返還されます 。弁護士に依頼する場合、裁判所に納付する費用を含めると、総額で60万円~100万円程度かかる可能性があります 。経済的に余裕がない場合、日本司法支援センター(法テラス)を利用することで、弁護士費用の立て替えや分割払い制度(最長5年)を利用できる可能性があります。初回相談は無料です 。
損害賠償請求(慰謝料の相場と請求要件)
投稿者を特定できた場合、誹謗中傷によって受けた精神的苦痛や経済的損害に対する「損害賠償請求」を行うことができます 。これは、加害者に対して金銭的な賠償を求める民事上の手続きです。
慰謝料の相場:
- 名誉毀損: 個人の場合で10万円~50万円程度、法人の場合で50万円~100万円程度が相場とされています 。誹謗中傷の内容や被害の程度によっては、数百万円程度の損害賠償が認められるケースもあります 。
- 侮辱: 数万円~10万円程度と、名誉毀損に比べて低額になる傾向があります 。
- プライバシー侵害: 10万円~50万円程度が相場とされています 。
損害賠償請求を行うには、「自分のどんな権利が侵害されたのか」を明確にし、法的根拠に基づいた主張が求められます 。まず弁護士から書面を送るなどして裁判外での交渉を試みることが多く、相手が応じない場合は裁判へと移行します 。
刑事告訴(侮辱罪・名誉毀損罪の厳罰化)
誹謗中傷の内容が刑法上の罪(名誉毀損罪や侮辱罪など)に該当する場合、警察などの捜査機関に被害を申告し、「刑事告訴」を行うことができます 。刑事告訴は、加害者の法的処罰(罰金刑や拘禁刑など)を求める意思表示です 。
侮辱罪の厳罰化: 令和4年(2022年)7月に刑法が改正され、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。これにより、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に対し、「1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されるようになりました 。この厳罰化は、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化し、その被害が深刻であるという認識が高まった結果として行われたものです 。この法改正は、オンライン上の誹謗中傷をより強力に抑止し、被害者を守るための重要な一歩であり、被害者にとって加害者の責任を追求する上でより有効な手段となり得ます 。
刑事告訴には原則として「犯人を知った日から6ヶ月以内」という期間制限があります。ただし、誹謗中傷の投稿が残り続けている限り告訴期間のカウントが進まないという見解もあるため、詳細は弁護士に相談することが重要です 。
一人で抱え込まないで!公的な相談窓口と専門家
誹謗中傷の被害に直面した際、一人で問題を抱え込むことは、精神的負担を増大させ、適切な解決策を見つけることを困難にします。国や地方自治体、専門機関は、被害者が安心して相談できる多様な窓口を提供しており、これらの支援を積極的に活用することが推奨されます。
総務省・法務省などの公的相談窓口
- 違法・有害情報相談センター(総務省支援事業): インターネット上の誹謗中傷に関する専門の相談員が、書き込みの削除方法などについて丁寧にアドバイスを提供しています。総務省の支援を受けているため、信頼性が高く、安心して相談できる窓口です 。
- 法務省インターネット人権相談受付窓口/みんなの人権110番: SNSでの誹謗中傷を含む、あらゆる人権に関する相談に応じています。削除依頼の方法について助言を行うほか、内容に応じて法務局からプロバイダやSNS事業者に削除要請を行うこともあります。相談内容は秘密厳守で扱われます 。
- ネットの誹謗中傷(セーファーインターネット協会): ネット上の誹謗中傷に対し、掲載サイトの利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。無料で相談を受け付けており、秘密は厳守されます 。
- まもろうよ こころ(厚生労働省): 悩みや不安を抱えている際に、電話、メール、チャット、SNSなど、様々な手段で気軽に相談できる窓口を紹介しています 。
- 法テラス(日本司法支援センター): 法的なトラブル全般について、情報提供や相談機関の紹介を行っています。経済的に余裕がない場合、弁護士費用の立て替え制度や分割払い制度を利用できる可能性があります。初回相談は無料の場合もあります 。
弁護士会・心理カウンセリング・心のケア専門機関
法的な問題と精神的な問題は密接に関連しているため、それぞれ専門の知識を持った機関への相談が重要です。
- 弁護士会: 各都道府県に設置されている弁護士の団体で、法律相談センターを運営しています。電話相談や対面相談など、弁護士会ごとに様々な相談体系があります。「ひまわりお悩み110番」から問い合わせが可能です 。弁護士は、誹謗中傷が法的にどのような権利侵害に当たるか、投稿削除依頼や発信者情報開示請求の手順、損害賠償請求や刑事告訴の進め方など、具体的な法的アドバイスを提供します 。
-
心理カウンセリング・心のケア専門機関: 誹謗中傷による精神的ダメージは深刻であり、一人で克服することは困難です 。専門の心理カウンセリングを受けることで、心の傷を癒し、回復を促すことができます。
- 全国心理業連合会(全心連): 全国SNSカウンセリング協議会のもと、「SNS誹謗中傷等の心のケア相談」として無料のLINE相談窓口を開設しています 。心理カウンセラーが「話を聴くプロ」として、何が起こっているかを整理し、相談者の意向を汲みながら対応方法を考えます。法律に関する相談は専門の窓口へ案内されます 。
- 費用: 心理カウンセリングは一般的に保険適用外となることが多く、1回あたり5,000円~20,000円程度が相場ですが、無料相談を受け付けている機関もあります 。
- 家族や友人によるサポート: 被害者の気持ちに寄り添い、具体的な対策を一緒に考えること、そして専門家や相談窓口への紹介を行うことは、家族や友人による重要な支援となります 。厚生労働省の「まもろうよ こころ」など、家族が相談できる窓口も存在します 。
これらの多様な相談窓口や専門機関は、被害者が直面する様々な問題に対して、適切な支援を提供するために存在しています。一人で抱え込まず、積極的にこれらのリソースを活用することが、誹謗中傷の被害から立ち直るための重要な一歩となります。
まとめ
SNSでの誹謗中傷は、私たちの心身に深刻な影響を及ぼす可能性がありますが、適切な対策と支援によって、その被害を最小限に抑え、回復への道を進むことができます。
ポイント:
- 心の健康を最優先: SNSのミュート・ブロック機能の活用や、信頼できる人への相談、マインドフルネス瞑想や運動などのセルフケアを通じて、心の負担を軽減しましょう。必要であれば、専門の心理カウンセリングも積極的に利用してください。
- 迅速な証拠保全が鍵: 誹謗中傷の投稿を発見したら、すぐにスクリーンショットや動画で投稿内容、日時、URLなどを記録することが極めて重要です。ログの保存期間には限りがあるため、迅速な対応がその後の法的措置の可能性を左右します。
- SNSプラットフォームへの報告: 各SNSに備わる報告機能を利用して、不適切な投稿の削除を依頼しましょう。報告は匿名で行えます。
- 法的措置の検討: SNS運営会社が削除に応じない場合や、加害者を特定したい場合は、弁護士を通じて「送信防止措置依頼書」の送付や「削除の仮処分」申立て、さらには「発信者情報開示請求」を検討できます。侮辱罪の厳罰化など、法整備も進んでいます。
- 一人で抱え込まない: 総務省や法務省などの公的相談窓口、弁護士会、心理カウンセリング機関など、多様な支援窓口が存在します。これらのリソースを積極的に活用し、専門家のサポートを得ることで、誹謗中傷の被害から立ち直り、安心して生活できる環境を取り戻しましょう。

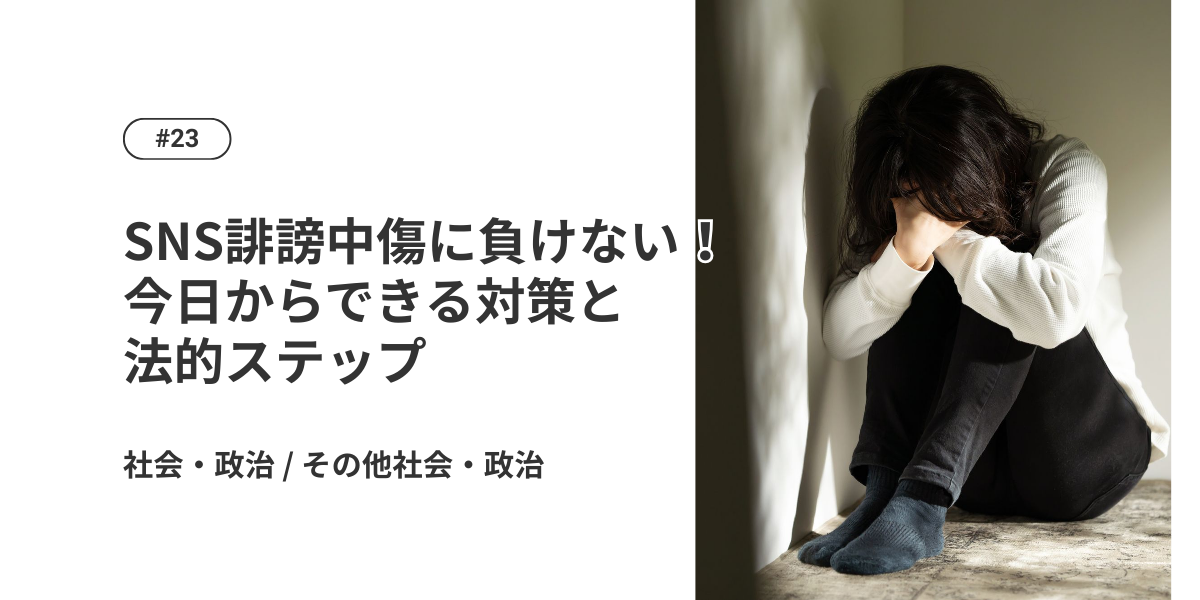



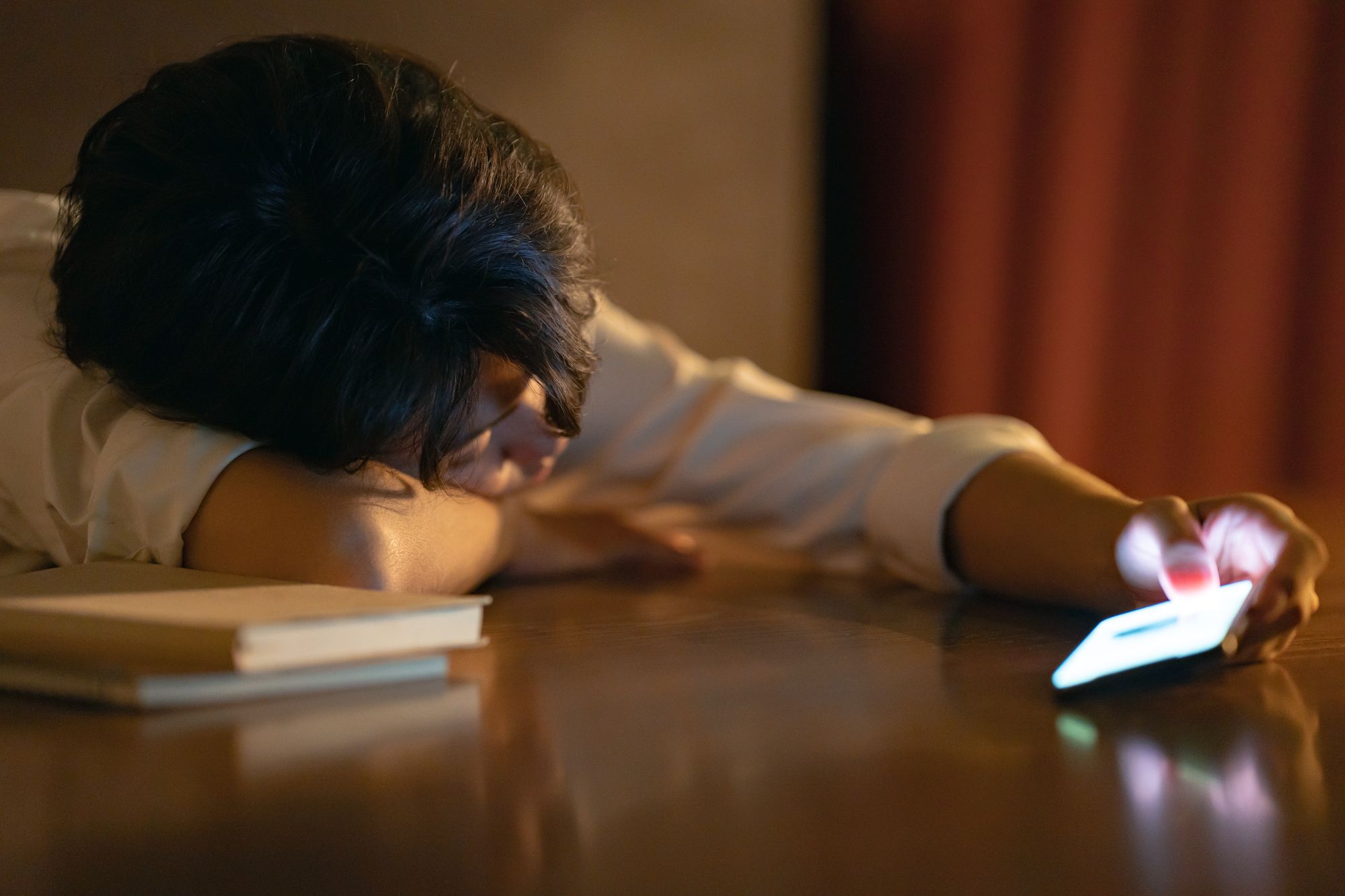
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。