「名前も告げず、少女を救った老人の正体──“月夜の奇跡”が教えてくれたこと」
プロローグ:月の光が照らす場所で
あの夜のことを、私はきっと一生忘れない。
春でもない、夏でもない、少し肌寒い風が頬をかすめる、そんな中途半端な季節の夜だった。団地のすぐ裏にある、誰もいない小さな公園。ベンチに腰を下ろし、私は空を見上げていた。月が、やけに眩しかった。
明るすぎるくらいのその月の光が、まるで何かを照らし出そうとしているように、私の足元を、そして心の奥をじっと見つめていた。
誰にも言えないことが、私にはたくさんあった。
進学を諦めた夢のこと。働き詰めの祖母に、これ以上迷惑をかけたくないという気持ち。学校では笑っていたけど、誰にも頼れないことに、息が詰まりそうな日々。
「きっと、大人になったら、少しは楽になるんだよね」
そう呟いてみる。けれど返ってくるのは、夜風の音だけだった。
私は気づかないふりをしていた。
この街の片隅で、自分がどれほど小さな存在か。
誰かが見てくれているなんて、期待するのも馬鹿らしいって。
でも——
「…あなたは、見てくれていたんですね」
その人は、名前も知らないまま、いつも遠くから私を見ていた。
声をかけてくることも、手を差し伸べることもなかった。
ただ、静かに、そこにいた。
そしてある日、世界が変わった。
それはきっと、月の光が照らす場所で始まった、
ひとつの静かな奇跡だったのだと思う。
 あの夜のことを、私はきっと一生忘れない。 ※以下イメージ画像
あの夜のことを、私はきっと一生忘れない。 ※以下イメージ画像
第一章:貧しさと孤独の中で笑おうとする、すず
朝のアラームが鳴ったとき、すずはすでに目を覚ましていた。
眠れなかったのではない。ただ、目を閉じると考えごとが止まらなくなってしまうのだ。夢よりも、現実のほうが重たい。それが彼女の毎日だった。
古びた団地の一室。築40年近く経ったコンクリートの壁は冬の寒さを容赦なく伝えてくる。起き上がると、すずは電気ポットのスイッチを入れ、朝ごはん代わりのインスタント味噌汁をつくった。具はわかめと豆腐、ほんの少し。
「ばあちゃん、起きてる?」
奥の和室から、ふとんの中で背中を丸めた祖母が「うん」とか細く返事をした。
すずは急いで制服に袖を通す。スカートは膝よりずっと上で止まり、上着のボタンの一つは取れかけていた。それでも、鏡の前ではにかむように笑ってみせる。
「よし、今日も大丈夫」
口癖のようにそう呟き、すずは祖母の部屋に顔を出す。
「行ってくるね。無理しないでよ、洗濯は帰ったらやるから」
「ありがとうねぇ、すず…」
祖母はそう言って、少し申し訳なさそうに微笑んだ。
足が悪く、数年前に介護を受けるようになってから、祖母はほとんど外に出なくなった。すずは昼の時間にコンビニでバイトをし、夜は夜間高校に通う。家事はすべて彼女がこなしていた。
駅までの道。周囲の高校生たちはにぎやかに話しながら歩いている。ブランドのバッグ、スマートフォン、流行りの制服の着こなし。すずは彼女たちとは、別の世界にいるような感覚を抱いていた。
同じ空気を吸っていても、話す言葉が違う。
同じ時間を生きていても、見る景色が違う。
彼女たちは、放課後にカフェで笑い合い、塾に通い、将来の夢を語り合っている。でも、すずは違う。彼女の夢は「生き抜くこと」だった。今日をなんとか乗り越えること。明日を無事に迎えること。それだけで精一杯だった。
学校の教室もまた、すずにとっては静かな戦場だった。
友達と呼べる存在はいない。声をかけられることはあっても、それは決まって「ノート貸してくれない?」か、「そのスカート、もう流行ってないよね?」というような無邪気な皮肉ばかりだった。
「すずって、いつも一人で平気なの?すごいね」
本気か冗談かわからない言葉。
それでも、すずはにっこりと笑って答える。
「うん、慣れてるから」
その笑顔の裏に、誰も気づくことはない。
放課後、バイト先のコンビニに直行する。レジ打ち、品出し、揚げ物の管理。接客中のすずは、誰よりも明るく「いらっしゃいませ」と言う。それだけが、自分を保つ術だった。
深夜に帰宅し、祖母の薬を準備し、洗濯機を回す。
ようやくふとんに横たわるころには、日付がとっくに変わっていた。
何度も「どうしてこんなに頑張ってるのに、報われないんだろう」と思ったことがある。
でも、すずは泣かない。泣く時間があれば、明日の予定を確認したほうがいい。
それでも——
心がふと、ぽっかりと空っぽになる瞬間がある。
そんな夜、彼女はよく団地の裏にある小さな公園に行く。
誰もいないブランコに座り、月を見上げる。
「ねぇ、月さん。私、ちゃんとやってるかな」
誰にも届かないつぶやき。
でも、その夜の月は、いつもより少しだけ大きくて、やさしく見えた。
風に揺れるブランコの音が、すずの心を少しだけ癒した。
月の光が、あたたかかった。
それだけで、もう少し頑張れるような気がした。
 月の光が、あたたかかった。
月の光が、あたたかかった。
第二章:見知らぬ老人と出会う
それは、春先の雨が上がった午後のことだった。
昼のバイトを終えて、すずは商店街を抜け、団地へ続く細道を歩いていた。
まだ夕方前だというのに、空はどんよりと曇っていて、肌寒い風がシャツの隙間から忍び込む。
「早く帰って洗濯物、取り込まなきゃ…」
つぶやいたそのときだった。
ふいに、視界の端に動く人影が見えた。
団地裏の公園の入り口、いつもは誰もいない場所に、ひとりの老人がいた。
ぼさぼさの白髪に、よれよれのジャケット。
細い背中を丸め、無言で公園の掃除をしている。
手には、年季の入った竹ぼうき。
地面に落ちたわずかな葉っぱや、誰かが放置した空き缶を、黙々と集めていた。
「……誰?」
すずは思わず足を止めた。
団地の住人なら、顔くらい見たことがあるはず。でもこの老人は見覚えがない。
そしてなにより、その姿が、どこか異様に感じられた。
「なんか……うさんくさい」
そう思ってしまった。
どこの誰かもわからない老人が、勝手に公園を掃除している。
ホームレス?それとも、どこか頭の足りない人?
そう思った瞬間、自分でも嫌な気分になった。
決めつけるような見方をしてしまったことに、心のどこかがチクリと痛んだ。
でも同時に、怖さもあった。
人通りの少ないこの裏道で、知らない大人とすれ違うのは、やはり不安だった。
「……急ご」
足早にその場を通りすぎようとしたときだった。
ザッ、ザッ——
老人の掃除の手が止まった。
顔を上げると、ふいに、すずと目が合った。
無言のまま、じっとこちらを見ている。
表情はわからない。瞳も何も語らない。ただ、静かに、淡々と。
「……なに?なに見てんの」
すずは目をそらした。
気まずさと、わずかな恐怖と、それを隠すような苛立ちが混ざり合う。
一瞬だけ、足を止めかけたが、そのまま踵を返して公園を通り抜けた。
「なんであんなとこ掃除してんの。気味悪……」
独りごとのようにそうつぶやくと、無理に笑ってみせた。
怖くなんてない、私は大丈夫。そうやって、自分を落ち着かせるのは癖になっていた。
けれど、団地の階段を上る途中、ふと胸がチクリと痛んだ。
あの老人——何もしていなかった。ただ掃除をしていただけなのに。
勝手に「気味悪い」と決めつけたのは、自分のほうだ。
「……ごめん」
そう思いながらも、すずはその夜、祖母に話すことはなかった。
翌朝、公園の前を通ると、またあの老人がいた。
昨日とまったく同じ服装で、同じように落ち葉を掃いている。
それだけで、すずは急に胸の奥がざわついた。
「……毎日、来てるの?」
彼女は横目でちらりと老人を見る。
やっぱり、目が合った。
けれど、今度はすぐに目をそらすのではなく、ほんの一瞬、視線を受け止めてしまった。
老人は、何も言わなかった。
ただ、またゆっくりと掃除の手を動かし始める。
無言で、まるで誰にも気づかれなくていいというように、ただ黙々と。
「……意味、わかんない」
すずはそう言い残して、少しだけ早足になった。
学校でも、家でも、バイト先でも、誰かと向き合うのは疲れる。
だからすずにとって、誰にも会わずに通る帰り道は、貴重な安らぎの時間だった。
でも、そこにあの老人がいるだけで、その静けさがかき乱される気がしていた。
「もう来ないでくれればいいのに……」
そう思いながらも、その日もまた、彼女は公園の横を通るたびに、老人の姿を確認してしまう。
そして、自分でも気づかないうちに、少しずつ心に何かが引っかかり始めていた。
ある日の夕方、すずが帰ると、祖母がぼんやりテレビを見ていた。
「すず、最近、公園きれいになったと思わないかい?」
「え?」
「ほら、前は空き缶だの吸い殻だので汚れてたけど、こないだ通ったら、砂場まできれいに掃かれてたのよ」
「……ああ、そうだね」
すずは曖昧に答えた。
頭の中に、あの老人の姿が浮かぶ。
掃除していたのは——あの人。
なぜだろう。たったそれだけのことなのに、心のどこかがざわついた。
無関係だと思っていた“あの人”が、自分たちの生活のすぐそばにいるということ。
誰にも気づかれず、感謝もされず、それでも黙々と公園をきれいにしているということ。
「なんなんだろう、あの人……」
その夜、すずは初めて、自分から老人のことを“気にしている”自分に気がついた。
でもそれは、まだほんの小さな、心のさざ波にすぎなかった。
 無言で公園の掃除をしている。
無言で公園の掃除をしている。
第三章:ある出来事で心が動く――パンと牛乳を分ける日
その日は、ひどく風が強かった。
朝から空は曇っていて、昼過ぎにはちらほらと雨粒も落ち始めた。
すずは昼のバイトを終え、制服のスカートを風で押し上げられないように押さえながら、団地へと続く細道を急いでいた。
買い物袋の中には、値引きシールの貼られた食パンと、紙パックの牛乳。
祖母が「少しだけでも朝食を食べられるように」と言っていたから、今日のうちに買っておこうと思った。
商店街を抜け、裏道の公園が見えてくる。
いつもの場所に、あの老人がいた。
いつも通り、黙って竹ぼうきを動かしている。
でも、その日はなぜか、違和感を覚えた。
風が強く、空き缶やビニール袋が公園を舞っているのに、老人はぼうっと立ち尽くしていた。
手にしていた竹ぼうきは、途中で折れてしまったのか、半分ほどの長さしかなかった。
「あの……」
気づいたときには、すずは足を止めていた。
自分でも驚いた。声をかけるつもりなんてなかったのに。
それなのに、身体が勝手に動いていた。
老人はゆっくりと顔を上げた。
その瞳には驚きも拒絶もなく、ただ淡々と、すずを見つめていた。
「……風、強いですよね。掃除、大変そう」
そう言ってから、すずは自分の言葉がどうにも場違いであることに気づいた。
まるで天気の話しかできない子供みたいで、恥ずかしかった。
老人は少しだけ微笑んだように見えた。
でも、何も言わなかった。ただ、またほうきを構え、散らばった落ち葉に視線を落とした。
沈黙が続いた。
「……これ、良かったら食べますか」
そう言って、すずは買い物袋の中から、まだ温かさの残るあんパンを取り出した。
バイト先のコンビニで、賞味期限ギリギリのものを見切りで買っただけの、特別なものではない。でも、祖母と分ける予定だったそれを、なぜか差し出したくなった。
「朝ごはん、食べてなかったら……って」
老人はゆっくりと顔を上げ、すずの手元を見つめた。
少しの間を置いて、おそるおそる手を伸ばす。
その手は、驚くほど骨ばっていた。指は細く、節々が固く浮かび上がっている。
寒さのせいか、少し震えていた。
あんパンを受け取ると、老人は胸に抱くようにして頭を下げた。
深く、何度も。
「……あ、牛乳も……」
すずは思わず、袋の中から紙パックを取り出して差し出した。
すると、老人は顔を上げて、すずの目を見つめた。
その目に、ほんの少しだけ、光が灯っていたように感じた。
「……ありがとう」
低く、掠れた声だった。でも、確かに言葉だった。
すずは、小さく息をのんだ。
今まで、一度もこの人が話すのを聞いたことがなかった。
表情もわからず、ただ無言で掃除する姿だけを見ていた。
けれど、今は違う。
彼の中に、確かに“人”がいた。言葉があり、感情があった。
「……じゃあ、私、これで」
そう言って踵を返しながらも、すずは何度も振り返ってしまった。
老人はベンチに座り、慎重にあんパンの包みを開けていた。
雨上がりの空の下、その姿はどこか温かく、そして少し寂しげでもあった。
団地の階段を上る途中、すずはふと気づいた。
ポケットの中が、少しだけ軽い。
あんパンと牛乳を渡したぶん、今日の晩ごはんは質素になるかもしれない。
でも、不思議と悔いはなかった。
むしろ、心のどこかが、すうっと軽くなっていた。
「あの人……やっぱり、ただの変な人じゃないのかも」
そんな風に思いながら、すずは小さく笑った。
その夜、祖母がふとつぶやいた。
「今日は、風がきつかったねえ。ベランダの鉢、倒れちゃったよ」
「……うん。でも、悪いことばっかりでもなかったよ」
すずは台所で米を研ぎながら、ぽつりと答えた。
「いいこと、あったの?」
祖母が不思議そうに聞く。
すずは少しだけ考えてから、答えた。
「……うん。ちょっとだけ、ね」
誰にも言わなくてもいい。説明できなくてもいい。
ただ、小さな優しさが、ほんの少しだけ世界を変えた。そんな気がした。
そしてその日以来、すずは老人を“見ないふり”をしなくなった。
遠くからでも、ちゃんと目で追うようになった。
挨拶はまだできない。でも、それでいい。
だって、少しずつでいいから——
その人のことを、知りたいと思ったから。
 「……これ、良かったら食べますか」
「……これ、良かったら食べますか」
第四章:バイト中にトラブルに巻き込まれる
「いらっしゃいませー」
すずの声が、静かなコンビニの店内に響いた。
放課後の時間帯。駅からも少し離れた場所にあるこの店は、平日の夜になると一気に人通りが減る。
冷蔵庫にドリンクを並べ直しながら、すずは腕時計を見た。
夜の8時。あと1時間半で今日の勤務も終わる。
「あと少し、がんばろ」
彼女はいつもそう自分に言い聞かせていた。
バイト先のコンビニは、すずにとって“ひと息つける場所”でもあった。
学校よりも、家よりも、誰にも気を遣わずにいられるこの場所は、無言で働ける分、楽だった。
──しかし、その“いつも通り”は、ある夜、突如として崩れることになる。
ガラガラッと、自動ドアの鈍い音が鳴った。
顔を上げたすずの目に飛び込んできたのは、泥酔した男の姿だった。
ボサボサの髪、酔っ払った勢いそのままに店内をふらつくように歩いている。
「ああ、めんどくさいの来たかも……」
心の中でつぶやきながら、すずはカウンターへと戻った。
酔客の対応は初めてではない。けれど、できれば今日は穏やかに終わってほしかった。
男はやたらと大きな声で缶ビールを3本レジに叩きつけるように置いた。
「へいへい、会計頼むよ、ねえちゃん。早くしろよ〜」
すずは丁寧にレジを打ち、「712円です」と静かに伝える。
男はポケットをごそごそと探るが、どうやら財布を持っていないことに気づいたらしい。
「ちょ、ないな……おかしいな……さっきまであったのに……」
次第に男の苛立ちが高まっていくのがわかった。
「おかしいなあ!てめぇ、金取ったんじゃねえのか?」
突如、男がすずの顔を睨みつけた。
「は……?」
「お前がレジの時になくなったんだ!こら、ふざけんなよ!」
「そんな……私は触ってません!」
「うるせえ!ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ!」
男の手が、レジのカウンターを思いきり叩いた。
大きな音が店内に響き、すずの背筋が凍る。心臓がバクバクと早鐘を打つ。
その瞬間だった。
「その子は、何もしていない」
低く、はっきりとした声が響いた。
ふと視線を向けると、店の奥の影から、あの老人が現れた。
いつものように地味なジャケットを羽織り、手には小さな買い物かごを持っていた。
いつからそこにいたのか、すずにはわからなかった。
けれど、その存在は確かに“そこ”にあった。
「はあ?なんだてめぇ……ジジイはすっこんでろ!」
男はそう怒鳴りながら、老人に詰め寄ろうとした。
しかし、老人は一歩も退かなかった。
「お前の財布は、ズボンの後ろポケットにある。右側だ」
その言葉に、男は思わず動きを止めた。
「……は?」
「たった今、入れていたのを見た。出す時に酔って落としたと思い込んでるだけだ」
男が震える手でズボンのポケットを探る。
──そこには、くしゃくしゃになった財布があった。
「……あ、あった……」
男は黙り込んだ。恥ずかしさと怒りと、プライドのやり場に困ったような顔で、黙って缶ビールを抱えたまま店を出ていった。
自動ドアの開閉音だけが、虚しく残る。
沈黙の中、すずはようやく息をついた。
「……ありがとう、ございます」
声が震えていた。
老人はすずの方を見て、静かに頷いた。
「何もできなくても、黙って立っているだけじゃ、守れない」
そう言って、買い物かごをレジに置いた。中には食パンと、お茶が入っていた。
「これ、お願いします」
「あ、はい!」
すずは慌ててレジを打った。手が少し震えていた。
袋詰めを終えると、老人は商品を受け取り、再びすずに頭を下げた。
「怖かっただろう。けれど、君は落ち着いていた。立派だったよ」
「……いえ、怖かったです。すごく……でも……」
「でも?」
「でも、来てくれて……ありがとうございます」
そう言ったとき、自分の目に涙がにじんでいることに気づいた。
涙なんて、見せたくなかったのに。
「私は、ただ働いてただけなんです。何も悪くないのに……」
その一言が、堰を切ったように胸に溜めていたものをあふれさせた。
「頑張っても、ちゃんとしてても、なんかいつも……」
老人は、そんなすずの言葉を遮らず、ただ静かに聞いていた。
そのまなざしには、何も言わずとも「わかっているよ」と伝える温かさがあった。
「きっと、誰にも見られていないと思うだろう。でも、君がちゃんとやっていることは、誰かが必ず見ている」
老人は、すずの目をまっすぐに見つめた。
「月は、いつも見ている。たとえ雲に隠れていてもね」
それだけ言って、老人はゆっくりと店を後にした。
夜の空は、いつの間にか晴れ間を取り戻していた。
すずは自転車で帰る途中、公園の前で一度だけ止まった。
ベンチに、誰もいない。
でも、どこかあたたかい余韻が残っているように感じた。
「……ありがとう。ほんとに」
夜風にそっと言葉を乗せると、雲の切れ間から月が顔をのぞかせた。
それはまるで、すずの胸の奥に灯った小さな光に、優しく呼応してくれたようだった。
 「ああ、めんどくさいの来たかも……」
「ああ、めんどくさいの来たかも……」
第五章:老人の過去を知る
――もと保育園経営者・震災で家族を亡くしていた
春の夜風が、少しだけ柔らかくなってきた頃。
すずは、いつもの帰り道にふと足を止めた。
団地裏の公園。
誰もいないはずのその場所に、あの老人がいた。
けれど今日の彼は、掃除道具も持たず、ただベンチに腰かけて、静かに空を見上げていた。
「こんばんは……」
すずは、初めて自分から声をかけた。
老人はゆっくりと顔を上げた。
その目には、いつものような淡々とした静けさの奥に、どこか遠くを見ているような深い陰りがあった。
「……座ってもいいですか?」
「もちろん」
すずはベンチの端に腰を下ろした。
ふたりの間には少し距離があったけれど、その沈黙は、以前のようなぎこちないものではなかった。
しばらくの間、何も言葉を交わさず、ただ夜の空を見上げた。
月が、雲の切れ間からのぞいていた。
「月って……変わらないですね。どこにいても、誰が見ても」
すずがそうつぶやくと、老人が微かに笑った。
「ええ。変わらないものも、少しはある」
その言い方に、どこか哀しみがにじんでいた。
「……あの、聞いてもいいですか?」
「何を?」
「どうして、いつもここを掃除してるんですか?」
老人は少しの間、答えなかった。
やがて、小さく息を吐くと、ぽつりと語り始めた。
「私は……昔、保育園を経営していたんですよ」
すずの目が大きく見開かれた。
「保育園……?」
「小さな町の、ごく普通の園でした。妻と一緒にやっていてね。私は園長として、毎朝、子どもたちを迎えては、一緒に遊び、絵本を読み、夕方にはお迎えを待って……」
老人の声が、少し震えていた。
「仕事は大変でしたが、楽しかった。子どもたちは無邪気で、毎日が宝物のようでした」
その表情に、一瞬だけ光が差した。
「でも、ある日……震災が起きた」
すずの身体がわずかに強張った。
「東日本大震災、ですか?」
「ええ。もう十年以上前になります」
老人は空を見上げながら、言葉を続けた。
「当時、私は被災地にいたんです。ちょうど保育園の改築工事で、仮設の園舎にいた。妻と娘、そして保育士の先生、子どもたち……皆、そこにいた」
沈黙が落ちる。
風の音だけが、二人の間を通り過ぎていく。
「津波が来ました」
その一言は、あまりにも静かで、だからこそ重たかった。
「私は……園の外に出ていて、偶然助かりました。けれど、あの日、あの時間に、園の中にいた全員が……」
言葉が続かない。
すずは何も言えなかった。ただ、胸の奥がじんわりと熱くなるのを感じていた。
「助けられなかったんです。誰一人として」
老人の手が、膝の上で静かに握られていた。
「保育園も、家族も、すべて……失った。それから私は……すべてを辞めて、名も変えて、この町に流れ着きました」
「……名前、変えたんですか?」
「ええ。あの日から、“自分”という存在に意味がなくなってしまったように感じたんです。何もかも、自分のせいに思えてならなかった」
静かな夜の中に、かすかな嗚咽が混じる。
「それでも、毎朝目が覚めてしまう。だったらせめて、誰にも気づかれないように、誰かの邪魔にならないように、小さな場所をきれいにして歩こうと……そんなことしかできなかった」
すずは、息を詰めて聞いていた。
「人から見れば、奇妙で意味のない行動かもしれません。でもね、私にとっては……」
そこで老人は言葉を止めた。
ゆっくりと、すずの方を見た。
「……生きていることの、言い訳だったのかもしれません」
その言葉に、すずの目に涙が溢れた。
「違います」
「え?」
「それは、言い訳なんかじゃないです」
すずは涙をぬぐいながら、しっかりと言った。
「私……ここがきれいだから、夜でも怖くなかった。
学校で嫌なことがあっても、この道を歩いてると、なんだか安心できたんです」
老人は、驚いたように目を見開いた。
「知らなかったかもしれないけど……ちゃんと、届いてました。あなたの優しさ、ちゃんと、誰かを守ってたんです」
すずの声は震えていたが、まっすぐだった。
「私は、そういう人になりたい。誰にも気づかれなくても、誰かを支えられる人に……」
老人は、小さく頷いた。
その顔に、初めて見るような、やわらかな微笑みが浮かんでいた。
「ありがとう」
その一言が、夜空に溶けていった。
ふたりの上に、月が静かに照っていた。
 風の音だけが、二人の間を通り過ぎていく。
風の音だけが、二人の間を通り過ぎていく。
第六章:すずの進学の夢と葛藤
――老人は何も語らず見守る
春の終わり。
団地の前の桜並木が、静かに緑の葉を広げ始めたころ、すずは一枚の紙を握りしめていた。
それは、夜間高校の進路指導室でもらった「奨学金申請書類」。
希望すれば、保育士の専門学校への進学が可能になるかもしれない。
ただし、それは「条件つき」だった。
学費のほかに必要となる、教材費、交通費、制服代、実習先までの交通費——。
いくら奨学金が出たとしても、生活費は別。
そして祖母との二人暮らし。どちらかが倒れたら、すべてが止まってしまう。
「……現実は、甘くないよね」
すずは、紙をそっと畳んで鞄の奥にしまった。
夢を追うことが、誰かを犠牲にすることになるなら、それは“ワガママ”なんじゃないか。
その問いが、ずっと胸の奥に渦巻いていた。
その夜、すずは遅くまで部屋で書類を眺めていた。
ちゃぶ台の上、ぼんやりと光る白熱灯の下で、奨学金の条件に目を通す。
「高等学校卒業見込者であり、かつ学業・人物ともに優れ……」
「うーん……“人物”って……私、何かしてきたっけ」
自嘲のように笑って、ため息をついた。
ふと、襖の向こうから祖母の小さな咳払いが聞こえた。
季節の変わり目は、いつも体調を崩しやすい。
「ばあちゃんが倒れたら、バイト増やすしかないよね……」
呟いたその声が、意外にも大きく響いた。
次の日、学校の帰りに公園の前を通ると、例の老人がいつものように、ほうきを手に落ち葉を集めていた。
すずは自然と、足を止めた。
「こんばんは」
「こんばんは」
短い挨拶。それだけなのに、胸の奥が少しだけ和らいだ。
しばらく並んで歩いたあと、すずがぽつりと話し始めた。
「……進学、悩んでるんです」
老人はほうきを止め、ゆっくりとすずに視線を向けた。
「本当は保育士になりたい。でも、家のことがあるし、現実的に厳しくて。
もし……もしばあちゃんが倒れたら、全部、終わっちゃうから」
老人は、何も言わなかった。
ただ、すずの言葉にじっと耳を傾けていた。
「進学って、夢を持つって、誰かの犠牲の上に成り立つものなんですかね」
すずの声は震えていた。
心の中の葛藤が、とうとう溢れそうになっていた。
「私は、ばあちゃんを守りたい。でも……それだけじゃ、ダメなのかな」
沈黙が落ちた。
けれど、その沈黙は決して冷たいものではなかった。
老人のまなざしには、言葉よりも深い何かが宿っていた。
「……私、欲張りなんでしょうか」
そう尋ねたとき、老人はゆっくりと首を横に振った。
それだけだった。
言葉はなかった。でもその仕草だけで、すずの胸の中の何かが、ふっと軽くなった。
「……ありがとうございます。なんか、ちょっと楽になりました」
すずは笑った。少しだけ涙ぐんでいたけれど、それは悲しみの涙ではなかった。
その夜、すずは祖母と夕食を囲んでいた。
食卓には、玉ねぎと人参だけのカレー。
それでも祖母は「おいしいねぇ」と言って笑った。
「すず、最近ちょっと顔つき変わったね。前より、強くなった」
「……そうかな?」
「うん。いい顔してるよ。きっと、いろんなことをちゃんと考えてるんだね」
祖母の言葉が、すずの胸に静かに染み込んだ。
「ばあちゃん……もし、私が進学したいって言ったら、どうする?」
「そうねぇ……うれしいと思うよ」
「でも、生活きつくなるよ?ばあちゃんも働けないし……」
祖母は、そっとすずの手を取った。
「すず、あなたには自分の道を歩んでほしいの。
私のために夢をあきらめたなんて、そんな話……聞きたくないよ」
その言葉に、すずは涙が溢れた。
「ありがとう……ばあちゃん」
カレーは少し冷めていたけど、今夜の食卓は、どこか温かかった。
その日の深夜。
すずはもう一度、鞄の奥から奨学金の申請書を取り出した。
ペンを握る手は、もう迷っていなかった。
すずは、静かに、でもしっかりと、自分の名前を記入した。
「……やってみる」
誰かのために。
そして、何よりも自分のために。
夜の窓の外には、またあの月が出ていた。
それはまるで、遠くからすずの決意を見守ってくれているようだった。
そして、あの公園の隅で、ひとりの老人もまた、
何も語らず、静かにその光を浴びていた。
 「……現実は、甘くないよね」
「……現実は、甘くないよね」
第七章:祖母が倒れ、進学どころではなくなる
それは、すずが進学願書を提出してからわずか一週間後のことだった。
その夜も、すずはいつものようにバイトを終え、コンビニの裏で自転車のチェーンに油をさしていた。風が冷たく、春の終わりとは思えないほど肌寒い夜だった。
ふと、スマートフォンが震えた。
祖母との共用電話番号からの着信。
こんな時間に?
嫌な予感がすずの背中をぞわりと走った。
「……はい、すずです」
『あの……高橋すずさんのご家族の方ですか?』
知らない女性の声。背景に機械音とアナウンス、そして人の話し声が聞こえる。
「……はい。孫です。祖母に何かありましたか?」
『実は、おばあさまが倒れられて、いま救急でこちらの病院に……』
その瞬間、すずの中で何かが「真っ白」に消えた。
病院に駆けつけたすずを迎えたのは、祖母のか細い寝息と、点滴の針が刺さった細い腕だった。
「脱水と栄養不足、そして軽い脳貧血……」
医師は冷静に説明したが、その言葉一つひとつがすずの胸に鋭く突き刺さる。
「もっと早く気づいていれば……私、ちゃんと見てたつもりだったのに……」
ベッドの傍らで、すずは小さく肩を震わせた。
祖母は、すずの手を握り返す力すらなかった。
それでも、うっすらと目を開けて、かすかに微笑んだ。
「ごめんねぇ、すず……」
「ばあちゃん……謝らないで。悪いのは私だから……」
涙が止まらなかった。
夢なんか見てる場合じゃなかった。進学どころじゃない。
翌朝、すずは学校に「しばらく休みたい」と連絡を入れ、バイトもすべてキャンセルした。
それからの数日は、祖母の入院手続きと家のことだけで精一杯だった。
病室に通いながら、保険証や介護申請の書類、病院との相談……。
やるべきことは山ほどあるのに、頭の中はまとまらなかった。
団地の部屋に戻ると、妙に部屋が広く感じられた。
祖母の湯呑み。
祖母の座布団。
祖母の杖。
どれもそこにあるのに、祖母がいないだけで、世界が色を失ってしまったようだった。
すずは、願書の写しを見つけて、そっと破り捨てた。
「……しょうがないよね。今は、こっちが大事だから」
自分に言い聞かせた。
でも、胸の奥に沈んだ“なにか”は、消えてくれなかった。
数日後、夕方の病室。
祖母は少し顔色が戻り、うっすらと声も出せるようになっていた。
「すず……学校は、どうしてるの?」
「今は行ってないよ。そんな場合じゃないから」
「バイトも……?」
「やめた。当分、休むって言ったよ」
祖母は、何も言わなかった。
ただ、少し寂しそうに笑った。
「ごめんねぇ。すずの邪魔ばっかりして……」
「違うってば。ばあちゃんのせいじゃないよ」
「でも……せっかく、夢を……」
すずは、少し声を強めた。
「もう、その話はやめよう。今は、ばあちゃんが元気になることが一番大事だから」
祖母は頷いた。けれど、わずかに潤んだ目の奥には、何かを飲み込んだような痛みがあった。
すずもまた、それを感じ取っていた。
病院からの帰り道、すずは団地裏の公園に足を向けた。
夜風が木々を揺らす。
ブランコが誰も乗っていないのに、かすかにきしんだ。
ベンチには、老人がひとり座っていた。
手には竹ぼうき。けれど今日は掃除をしていなかった。
すずは、その隣に無言で腰を下ろした。
しばらくの間、ふたりとも何も話さなかった。
やがて、すずが口を開く。
「……進学、やめました」
老人はすずを見なかった。ただ、月を見つめたまま、静かに呼吸を続けていた。
「ばあちゃんが倒れちゃって、もう無理なんです。
だから、もうあの道は選ばない。仕方ないって、思ってます」
しばらく沈黙があった。
そして、老人がぽつりと言った。
「……月は、欠けても、また満ちるよ」
すずは目を見開いた。
「え?」
「今は、そう思えなくても。欠けた月も、必ずまた満ちていく。
道は、一本きりじゃない。少し休んで、また別の道を歩けばいい」
その声は、穏やかで、でも芯のあるものだった。
「でも……私には時間も、お金も、余裕も……」
「君には、“心”がある。今、それを大事にしてる。
それだけで、十分すごいことだと思うよ」
すずは、目を伏せた。
頬をつたった涙が、静かにベンチに落ちた。
「ありがとう……ございます」
老人は何も言わなかった。
ただその場に、黙って寄り添ってくれていた。
月は、雲の切れ間から静かに顔を出していた。
その光が、すずの肩を優しく照らしていた。
その夜、すずは久しぶりに深く眠った。
明日、どんな朝が来るかはわからない。
けれど、月が見てくれている。
そう思えるだけで、少しだけ前に進める気がした。
 「脱水と栄養不足、そして軽い脳貧血……」
「脱水と栄養不足、そして軽い脳貧血……」
第八章:老人から手紙だけが届く
あの日から、公園に老人の姿はなかった。
風が吹いても、雨が降っても、決まった時間にそこにいたはずの人が、ふいに消えてしまった。
すずは、最初の数日は「たまたま会えなかっただけ」と思い込もうとした。
でも、三日経ち、一週間が過ぎても、ベンチには誰も座っていなかった。
掃き清められていた公園の地面には、いつの間にか落ち葉が積もり、風に転がる空き缶がやけに耳に残る。
「……まさか、どこか具合でも……」
不安が心の中にじわじわと広がっていく。
名前も住所も知らない。
ただ、あの場所に毎日いた、という事実しか手がかりはなかった。
何も知らない。けれど、確かにあの人は、自分の心の支えだった。
「いなくならないでほしい」
そう願っても、現実は残酷に静かだった。
そして、その日。団地の郵便受けに、一通の封筒が届いていた。
差出人の欄は、空白。
けれど、見覚えのある、筆ペンのような癖のある文字で、宛名にこう書かれていた。
――すずさんへ
すずの手が、わずかに震えた。
封を開けると、中には一枚の便箋と、もう一つ、古びた鍵が同封されていた。
手紙の内容は、こうだった。
すずさんへ
この手紙が届く頃、私はもう、この町を離れていることでしょう。
あなたに、何も告げずに姿を消すこと、どうか許してください。
本当は、もう少しあなたの側にいたかった。
あなたのように強く、そして優しい若者が、この町にいることが、私にとってどれだけ救いだったか。
でも、私にはもう、あなたに何もしてあげられない。
あの日、公園であなたと話してから、私はようやく自分の時間を前に進める決意ができました。
ずっと、あの震災の日に立ち止まったままでした。
でも、あなたの言葉が、少しずつ私を歩かせてくれた。
同封の鍵は、私がひとりで借りていた、小さな貸倉庫のものです。
掃除用具や古い品しかありませんが、ひとつだけ、あなたに渡したいものが入っています。
それは、私が保育園を経営していた頃、園児たちのために残した“あるノート”です。
将来、あなたが再び夢を思い出す日が来たときに、それを手に取ってほしい。
そこには、何も特別なことは書いてありません。
ただ、子どもたちと過ごした時間、彼らが笑った言葉、泣いた理由――
そして、“大人が子どもにできる、たった一つのこと”について、私はそのノートにずっと問い続けてきました。
すずさん。あなたには、その問いに向き合える力があると、私は信じています。
ありがとう。出会ってくれて。
最後に、ひとつだけお願いです。
いつかあなたが、誰かの手を握る大人になったとき、
「誰かが自分を信じてくれた」――そう思い出してください。
それが、私にとって最高の報いです。
月の光の下で、またどこかで。
老人より
手紙を読み終えたあと、すずはしばらくその場から動けなかった。
温かいのに、切なくて。
嬉しいのに、どうしようもなく胸が痛かった。
「……どうして、何も言わずに……」
でも、その気持ちもすぐに消えていった。
だって、あの人らしい、と思ったから。
言葉で説明するのではなく、行動と沈黙で伝える人だった。
次の日、すずは放課後の時間を使って、手紙に書かれていた貸倉庫に向かった。
そこは公園からそう遠くない、古びたトランクルーム。
番号の書かれた南京錠を鍵で開け、中に入ると、埃をかぶった棚やダンボールがいくつか積まれていた。
すずはその中から、一冊の分厚いノートを見つけた。
表紙には子どもの落書きのようなクレヨン画が描かれ、「こどもたちのこと」とだけ書かれていた。
ページをめくるたびに、丁寧な文字で書かれた日記や観察記録が続く。
「友樹くんが転んで泣いたけど、すぐに“痛くない”って強がった。強さと優しさは、表裏一体だ」
「雨の日、外に出られず泣いていた子が、“園長先生がいるから安心した”と言ってくれた。大人は“在る”だけで力になることがある」
すずの目から、知らず知らずに涙が落ちた。
ページの隅には、小さな手形のスタンプ。
保育園の子どもたちが残していった、“確かな証”だった。
老人は、忘れてなどいなかった。
失った人々のことも、自分の想いも。
すずはそっとノートを胸に抱きしめた。
「……ありがとう」
声に出して言った瞬間、不思議と心の奥が、ふっと軽くなった。
姿は消えてしまったけれど、あの人はちゃんと“遺して”くれていた。
想いを。問いを。道しるべを。
その夜。
すずは団地裏の公園に一人で立った。
月が、静かに光を落としていた。
ベンチに腰かけ、ノートを膝に置いて空を見上げた。
「まだ……進むのは怖いけど、私、もう一度だけ夢を見てもいいかな」
返事はない。
でも、風の音が、そっと背中を押してくれたような気がした。
 団地の郵便受けに、一通の封筒が届いていた。
団地の郵便受けに、一通の封筒が届いていた。
第九章:手紙の真相
――老人が残した奨学金の金/名前も伏せて
数日後、すずは再び学校の進路指導室に足を運んでいた。
保育士になるという夢。
一度は諦めかけたその道を、もう一度歩き出すために。
机の上に広げられた申請書類。
担当の教師は静かにすずの話を聞いていた。
「……で、本当にいいの?今から出願しても、奨学金の審査はかなり厳しいよ」
「はい。わかってます。でも、やっぱり進みたいんです。保育士になりたいんです」
強くは言えなかったが、すずの目には迷いがなかった。
教師はひとつ頷き、書類を整えながらふと声をひそめた。
「実はね……不思議なことがあったんだ」
「え?」
「先週、学校宛に“ある個人”からの匿名の寄付が届いたんだ。
君の進学費用として、全額。しかも、受取人を“すずさん”と明記して」
すずは、息をのんだ。
「……匿名、ですか?」
「うん。名前も何も書かれていなかった。ただ一通だけ、短いメッセージが添えられていたよ」
教師は、机の引き出しからコピーを取り出して、すずに渡した。
その紙に記されていたのは、たった二行。
“誰にも気づかれなくても、灯した光は誰かを照らしている”
“これは、恩返しではありません。恩送りです”
すずは、目を見開いた。
その言葉を、自分は知っている。
かつて、公園のベンチで老人が語った、あの言葉。
「……あの人、だったんだ」
確信に近いものが、心の奥でじんわりと広がった。
教師は続けた。
「そのお金で、学費はすべてまかなえる。でも、それでも進むかどうかは、君自身が決めることだよ」
すずは静かに頷いた。
「……私、進みます。その人のためにも、自分のためにも」
そう言ったとき、初めて心の奥にあった“迷い”が、完全に消えた気がした。
その帰り道、すずは貸倉庫に預けたノートを抱えて、公園のベンチに腰を下ろした。
ページをめくるたびに、子どもたちの声が聞こえてくるようだった。
泣いた日も、笑った日も、きっとその老人は全部覚えていたのだ。
そして、それを忘れないように綴っていた。
「ねえ、先生。子どもって、どうやって守るの?」
「子どもを守るっていうのはね、手を差し伸べることでもあるけど、
その子が“自分で立てるようになるまで、待ってあげること”でもあるんだよ」
そんなメモが、ノートの隅にあった。
すずは、思わず涙ぐんだ。
あの人は、今まで一度も“手を引っ張ってくれ”とは言わなかった。
ただそばにいて、見守ってくれていた。
問いかけてくれる人だった。
信じて、託してくれた人だった。
その日の夜。
すずは祖母のベッドの傍らに座り、初めて自分の夢を語った。
「ばあちゃん……私、やっぱり保育士になる。
今すぐじゃなくてもいい。でも、この気持ちだけは、本物だと思うから」
祖母は、小さく目を開け、涙を浮かべながら微笑んだ。
「……そうかい。それが、すずの生きる道なら、私はもう何も言わないよ」
「ごめんね、たくさん迷惑かけて」
「いいのよ。夢を持ってくれて、ありがとう」
二人は、手をそっと重ねた。
ぬくもりが、確かにそこにあった。
そして数日後。
すずは正式に進学が決まり、春から保育の専門学校へ通うことになった。
奨学金の欄には、「匿名の支援者より」とだけ記されていた。
だれもその正体を知らない。
けれど、すずの中では、それが誰かは、もう疑う余地がなかった。
名前も残さず、感謝も受け取らず、
ただ誰かの人生を静かに後押しする——
それが、あの人のやり方だった。
春。
入学式を終えたすずは、新しい制服を着て、もう一度、公園のベンチに立った。
「先生、私……一歩踏み出しましたよ」
空を見上げると、雲の間から月が顔をのぞかせていた。
まだ明るい夕方の月。
それでも、ちゃんと光を放っていた。
すずは、小さく手を振った。
「きっと、見てくれてますよね」
その声が、風に乗って、静かに消えていった。
 保育士になるという夢。
保育士になるという夢。
第十章:数年後、保育士になった、すずが…
「せんせーい!彩香ちゃんが泣いてるー!」
「わたし、おしっこー!」
「おなかすいたー!」
四方八方から飛んでくる園児たちの声。
笑い声、泣き声、靴の音、小さな手が伸びる気配——
すずは、慣れた手つきでそのすべてに応えながら、軽やかに園庭を駆け回っていた。
小さな保育園。古いけれど、どこか温かくて懐かしいこの場所で、すずは今日も一日を過ごしていた。
あの日の決意から数年。
夢だった「保育士」という肩書きを、すずはようやく自分のものにしていた。
「すず先生、お手紙書いたの〜!」
小さな女の子が、色鉛筆で描いたぐちゃぐちゃの紙を差し出す。
ハートのような形と、「だいすき」の文字。
すずは心からの笑顔でそれを受け取った。
「ありがとう。せんせいの宝物だね」
その子は照れくさそうに笑って、仲間たちの輪に戻っていった。
ふと、園庭の隅に一人でぽつんと座っている男の子に気づく。
「……陽翔くん、どうしたの?」
すずはゆっくりしゃがんで、同じ目線になった。
男の子はもじもじしながら、なかなか口を開かない。
しばらく待っていると、ポツリとつぶやいた。
「……ママ、お仕事で今日も来ないかもしれないって」
その言葉に、すずの胸がチクリと痛んだ。
自分も、そういう“寂しさ”を知っていた。
何もできなかった日々、誰にも言えなかった気持ち。
だからこそ、すずは言葉ではなく、手を差し伸べた。
「……そっか。じゃあ、先生と一緒に待ってようか」
陽翔くんは、小さくうなずいた。
すずの手を握るその手は、小さくて、でも確かに誰かの“未来”だった。
保育が終わった夕方。
静かな園庭を掃きながら、すずはふと空を見上げた。
薄く夕焼けが残る空。
その端に、うっすらと白い月が浮かんでいた。
「……あの人が見てくれてたみたいに、今度は、私が誰かを見守る番だね」
すずは、園の倉庫からあるノートを取り出した。
表紙に「こどもたちのこと」と書かれた、あの老人の遺したノート。
園の本棚の片隅に、彼女はひっそりと置いている。
まだ誰にも見せていない。
でもいつか、誰かに手渡す日がくると信じていた。
“恩返しじゃなくて、恩送り”
その言葉は、すずの心の中で、灯台のように静かに輝き続けていた。
その夜、自宅に戻ったすずは、祖母と並んで夕食を囲んでいた。
「今日も、忙しかった?」
「うん。でもね、泣いてた子が、笑ってくれたの」
「それはよかった」
祖母はゆっくりごはんを噛みながら、穏やかに頷いた。
もう高齢で以前のようには動けないけれど、笑顔は変わらない。
「……あの人がいなかったら、私はここにいなかったと思う」
ふと、すずはそう呟いた。
「恩人だね」
「うん。でも、名前も知らないんだ。何も残さずに、消えちゃったから」
祖母は目を細めた。
「でも、ちゃんと残していったじゃない。あんたの中に」
その言葉に、すずは静かにうなずいた。
ある雨の日の夕方。
すずは、小さな子どもを連れた若い母親に呼び止められた。
「先生……あの、ちょっとだけ話、いいですか?」
「もちろんです」
「子育てが、思ってた以上にしんどくて……正直、仕事も手一杯で……。
ちゃんとやれてるのか、わからなくて」
その言葉に、すずはにっこりと笑った。
「大丈夫ですよ。ちゃんとやれてます。
泣いても怒っても、疲れても、それでもお子さんをここに連れてきてくれてる。
それだけで、もう十分です」
母親の目に、ふっと涙が浮かんだ。
「ありがとう……そんなふうに言ってもらえるの、初めてで」
「私も、昔そうやって励ましてもらったんです。だから今度は、私が」
雨上がりの空に、また月が顔をのぞかせていた。
それは、何も語らずに人を照らす、あの日と同じ月。
すずは、その光の下で、誰かの背中をそっと押す人になっていた。
かつて、名前も知らない“誰か”に救われたように。
 四方八方から飛んでくる園児たちの声。
四方八方から飛んでくる園児たちの声。
エピローグ:月の光が照らす場所で
静かな夜の公園。
今では子どもたちがよく遊ぶ、安全できれいな場所になっていた。
すずは、ベンチに腰かけ、そっと空を見上げる。
「先生。私ね、今、笑ってますよ。泣いてばっかりだったけど、今は、ちゃんと笑えてます」
風がやさしく木々を揺らす。
月が、その上で静かに光っていた。
あの日、誰かが灯してくれた小さな光。
それは、確かに今も、誰かの人生を照らしている。
静かに、月の光のように。
 ベンチに腰かけ、そっと空を見上げる。
ベンチに腰かけ、そっと空を見上げる。
この内容は動画でもわかりやすくご紹介しています。
※動画はこのページ上部からご覧いただけます。


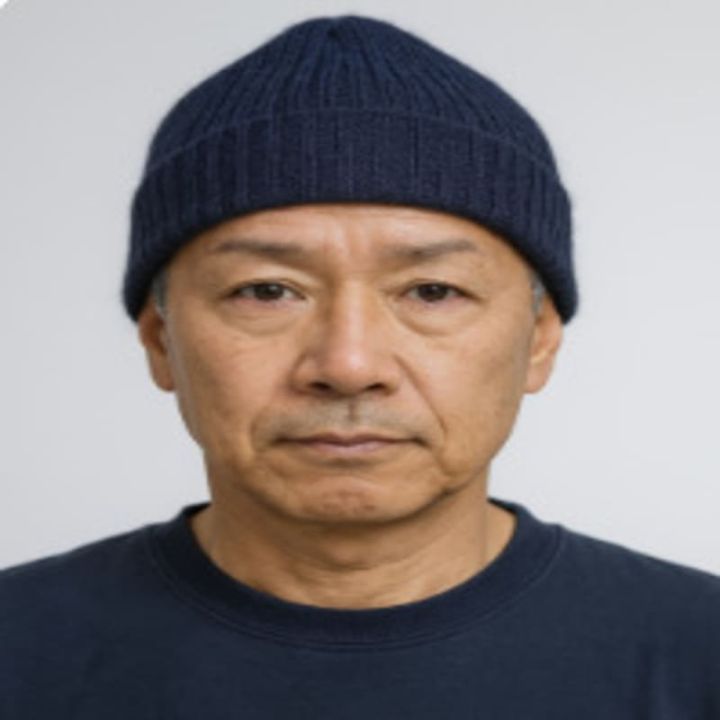



まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。