「もう一度会いたくて――命が託した 最後の祈り」
第一章:奪われた未来
ほんの一瞬の不注意で、大切な未来は失われてしまう。
その恐ろしさを、私たちは本当に想像できているでしょうか。
その朝、夫はいつもより早く目を覚ました。外は冬の冷たい光に包まれ、窓の外には霜がきらきらと輝いていた。吐く息は白く、まだ夜の名残を引きずっている。
布団の中で身を起こした妻は、大きなお腹をさすりながら微笑んだ。出産予定日が近づき、少しの体調変化にも敏感になっていた。
「病院で診てもらおう。君と赤ちゃんのために」
夫はそう言ってコートを取りに行き、妻に着せかけた。いつもなら気恥ずかしくてそんなことはしないのに、この日は違った。
玄関を出ると、冷たい風が吹き抜けた。妻の手を取り、車までゆっくりと歩く。足元の霜がシャリシャリと音を立て、遠くでは登校中の子どもたちの笑い声が聞こえた。
「もうすぐ、うちの子もこの道を歩くんだね」
夫の言葉に、妻は小さくうなずき、嬉しそうにお腹を撫でた。
車に乗り込むと、暖房のぬくもりが少しずつ広がっていった。ラジオから流れる軽やかな曲が車内を満たし、ふたりの緊張をやわらげていく。
「もうすぐだね、赤ちゃんに会えるの」
「そうだな……でも正直、まだ実感が湧かないよ」
「大丈夫。あなたはきっと優しいお父さんになる」
その言葉に、夫は胸の奥が温かくなるのを感じた。
走り出すと、窓の外には冬の景色が流れていく。街路樹の枝には雪が残り、信号待ちの交差点では人々がマフラーに顔を埋めて急ぎ足で横断していく。
「名前、どうしようか。候補はいっぱいあるけど」
「私はね、呼びやすい名前がいいな。毎日呼ぶものだから」
「たしかに。俺、変わった名前だと噛みそうだな」
ふたりは顔を見合わせ、声をあげて笑った。
その笑い声に包まれた車内は、たしかに幸せだった。
「桜が咲くころには抱っこできるんだよね」
妻の何気ない言葉が、夫の胸を締めつけた。春の風に揺れる桜の下を、三人で歩く光景が脳裏に浮かんだ。だが同時に、仕事ばかりで妻に負担をかけてきた自分を思い出し、心に小さな痛みが走った。
「赤ちゃんが生まれたら、ちゃんと一緒にいるよ。君を一人にしない」
その言葉に、妻は安心したように微笑んだ。
やがて病院へ向かう大通りに入ると、夫の目に大型トラックが映った。動きが不自然にふらついている。
「気をつけてね」
妻の声が、冷たい空気を震わせるように響いた。
その瞬間、夫の胸に強い予感が走った。守らなくては。父親になる自分が。
前方のトラックの運転席で、男が視線を下に落とすのが見えた。缶コーヒーを拾ったのか、スマホを見たのか。ほんの数秒の不注意。
それが、全てを変えることになる。
信号が黄色に変わり、夫はブレーキに足をかけた。その刹那――。
トラックが突然、車線をはみ出して突っ込んできた。
時間が伸び縮みする。
妻の驚いた瞳。
夫を庇うために身を乗り出す姿。
彼女の髪がふわりと舞い、冬の光を浴びて一瞬きらめいた。
衝突。轟音。
ガラスが粉々に砕け散り、鉄が悲鳴のように軋む。
衝撃が全身を襲い、視界が真っ白に塗りつぶされた。
耳鳴りが響き、周囲の声は遠ざかっていく。
その中で、最後に確かに聞こえたのは妻の声だった。
「あなたは……生きて……」
その一言が胸に深く突き刺さり、夫の意識は暗闇に沈んでいった。
体は鉛のように重く、指一本動かせない。
声を出そうとしても喉は凍りついたように動かない。
「俺は……まだここにいるのに……」
必死に叫んでも、その声は虚空に溶けていく。
遠くでサイレンの音が聞こえた。
人々のざわめき。誰かが泣きながら叫ぶ声。
すべてが遠ざかり、やがて完全な静寂が訪れる。
闇の中で、彼は確かに感じた。
手を握られる感覚。
頬を撫でる指先の温もり。
「大丈夫、そばにいるから」
妻の声が耳に響き、胸を揺さぶった。
その声にすがろうとした瞬間、彼の意識はさらに深く沈み、長い長い眠りへと落ちていった。
ほんの一瞬の不注意。それだけで、二人が描いていた未来は音を立てて崩れ去った。
妻は夫を庇い、命を落とした。夫は昏睡の闇に囚われ、やがて一年もの眠りへと沈んでいく。
あなたならどうしますか。もしも明日、大切な人との未来が突然奪われるとしたら――。
「守りたい人は誰ですか?」
その問いかけが、彼の物語の始まりだった。
 病院で診てもらおう。君と赤ちゃんのために
病院で診てもらおう。君と赤ちゃんのために
第二章:ささやかな日々
結婚して間もない頃、二人の暮らしは小さなアパートの一室にすべて収まっていた。
狭いキッチンで肩をぶつけ合い、安売りの食材で工夫しながら晩ごはんを作る。
炊飯器のスイッチを押し忘れて白米ができていない夜には、二人で笑いながらインスタント麺に卵を落とし、「これが意外と最高なんだよ」と胸を張る。
窓辺に置いた観葉植物はすぐに元気をなくしたが、彼女は毎朝霧吹きで水をかけ、「大丈夫、ここから強くなるからね」と植物にも自分たちにも言い聞かせるみたいに微笑んだ。
やがて彼の仕事が忙しくなった。
始発で出て終電で帰る日が増え、休日出勤は珍しくなくなった。
彼女はそんな彼に合わせて生活のリズムを少しずつずらし、夜の十時を過ぎるとお米を研ぎ、十一時を過ぎると味噌汁を温め直し、日付が変わりそうになるとラップの上からそっと手で温度を確かめた。
彼がドアを開ける音に合わせて立ち上がり、「おかえり」と言う声の高さを、疲れに合わせて毎回ほんの少しだけ調整する。
その気遣いは、誰にも気づかれないほど細いけれど、確かに届いていた。
料理は得意ではなかった。
卵焼きは端が丸まらず、いつもどこかが破れた。
ハンバーグは火加減を誤って焦げ目が濃すぎ、シチューはとろみがつかずに水っぽくなる日もある。
彼女は「また失敗しちゃった」と笑って両手を合わせ、彼は「この味が一番いい」とわざと大げさに褒めた。
二人の間に立ちのぼる湯気は、完璧からは遠いのに、なぜだか安心の匂いがした。
リンゴを剥けば皮は分厚く、断面は不揃いだが、果汁は逃げずに皿に滲み、彼はその甘さに目を細めた。
「厚いほうが甘いね」と言うと、彼女は毎回少し照れた顔をして、「ほんと? よかった」と答えた。
彼は感謝を言葉にするのが下手だった。
喉まで上がってきた「ありがとう」が、疲労に引っかかって形にならない。
玄関で靴を脱ぎながら「うまかったよ」と言えなかった夜がいくつ積もっただろう。
テーブルの上に残された付箋には「レンジで30秒」「おみそは薄め」「お茶わかしてね」と、丸い字で優しい命令が並び、どの行の端にも「ね」がついている。
彼はその「ね」に何度も救われた。
強制にはならず、頼りない夜の自分にも届く合図だった。
季節が巡る。
春、二人は散歩ついでに公園のベンチでパンを分け合い、彼女は鳩におそるおそるパン屑を配っては「わ、来た」と笑い、彼は「社交的だな」と肩をすくめた。
夏、扇風機の首振りに合わせて二人の前髪が同じリズムで揺れるのを眺め、冷凍庫からアイスを取り出して同時に包みを破る。
秋、帰り道に彼女が拾った落ち葉を紙袋に詰めて「ミニ紅葉狩りだよ」とテーブルにひろげる。
冬、こたつの中で靴下を脱ぎ忘れたままうたた寝してしまい、彼がそっと毛布をかけると、彼女は寝言で「ありがとうね」と言った。
うとうとしたその瞬間の「ね」は、どんな詩よりもあたたかかった。
妊娠が分かった日、彼女は検査薬を握ったまま言葉を探し、目尻を震わせながら笑った。
「あなた、パパになるんだって」
彼は「本当に?」を何度も繰り返し、二人で湯気の立たないお茶を何度もすすった。
妊娠初期のつわりが始まると、冷蔵庫の匂いで顔をしかめ、キッチンに立つ時間が短くなった。
彼は代わりにインスタントスープを用意し、「今日は無理しないで」と差し出す。
彼女は申し訳なさそうに「ごめんね」と言い、彼は「いいよ」と返す。
そのやりとりは同じ言葉でも、日ごとに含む気持ちが増えていった。
エコー写真が冷蔵庫の扉を埋めていく。
写真の端には日付と週数、そして「指しゃぶり」「横向き」「あくび」と短いメモ。
彼は仕事から帰るたび、それをひとつずつ指先でなぞり、離れていた時間のぶんだけ父親に近づいた気がした。
名前の候補を書いたメモは次々に貼り替えられた。
彼女は「あなたが呼ぶ声で決めたい」と言い、彼は洗濯物を畳みながら小声で候補を呼ぶ練習をした。
寝室の明かりの下、キッチンの隅、ベランダの椅子。
家じゅうの空気に、まだ見ぬ子どもの名前がしみ込んでいった。
小さな喧嘩もある。
買い忘れた牛乳、洗濯物の干し方、シンクに置きっぱなしのマグカップ。
口調が強くなって沈黙が落ちる。
しばらくして、彼女が台所の入り口から顔を出し、「ごめんね」と言う。
彼も「ごめん」と言う。
謝る順番を譲り合うみたいに同時に頭を下げ、二人で笑って仲直りをする。
喧嘩のあとに作るスープは、どんなご馳走よりも温かかった。
妊娠後期、階段の一段一段をゆっくり上るようになり、靴ひもを結ぶときに彼女は息を整える。
彼は靴ひもを代わりに結び、コートのボタンを留めてから、最後のボタンだけ少し緩める。
「きつくない?」と聞くと、彼女は「だいじょうぶね」と笑って、いつもの「ね」を語尾に置く。
彼はそのたび、胸の内側に見えない印を増やした。
だいじょうぶ、ね。
大丈夫だ、と言い切らないやさしさに、二人の余白があった。
仕事がさらに忙しくなったある時期、彼は自分なりに工夫をした。
帰り道のコンビニで温かい肉まんを二つ買い、家の前で湯気が逃げないよう袋の口をきつく縛って帰る。
彼女はドアを開けるなり「わ、匂い」と目を細め、半分こにした肉まんの熱に「あつっ」と笑う。
遅い夜の簡単なご馳走。
たったそれだけで、暮らしはやわらかいほうへ少し傾いた。
ある雨の日、彼が傘を忘れて濡れて帰ると、彼女はタオルを二枚持って走ってきて、一本は彼に、もう一本は自分の肩に。
彼の髪を拙い手つきで拭きながら、指先のささくれにタオルが引っかかる。
「風邪ひいちゃうよ」と言う声に、彼は何も言えず頷く。
彼女は自分の肩を濡らしたまま、どこか誇らしげだった。
翌朝、玄関に二人分の折りたたみ傘が並んでいるのを見て、彼は小さく笑った。
取っ手には、彼女の丸い字で「忘れないでね」と書かれた付箋が貼られていた。
夜更けに目が覚めると、彼女が彼の手を握って眠っていることがあった。
枕元のティッシュの丸い塊が、泣いたあとを物語る。
彼はその手をほどかずに、そっと握り返す。
言葉は出てこない。
でも、返す圧は確かだった。
胸の奥から「ありがとう」が何度もあふれては、喉の途中でほどけて消える。
明日の朝こそは言おう――そう決めて目を閉じるのに、朝になると電車の時間に追い立てられ、靴ひもの結び目が固くなるほど余裕がなくなる。
ある朝、彼女はエプロン姿のまま玄関まで送りに出て、「いってらっしゃい」をいつもより半音だけ明るく言った。
背中がドアの向こうに消えかけた瞬間、彼は衝動的に振り返りかけて、結局そのまま階段を下りた。
踊り場の窓から差し込む光が、彼の影を細く伸ばす。
改札を通りながら、彼は胸の奥でつぶやいた。
――今夜はちゃんと言おう。「ありがとう」を、言おう。
検診のたび、彼女は小さな報告を持ち帰った。
「今日は横向きだった」「しゃっくりしてた」「手を振った気がする」。
エコー写真の白と黒の世界に、彼は現実感を持てずにいたが、彼女の声の色だけは鮮やかに胸へ染み込んだ。
帰宅が遅い日、テーブルに置かれた彼女のメモは短くなる。
「先に寝るね」「体調まずまず」「あなたも無理しないで」。
そしてやっぱり、末尾には「ね」がいる。
彼はメモを財布に一枚忍ばせ、職場の昼休みにそっと読み返した。
そこには、家の匂いと彼女の気配が確かにあった。
出産準備のリストを二人で作った。
母子手帳、入院バッグ、ガーゼ、産着。
名前の候補を冷蔵庫に貼り、呼びやすさと苗字との相性を夜更けまで議論する。
彼はふざけて珍妙な案を出し、彼女は笑い転げた。
笑いすぎてお腹を押さえ、「だめだよ」と眉を下げる。
彼は慌てて水を差し出し、二人で落ち着くと、また候補の紙に戻った。
彼女は指で「この音、好き」となぞり、彼はその指の動きを目で追った。
紙の上で未来が少しずつ形になるのを、二人とも信じていた。
事故の前日、彼女はリンゴを剥く練習をしていた。
包丁を握る手つきは相変わらずおぼつかない。
皮は分厚く、ところどころで途切れ、皿には不揃いな白い月が並んだ。
「ほら、厚くなっちゃった」と彼女は笑った。
彼はひと切れ頬張り、「甘い」と言った。
ほんとうに甘かった。
彼女は安堵のため息をつき、「よかった」と小さく拍手した。
彼はその拍手の音を、たぶんずっと忘れない。
その夜、寝る前に彼女はぽつりと言った。
「ねえ、あなた。パパになるんだから、しっかりしてよ」
叱っているわけでも、追いつめているわけでもない。
信じている人の声だった。
彼はうなずき、「任せて」とだけ言った。
本当は、もっと言いたいことがあった。
ありがとう、ごめん、愛してる。
全部言おうとしたが、うまく言葉が並ばなかった。
明日、病院へ向かう車の中で言えばいい。
そう思って、目を閉じた。
翌日、朝の光は澄んでいた。
窓のカーテンの隙間から射す線が床に落ち、彼女の荷物の影を細長く引き延ばす。
彼はカバンの中身を最終確認し、彼女は母子手帳のポケットを何度も触って安心を確かめる。
玄関で靴を履くとき、彼はしゃがんで彼女の靴ひもを結び、結び目を二重に固くした。
「ほどけないようにね」と言うと、彼女は頷いて、例の付箋の「ね」みたいに柔らかい返事をした。
ドアを開ける。
空気は少し冷たく、道路の向こうの街路樹が静かに揺れていた。
ハンドルを握る手のひらに汗が滲む。
彼女がシートベルトを確かめ、「準備、完了」と小さく親指を立てる。
彼は頷き、エンジンをかけた。
あの時点でも、世界はまだいつもの続きだった。
彼は言おうとしていた。「ありがとう」を。
信号がいくつか過ぎたら、少し広い道に出たら、タイミングのいいところで。
彼は胸の内側で言葉の順番を決める。
「ありがとう」から始めよう。
「心配かけてごめん」と続けよう。
「愛してる」で締めくくろう。
右折のウィンカーを出し、ミラーを確かめ、彼女の横顔を一瞬見た。
目尻に細い光が宿っている。
彼はそこで、ようやくほんの少し口を開いた。
最初の一文字が喉の奥で震え、空気が息と一緒に動き出す――
その刹那まで、世界はたしかに、優しかった。
 安売りの食材で工夫しながら晩ごはんを作る
安売りの食材で工夫しながら晩ごはんを作る
第三章:昏睡の闇で聞こえる声
闇の底で、彼は漂っていた。
真っ暗な深淵の中、時間の感覚はなく、昼も夜も、季節の移ろいも、すべてが飲み込まれている。
どれほど沈み続けているのか、自分が生きているのか死んでいるのかさえ分からない。
ただ、冷たい水の中をゆらゆらと漂っているような、孤独と恐怖だけがつきまとっていた。
そのとき、不意に声が聞こえた。
「……あなた、聞こえる?」
柔らかく、かすれた声が耳の奥に触れる。
声がするたびに、冷たい海の中に落ちていた体が一瞬だけ浮かび上がる。
それは妻の声だった。
最初は夢だと思った。
けれど何度も繰り返し聞こえてくるうちに、彼はその声を頼りにしはじめる。
「大丈夫。そばにいるから」
「ほら、りんご……ちょっと厚くなっちゃったけど」
「今日は、あなたの好きな匂いの柔軟剤にしたの」
――果物の甘い匂い。
――ぎこちない包丁の音。
――夜中に手を握られる感覚。
現実か幻かは分からない。
けれど、愛する人の存在を必死に感じ続けるその時間だけが、彼を生かしていた。
意識の奥底では、しばしば冷たい孤独に襲われた。
「もう戻れないのではないか」
「自分はこのまま忘れられてしまうのではないか」
そんな恐怖が押し寄せ、心臓の鼓動が遠ざかり、呼吸が薄くなっていく。
そのたびに、妻の声が現れる。
「しっかりして。あなたはパパになるんだから」
「赤ちゃんも、待ってるよ」
その言葉に縋りつくようにして、彼は再び浮かび上がる。
ある日、額に冷たい滴が落ちてきた。
それは水ではなく、涙だった。
妻の涙が頬を伝い、胸の奥に小さな火を灯した。
「泣かないで……俺は、ここにいる」
言葉にならない声を心で叫ぶ。
またある日には、手の中に柔らかい感触があった。
小さな指が、自分の指に重なったような感覚。
「この子、元気に動いてるよ。あなたに似て、力強いの」
――赤ん坊の胎動だろうか。
幻かもしれない。けれど、そのぬくもりが確かに伝わってきた。
彼は次第に悟り始める。
「これは現実ではないのかもしれない」
「でも、ここにとどまる限り、妻と一緒にいられる」
その甘美な誘惑が、心を蝕んでいく。
しかし、妻の声はいつも同じ言葉を残す。
「起きて。あなたが目を覚まさなきゃ、この子はひとりになっちゃう」
「ほら、もう一度、一緒に歩こう」
彼の胸に矛盾が生まれる。
この闇にいれば、妻とずっと一緒にいられる。
けれど、それでは生まれてくる命を守れない。
――妻が本当に望んでいるのはどちらだろうか。
その問いが、彼を揺さぶり続けた。
闇の中、妻が最後にそっと耳元で囁いた。
「あなたは、生きて」
「この子を、お願いね」
その瞬間、彼はすべてを理解した。
妻は自分を守り、代わりに未来を託したのだ。
彼は胸の奥で叫んだ。
「分かった。俺は生きる。必ず、守る」
すると、どこか遠くで光が揺れた。
長い闇を切り裂くように、白い光が差し込んでくる。
まぶたが震え、重い扉がゆっくりと開いていく。
闇は、果てしなく深かった。
昼も夜もなく、上も下もなく、時間の進みさえ感じられない。
ただ漂うだけの意識は、時折、絶望に飲み込まれそうになる。
けれど、その闇の向こうから、必ず声が聞こえてきた。
「あなた……聞こえる?」
その声が現れるたびに、沈んでいく体がふわりと浮かぶ。
彼の名を呼ぶ声。震えながらも必死に届こうとする声。
それは間違いなく、妻の声だった。
「そばにいるから、大丈夫」
「手、握ってるよ。分かる?」
やわらかな感触が指先を包む。
それが幻なのか、現実なのか、分からない。
けれど、その温もりに触れた瞬間だけ、孤独がやわらいだ。
日によって、声の調子は違っていた。
ある日は明るく、「今日はね、あなたの好きなりんごを剥いたの」
その音に重なるように、シャクッと包丁が果実を割る音が聞こえる。
厚めに皮が残っている不格好なりんご。
けれど、その不格好さが愛しくて、胸が熱くなる。
またある日は、泣きながら囁かれる。
「お願いだから、帰ってきて」
その声とともに、頬に冷たい滴が落ちる。
涙だ。妻の涙が、自分の顔に触れている。
彼は必死に返そうとする。
――泣かないで、俺はここにいる。
けれど、声にならない。思いだけが胸にこだまし、闇に溶けていく。
時には、別の感覚も混じった。
まだ見ぬ命の胎動。小さな足で蹴るような感覚が掌に広がる。
「この子ね、元気に動いてるの。きっと、あなたに似てるんだと思う」
妻の笑い声が重なる。
彼はその一瞬、胸の奥から光が溢れるのを感じた。
――守らなければ。
そう思ったのに、体はまだ動かない。
闇の底での暮らしは、永遠にも感じられた。
孤独と、愛情の声とが交互に訪れる。
彼の心は何度も揺れた。
この闇にいれば、妻とずっと一緒にいられる。
「ここに残ってもいいのではないか」という甘い誘惑が忍び寄る。
だが、妻の声はいつも最後に同じ言葉を置いていった。
「起きて。あなたが目を覚まさなきゃ、この子はひとりになっちゃう」
「大丈夫。あなたならできる。だから……戻ってきて」
その言葉が、胸の奥に杭のように打ち込まれる。
彼は考える。
――妻が本当に望んでいるのは、どちらだろうか。
闇に留まり、共にいることか。
それとも、光に戻り、命を守ることか。
答えは分かっていた。
妻はいつだって、不器用なほど他人を優先する人だった。
焦げた目玉焼きを「ごめん」と差し出しながら笑った顔。
風邪をひいても熱を隠してでも彼を看病した姿。
――あの人なら、迷わず命を託す。
「君は、俺に生きろと言っているんだな」
闇の中で、彼は震える声を絞り出す。
すると、妻の声が近くで囁いた。
「あなたは、生きて」
「この子を、お願いね」
その瞬間、全身に熱が走る。
長い間沈んでいた体が、一気に浮かび上がる感覚。
闇の中に、白い光が差し込む。
光は最初は小さな点だったが、次第に大きく広がり、闇を押しのけていく。
まぶたが震え、重い扉のようにゆっくりと開きはじめる。
世界が戻ってくる。
消毒液の匂い、機械の規則的な音、遠くで泣き声が混じっている。
耳の奥で、妻の声が最後に響いた。
「ありがとう。大好きだよ」
涙が、閉じたまぶたの隙間から零れ落ちた。
彼はその瞬間、全身で理解した。
妻は、もういない。
けれど、守られた命が待っている。
――生きる。
彼は心の底で誓った。
妻の分まで、生き抜いてみせると。
 ……あなた、聞こえる?
……あなた、聞こえる?
第四章:失われた命、託された命
まぶたの裏で、白い光がふくらんでは縮み、またふくらむ。
長い長い海底から浮上してくるように、世界が音を取り戻していった。
ピッ、ピッ、と一定の合図。どこかで布の擦れる音。消毒液の乾いた匂い。
喉は砂を飲み込んだみたいに痛く、胸は自分のものではないように重い。息を吸うたび、肺の奥がきしんだ。
「……っ、ぁ……」
掠れた声が自分のものだと理解するまでに、少し時間がかかった。
視界がまだらに解け、天井の白が輪郭を持ちはじめる。
次に見えたのは、目尻を濡らして笑った母の顔だった。
「起きた、起きたのね……!」
肩を震わせ、母は手を取り、子どもの頃みたいに何度も何度もその手を擦った。
父がその横で大きく息を吐き、こわばった口元を手の甲で押さえた。
「……俺は、どれくらい……」
言葉に形が宿る。
父が短く目をつむってから、ゆっくり答えた。
「一年だ。よく、帰ってきた」
一年。
数字が頭のどこかで転げ落ちる。
時間の実感はない。あるのは、闇の底で聞こえた声の記憶ばかりだ。
――大丈夫、そばにいるから。
――りんご、うまく剥けたよ。
――ねえ、もうすぐ会えるよ。
あの声に導かれてここまで来た。だから。
「……妻は」
喉の痛みよりも先に、その言葉が出た。
「妻は、どこ……」
母の瞳が揺れ、父の喉仏が上下する。
一瞬、病室の音がすべて遠のいた。
「……あの子は」
父は言葉を探す手つきで、ベッドの柵を握り、
「君を、かばって」
そこで、言葉が折れた。
空気が重く沈む。
胸の奥で、何かが静かに崩れる音がした。
理解したくない。
彼は首を振る。点滴の管がかすかに揺れ、痛みが腕を走る。
「嘘だ。だって、ずっと……ずっと、そばにいた。手も、声も、りんごの匂いも」
あの温もりは、あまりに鮮明だった。
幻覚というには、あまりに生々しく、優しかった。
母がベッドに身を寄せ、彼の額にそっと手を置いた。
「聞いて。あなたに、どうしても見てほしい人たちがいるの」
「人“たち”……?」
扉が開く音がして、柔らかな靴音が三つ、ちいさく重なって近づいてきた。
かすかな鈴の音。布の衣擦れ。ころん、と床に転びそうな足取り。
最初に顔を出したのは、白い毛布をぎゅっと握った子だった。
大きな瞳が、彼を真っ直ぐに映す。
続いて、少し慎重な様子で、母の足元に隠れながらじりじりと進む子。
最後に、つかまり立ちをしながらも笑顔で手を振る子が、ベッドの柵につかまって「アッ」と声を上げた。
三人――。
三つの命。
一年のあいだに確かに育った、彼と彼女の子どもたち。
「この子たちはね」
母は涙を拭いながら微笑む。
「あなたとあの子から託された、三つの“つづき”なの」
初めて見るはずの顔に、既視感が走った。
目尻の形。笑うと口の端にできる小さな影。
髪の毛の生え方、鼻筋のやわらかな線。
妻だ――。
そこに、間違いなく彼女がいた。
ひとりが、おそるおそる手を伸ばしてきた。
小さな指。まだ少し湿った手のひらが、彼の指に絡む。
ぎゅ、と握る力は驚くほど強く、彼は息を呑んだ。
「パ、パ」
言葉とも音ともつかない呼びかけが、胸の内側を一瞬で満たした。
涙が、勝手にこぼれた。
視界が波打つ。喉がひゅっと鳴り、声が壊れた。
「ごめん……」
なにに対する“ごめん”なのか、自分でもわからない。
守れなかったことに。
間に合わなかったことに。
一年という時間に置いていかれた自分に。
それでも、三人の体温は逃げず、彼の指に、胸に、頬に、確かに触れ続けた。
「この子はよく笑うの。なんでも楽しいみたい」
母が一人の頬を軽くつつくと、くすりと笑い、手をぱたぱたさせた。
「この子は慎重派。新しい靴に時間がかかるのよ」
おずおずと彼の袖をつまんでいた子が、少しだけ顔を上げる。
「この子は……泣き虫。でも、人が泣いてると一番先に近づいてくるの」
さっき彼の指を握った子が、今度は彼の袖口に額を押し当てた。
小さな鼻息がくすぐったくて、彼は笑いながら泣いた。
「……妻は、知っていたのかな。三人も、ここにいるって」
父がうなずいた。
「覚えているか? 事故の前の日、冷蔵庫に貼ってあった名前のメモ」
彼は息を止めた。
思い出す。付箋の“ね”。
丸い字で並んだ候補。
いつかの夜、二人で何度も口に出して練習した音の並び。
母がそっとファイルを開いた。そこには、母子手帳と、退院のときにもらった注意書きと一緒に、小さなメモが挟まれている。
――「あなたが呼ぶ声で決めたいから、練習してね」
その一文の最後にも、やはり柔らかな“ね”があった。
彼は三人の顔を順に見つめ、震える声でひとつ、またひとつ、ゆっくりと名前を呼んだ。
初めてその音に自分の存在を重ねたかのように、子どもたちが目を丸くし、次の瞬間、みんな一度に笑った。
その笑い方まで、妻に似ていた。
胸が痛く、そして温かかった。
「君は、もういないのか」
心の中で問い、すぐに答える。
――ここにいるよ。
三人の掌の温度の中に。
「厚く剥けたリンゴ」のたどたどしさの中に。
冷蔵庫の付箋に多かった、あの語尾の“ね”の中に。
彼は気づく。失われた命と、託された命は、一本の川の水面のように途切れずつながっているのだと。
看護師がそっと病室の時計を見た。面会の時間は長くない。
けれど、時間が砂のように零れ落ちる音はもう怖くなかった。
三人が彼の手を取り、交代で指を握る。
ひとりがあくびをし、ひとりが靴のマジックテープをいじり、もうひとりが毛布の端をしゃぶっている。
どれも、世界のありふれた音。
だが、今の彼にとっては世界を再び動かし始めるための鼓動だった。
母が小さなタッパーを取り出して見せた。
中には少し厚めに剥かれたリンゴ。
「病院の規則があるから、今日は見せるだけ。でもね……あなたの“好き”を、忘れたくなくて」
彼は笑って頷いた。
「ありがとう。……あいつの剥き方だ」
母は「そうね」と言って目を細めた。
不揃いの切り口が、なぜだか宝石のように見えた。
「君が守ってくれた命を、俺が守る」
彼は三人を胸に寄せながら、声を出さずに誓う。
転ぶときは先に手を差し出し、熱を出した夜はずっと背中をさする。
朝は髪を整えて、靴下を片方ずつ履かせ、リンゴは厚く剥く。
泣いたら一緒に泣き、笑ったら少し大げさに笑う。
そして、ときどきは必ず言う。「ありがとう」と。
当たり前を後回しにしない。伝えるべき言葉を、今日伝える。
それが、彼に託されたバトンだ。
父が静かに言った。
「悲しみは消えない。だけど、おまえが抱いているものは、それだけじゃない」
母も続ける。
「泣いていいの。何度でも。でも、同じ数だけ笑ってね。三人の前で」
彼は三人の額に唇を当てた。
塩気の混じった、自分の涙の味がした。
「ただいま」
それは、彼自身の、生の中心から出た音だった。
三人は意味もなく笑い返し、彼の胸を小さな拳でとん、と叩いた。
その小さな衝撃が、未来の方向を教えてくれる。
ふと、窓の外に気づく。
空は柔らかな薄曇りで、遠くの街路樹が風にわずかに揺れている。
一年のあいだに、世界は何度も色を変えただろう。
けれど彼の目には、今がはじめての色に見えた。
失われた命の痛みと、託された命のぬくもりが、同じ光の中でゆっくりと溶け合っていく。
――命は、等価に交換できるものではない。
だが、引き継ぐことはできる。
そして、引き継がれた命は、今日という“ささやかな日常”の中でこそ育つ。
焦げた目玉焼きも、厚く剥けたりんごも、付箋の「ね」も。
その全部が、これからの三人を育てる土になる。
彼はもう一度、三人の名前を呼んだ。
声はまだ弱い。でも、確かだった。
呼ぶたびに、呼ばれた命がこちらを向く。
それだけで、生きていける気がした。
「待っていてくれて、ありがとう」
心の中で、彼女に言う。
「ここからは、俺の番だ」
病室の時計の針が、静かに進む。
世界は相変わらずピッ、ピッ、と時を刻み、足音は遠ざかったり近づいたりする。
けれどもう、彼はそのどれにも取り残されてはいない。
三つの手が、彼の指を離さないからだ。
失われた命を胸に抱き、託された命を腕に抱いて――
彼は、新しい日常に、ゆっくりと歩み出した。
 ――りんご、うまく剥けたよ。
――りんご、うまく剥けたよ。
第五章:明日を抱きしめる
夜の病室は、昼のざわめきが嘘みたいに静かだ。
天井近くの非常灯が淡く緑を落とし、点滴スタンドの影だけが壁を細長く伸びている。
三つの寝息が、すこしずつズレて重なりあい、波のように寄せては返す。
一人は毛布の角を握ったまま親指を口元に運び、もう一人は丸まった背中を小さく上下させ、最後の一人は寝返りのたびに薄い声で「あ」と空気を鳴らす。
彼はその一つひとつを、胸の内側でそっと数える。――生きている。ここにいる。守るべき明日が、確かに息をしている。
目を閉じると、妻の気配がやって来る。
厚く剥けたりんごのやわらかな匂い、いくつになっても直らなかった不器用な包丁の音、付箋の角を丸く折る癖。
「ほら、あなた。大丈夫」
声がするたびに、彼はわずかに頷く。大丈夫じゃない夜でも、大丈夫と言ってくれる声があるだけで、大丈夫に近づいていける。
涙がひとしずく、枕に落ちて滲む。悲しみは引かない。けれど、悲しみだけではない別の温度も、胸のどこかに灯っている。
彼はポケットからメモ帳を取り出し、震える手で三行だけ書く。
「おはよう」「ありがとう」「愛してる」。
言えなかった言葉、後回しにして失った言葉。
明日からは、後回しにしない。たとえ囁きみたいに小さな声でも、毎日届ける。
ページの端に小さく「ね」と書き足して、彼は目を閉じた。文字の“ね”が、妻の文字とよく似て見えた。
夜明け前、最初に泣いたのは真ん中の子だった。
小さな口をすぼめ、目尻を潤ませ、顔全体で「寂しい」を伝えてくる。
抱き上げると、胸に当たる鼓動が早い。背中を縦にゆっくりなで下ろしながら、彼は口の中で調子を探す。
――子守歌。妻がいつも外した音程で歌っていた、あの歌。
「ら、らら……」
心許ない声でも、不思議と泣き声は弱まっていく。やがて肩口に額を預け、涙が肌にひんやりと触れた。
「大丈夫。ここにいるよ」
耳もとで囁くと、真ん中の子の指が彼のシャツをぎゅっとつまんだ。小さな意思が、確かに伝わってくる。
泣き声は連鎖する。端の子が目を覚まし、毛布の角を探して不安な声を漏らす。
もう一人は、眠ったまま眉間に皺を寄せた。夢の中で何かと闘っているらしい。
三人それぞれの泣き方、泣く前の合図、泣き終わりの癖――覚えるべきことは山のようにある。
彼は焦らない。ひとつずつ、名前を呼び、背中をさすり、鼻先に指を近づけて「ほら、ここにいる」と伝える。
言葉の意味はまだ分からないかもしれない。けれど言葉は、意味の前に温度を運ぶ。彼はそれを、今日からの自分の仕事だと受け止める。
窓の向こうが少しずつ白み、街の輪郭が起き始める。
夜を越えるたび、彼は父親になる。
「おはよう」
三人に順番に言う。
「おはよう」
言うたびに、昨日までの自分から一歩分、離れる気がした。
朝は、言葉を試すのに最適だ。世界の始まりに、最初に渡す言葉を選び直せるから。
祖父母が病室に入ってくる足音がして、彼は顔を上げる。
母は透明なタッパーを胸に抱えている。中には、やっぱり厚く剥かれた輪切りのりんご。
「今日は消毒のことがあるから、一緒には食べられないけど……見せに来たの」
母が蓋を開けると、白い皿の上に月のかけらみたいな果肉が並んだ。
「おばあちゃんの味だ」
彼が笑うと、母は首を横に振る。
「違うわよ。あの子の剥き方。ね、覚えてる?」
覚えている。皮は厚すぎて、角は欠けて、でも甘さが逃げない不思議な切り方。
彼はひとつ手に取り、そっと鼻に寄せた。
果汁の匂いの中に、暮らしそのものの匂いが混じっている。洗剤、陽の当たった布、台所の木。
「これでいい。これがいい」
彼はタッパーを見つめながら言う。
完璧じゃないものの中に、愛の芯がある。彼はそれを、これからも選び続ける。
昼下がり、看護師がベビーカーの並べ方を教えてくれる。
三人を一台に、というのは無理だから、二台に分け、ひとりは抱えて歩く練習。
マジックテープの留め方、靴下の左右、ミルクの角度。
覚えることを書き留める彼のメモには、やがて妻の付箋と見分けがつかないほど丸い字が増えていく。
文字が似てきたのか、それとも言葉の扱い方が似てきたのか。
「ね」を書くたびに胸が温かい。
言葉の最後に「ね」を置くと、命令も独り言も、相手へそっと手渡す形に変わる。
彼はこれから、できるだけ「ね」を使うと決めた。
「靴、はこうね」「お水、のもうね」「ありがとう、って言おうね」。
未来に向けて開いた、小さな合図。
夕暮れ前、三人が同時に泣いた。
空腹、眠気、退屈、理由は三者三様だ。
彼は深呼吸し、順番を決める。まずは一番泣き声の細い子から。
抱き上げ、背中をぽんぽん。次に真ん中の子のベルトを直し、最後の子の頬を指でなぞる。
泣き声はしばらく続いたが、やがて三人とも彼の胸か、腕か、肩に顔をあずけた。
汗が首筋をつたい、髪が額に張り付く。
「よくがんばった。俺も、よくがんばった」
小さく笑うと、泣き顔の口角が同時に上がる。
嬉しさは伝染する。安心も伝染する。心の温度は、抱く腕の太さではなく、そこに流れる時間で決まるのだと、彼は知る。
夜、祖父母が帰り、病室がふたたび静かになる。
彼は枕元でスマホのメモを開き、妻に宛てて短い手紙を書く。
――今日は三人とも、泣きながら笑いました。
――りんごは厚く剥く練習を始めました。
――「ありがとう」を三回言いました。
送る宛先はどこにもない。けれど、書いた瞬間に届く場所がある。
言葉にすると、時間が手の中に残る。
彼はそれを、やっと理解し始めていた。
数日後、外気を吸う許可が出た。
彼は祖父母に手伝ってもらい、病院の小さな庭へと出る。
ベビーカーの車輪が苔むした石を越えるたび、小さな振動が三つの体をふるわせ、三つの瞳が同時に見開かれる。
空は薄い水色で、風は低く、草の匂いが濃い。
「空、青いね」
彼が言うと、三人は言葉の意味ではなく声の色に反応するように、手足をばたつかせた。
「君のお母さんはね、ここで四季の話をするのが好きだったんだ」
彼はベビーカーの取っ手を握りながら、ゆっくりと語る。
春の川沿い、夏のベランダの風鈴、秋の落ち葉のしおり、冬のこたつとみかん――。
どの話にも、必ず“不器用だけどまっすぐな笑顔”が付いてくる。
三人はもちろん分からない。けれど、言葉に包まれた時間は、きっと体に染み込んでいく。
物語は、先に生まれた者の責任だ。伝える、という仕事は、今日から彼の毎日になる。
病室に戻る途中、彼はふと足を止める。
ガラス扉に映る自分は、まだ弱々しい。頬がこけ、目の下に影が落ちている。
それでも、腕の中にある重さは確かなものだ。
「大丈夫。今日できなかったことは、明日、いっしょに覚えよう」
誰に向けてでもない声が、明日の彼を少しだけ軽くした。
完璧をやめる。続けることを選ぶ。
妻が残してくれたやり方は、いつもそうだった。少しずつ、でも確かに。
夜。
三人の寝顔を見渡し、彼は小さく会釈をするみたいに頭を下げる。
「ありがとう。生まれてきてくれて」
言った瞬間、胸の奥で何かがほどけた。
ありがとうは、言う側も救う。
伝えた言葉が、相手の心だけでなく自分の心にも灯りを点す。
彼は、この灯りを消さないと決める。
どんな嵐の夜でも、どんなに疲れた日でも、最低三つの言葉だけは必ず渡す。
「おはよう」「ありがとう」「愛してる」。
これが彼の、新しい生活の土台になる。
ここで、彼は静かに視線を上げ、まだ出会っていない誰かへと語りかける。
――あなたの隣にいる人は、当たり前ではありません。
――“明日でいいや”は、明日にならないことがある。
――後回しにして消えてしまう言葉が、世界には想像以上に多い。
だから、どうか今日、ひとことだけでも渡してほしい。
たった一行でいい。メッセージでも、付箋でも、声でも。
「ありがとう」「ごめんね」「大好きだよ」。
照れくさくて構わない。拙くて構わない。
厚く剥けたりんごが甘さを閉じ込めるように、拙い言葉ほど、心に長く残ることがある。
若い二人へ――。
ケンカの翌朝、沈黙のまま出かけないで。「昨日はごめん」を、短くでいいから。
働き盛りのあなたへ――。
深夜の食卓に残った皿一枚に、どれほどの思いやりが詰まっているかを、どうか時々思い出して。
遠く離れて暮らす親へ――。
「体調どう?」の一行で、この世の不安の半分が溶ける人がいる。
子育ての真ん中にいるあなたへ――。
完璧をやめても、愛は減らない。むしろ笑いが増える。
彼はベッドサイドのランプを最も低い明るさに落とす。
小さな光が、四人の輪郭をやさしく浮かび上がらせる。
「おやすみ」
囁くと、三つの寝息がわずかに弾んで、また整った。
彼は静かに目を閉じ、胸の奥で妻に語りかける。
――君が守ってくれた目の前の命に、毎日言葉を渡すよ。
――愛してる、を惜しまない。ありがとう、をためらわない。ごめんね、を飲み込まない。
――それが、君に渡されたバトンを次へつなぐ、たしかな手つきだと信じて。
カーテンのすき間から、夜の街灯が細い線になって床に落ちている。
その線は、まるで明日への下書きだ。
彼は、ゆっくりと息を吸い、吐く。
失われたものは大きい。埋めることはできない。
それでも、人は“つづける”ことができる。
当たり前を当たり前にしない、という決意を背に、彼は眠りに落ちていく。
明日の朝、最初の三つの言葉を渡すために。
 三つの寝息が、波のように寄せては返す。
三つの寝息が、波のように寄せては返す。
第六章:明日へ手渡す言葉
彼は知った。
人は「失ったもの」を抱えたままでも、「渡せるもの」を増やしていけるのだと。
だからここから先は、物語を読んでくれたあなたに、静かに、確かに、手渡したい。
――今日という一日のうちに、できることを。
朝、目が覚めたら最初に口にしてほしい。
「おはよう」。
たった四文字だ。けれど、それは今日の世界に灯を入れる合図になる。
言い慣れていないなら、声が小さくてもいい。視線が泳いでもかまわない。
相手が隣にいればその肩の高さで、離れていればスマホの画面越しで。
返事が返ってくるかどうかより、あなたが差し出すことに意味がある。
言葉は投げるものではなく、置いてくるものだ。そっと。相手が拾いやすいように。
日中、ふと思い出したときに、もうひとつ。
「ありがとう」。
理由を考えなくていい。思い浮かばなければ、「いてくれて、ありがとう」で十分だ。
仕事に向かう背中に、食卓へ並ぶ皿に、洗濯物の柔らかさに、帰ってくる足音に。
私たちは気づかないまま数え切れない恩恵の上に立っている。
「ありがとう」と言うたびに、あなたの中の誰かが、少しやさしくなる。
それはやがて、あなたの周りの誰かの呼吸を楽にする。
夜、寝る前に、最後のひとこと。
「愛してる」。
もし照れくさければ、「好きだよ」「大事だよ」でもいい。
声にするのが難しければ、書いてもいい。短いメッセージでも、テーブルに置く小さなメモでも。
要るのは完璧な言い方ではなく、いま、この瞬間に言うという勇気だけだ。
明日は保証されていない。けれど、今は、ここにある。
三つの言葉を続けるコツを、彼は見つけた。
形を整えすぎないこと。
厚く剥いたリンゴが甘さを閉じ込めるように、不器用な言葉ほど、あとからじんわり効いてくる。
「ね」を添えること。
「おはようね」「ありがとうね」「大事だよ、ね」。
命令でも確認でもない、手渡しの語尾。あなたの声の角を、やわらかく丸くしてくれる。
そして、毎日同じ時間に置くこと。
朝起きたら――昼に一度――寝る前に。
歯磨きやカレンダーの印のように、習慣に変えていく。
一日抜けてもいい。抜けたら、また次の瞬間から再開すればいい。
続ける人は、失敗の回数ではなく、再開の回数でできている。
もし、いま隣にいない人がいるなら、遠くの誰かに届けてほしい。
久しぶりの友だちに「元気?」と短い一行を。
離れて暮らす親に「体調どう?」とやさしい句読点を。
喧嘩中の相手に「さっきはごめん」と、それだけを。
上手にまとめない勇気を持とう。
言い訳や余計な飾りを脱ぎ捨てた言葉は、驚くほど早く届く。
あなたの中に小さな不安があるだろう。
「いまさら言って、どう思われるだろう」
「同じ家なのに、改まって言うのが照れくさい」
「言葉だけで何が変わるの」
その全部に、彼は答える。
言葉は、現実を一瞬で完璧には変えない。
でも、現実の“向き”を確実に変える。
方向が変われば、時間の中で到着地が変わる。
今日の四文字が、二週間後の笑顔の角度を、半年後のまなざしの温度を、知らないうちに修正してくれる。
忘れがちな人へは、目印を作ろう。
冷蔵庫の扉に、小さな付箋を一枚。「おはよう」「ありがとう」「愛してる」。
鏡の端に、もう一枚。「今日のあなたに、やさしくね」。
スマホのリマインダーに、小さな通知を設定するのもいい。
機械的だと感じる? それでいい。最初はギアでも、やがて心が追いついてくる。
形から入って、気持ちで満たす。暮らしはたいてい、その順番で温かくなる。
三つ子の父になった彼は、約束を決めた。
転んだときは、叱る前に抱き上げる。
泣いた夜は、黙って背中をさする。
嬉しかった日は、少し大げさに笑う。
そして、どんなに忙しい朝でも、三人の額に唇を当てて、「おはよう」を忘れない。
彼は悟ったのだ。
子どもに伝わるのは、正しさより、繰り返しだと。
月に一度の完璧より、毎日の拙い儀式だと。
これは親だけの話じゃない。
恋人でも、夫婦でも、友だちでも、職場の誰かでも、同じだ。
あなたが今日置いた言葉は、たしかに積み重なって、関係の地面をやわらかくしていく。
もし、過去に「言えなかった言葉」を抱えているなら、自分を責め続けなくていい。
取り戻せない時間は確かにある。けれど、その後ろ姿に謝りながら歩くより、
目の前の人に一言だけ渡すほうが、あなたを確かに前へ押し出す。
「今からでも遅くない」という言葉は、今日という日のためにある。
どうしても声が出ない夜には、手紙を。
難しければ、メモに「ありがとうね」だけでも。
もっと難しければ、厚く剥いたリンゴを一皿。
「言葉のかわり」は、暮らしの中にいくらでもある。
差し出した皿の不器用な丸みは、あなたのまっすぐさと同じ形をしている。
相手はそれを、たいてい分かってくれる。
たとえ言葉を返してくれなくても、皿は空になる。
それで十分だ。伝わることと、反応があることは、似ているが同じではない。
伝わることは、あなたの側の行為だ。そこで完結していい。
この物語は、悲しみで始まり、手渡すことで終わる。
彼が受け取ったのは、失われた命の重さと、託された命の温度。
あなたが受け取るのは、今日の小さな一歩だ。
言葉は、未来の貯金になる。
「おはよう」で朝が整い、「ありがとう」で昼がやわらぎ、「愛してる」で夜が安らぐ。
それを七日続けたら、一週間の景色が変わる。
四週間続けたら、季節の手触りが変わる。
一年続けたら、ふり返ったあなたの声が変わる。
いつかのあなたが、今日のあなたに感謝する。
「始めてくれて、ありがとう」と。
だから、今、深呼吸をひとつ。
思い浮かべてほしい。
あなたが守りたい人の顔を。
隣にいるかもしれないし、遠くで暮らしているかもしれない。
もう会えない誰かの面影でもいい。
その人に向けて、心の中で言ってみてほしい。
――おはよう。
――ありがとう。
――愛してる。
言えたら、次は声に。
声が難しければ、文字に。
文字が難しければ、厚く剥いたリンゴに。
どれか一つでいい。
完璧を目指さないで、今日を選んでほしい。
最後に、彼が毎晩欠かさず書く一行を、あなたにも。
「当たり前を、当たり前にしない」
この一行が、明日のあなたの手を、きっとやさしく導く。
さあ、行ってらっしゃい。
あなたの大切な人のところへ。
今日の三つの言葉を、そっと置きに。
そしてまた、明日も。
 冷蔵庫の扉に、小さな付箋
冷蔵庫の扉に、小さな付箋


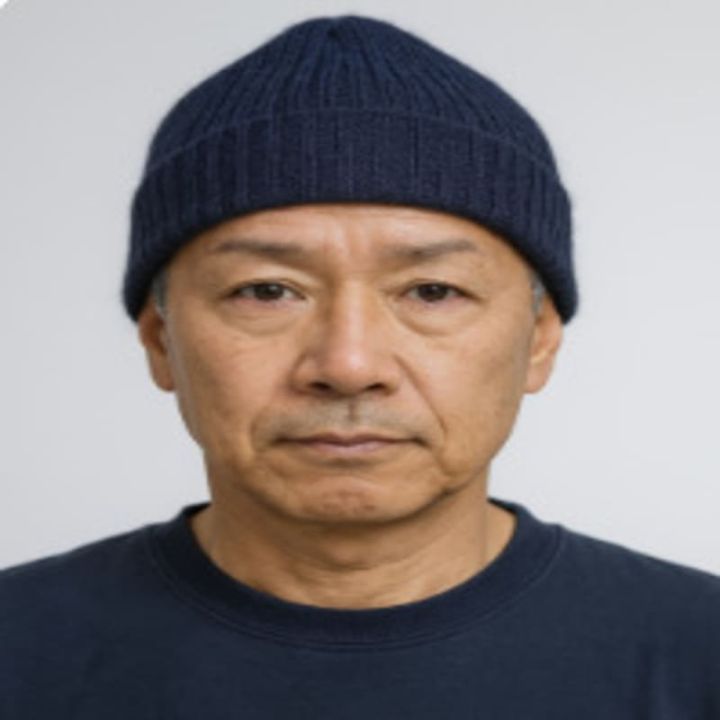



まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。