家族信託で認知症対策|仕組み・費用・デメリットを解説
「親が認知症になったら、実家の売却や預金の引き出しができなくなるって本当?」…そんな不安はありませんか?
結論から言うと、家族信託は、認知症による判断能力の低下に備え、元気なうちに信頼できる家族へ財産の管理を託しておくための有効な制度です。 裁判所が関与する成年後見制度と比べて自由度が高く、柔軟な財産管理が可能になります。
この記事では、認知症対策としての家族信託の仕組みから、メリット・デメリット、費用、成年後見制度との違いまで、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。将来の不安を解消し、家族みんなが安心できる準備を始めましょう。
家族信託とは?認知症による「資産凍結」を防ぐ仕組み
家族信託とは、ひと言でいえば「自分の財産管理を、信頼する家族に託す」ための契約です。認知症になると、本人の意思確認ができなくなり、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりする「資産凍結」のリスクがあります。家族信託は、この資産凍結を未然に防ぐことを最大の目的としています。
登場人物は財産を「託す人」「託される人」「利益を得る人」
家族信託は、主に以下の3者の登場人物で成り立ちます。
- 委託者:財産を所有し、管理を託す人(例:親)
- 受託者:財産の管理を託される人(例:子)
- 受益者:信託された財産から利益(生活費や介護費用など)を受け取る人(例:親)
委託者(親)が元気なうちに、受託者(子)と契約を結び、「自分が認知症になったら、この預金を使って介護費用を支払ってほしい」「施設に入るために実家を売却してほしい」といった財産管理のルールを具体的に決めておくことができます。
家族信託のメリット・デメリット|後悔しないための全知識
家族信託は万能ではありません。メリットとデメリットを正しく理解することが、後悔しないための第一歩です。
家族信託の4つのメリット
- 柔軟な財産管理ができる:契約内容を自由に設計できるため、「不動産を売却して施設入居費に充てる」など、本人の希望に沿った柔軟な対応が可能です。
- 資産凍結を回避できる:認知症になっても、受託者が契約に基づいて財産を動かせるため、必要な時に必要な資金を使えます。
- 裁判所の関与が不要で迅速:成年後見制度と違い、家庭裁判所の許可なく手続きを進められるため、スピーディーな対応が可能です。
- 二次相続以降の資産承継も指定できる:遺言では一代先までしか指定できませんが、家族信託なら「自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は長男に」といった先の代までの財産承継を指定できます。
知っておくべき3つのデメリット・注意点
- 受託者の負担が大きい:財産を管理する受託者には、帳簿作成などの重い責任と手間がかかります。家族間でよく話し合い、協力体制を築くことが不可欠です。
- 身上監護はできない:家族信託はあくまで財産管理の制度です。介護施設の入所契約や入院手続きといった「身上監護」行為は行えません(任意後見制度との併用でカバー可能)。
- 専門家のサポートがほぼ必須:契約書の作成には専門的な知識が必要で、自分たちだけで行うのは困難です。司法書士などの専門家への依頼費用が発生します。
家族信託と成年後見制度の違いは?どっちを選ぶべきか比較
認知症対策としてよく比較されるのが「成年後見制度」です。両者は似て非なるもので、どちらが良いかは状況によります。
「事前対策」か「事後対策」かが最大の違い
- 家族信託:判断能力があるうちに契約する「事前対策」。本人の意思を反映させやすく、財産管理の自由度が高い。
- 成年後見制度:判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「事後対策」。財産は厳格に保護されるが、不動産の売却などには裁判所の許可が必要で、柔軟な対応は難しい。
家族信託が向いているケース
- 元気なうちに、将来の認知症対策を積極的に行いたい。
- 不動産の売却や賃貸経営など、柔軟な財産活用を続けたい。
- 家族間の信頼関係が良好で、財産管理を任せられる人がいる。
成年後見制度が必要になるケース
- すでに認知症が進行し、本人に契約能力がない。
- 家族間に争いがあり、財産管理を任せられる人がいない。
- 身上監護(介護契約など)も含めて専門家に任せたい。
【具体例】認知症対策での家族信託の活用事例
家族信託が実際にどのように役立つのか、具体的な事例を見てみましょう。
事例1:実家の売却資金を介護費用に充てる
親が認知症になり老人ホームへ入居する際、その費用を捻出するために実家を売りたいと考えても、本人の意思確認ができなければ売却できません。事前に家族信託で子どもを受託者にしておけば、親の判断能力が低下した後でも、子どもが代理で実家を売却し、その資金を介護費用に充てることができます。
事例2:預貯金を引き出して生活費や医療費を支払う
認知症になると、銀行が口座を凍結し、たとえ家族でも預金を引き出せなくなることがあります。家族信託で設定した「信託口口座」に資金を移しておけば、受託者である子どもが、そこから親の生活費や医療費、介護費用などを計画的に支払うことができ、資金ショートの心配がなくなります。
家族信託の始め方|相談から契約までの4ステップ
家族信託を始めるには、専門家のサポートを受けながら以下のステップで進めるのが一般的です。
ステップ1:家族会議で方針を決める
なぜ信託が必要か、誰に何を託したいかなど、家族全員で目的や希望を共有します。受託者になる人の理解と協力が不可欠です。
ステップ2:専門家(司法書士など)に相談する
家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談し、自分たちの希望に合った契約内容を設計してもらいます。
ステップ3:信託契約書を作成する(公正証書がおすすめ)
専門家が作成した契約書案をもとに、最終的な内容を固めます。後々のトラブルを防ぐため、法的効力の高い「公正証書」として作成するのが一般的です。
ステップ4:信託口口座の開設と不動産登記
金銭を信託する場合は、信託財産を管理するための専用口座「信託口口座」を開設します。不動産を信託する場合は、法務局で所有権移転の登記を行います。
家族信託にかかる費用の目安は?初期費用とランニングコスト
家族信託には一定の費用がかかります。事前に把握しておきましょう。
初期費用:専門家報酬と登記費用など
- 専門家へのコンサルティング・作成費用:30万円~100万円程度が目安。信託する財産の額や契約内容の複雑さによって変動します。
- 公正証書作成費用:数万円~十数万円。公証役場に支払う手数料です。
- 登記費用(登録免許税など):不動産を信託する場合に必要。固定資産税評価額によって決まります。
運用中の費用:受託者への報酬や税金など
- 受託者への報酬:家族が受託者になる場合は無報酬のことも多いですが、報酬を設定することも可能です。専門家を受託者にする場合は月額報酬が発生します。
- 税金:信託財産から生じる利益(家賃収入など)には税金がかかります。
まとめ:元気なうちの家族信託が、未来の安心につながる
認知症による資産凍結は、誰の身にも起こりうる現実的なリスクです。 家族信託は、そのリスクに備え、本人の意思を尊重しながら大切な財産を守り、家族の負担を軽減するための強力なツールとなります。
手続きには専門家の力が必要で、費用もかかりますが、将来「あの時やっておけばよかった」と後悔しないために、家族が元気なうちに一度検討してみてはいかがでしょうか。早めの準備が、あなたと家族の未来の安心につながります。



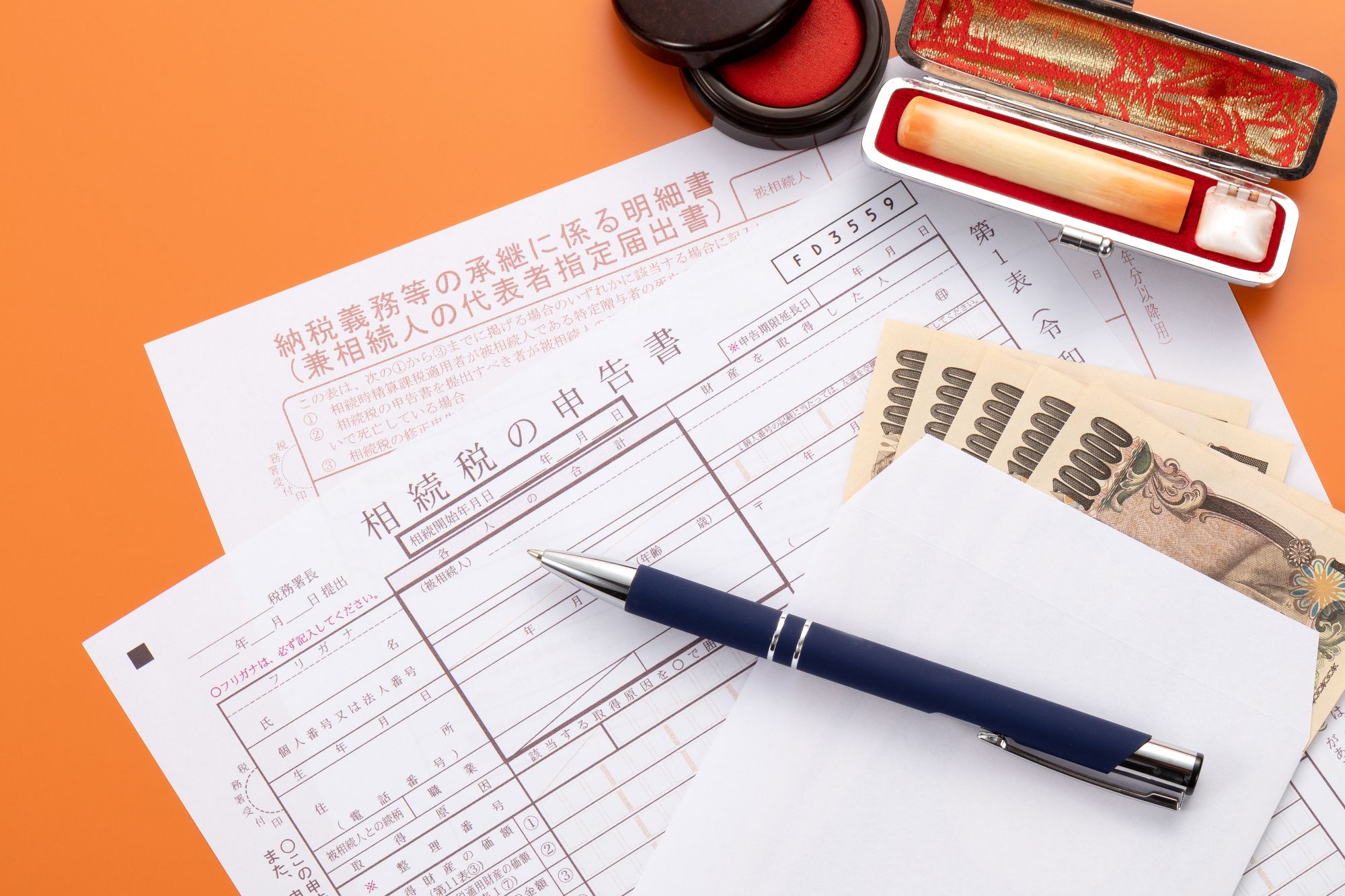


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。