「ラクしたいんじゃない、意味がほしい」26卒の本音にどう応える?
本当はがんばりたい。でも“意味”が見えないだけ
「最近の若い子ってさ、すぐ辞めるよね」
「ちょっと注意したら、次の日には来なくなってるとか」
そんな話、耳にしたことありませんか?
一方で、こんなデータが出ています。
26卒の学生のうち、「20代はワークを重視したい」と考えている人が過半数を超えている。
つまり、働くことに対して意欲がある。でも、残業時間には敏感で、「月20時間が限界」と答えた人も多い。
この矛盾、どう読み解けばいいのでしょうか?
彼らは、“ラクをしたい”わけじゃない。
ただ、“意味のないこと”にエネルギーを使いたくないだけ。
言われたからやる、形だけのルール、結果につながらない努力――
そういうのに敏感なんです。
裏を返せば、意味さえ見出せれば、めちゃくちゃ頑張る。
要は、「なぜやるのか」「この仕事が誰の役に立つのか」
そこが見えないと、モチベーションのスイッチが入らないんです。
「やる気がない」のではなく「納得できない」だけ
たとえば、ある中小企業であった話。
若手のA君は、入社当初とても前向きでした。
「営業って、難しそうだけどチャレンジしてみたいです!」
でも、3ヶ月後には完全にやる気を失っていました。
何があったかというと、毎日のように意味不明な作業を押し付けられていたんです。
「前にも提出したはずの報告書をもう一度出して」
「Excelのフォーマットはこっちに直して」
「理由はいいからとにかくやって」
そのたびにA君はこう思ったそうです。
「なんで?」「誰のために?」「これ、意味あるの?」
頑張りたくないわけじゃない。
けれど、やる意味がわからないことには命を使いたくない。
そしてついに、彼はこうつぶやいて退職しました。
「“やりがい”って、こういうことじゃないですよね?」
若手は“自分ごと”にできる会社に惹かれている
いま、若い世代に共通しているのは、「意味へのこだわり」です。
昭和・平成の働き方は「やればわかる」「背中を見て覚えろ」が主流でした。
でもZ世代は違います。説明がないと納得できない。
ただし、その説明が腑に落ちれば、スイッチが入るのも早いんです。
要は、“やらされ仕事”ではなく、“自分ごと仕事”に変わった瞬間、
一気にやる気があふれてくる。
たとえばこんな取り組みをしている会社があります。
・全体朝礼の代わりに、1日1回「今日の仕事が誰の役に立つか」を共有
・社内SNSで「ありがとうの投稿」を可視化して、仕事の意味を感じやすくする
・新人研修で「失敗体験シェア会」を開いて、リアルな職場ストーリーを語ってもらう
すごく地味に見えるかもしれません。
でも、こういう“小さな意味づけ”が、彼らのモチベーションのスイッチを押してくれるんです。
ある企業では、たった1回の“ありがとう投稿”がきっかけで、
「自分の仕事にも価値があるんだ」と涙をこぼした新卒がいたそうです。
意味がある職場は、数字じゃなく“納得”で動いている
この数年で、採用の現場は大きく変わりました。
求人票に「高収入」「やりがい」「成長できる環境」と書いても、もう響かない。
彼らが求めているのは、キラキラした言葉ではなく、「自分がここで働く意味」です。
・誰のためにこの仕事をしているのか?
・自分の時間を使うだけの価値があるのか?
・この会社は、何を大切にしているのか?
そうした問いにちゃんと答えられる会社が、選ばれるんです。
そしてその答えは、社長の言葉でも上司のスピーチでもない。
「現場でのふるまい」や「日々の声かけ」の中にあるんです。
たとえば、若手社員がつまずいたときに、
「何やってんだよ」じゃなくて「どこが難しかった?」と聞けるか。
これだけでも、その社員にとっては「自分は意味のある存在なんだ」と思える瞬間になる。
つまり、意味のある職場っていうのは、派手なことをしてるわけじゃなくて、
“意味を伝える言葉と態度”が日常にあるんです。
結局、何が彼らを動かすのか?
結論としてはこうです。
若者は、やる気がないわけじゃない。
ただ、やる理由が見えていないだけ。
ラクしたいんじゃない、自分の人生の時間を無駄にしたくないんです。
だからこそ、経営者の役割はただ一つ。
「意味を伝える人」になること。
たとえば、こんなところから始めてみてください。
・仕事の指示を出すときに、「なぜやるか」を一言添える
・月に一度、若手の「仕事の意味を感じた瞬間」を聞く
・社内で「誰かの役に立った話」を共有する場をつくる
これだけでも、社内の空気は変わります。
数字の評価より、意味の共有。
指示命令より、共感の設計。
そういう組織に変わっていける会社こそ、これから若者に選ばれ続ける会社です。
あなたの職場には、“意味の対話”がありますか?
人は、意味を感じたときに、はじめて本気で動きます。
今の若者は、それを隠さずに伝えてくれる世代です。
だからこそ、これはチャンスなんです。
「何のために働くのか」「この仕事は誰を幸せにするのか」
その問いに向き合ってくれる若者がいる職場は、必ず強くなる。
「ラクしたいんじゃない、意味がほしい」
この言葉をきっかけに、あなたの会社にどんな問いが生まれるか。
ぜひ、今日から考えてみてください。

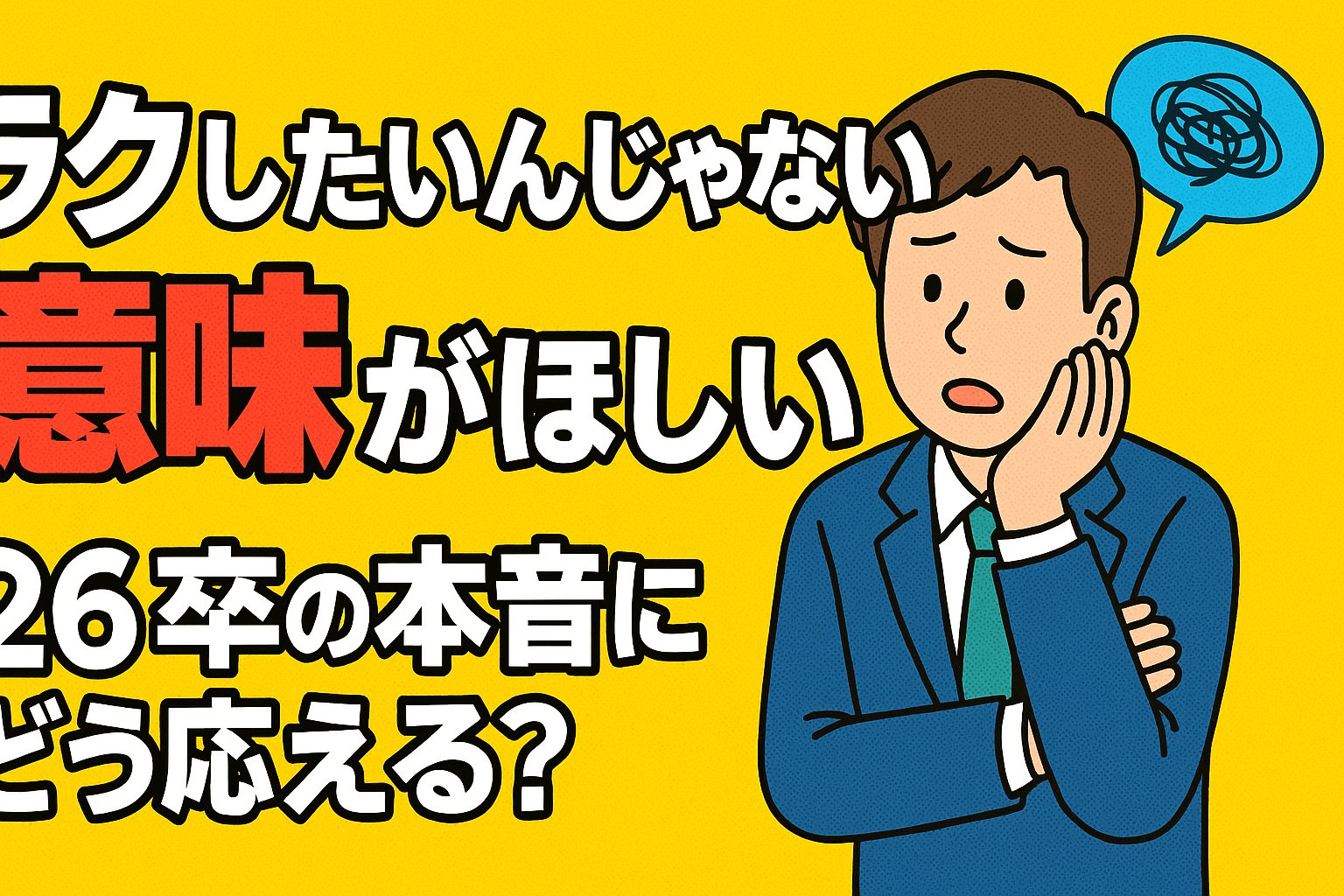

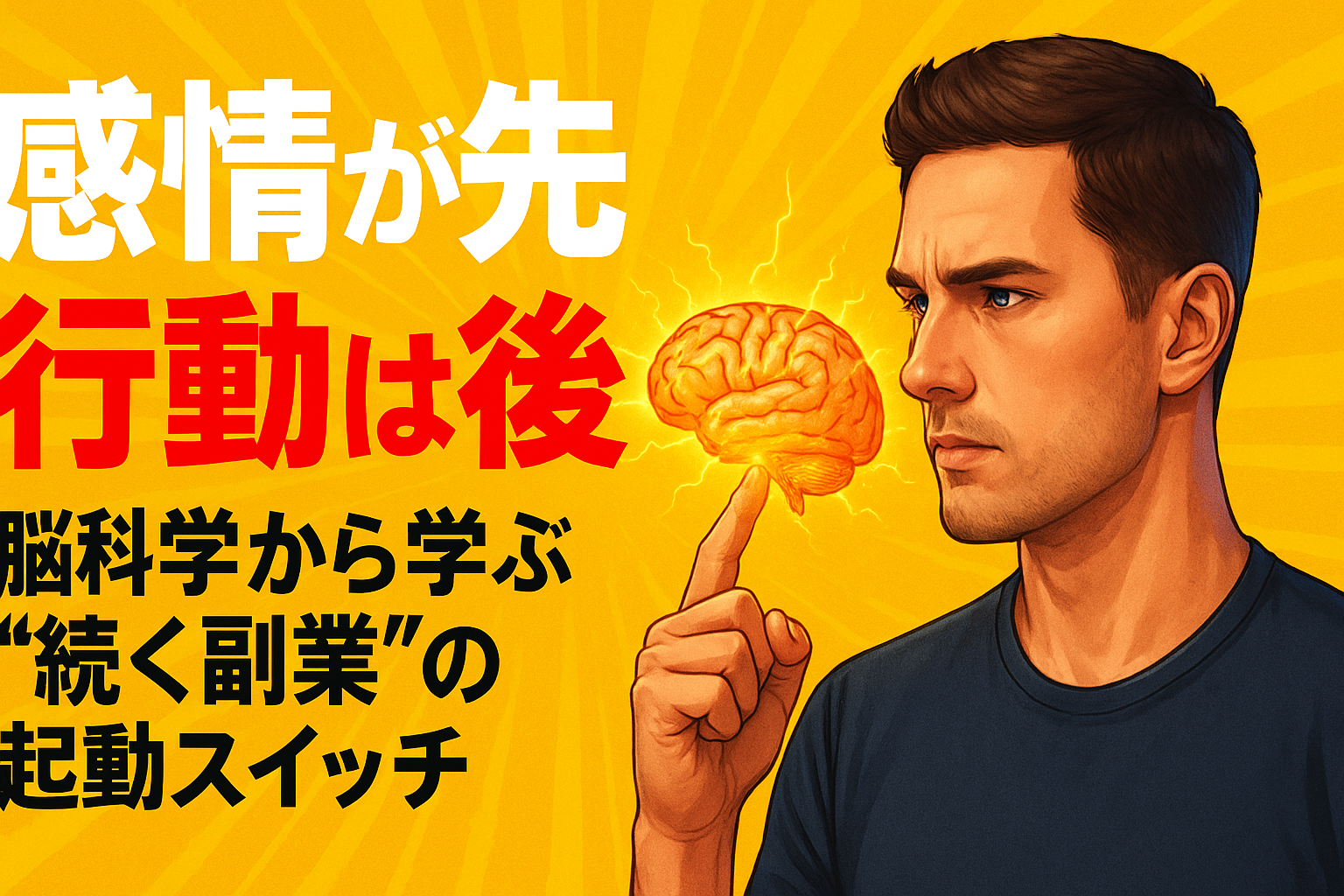
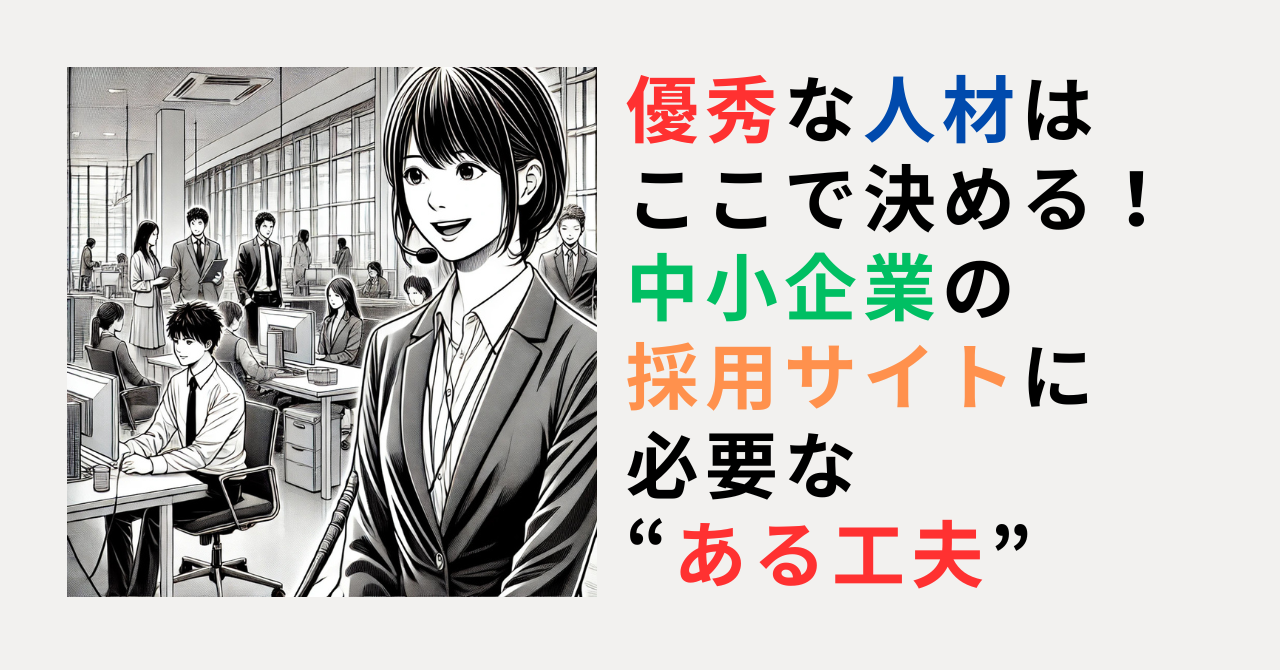

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。