「え、この年齢で10万円もらえる制度、知っていますか?」
🔸第1章🔸
えっ、本当に?知られていない“もらえるお金”の正体とは・・
こんにちは、みなさん!
今回は「給付金・助成金」といった、“もらえる制度”をテーマに、
知らなきゃ損する驚きの内容をお届けします。
突然ですが、あなたはこんな話を耳にしたことがありますか?
■「65歳で申請すれば、10万円近くの給付金がもらえるらしい」
■「ある条件を満たすだけで、医療費の負担が減らせるって本当?」
■「“高齢者”というだけで、支給対象になる制度がある…?」
実は、こうした情報は意外と役所の窓口やWebサイトを調べただけでは
見つかりません。
制度の名称がわかりづらく、自治体によって内容も違うため、「もらえる人」と「もらえず終わる人」に分かれてしまうのです。
今回の動画では、
✅ 高齢者がもらえる「知られざる給付金・助成金」
✅ 10万円を超える支給例
✅ 申請しないと損する制度の“落とし穴”
を徹底的にわかりやすく解説していきます。
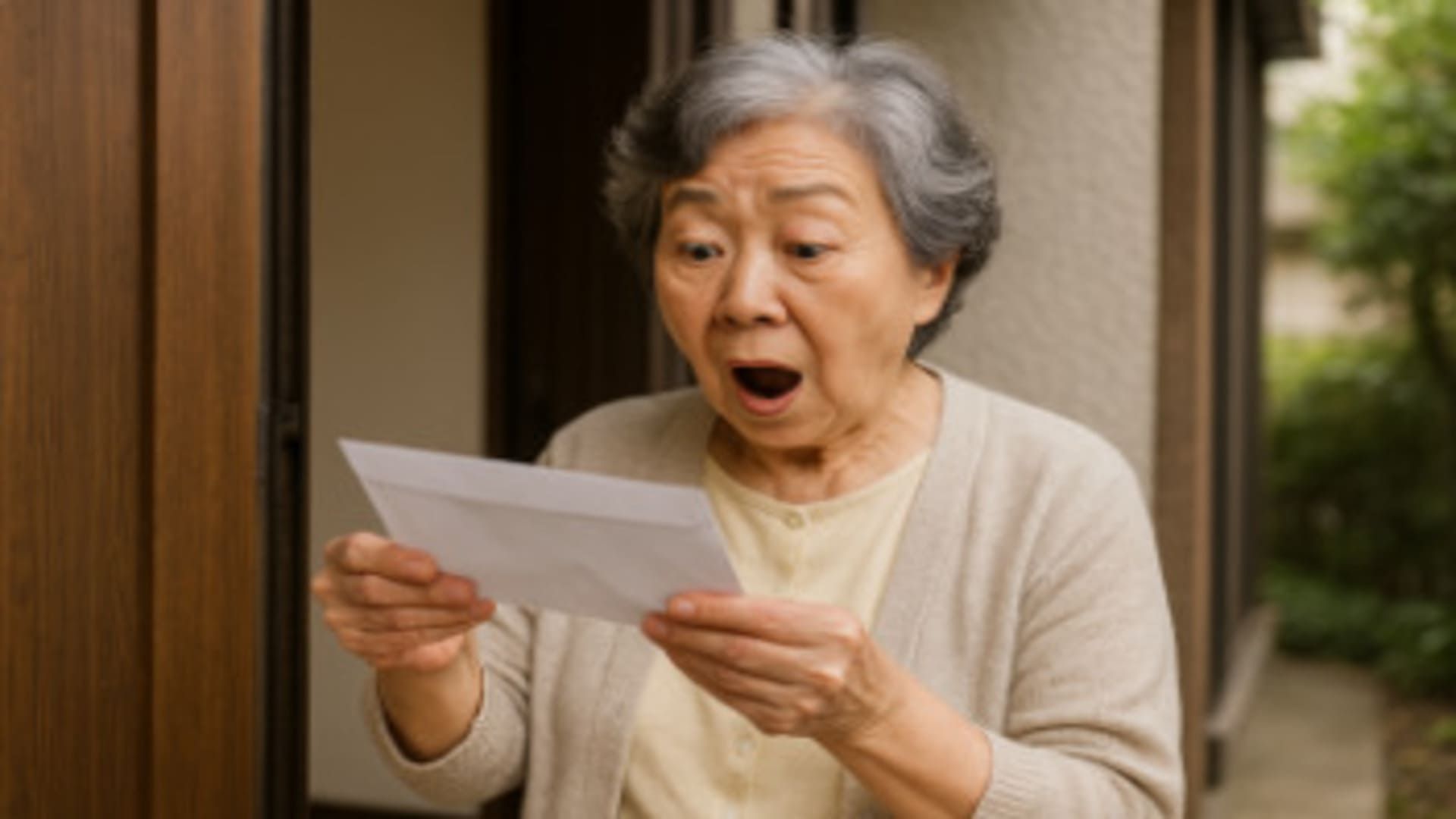 知らないと!損思いがけず10万円もらえることも ※以下イメージ画像
知らないと!損思いがけず10万円もらえることも ※以下イメージ画像
🔸第2章🔸
高齢者向けの主な“現金支給型”給付制度とは?
まず注目したいのが、「現金がもらえる給付制度」。
一番わかりやすく、生活にも直結する支援です。
◆① 高齢者向け生活支援給付金(例:年金生活者支援給付金)
国の制度として年金とあわせて支給される、月5,000円前後の給付金です。
年間にすれば約6万円。しかも、条件が合えば自動で支給されるケースもあります。
◆② 地方自治体による臨時特別給付金
例えば、東京都の一部地域では「高齢者臨時福祉給付金」として1人10万円の
支給があった事例も。
特別定額給付金の名残として行われている制度で、今後も実施される可能性が
あります。
◆③ 医療・介護支援金
一定以上の医療費を負担している高齢者に対し、年間数万円の支援金が
返ってくる制度。
こちらも「高額療養費制度」や「介護保険負担限度額認定証」などと併用することで
負担が大きく軽減されます。
次は、**「条件次第でもらえる給付金」**について、第3章に進みます。
 「こんな制度があったの⁈」と驚く現実
「こんな制度があったの⁈」と驚く現実
🔸第3章🔸
条件を満たせば支給!“もらえる可能性”を見逃さない
ここからは、「自動で支給されないけれど、条件を満たせば確実にもらえる制度」を見ていきましょう。
これらは**“申請しなければもらえない”**ことが最大の落とし穴です。
◆① 障害者控除対象者認定(高齢者にも対象あり)
要介護認定を受けている方は、市区町村から「障害者控除対象者証明書」をもらうことで、
所得税や住民税の軽減、そして介護保険料の減額や給付金の対象になることもあります。
◆② 住宅確保給付金(高齢者世帯でも可)
住居を失う可能性がある人に対し、家賃相当額(上限あり)を最大9ヶ月給付。
「生活保護ではないけれど生活が厳しい」高齢者にも適用されることがあり、
実際に受給した高齢者の声もあります。
◆③ 冬季加算・光熱費補助制度
冬の光熱費が厳しい時期に、高齢者世帯に対して灯油代・電気代の補助を行う
自治体もあります。
自治体によっては10,000円以上の支給実績もあり、「寒冷地対策」として
全国に広がっています。
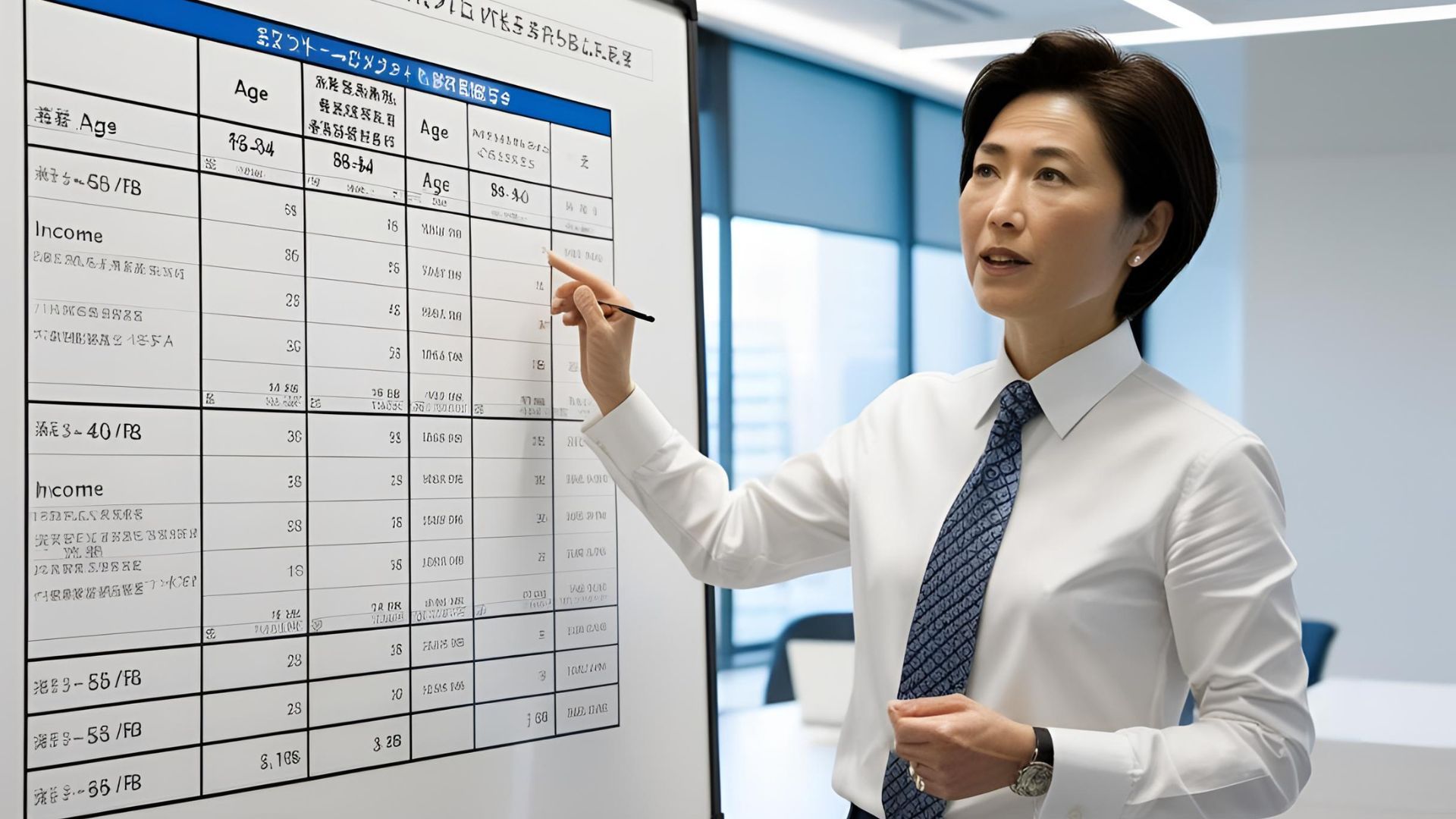 あなたも該当するかも?複雑な条件を説明するスタッフ
あなたも該当するかも?複雑な条件を説明するスタッフ
🔸第4章🔸
申請が“面倒”で損をする? 高齢者に多い3つのつまずき
では、なぜ多くの人が「制度があるのに、もらえていない」のでしょうか?
その理由は、以下の3つが圧倒的に多いのです。
①「そもそも制度の存在を知らない」
→ 名前が難しかったり、チラシも読まずに捨ててしまうことが…。
②「どこで申請するのかわからない」
→ 市役所?年金事務所?民生委員?となって、あきらめてしまう人が多数。
③「申請書類が難しそうに見えてしまう」
→ 実際は名前・住所を書いて印鑑を押すだけのことも多く、窓口で聞けば
親切に教えてくれます。
ここで重要なのは、「知る → 問い合わせる → 書類を出す」だけで10万円単位の支援が得られることもあるという点です。
次は第5章、実際の支給例や体験談をご紹介し、より具体的に“もらえる実感”
を持っていただきます。
 申請は意外と簡単!書いて出すだけのものも・・
申請は意外と簡単!書いて出すだけのものも・・
🔸第5章🔸
本当に10万円もらえた!? 実際の支給事例と体験談
「そんな制度、本当にあるの?」
「実際にもらえた人っているの?」
そんな疑問にお応えするために、実際の体験談をいくつかご紹介しましょう。
◆事例①:東京都在住・72歳女性
「高齢者臨時福祉給付金」で、10万円が振り込まれたという事例。
もともと郵送されたチラシを見て市役所に問い合わせ、申請書を記入しただけで完了。
「こんな簡単なことで10万円ももらえるなんて、もっと早く知っていれば…」との声。
◆事例②:北海道・高齢者世帯(夫婦2人暮らし)
冬季の灯油代が高騰する中、「冬期光熱費助成金」を利用して、2人で合計20,000円の支援を受け取る。
町内会を通じて制度を知ったとのこと。
◆事例③:兵庫県の年金生活者・68歳男性
「年金生活者支援給付金」で年間6万円を上乗せ支給。
年金額が少なく生活が厳しかった中、友人のアドバイスで制度を知り、申請。
◆事例④:岡山県・65歳男性(失業後の単身生活)
「自己都合で早期退職して年金受給までの空白期間があり、住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金(5万円)をもらえた。ハローワークで教えてもらったが、自分から調べなければわからなかったと思う。“早めの退職”も該当条件になるとは思わなかった。」
◆事例⑤:新潟県・70代後半の夫婦世帯(持ち家・年金生活)
「冬の灯油支援と、配食サービスの申請で合わせて年間3万円分の支援を受けた。
家はあるけど収入が少ないというケースでも、固定資産があっても対象になる制度があると知って驚いた。申請のきっかけは、隣に住む娘が教えてくれたこと。」
このように、居住地・収入状況・家族構成・健康状態の違いによって支援の入り口は様々です。
共通しているのは、「制度を知った瞬間から、生活がラクになった」という実感。
こうした実例から見ても、知らなかっただけで損をしていた人が非常に多いことがわかります。
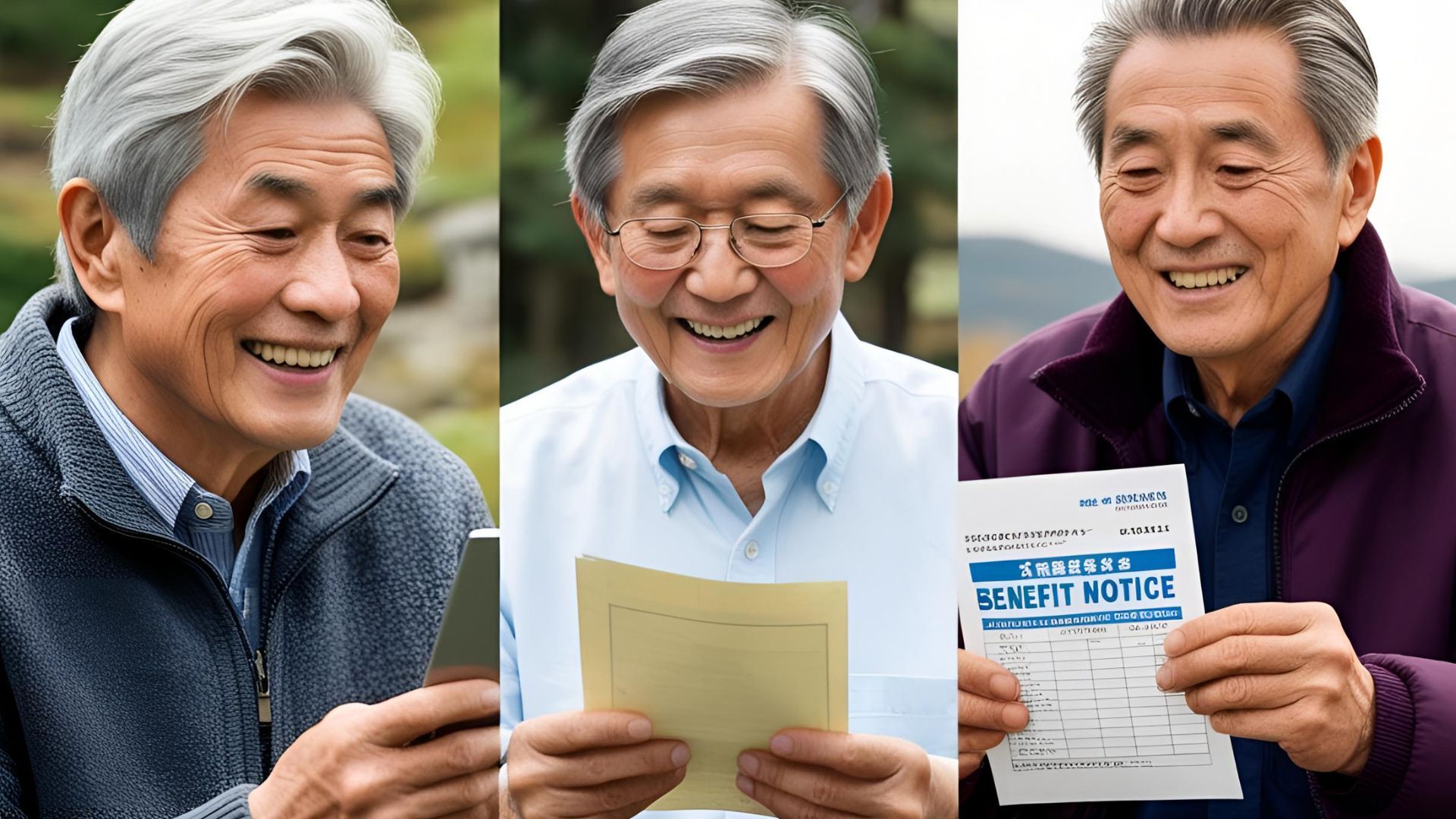 給付金の知らせを受け取った人のリアルな表情
給付金の知らせを受け取った人のリアルな表情
🔸第6章🔸
2025年最新!給付金・助成金情報のチェック方法
給付金や助成金の情報は、年によって内容が変わります。
では、どうすれば最新の情報を見逃さずキャッチできるのでしょうか?
◆① 自治体の公式サイトをブックマークする
→ 「◯◯市 高齢者 給付金」「◯◯町 助成金」と検索すると、地域ごとの
制度ページにアクセスできます。
◆② 地域包括支援センターに相談する
→ 特に高齢者向け支援は、包括支援センターが窓口になることが多いです。
「こんな制度ある?」と聞くだけでも、新たな情報を得られることがあります。
◆③ SNS・動画・チラシも侮れない
→ YouTubeや地域掲示板、町内会の回覧板なども情報源として活用。
特に高齢者向けにやさしく解説した動画(まさにあなたの動画のようなもの)
も大変役立ちます。
次の第7章では、申請手順と注意点をくわしく解説します。
「どうやって書くの?どこへ出すの?」という不安を一緒に解消しましょう。
 年金のみの暮らしでも該当する制度はたくさんある!
年金のみの暮らしでも該当する制度はたくさんある!
🔸第7章🔸
もらいそこねないために!申請手順と注意点
「制度があるのはわかった。でも、どうやって申請するの?」
ここでは、給付金・助成金の基本的な申請手順と注意点を解説します。
◆ステップ①:まずは“自分が対象か”を確認する
自治体のサイトや窓口で、以下のようなキーワードで調べてみてください。
「高齢者 給付金」
「名称+市町村名」
「福祉支援制度」
不明な場合は「包括支援センター」「民生委員」に相談すれば確実です。
◆ステップ②:必要書類を集める
多くの制度で求められるもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・通帳のコピー(振込先確認)
・住民票(自治体によって異なる)
・印鑑(認印でOKのケース多数)
◆ステップ③:申請書を記入し、提出
・役所での直接提出
・郵送対応(高齢者には便利)
・窓口での代筆や記入サポートもあり
申請用紙が難しそうに見えても、「名前・住所・生年月日+サイン」で完了することも多いです。
◆注意点①:申請期限に注意!
給付金制度には「受付期間」があります。
締め切りを過ぎると原則もらえませんので、情報を見つけたらすぐに行動しましょう。
◆注意点②:自治体によって内容が異なる
同じ「高齢者給付金」でも、A市では1万円、B市では5万円など大きく差があります。
必ず自分の住んでいる市区町村で確認しましょう。
続く第8章では、「勘違いしているともらえない」落とし穴と誤解についてご紹介します。
せっかく制度を知っても、“誤解”で申請しないのは非常にもったいないです。
 一度限りじゃない⁈知らないと損する”再申請制度”
一度限りじゃない⁈知らないと損する”再申請制度”
🔸第8章🔸
その思い込みが損の元!給付金制度の“よくある誤解”とは?
せっかく制度があっても、「自分には関係ない」と思い込んでしまっている人が多くいます。
ここでは、高齢者に多い誤解と、その真実をはっきりさせていきましょう。
◆誤解①:「年金をもらっているから、もう何ももらえない」
→いいえ、それは誤解です。
多くの制度は“低年金者”向けや“特定条件を満たす人”が対象であり、
年金を受けていても併用可能な給付金があります。
実際、「年金生活者支援給付金」などはその代表です。
◆誤解②:「制度は難しそうで自分には無理」
→書類が複雑そうに見えるだけで、実際は名前・住所・振込口座を書くだけの
申請書も多いです。
不安な場合は役所の窓口で「教えてください」と言えば、親切に案内してくれます。
高齢者対応に慣れた相談員が常駐している自治体も増えています。
◆誤解③:「もらえるのは生活保護の人だけでしょ?」
→全くの誤解です。
生活保護対象でなくても、低所得者・単身高齢者・障害がある人など、
細かく制度が分かれているのです。
「生活保護ほど困窮していない」からといって、支援対象外になるとは限りません。
◆誤解④:「昔、断られたから、もう関係ない」
→制度は毎年更新されています。
以前は対象外でも、今年の条件であれば該当する可能性があるのです。
◆誤解⑤:「制度って“特別な人”だけが使えるものだと思ってた」
→多くの人が「支援を受けること=自分が困っていると認めること」
と感じてしまいます。
特に戦後世代では「人に頼らず生きるべき」という意識が強く、申請をためらう方も。
📌実際の行政では?
地域包括支援センターの職員の声:
「“困っている”という自覚がなくても、制度の条件に合っていれば“当然の権利”
としてご案内します。」
受給は“施し”ではなく、**納税や保険料支払いに対する“還元”でもあります。
安心して活用を。
◆誤解⑥:「ネットに載ってる情報は信用できない」
→詐欺や偽情報が多い昨今、特に高齢者は**「ネット情報=怪しい」と警戒しがち**です。
しかし、正確な情報を発信している公的機関のサイトもあります。
📌確認方法のコツ:
「.go.jp」「.lg.jp」など、公式ドメインのついたサイトを利用する
自治体名+「給付金」で検索すれば、該当ページが上位に出てくる
こうした誤解は、自分を守るつもりが結果的に損をしてしまう原因にもなります。
「わからないことは窓口で聞けばいい」──この考えが、制度を正しく活用する第一歩です。
続く第9章では、“制度を活用して生活を改善できた人”の声をまとめてご紹介します。
申請によって変わった日常、ちょっとしたゆとり──そんなリアルな声をご覧いただきます。
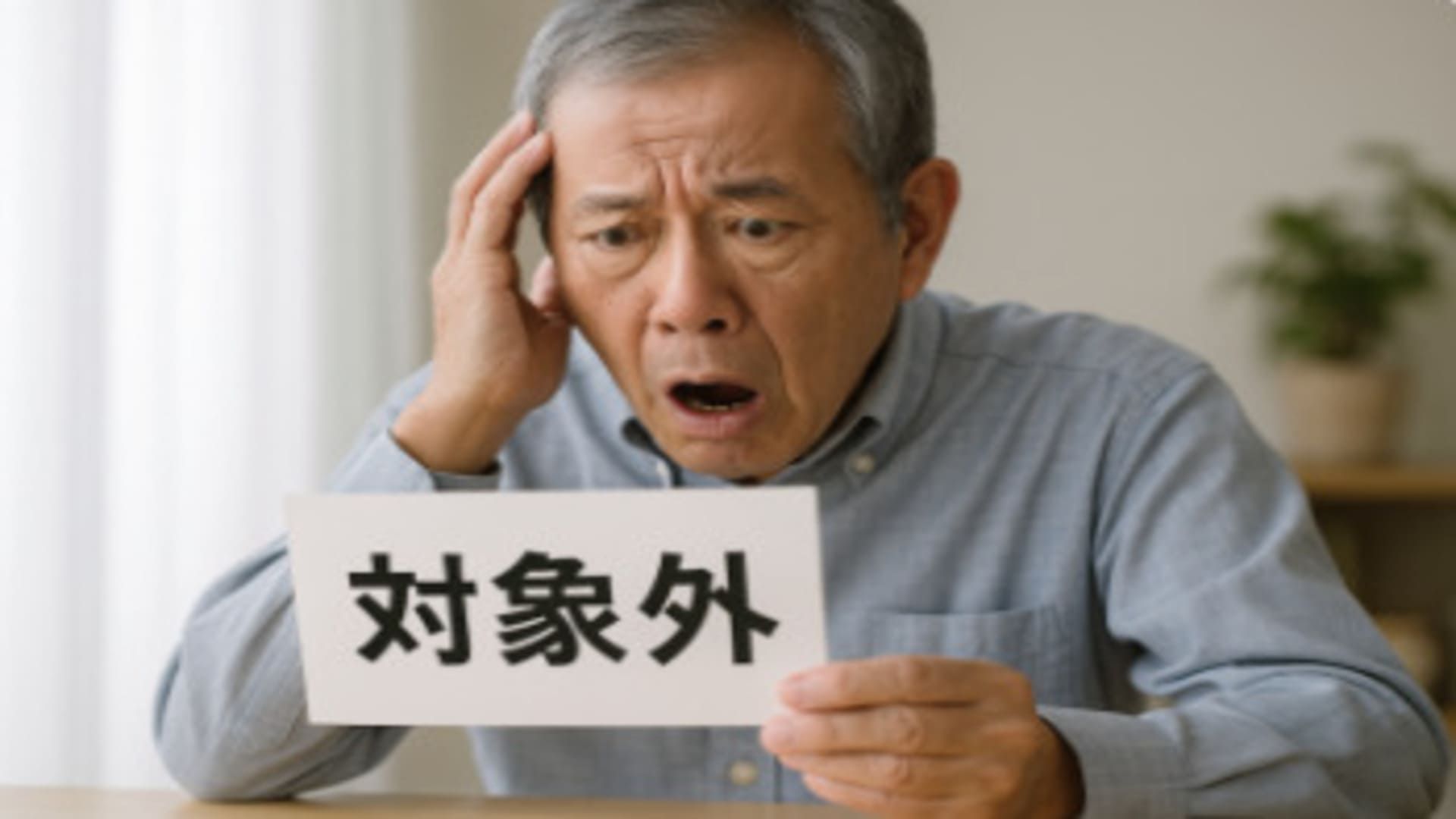 「自分は無理」と決めつけていませんか?
「自分は無理」と決めつけていませんか?
🔸第9章🔸
申請してよかった!“支援が暮らしを変えた”という実例の声
支給を受けたことで、日常が少しだけラクになった。
そんな実感を語ってくれた人たちの“リアルな声”をご紹介します。
◆声①:千葉県・76歳女性(年金月額6万円)
「月に5,000円の給付が上乗せされて、食費を削らなくてもよくなった。今までは、冷凍うどんばかりだったけど、たまに果物が買えるのが嬉しい。」
◆声②:大阪市・80歳男性(独居)
「友人に教えられて、冬の灯油代1万円が支給された。身体の冷えがひどかったので、本当にありがたい支援だった。“自分から調べないと損する”ことを実感。」
◆声③:長野県・68歳夫婦世帯
「介護で収入が減ったが、医療・介護の負担軽減制度を知り、月々の支払いが1万円以上も減った。おかげで生活が安定し、気持ちにも余裕が出た。」
◆声④:福岡県・70代前半男性
「“自分は対象外だ”と思い込んでいたけど、地域包括支援センターに相談してみたら、実は複数の制度に該当していた。合計12万円以上の支給が受けられた。」
こうした声が示すのは・・
**「調べて・動いて・相談した人ほど、生活が好転している」**という事実です。
🔸「知らないままで損しないために、今すぐできること」
🔸「まとめと行動のすすめ」
 給付金詐欺に要注!意注意すべきポイントは・・
給付金詐欺に要注!意注意すべきポイントは・・
🔸第10章🔸
行動のすすめ──「もらえるお金」はあなたのすぐそばにある
ここまで、驚きのある給付金・助成金の数々をご紹介してきました。
「本当にこんな制度があるの?」と感じた方も、
「もしかして、自分も対象かもしれない」と思い始めた方もいることでしょう。
では、今すぐあなたにできる行動をまとめます。
◆【ステップ1】「◯◯市 給付金 高齢者」でネット検索してみましょう!
→ 自治体ごとの最新情報にアクセス。
→ PDFのチラシや申請書が掲載されていることもあります。
◆【ステップ2】役所・包括支援センター・民生委員に気軽に相談
→ 窓口で「高齢者向けの給付金・助成金はありますか?」と聞くだけ。
→ 親切に案内してもらえるケースが大半です。
◆【ステップ3】「申請書を出すだけ」で、もらえるかもしれない
→ 名前と口座情報を書くだけの申請もあります。
→ 難しそうに見えても、一度やってみれば簡単です。
 スマホの使いかたを孫に教わる
スマホの使いかたを孫に教わる
🔸第11章🔸
もらえる“以外”にも!高齢者向け支援制度の一覧
ここまで「現金がもらえる制度」に焦点を当ててきましたが、実はそれだけではありません。
**“お金ではないけれど、生活を直接助けてくれる支援”**も数多く存在しています。
◆① 介護用品支給制度
要介護認定を受けている高齢者に対して、紙おむつ・防水シーツ・介護用手すりなどを無料または格安で支給。
多くの自治体で実施されており、年間にすると数万円分の負担軽減に。
◆② タクシー券・バス回数券の支給
通院や買い物が困難な高齢者を対象に、移動手段の支援としてタクシー券などを定期配布。
「外出ができないから病院にも行けない」という悩みを、自治体が解消してくれるケースです。
◆③ 配食サービス(食事の宅配支援)
高齢者単身世帯や身体の不自由な方に向けて、栄養バランスのとれた食事を届けてくれる支援制度もあります。
1食300円〜500円ほどで提供されることが多く、毎日利用すれば月1万円以上の節約に。
◆④ エアコン設置・修理の助成(熱中症対策)
熱中症対策として、高齢者世帯にエアコンの設置・修理費用を補助する自治体が急増中。
「今年の夏から申請できる」という市町村も多く、支援額は数万円規模です。
お金そのものを受け取らなくても、生活支出を大幅に減らすことができる支援は見逃せません。
では次に、「こんな自治体もやっているの?」というユニークな支給例をご紹介します。
 お金じゃない支援も豊富!生活を支える制度はいっぱい
お金じゃない支援も豊富!生活を支える制度はいっぱい
🔸第12章🔸
全国にあった!ユニークで助かる自治体独自の給付例
自治体によっては、思わず「そんな制度まであるの!?」と驚くような支援策を実施しているケースがあります。
ここでは、全国の中でも特にユニークな支援例をご紹介します。
◆東京都葛飾区:「おむつ代給付」
在宅で要介護認定を受けている高齢者に対して、月額5,000円相当の紙おむつを給付。
医師の意見書や介護認定書類をもとに支給され、年間6万円相当の支援に。
◆長崎県平戸市:「高齢者見守り電球」支給
高齢者世帯の部屋に「見守り機能付きLED電球」を設置。
一定期間電気が使われないと自動通報される仕組みで、孤独死の防止にもつながっています。
◆京都市:「冬季灯油購入助成」
寒冷地でない地域でも、暖房費の負担を考慮し、最大5,000円分の灯油助成券を配布。
毎年対象者を絞って実施しており、高齢者世帯には大変ありがたい制度です。
◆北海道北見市:「買い物サポートカー」運行
買い物弱者と呼ばれる高齢者のために、スーパーと自宅の間を巡回する無料車両を運行。「移動販売バス」と合わせて、買い物機会の確保を支援しています。
こうした制度は、行政が“現場の声”を拾って生まれた支援策です。
「うちの自治体は何をしてくれているだろう?」と、一度調べてみる価値は十分にあります。
次は第13章、**「年齢だけでは判断できない、意外な受給条件」**に焦点を当てます。
「高齢者じゃなくても対象になる?」という視点で見ていきましょう。
 地方にはいろいろな支援制度がたくさんあります
地方にはいろいろな支援制度がたくさんあります
🔸第13章🔸
意外な落とし穴!? “年齢だけでは決まらない”受給条件とは
「65歳以上じゃないと対象外でしょう?」
そう思っている方も多いかもしれませんが、実は給付金・助成金の多くは“年齢だけ”判断されるものではありません。
◆① 60歳未満でも対象になる「所得基準」制度
例えば「住民税非課税世帯向けの給付金」などは、年齢ではなく“収入が一定以下”かどうかがポイントです。
年金だけの暮らしをしている60代前半離職して収入が減った人
こうしたケースでは、高齢者でなくても支給対象になります。
◆② 介護認定・障害認定がカギになることも
高齢者でなくても、要介護認定や障害認定を受けていれば特定の制度に該当することがあります。
「40歳以上で介護保険料を支払っている人」なども条件に含まれる場合があるため、“何歳か”よりも“どんな状態か”が重要です。
◆③ 扶養家族としてカウントされる場合
本人ではなく、同居する親や祖父母が対象者というケースも。
この場合、家族が申請手続きをする必要がありますが、結果として家計全体に給付が入ることになります。
◆④ 「世帯合算」が落とし穴に
「自分ひとりだと収入が低くて該当しそうなのに、同居している子どもが働いていて…」というケース。
自治体によっては、世帯収入全体での審査を行うため、「個人での収入が低くても対象外」になることも。
この点は申請前に必ず確認が必要です。
つまり、「年齢」や「見た目の生活水準」だけでは判断できません。
“今の自分の状態がどうか”を正確に把握し、それに合った制度を探すことが、
最も確実な方法です。
次の第14章では、申請時にありがちなミスや失敗例を紹介します。
「せっかく調べたのに受け取れなかった…」という残念な結果を避けるために、
ぜひご覧ください。
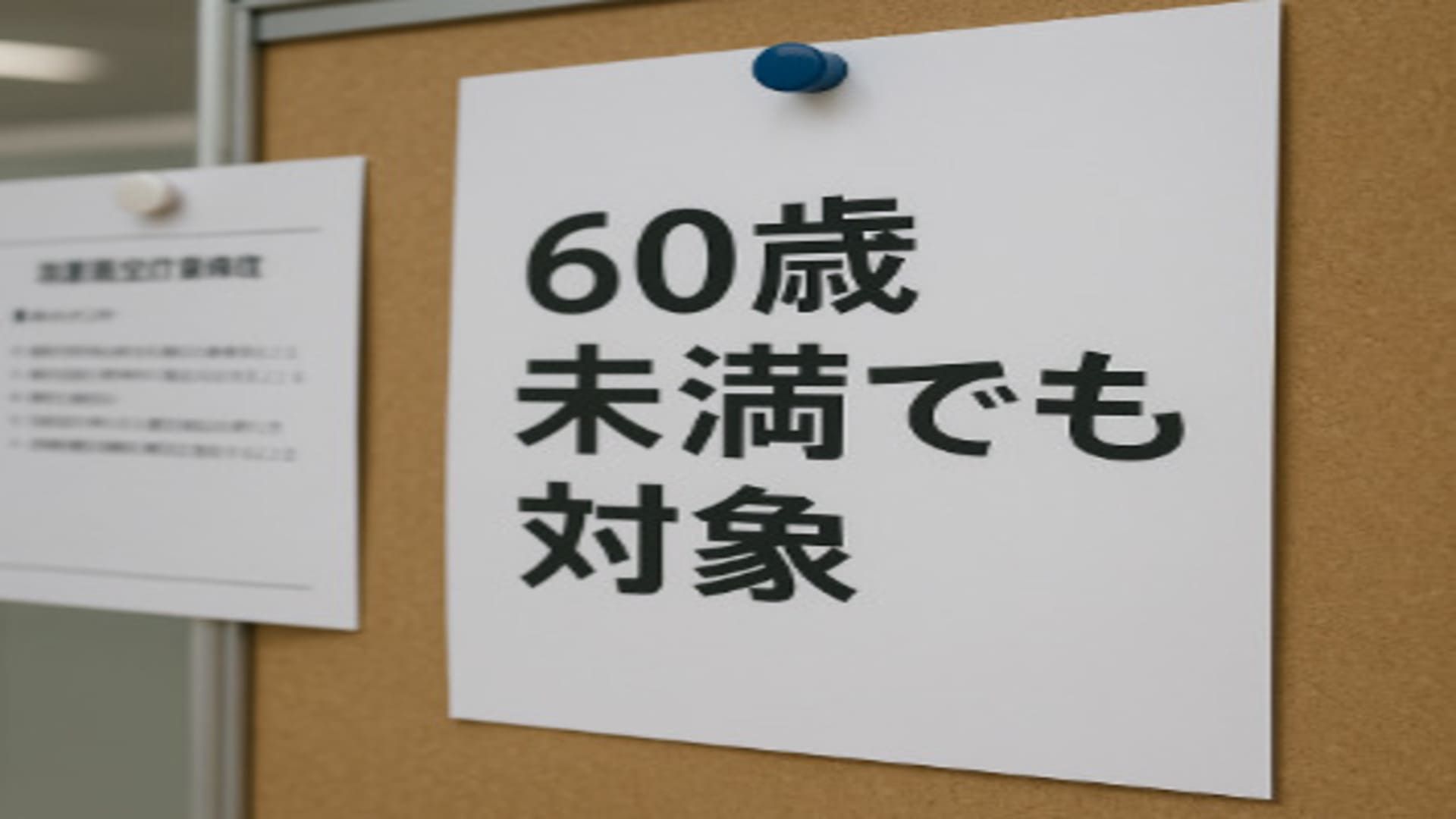 年齢だけじゃない!”条件”を見落とさないで
年齢だけじゃない!”条件”を見落とさないで
🔸第14章🔸
もったいない!申請時によくあるミス・失敗例とは?
制度の存在を知り、条件も満たしているのに、ちょっとしたミスで“もらいそこねる”人が意外と多いのです。
ここでは、実際によくある申請ミスとその対策をご紹介します。
◆① 申請期限を過ぎてしまった
「来月でいいか」と後回しにした結果、**気づいたときには申請締め切りが過ぎていた…**という声は多く聞かれます。
→対策:見つけたら即メモ、即行動。「一週間以内に申請する」と決めましょう。
◆② 必要書類の不備や未提出
特に多いのが「本人確認書類のコピー忘れ」や「印鑑の押し忘れ」。
→対策:申請書の裏面にある「チェックリスト」を活用。コピー機のある役所でその場で確認するのがおすすめです。
◆③ 自治体に出す書類と年金機構に出す書類を混同
給付金によっては、提出先が違うことがあります。
→対策:「どこに出す書類か」を窓口で必ず確認しましょう。
◆④ 条件を“自己判断”で除外してしまう
「どうせ自分は対象じゃない」と勝手に判断して申請しない人が多いのも事実。
→対策:「自分は対象ですか?」と一言聞くだけでチャンスが広がります。
◆⑤ 領収書・証明書が必要なタイプの助成で準備不足
介護用品や医療費の助成では、“領収書の原本提出”が必須な場合もあります。
→対策:日頃からレシート・領収書を保管しておくクセをつけておきましょう。
支給額が数万円〜十万円規模になる支援も多い中、ミス一つで失うには大きすぎる金額です。
「せっかくの権利を無駄にしないための準備」をしっかり行いましょう。
◆失敗例①:申請書の「印鑑」を忘れて返送
→よくあるケースで、「記入内容は合っているのにハンコが押されていない」
ことによる差し戻し。
特に郵送申請の場合、不備通知が届くまでに数週間かかり、締め切りを過ぎて
アウトになるリスクも。
📌対策:申請書記入後は「提出前チェックリスト」を作って、2度確認。
窓口提出の場合は、その場で職員が確認してくれるので安心。
◆失敗例②:「受給できると思っていたのに、所得オーバーだった」
→年金や副収入が微妙に上回っていたために不支給となる例。
「非課税世帯」と思っていても、実際は課税されていたという誤認が原因。
📌対策:住民税非課税証明書を役所で取得するのが最も確実。
自分で判断せず、申請前に「収入条件に該当しているか?」を確認するクセをつけましょう。
◆失敗例③:「もらったが、報告書や使途証明を忘れて“次回以降の申請不可”に」
→助成金や貸付制度の一部には、「使途の証明書」や「報告義務」がある場合があります。
知らずに放置してしまい、次回の申請資格を失ったという声も。
📌対策:申請後も、制度の説明文書や注意書きをしっかり保管・確認。
心配な場合は、「申請後に必要な書類はありますか?」と窓口で聞いておくのがベストです。
◆再申請できる?
基本的に、「提出ミス」「不備による差し戻し」程度であれば期間内であれば
再提出が可能です。
しかし「申請期限を過ぎた」「必要書類を揃えなかった」場合は、原則アウト。
だからこそ、**“1回目の申請で確実に通す”**という意識が大切です。
次の第15章では、2025年以降に変わる可能性のある制度や国の動きを展望します。
「今は該当しないけれど、来年は対象かも?」という視点で読み進めてください。
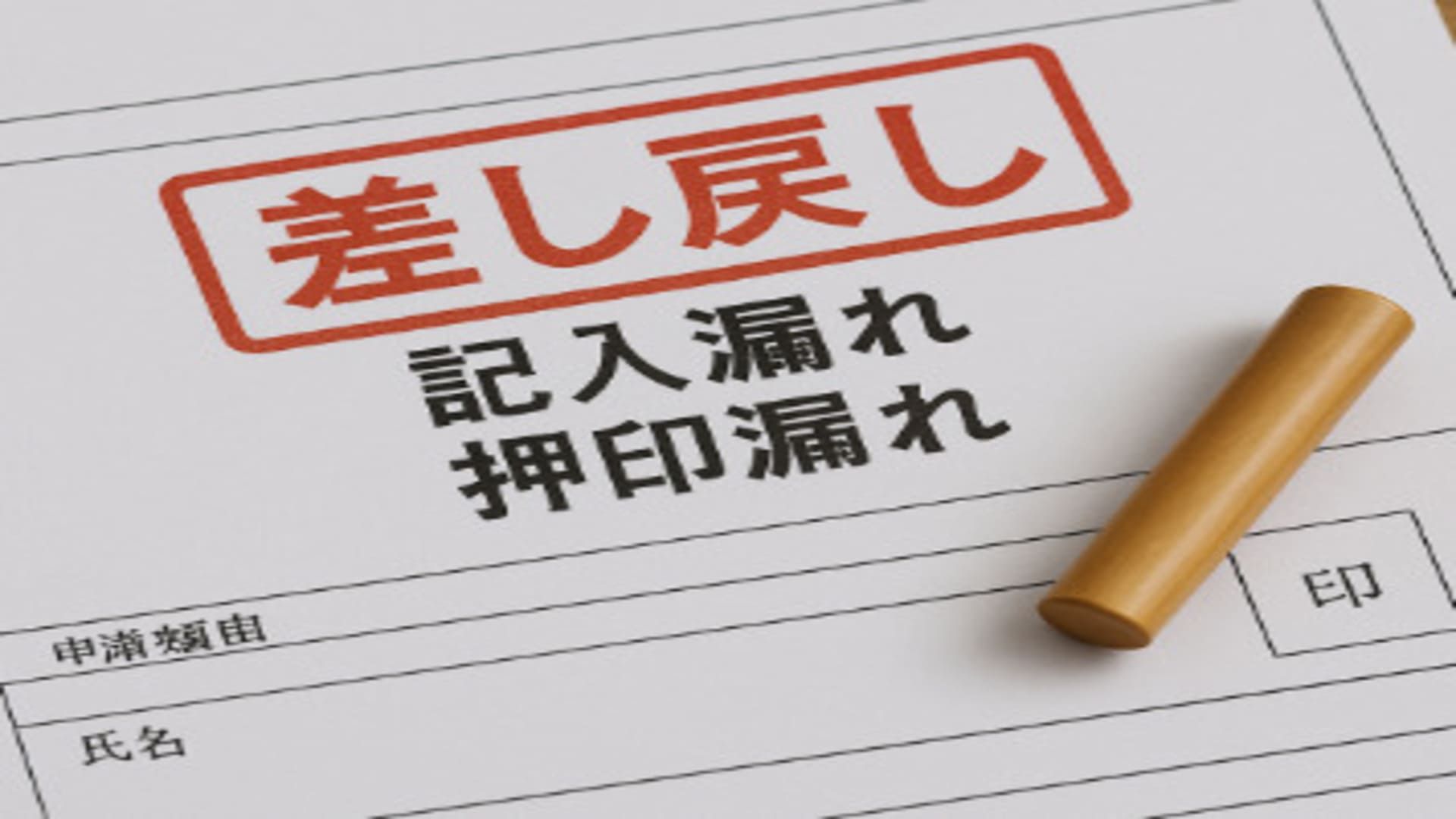 記入漏れ・締め切りミス…避けたい”もったいない落とし穴”
記入漏れ・締め切りミス…避けたい”もったいない落とし穴”
🔸第15章🔸
2025年以降、制度はどう変わる?今後の動きを見逃さないために
給付金や助成金制度は、「永続的なもの」ではありません。
政治・経済・人口動態に応じて、毎年のように見直されていくのが特徴です。
ここでは、2025年以降に注目すべき動きや改正の兆しを解説します。
◆① 「高齢者支援の重点化」方針が進行中
国は「高齢者単身世帯の増加」「年金額の格差」などを背景に、
“直接支援”の比重を増やす方向にシフトしています。
→たとえば、年金生活者支援給付金の所得要件の緩和や、
→高齢者の「医療・介護自己負担額の減免強化」などが検討されています。
◆② 物価高騰に伴う“臨時給付”が再びある可能性
2024年も行われたように、急な物価高に対しての一時金支給が今後も実施される可能性があります。
その際、対象は“住民税非課税世帯”が中心となることが多いため、あらかじめ
非課税判定の確認をしておくことがカギです。
◆③ 「デジタル申請」制度の拡大
マイナポータルを使った申請や、オンラインでの情報提供が推進されており、
高齢者にもスマホを通じて申請できる制度が増加傾向にあります。
→自治体によっては「スマホサポーター」制度で、申請支援を無料で受けられるところも。
◆④ 今後の財源議論と“対象者の絞り込み”に注意
支援制度の充実とは裏腹に、財源の問題も深刻です。
そのため、「全員対象」から「より困窮した人へ重点化」という流れが強まる可能性が高く、今は対象でも来年は対象外になるということも起こり得ます。
このように、制度は“今知っておくべき情報”と“来年への備え”の両方が重要です。
では最後の第16章では、今すぐできる**「行動チェックリスト」**をお渡しして、実際に一歩踏み出すお手伝いをします。
 制度は毎年変わる!来年の準備を今からしよう!
制度は毎年変わる!来年の準備を今からしよう!
🔸第16章🔸
あなたも今すぐできる!
もらい損ねないための行動チェックリスト
ここまでの内容をふまえて、最後に「見て終わり」にならないための
チェックリストをご紹介します。
ぜひ、この章を開きながら、スマホや手帳にメモを取ってみてください。
✅【1】自分の自治体の「給付金・助成金ページ」を検索した
検索例:「◯◯市 高齢者 給付金」
ブックマークしておくと便利
✅【2】住民税課税・非課税の状況を把握している
直近の住民税通知書や年金支払通知書で確認
わからなければ役所で問い合わせを
✅【3】地域包括支援センターや役所の福祉課に一度相談した
相談は無料。電話でもOK
「対象になりそうな支援制度はありますか?」と聞くだけでOK
✅【4】申請書類を集めた・準備中
本人確認書類、通帳コピー、印鑑、介護認定証など
書き方が分からなくても、役所で記入サポートしてもらえる
✅【5】支援を受けた後の使い道を想像してみた
食費にあてる
暖房費や通院交通費にまわす
自分や家族の安心につながるように使う
 今すぐできる!もらい損ね防止チェックリスト
今すぐできる!もらい損ね防止チェックリスト
🔸第17章🔸
もらった給付金、どう使う?
生活を豊かにする“お金の使い方”のヒント
給付金や助成金を受け取ったあとは、「何に使うか?」がとても大切です。
せっかく手に入った“ゆとり”を、どのように活かせば生活がより豊かになるのでしょうか?
◆① 生活の不安を先に解消する
最も基本的なのは、「いつも不安に思っている出費」にあてること。
たとえば──
・通院の交通費や薬代
・水道光熱費(特に冬季・夏季)
・食費のなかでも「果物」「肉」「魚」など、普段節約しがちな品目
一時的でもこうした不安が軽減されれば、精神的な安心感が大きく変わります。
◆② “ちょっとした楽しみ”に使って心の健康を
給付金の一部は、生活に潤いを与える使い方をしてみるのもおすすめです。
・外食でお寿司や定食を楽しむ
・映画や展覧会を見に行く
・温泉や銭湯へ出かける
・図書カードや趣味の材料費にあてる
ほんの少しでも「自分のためにお金を使う」経験は、高齢期のメンタルケアにも非常に効果的です。
◆③ 子や孫への“心の贈り物”にする
自分だけでなく、家族とのつながりを深める使い方もあります。
・孫へのプレゼントやおこづかい
・家族での外食費
・写真館での家族写真撮影 など
「もらったお金を“ありがとう”に変える」ことも、給付金の価値を高める
使い方のひとつです。
◆④ 次の備えにあてる
・非常食や防災用品の購入
・老朽化した家具・家電の買い替え
・電球のLED化など電気代削減への先行投資
給付金が単なる“消費”ではなく、生活の安定と安心につながる投資になれば、
その効果は長く続きます。
◆やってよかった!実例集
📌千葉県・68歳男性
「もらった給付金で、毎月通っていたマッサージを1回増やした。
肩こりが軽減して、夜眠れるようになった。体調が整うと気持ちも前向きになることに気づいた。」
📌大阪府・74歳女性
「給付金でスマートフォンを買い換えた。包括支援センターに申請の方法を
教えてもらったとき、
“これからはスマホで情報を見る時代ですよ”と言われて、思い切って購入。
制度を知るきっかけが格段に増えた。」
◆やめておけばよかった…という声
📌「パチンコや競馬に使ってしまった」
→これは実際に複数の福祉相談員から聞いた“失敗例”。
一時的な娯楽のために使い切ってしまい、次の月の食費や医療費に困ったケースも。
📌「知らぬ間に詐欺サイトで“手数料名目”でお金を取られた」
→給付金の使い道ではないが、“もらえるお金”の情報に便乗した詐欺が横行。
「口座情報を入れれば即入金」などのメールには絶対に注意。
◆感情面の変化にも注目
「“自分も社会に大事にされている”と感じた」
「余裕ができた分、近所の人との会話が増えた」
「買い物が楽しくなって外に出るようになった」
お金は“モノ”だけでなく、“気持ち”も動かします。
支援を「遠慮なく受け取り」、自分にとって前向きな使い道を考えることが
大切です。
続いて第18章では、親や家族の給付申請をサポートしたい人向けの実用的な
アドバイスをお届けします。
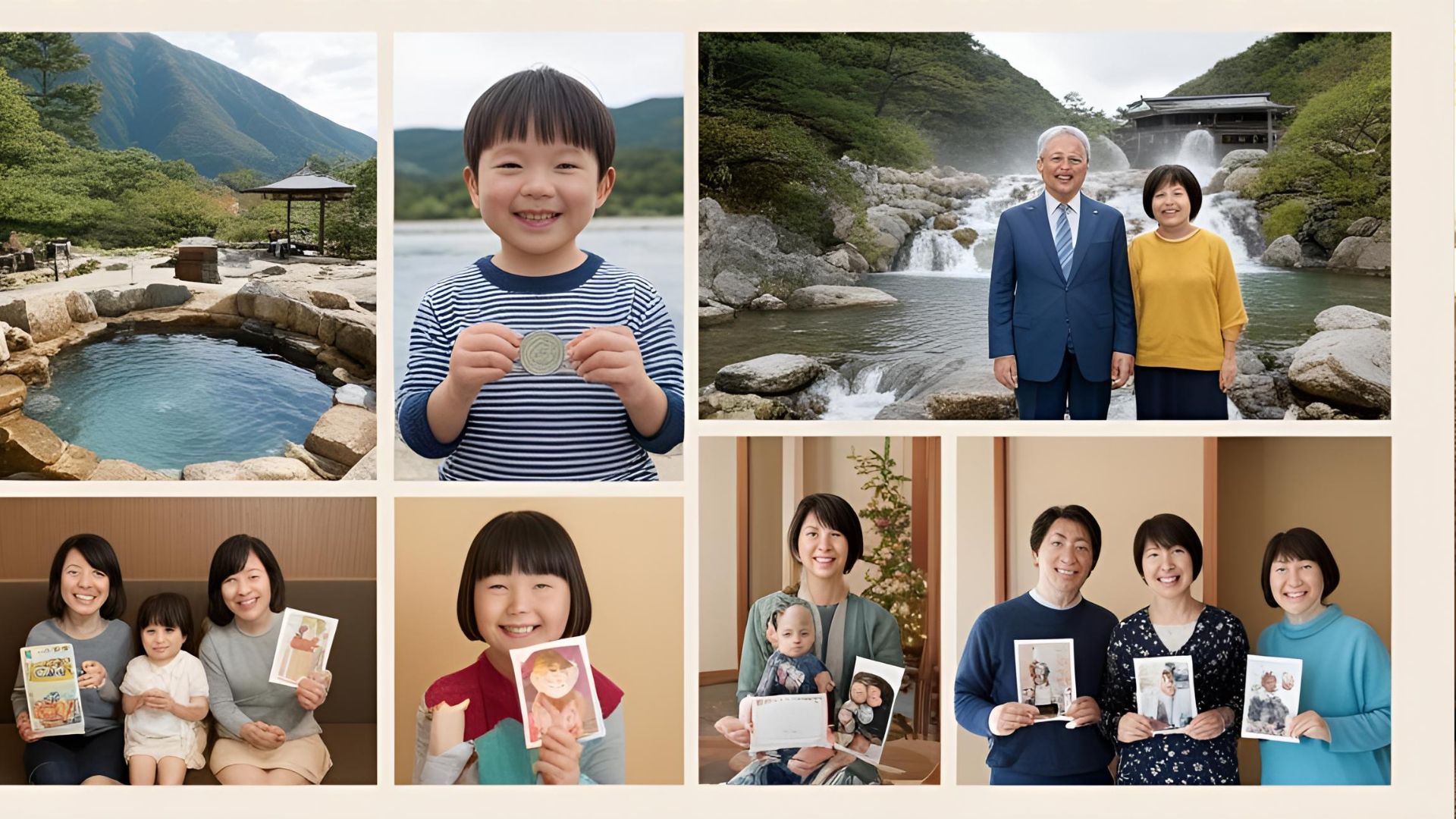 生活が楽しくなる!賢い給付金の使いかたとは?
生活が楽しくなる!賢い給付金の使いかたとは?
🔸第18章🔸
親や家族のために申請したいときの注意点とサポート法
「親が高齢になってきたけど、制度のことなんてまるで知らない…」
そんな声が今、若い世代からも多く寄せられています。
この章では、**ご家族が高齢者本人に代わって申請を手助けする場合の
“注意点と実践のコツ”**をお伝えします。
◆① 一緒に制度を調べて「必要性」を共有する
まずは、親御さんに「給付金や助成金があるらしいよ」と優しく切り出し、
ネットやパンフレットで一緒に情報を見てみましょう。
→高齢者の多くは「詐欺と疑ってしまう」「制度に不信感がある」ため、
信頼できる家族がそばにいて説明することが安心感に繋がります。
◆② 窓口に同行・代筆・書類準備のサポート
・印鑑、通帳、本人確認書類を一緒に用意
・申請書の記入欄を代筆してあげる
・記入後、一緒に役所や包括支援センターへ行く
このようなちょっとしたサポートだけで、申請に踏み切れなかった高齢者が多く制度を活用できるようになります。
◆③ 過度な“代行”ではなく、あくまで“伴走者”として関わる
たとえ家族でも、「勝手に申請してしまう」とトラブルの元。
必ず事前に本人の了承を得て、“一緒に申請する”という姿勢が大切です。
→本人の名前で申請する以上、受給後の使い方も含めて共通理解を持って
おくと安心です。
◆④ 書類提出後も「確認の電話」や「受給通知」のチェックを
申請後、「ちゃんと届いたかな?」「通帳に振り込まれているかな?」
と確認するのも家族の大事な役割です。
→受給漏れや誤振込などを防ぐため、“フォローする意識”も持ちましょう。
家族が一緒に動くことで、申請のハードルは一気に下がり、結果的に安心も
増えます。
次の第19章では、家族や代理人が実際に“代理申請”する場合の制度や
手続きの流れをご紹介します。
 家族と一緒なら安心!”申請の壁”を越えるサポート
家族と一緒なら安心!”申請の壁”を越えるサポート
🔸第19章🔸
高齢者本人に代わってできる“代理申請”とは?家族が知って
おくべき手順
高齢の親が入院中、認知症を抱えている、または身体的に動けない──
そんなとき、「代理申請」という制度を活用すれば、家族が申請手続きを
代行できます。
この章では、その具体的な仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
◆① 代理申請とは何か?
代理申請とは、「本人の代わりに、家族や支援者が書類を提出すること」です。
ただし、誰でも自由に代理できるわけではなく、“正しい手続き”が必要です。
◆② よくある代理申請のケース
・認知症や障害で自署が難しい場合
・長期入院や施設入所中のため、窓口へ行けない場合
・高齢の親の代わりに、遠方に住む子どもが手続きする場合
こうした状況で、本人の意思を尊重しながら家族が手続きを代行します。
◆③ 必要な書類と注意点
多くの自治体で必要とされるのは以下の通りです。
・本人の委任状(手書き・署名入り)
・代理人の本人確認書類(免許証・健康保険証など)
・本人の通帳コピーや印鑑(給付金の場合)
認知症等による判断困難がある場合は診断書の提出が求められることも
→委任状の様式は、自治体の公式サイトにPDFで掲載されていることが多いので、必ず確認しましょう。
◆④ 代理申請時の落とし穴
・委任状の不備(署名・日付・押印漏れ)
・本人が後から「そんな申請していない」と誤解するトラブル
・申請先窓口の誤認(福祉課・地域包括・年金機構など混同)
→書類提出前に、窓口に電話で「この場合はどうすれば?」と事前確認するのがおすすめです。
◆⑤ 代理申請を“悪用と見なされない”ための心構え
行政側は、「代理申請=本人の意思でない可能性がある」と警戒することも
あります。
そのため、説明・記録・書類の保存を丁寧に行い、家族として誠意ある対応を
心がけましょう。
代理申請制度は、正しく使えば家族にとっても大きな支えとなる仕組みです。
「家族の誰かが困っている」と感じたら、制度を味方にしてみてください。
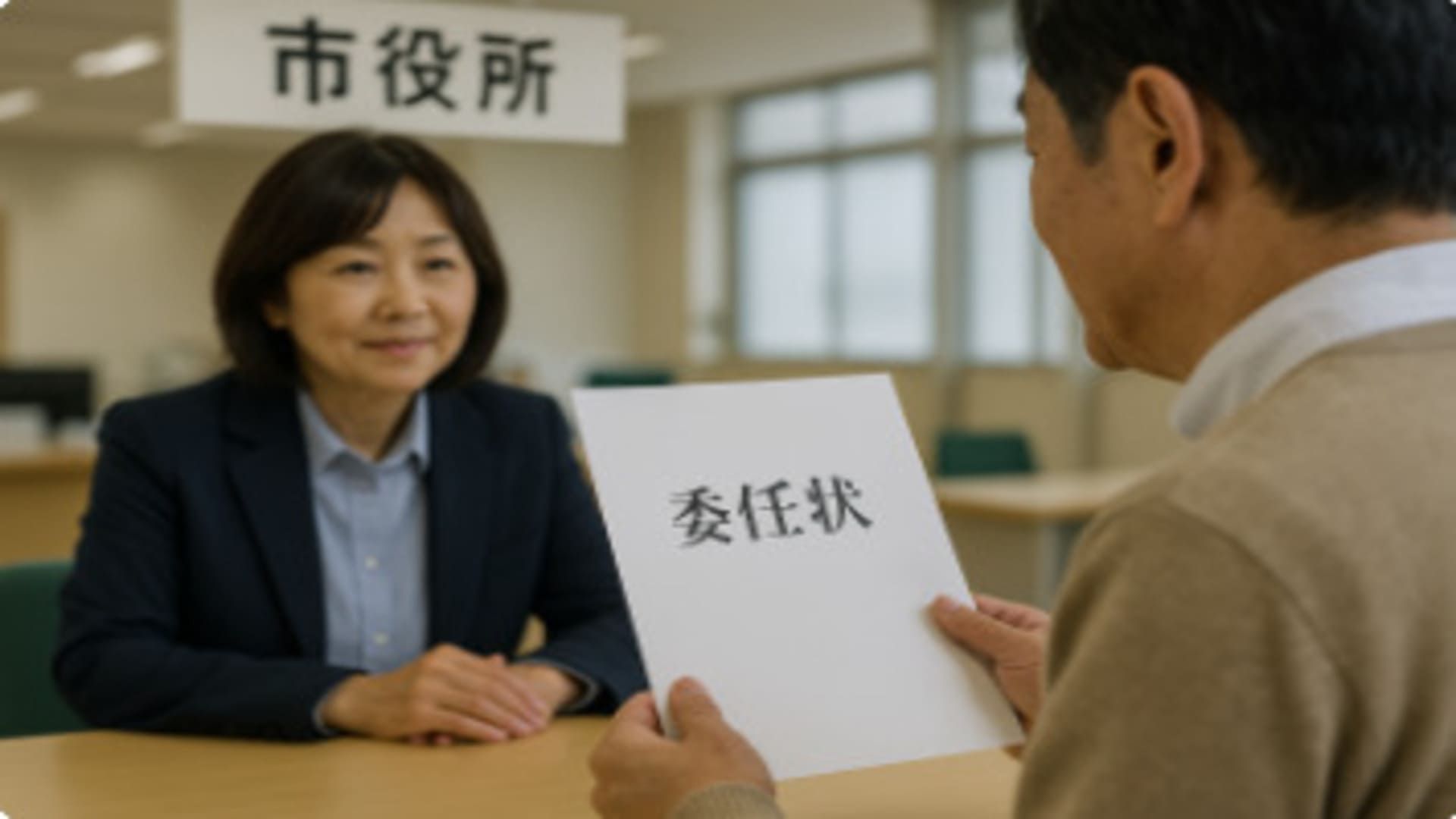 本人が無理でもOK!”家族による代理申請”の流れ
本人が無理でもOK!”家族による代理申請”の流れ
🔸第20章🔸
**「どこに相談すればいい?」困ったときの制度相談窓口
まとめ**
ここまで読み進めて、「この制度、自分も使えるかも…でも、やっぱり不安」
「誰に聞けばいいかわからない」という方もいらっしゃると思います。
そこで、**高齢者向けの給付金・助成金に関する“相談窓口”**を、
目的別にわかりやすく整理してお伝えします。
◆① 地域包括支援センター(高齢者支援の総合窓口)
各市町村に設置されている「地域包括支援センター」は、高齢者の生活・
福祉・介護に関する総合的な相談先です。
「自分に合う制度があるか知りたい」
「何を申請すればいいのかわからない」
そんなときに最も頼れる場所です。予約なしでも訪問OKのところが多く、
丁寧な対応で安心できます。
◆② 市区町村の役所「福祉課」「高齢者福祉係」
給付金や助成金の**受付・審査・振込手続きなどを行っている“実務窓口”**です。
【制度名が分かっている場合はこちら】
「申請書をもらいたい」「書き方を教えてほしい」ときも対応してくれます
電話口で「高齢者の給付金のことで伺いたいのですが…」と伝えるだけでも、
きちんと部署に取り次いでもらえます。
◆③ 年金事務所(年金に関係する給付金)
「年金生活者支援給付金」などは、日本年金機構が管理する制度です。
年金額や保険料納付状況の確認、給付対象かどうかなどを調べてもらえます。
※ただし、年金事務所は非常に混み合うため、電話予約・事前準備がおすすめです。
◆④ 社会福祉協議会(生活福祉資金や貸付支援の相談)
急な医療費や生活困窮時に対応する「生活福祉資金」や、「一時的な貸付制度」は、各地の**社会福祉協議会(社協)**が窓口です。
「給付制度では足りないとき」
「緊急の支出があり、生活が回らないとき」などもここへ
◆⑤ 民生委員・町内会経由の情報も大事に
特に紙の情報や訪問サポートを重視する高齢者向けには、地域の民生委員や
町内会からの通知が重要な窓口になります。
・家までチラシを届けてくれたり
・実際に相談に乗ってくれたり
制度に精通している人が多いのも特徴です。
✅「迷ったら“包括支援センター”へ」が鉄則!
制度に詳しくなくても、「包括支援センターに電話すれば何とかなる」
──これは現場の実感としてよく聞く声です。
全国に5,000カ所以上あるため、“自分の住んでいる地域名+包括支援センター”
で検索すればすぐに見つかります。
◆相談事例①:制度名がわからなくてもOK
📌東京都内・70代女性のケース
“住民税非課税世帯って何?”という状態で地域包括支援センターに電話したところ、“お住まいの市では、給付金の対象になりますよ”とすぐに説明してもらえました。
申請書の取り寄せ、記入方法、提出先まで電話一本で全部教えてもらえました。
◆相談事例②:書類の記入が苦手でも心配無用
📌岐阜県・80代男性
手が震えて字がうまく書けないので相談したら、“代筆サポートがあります”
と言われて安心。窓口まで行けない事情も伝えたら、出張対応をしてくれた。
◆電話をかけるときのポイント
・自治体名を伝える(例:「○○市に住んでいる○○です」)
・年齢や世帯構成を軽く伝える(例:「年金暮らしで1人暮らしです」)
・知りたい内容が曖昧でも「何か該当する制度ありますか?」でOK
◆相談前に用意しておくとスムーズなもの
・健康保険証や年金手帳(本人確認用)
・住民税通知書や所得証明書(所得確認が必要な場合)
・通帳(口座情報を伝えるため)
・過去に受け取った通知や書類(再申請や追加入力がある場合)
◆“何も知らずに1人で悩まない”のが一番大切
「こんなことで相談していいのかな」と思う内容でも、
**窓口の人たちは“誰かの不安を取り除くプロ”**です。
勇気を出して1本電話をかけることで、生活が大きく変わる第一歩になります。
 「ここに相談すれば大丈夫!」安心の相談窓口
「ここに相談すれば大丈夫!」安心の相談窓口
✅ 最後に・・
ここまで、お付き合いいただきありがとうございました。
今や、制度を知っているかどうかで、年に数万円〜10万円以上の差がつく時代です。
しかも、それは「頑張って働くこと」や「我慢すること」ではなく、
ただ知って、申請するだけで得られるもの。
■あなた自身のために──
■あるいはご両親やご家族のために──
今日、調べる・相談するという“ひと手間”を、ぜひ踏み出してみてください。


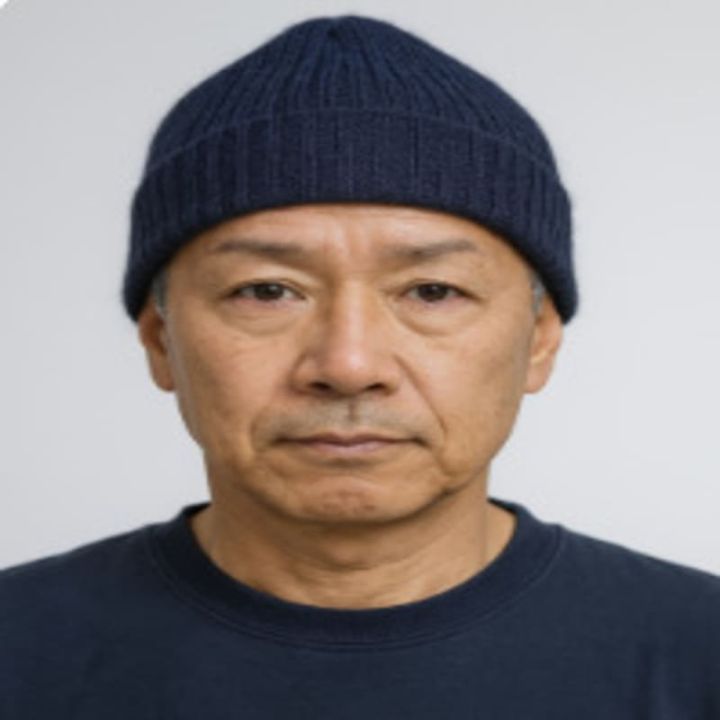



まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。