『極道からの贈り物』
序章:鉄の男と犬嫌い
鉄のような男だった。
涙を流した姿を見た者など、一人としていない。
怒鳴る声と鋭い目つき、夜の街をひと睨みすれば誰もが道を空ける。
その背中には、言葉にできない数々の修羅場を背負っていた。
人呼んで「鬼の親分」。
仁義と義理に生きる男たちの中でも、ひときわ恐れられる存在だった。
ただし、本人にはひとつだけ、絶対に譲れない主張があった。
「俺ァな、犬が大嫌いなんだよ」
それはただの好みというレベルではない。
犬を連れて歩く人間さえ近づけず、吠え声が聞こえれば顔をしかめ、
たとえ子犬であろうと、まるで悪霊でも見るような目で睨みつける。
理由を尋ねた子分が一人いたが、翌日から姿を見なくなった。
それ以来、親分の前では「イヌ」の話題は絶対にタブー。
それが、この組での生き残り術だった。
そんな鬼のような男に、ひとりだけ頭が上がらない相手がいた。
それが、ひとり娘の「美咲」だった。
年頃の女の子らしいあどけなさと、妙に芯のある優しさをもった美咲は、
親分のことを「パパ」と呼び、まるで普通の家庭のように笑いかけていた。
親分の方も、娘にだけは怒鳴らなかった。
どれだけ忙しくても、帰れば必ず「ただいま」と声をかけ、
娘の寝顔をそっと見守ることを、密かな日課にしていた。
「犬が嫌いなこと以外は、いいお父さんだと思うよ?」
ある晩、笑いながらそう言った娘の顔に、
親分は一瞬だけ照れたような表情を浮かべた。
子分たちはその瞬間を見て、「伝説の瞬間」と密かに呼んだという。
でも、その夜から、この物語は静かに動き始める。
娘が、まだ温もりを保った小さな命を、
こっそりと家に連れて帰ってきたのは、それから間もなくのことだった。
 こっそりと家に連れて帰ってきた仔犬 ※以下イメージ画像
こっそりと家に連れて帰ってきた仔犬 ※以下イメージ画像
第1章:小さな命との出会い
夜風が冷たくなり始めた、ある秋の日の夕暮れ。
いつもより少しだけ帰りが遅くなった美咲は、人気のない路地裏で、ふと足を止めた。
「クゥン……クゥン……」
どこか頼りない、でも必死に生きようとするような小さな鳴き声。
その声の方へゆっくり歩いていくと、段ボールの中にうずくまる、ひときわ小さな子犬がいた。
全身は泥だらけで、痩せ細った身体が震えている。
まだ目も開ききっていないようで、時折、小さく咳をしていた。
「だいじょうぶ? 生きてる?」
美咲はしゃがみ込み、そっとその体を抱き上げた。
手のひらに収まるほどの小さな命。だがその鼓動は、はっきりと彼女の手に伝わってきた。
その瞬間、少女の中で何かが決まった。
この子を、助けなきゃいけない――そう思った。
問題は、家に連れて帰ることだった。
何よりも、あの「犬嫌いの親分」である父の存在があったからだ。
でも、ためらっている暇はなかった。
このままじゃ、この子は朝まで生きられないかもしれない。
「絶対に、パパには内緒ね」
美咲はそう小さく囁くと、子犬を自分の上着で包み、そのままこっそりと家へ戻った。
親分が家に帰ってきたとき、いつも通りの重い足音とドスのきいた声が廊下を満たした。
ただいま……
おかえりなさい、パパ! お風呂、沸いてるよ!
美咲は少し声を高めに明るく振る舞い、いつも以上に丁寧にお茶を出した。
親分は「ふむ」と短くうなずくと、何も気づかぬ様子で自室へ向かった。
その隙に、美咲は自分の部屋へ駆け込んだ。
毛布の中で小さく丸くなる子犬に、水と少しのパンを与えると、ほんの少しだけ尾を振った。
小さな命が、ほんのわずかに反応を返してくれたことが嬉しかった。
コロ……今日からあなたは“コロ”ね。
名前を付けた瞬間、その子は家族になった。
それから数日、美咲は必死に“秘密の看病”を続けた。
学校から帰るとすぐにコロのもとへ駆け寄り、
夜は自分の部屋に布団をかぶって、咳が出ないよう息を殺して過ごす。
親分の目をごまかすために、子犬用の餌も近所のスーパーではなく、
二駅離れたコンビニでこっそり購入した。
どんなに大変でも、美咲の表情には疲れた色はなかった。
むしろ毎日が少しだけ楽しく、暖かくなった気がした。
がんばれ、コロ。……絶対、元気になろうね!
それは、美咲が初めて“守る”と決めた、小さな命との約束だった。
だが、その日々は長くは続かなかった。
ある夜、親分がふと、家の中を歩いていたとき――
娘の部屋から、小さく、かすかな鳴き声が聞こえた。
「……クゥン……」
足を止めた親分の顔が、鋭くこわばる。
まさか、と思いながらドアをそっと開けると、
娘は毛布の中で、何かを必死に隠すようにしていた。
……美咲、おまえ……何をしてる?
声は低く、震えていた。
美咲は驚き、でもすぐに前に出て、小さな命を両手に抱えて差し出した。
パパ、ごめんなさい。でも……この子、死にかけてたの。私、見捨てられなかったの。
親分は言葉を失った。
その目には、泥だらけだったころとは違う、少しだけ目を開き、
震える足で娘の手に寄り添う、小さな命があった。
……コロっていうの。私がつけたの。
美咲の声は、震えていなかった。
むしろ、誰よりも強い覚悟を感じさせるものだった。
親分はしばらく黙っていたが、
やがて深く息を吐き、ぽつりとこう言った。
……好きにしろ!ただし……俺の前には絶対に出すな!
そう言い残し、静かにドアを閉めた。
その夜、美咲は涙を流した。
怒られなかったことにではなく、父が、たった一言だけど自分の想いを受け止めてくれたことが嬉しかった。
そして、小さな命は確かにその手の中で、
温かく、確かに生きていた。
 自分の想いを受け止めてくれたその夜、美咲は涙を流した
自分の想いを受け止めてくれたその夜、美咲は涙を流した
第2章:少女の異変
冬の足音が近づくころ、コロは目をしっかりと開き、しっぽを振るようになっていた。
美咲が部屋に入るたび、小さな声で鳴きながら駆け寄ってくる。
食事も少しずつ食べるようになり、まだ細いながらも、ぬくもりに満ちた命がそこにはあった。
よかったね、コロ。もう大丈夫だよ!
……ずっと、いっしょにいようね!
美咲の声は明るく、表情も笑顔に満ちていた。
しかし、それはほんの一瞬の“奇跡の時間”だった。
その日、美咲は学校から帰る途中、ふと足を止めた。
いつもの道が、なぜかぼやけて見える。
胸が苦しい。息が、深く吸えない。
それでも、「疲れてるだけ」と自分に言い聞かせて歩き続けた。
夜になり、布団に入ってからも身体が火照っていた。
咳が止まらず、体の節々が痛む。
コロのことが心配で起き上がろうとしても、足に力が入らなかった。
……大丈夫、大丈夫!私が守らなきゃ……
かすれた声でそうつぶやきながら、美咲はその晩、眠りについた。
翌朝、親分は美咲の顔色に異変を感じた。
顔が真っ青じゃねぇか。学校は休め!
……うん。ちょっと風邪、かも?
美咲は小さく笑ったが、その笑顔は力なく、かすれていた。
念のため病院に連れていくと、医師は首をかしげながら、詳しい検査を勧めてきた。
……原因がはっきりしません。少し大きな病院で精密検査を!
なんだと……?
親分の眉間にしわが寄る。
ただの風邪だろ? そうだろ、美咲!
娘に問いかける声は、いつになく弱かった。
美咲は首を横に振らず、ただ静かに親分の手を握った。
ごめんね、パパ。なんか、変なのかも!
それから、病院通いの日々が始まった。
様々な検査が行われたが、病名ははっきりせず、ただひとつだけ確かなのは――
美咲の身体は、少しずつ、確実に弱っていっているということだった。
コロの看病どころか、自分の身体さえも自由にならなくなっていく。
それでも、美咲は決して泣かなかった。
病室のベッドに横たわりながら、親分が持ってきた写真の中のコロを見つめ、微笑みながらこう言った。
あの子、ちゃんと元気でいてくれてる?
ああ。お前が育てたからな。もう立派に歩き回ってるぜ!
嘘だった。
親分は“世話”というものがどういうものかも知らなかった。
だが、あのときからコロは、親分の手で育てられていた。
こっそりではあるが、餌もやり、散歩にも連れ出していた。
犬嫌いだったはずの自分が、今ではコロの寝顔に安心する夜を過ごしている。
まるで、美咲と会話しているかのように。
病室の窓の外では、雪がちらつき始めていた。
パパ、お願いがあるの……
その夜、美咲は親分の手を握り、穏やかな声で言った。
もし……もしも、私がいなくなっても……コロのこと、ちゃんと……守ってね……
バカ言ってんじゃねぇよ……何が“いなくなる”だ。お前は……
声が震えた。言葉の続きが出てこなかった。
うん。でも、ね……もしもの話。
美咲は笑った。
まるで、自分の運命をすべて受け入れているかのように、静かに、優しく。
親分は、強く拳を握った。
わかった。絶対に守る。……必ず、俺が!
それが、美咲がはっきりとした言葉を発した最後の日となった。
その後、彼女の容態は急激に悪化し、意識も遠のいていった。
病室のベッドのそばには、
親分と、静かに写真の中の娘を見つめる小さなコロがいた。
小さな命を拾った少女が、
今度は自分の命を託して、去ろうとしていた。
そしてその想いは、確かにひとりの男の胸に、深く刻まれていった。
 小さな命を拾った少女が・・
小さな命を拾った少女が・・
第3章:別れと約束
その日、空はまるで泣いているようだった。
病室の窓を叩く雨粒が、音もなく流れ落ちていく。
まるで、何かが終わりに向かって静かに進んでいることを、
空さえも感じ取っているかのようだった。
病室の中には、美咲と親分、そして小さなコロだけがいた。
呼吸器の音だけが一定のリズムで響くなか、
美咲の身体は、もうほとんど動かなかった。
それでも、コロがそっと手のひらに触れると、わずかに指先が反応した。
「……コロ……あったかいね」
唇がかすかに動く。
それが、精一杯の命の声だった。
親分はベッドのすぐ横で、美咲の手を握っていた。
その手は細く、骨ばっていて、信じられないくらい軽かった。
おい、美咲。ちゃんと食わねぇと……退院できねぇぞ!
言葉は強がっていたが、その声の奥には、張り裂けそうな想いが隠されていた。
美咲は、ゆっくりとまぶたを開けた。
その瞳は、もうほとんど焦点を結んでいなかったが、
確かに、父の顔を見ようとしていた。
「……パパ……」
「おう……ここにいるぞ……ずっと、ここにいる」
親分の手が、美咲の頬をそっとなでた。
この手で人を殴ってきたこともある。
この手で恐れられてきた。
けれど、いまこの手は、世界で一番優しい父親の手だった。
「……ねえ……パパ……」
「……ああ」
「コロのこと……お願いね」
小さな声だった。
それはもう、娘としてのわがままではなく、
ひとりの人間として、最後の意志だった。
親分はぐっと歯を食いしばり、目をそらした。
言葉にするだけで、何かが壊れてしまいそうだった。
だが、美咲の手が、ほんの少しだけ力をこめた。
親分の指を、弱々しくも、確かに握り返した。
守ってね……この子……私の……命だから……
その一言が、親分の心の奥に深く突き刺さった。
この子は、ただの犬じゃねぇ。
お前の“命”そのものなんだな――そう思った。
親分は、大きく息を吸い込み、うなずいた。
ああ。約束する。俺が、コロを守る。……お前の分まで、絶対に!
美咲の唇が、かすかに笑った。
まるで、それを聞けただけで、もう安心したかのように。
その夜、美咲は眠るように、静かに旅立った。
機械の音が止まり、看護師が静かに駆け寄ってきても、
親分は何も言わず、ただその手を握り続けた。
小さなベッドの上で、ひとりの少女が、永遠の眠りについた。
親分はその横顔を見つめ、
言葉にならない声で、何度も、何度も呟いた。
すまねぇ……ありがとう……お前が俺の娘で……本当によかった……
家に帰ると、玄関先でコロが親分を待っていた。
じっと見つめるその瞳に、親分はしばらく何も言えなかった。
コロを抱き上げると、その小さな体がふるふると震えていた。
「……お前、感じてたんだな」
親分はそう言って、コロを胸に抱きしめた。
この犬は、美咲の命そのもの。
あの子が最後に残してくれた“贈り物”。
これからは、この命とともに生きていく。
そう、胸に深く刻んだ夜だった。
それは、ひとつの別れだった。
だが同時に、ひとつの“約束”が始まった夜でもあった。
鉄のような男が、初めて本気で抱きしめた、小さな命。
それは、美咲の願いであり、
そして、父親としての“償い”の始まりだった。
 鉄のような男が、初めて本気で抱きしめた
鉄のような男が、初めて本気で抱きしめた
第4章:形見と誓い
葬儀の日。
冷たい雨がしとしとと降り続けていた。
傘を差す者もいれば、ただ濡れたまま立ち尽くす者もいた。
だが、その中心で一人、喪服を着た大柄な男は、雨にも気づかぬようにじっと棺を見つめていた。
親分だった。
鬼と恐れられたその男が、
今はただ、ひとりの父親として、娘を見送っていた。
“コロのこと、お願いね”
その言葉が、ずっと耳の奥で繰り返されていた。
白い棺の中には、やせ細った美咲の身体と、
その手のすぐそばに、小さなぬいぐるみと、一枚の写真。
美咲とコロが寄り添って笑っている、唯一のツーショットだった。
数日後、組の者たちが気を遣い、親分にこう声をかけた。
親分……しばらく静養なさっては。お疲れもあるでしょう!
だが親分は首を横に振り、低く答えた。
「……まだ、やることがあんだよ」
親分の部屋には、美咲の遺影と、仏壇の前にちょこんと座るコロの姿があった。
写真の中の美咲をじっと見つめるその子犬に、親分はふと語りかける。
お前、覚えてんのか? あいつの声。ぬくもり……あいつの笑い方。
コロは何も言わない。
けれど、親分の目をまっすぐに見つめ、しっぽを一度だけ小さく振った。
そうか……そうか。お前の中には、まだあいつが生きてるんだな!
親分は、その場にしゃがみこむと、
慣れない手つきでコロの頭を撫でた。
この手で、いつかあの子を抱きしめることができたなら。
そう思った瞬間、胸の奥が締めつけられた。
それからの親分は変わった。
夜の街に顔を出すことも減り、
朝にはコロのために飯を用意し、夜には散歩に出るようになった。
しかし――それは誰にも知られてはならない“秘密”だった。
おい、誰にも言うんじゃねぇぞ。これはあいつとの約束だ!
極道の親分が犬を溺愛してるなどと、子分たちにバレたら一大事。
その威厳も、統率も、地に落ちる。
だからこそ、親分はすべて自分でやった。
散歩は深夜。買い物は変装。
コロを抱いて歩くときは、誰にも見られない裏道だけを選んだ。
だが、そんな日々の中で、親分の表情は少しずつ変わっていった。
“優しさ”と“寂しさ”が、あの強面の中に宿るようになっていた。
ある晩、親分は仏壇の前に正座し、そっとコロを膝に乗せた。
部屋の灯りは、蝋燭の明かりだけ。
静かな空間に、親分の低い声が響く。
美咲。コロはちゃんと育ってる。……お前の分まで、生きてる。
俺はまだ不器用だけどよ、こいつに教わってる気がすんだよ。
人を想うこと……命を預かること……それがどれだけ重いことか、な。
親分は、ふと涙を拭った。
それが娘の前で見せる、初めての涙だった。
だから、もう少しだけ……俺に時間をくれ!
コロが立派に生きてるって、胸張って言えるようになるまで……
蝋燭の炎が、ゆらりと揺れた。
そのとき、コロが小さく鳴いた。
「……そうか。お前も、そう思ってんのか」
親分はふっと笑い、小さく頷いた。
それは、静かなる誓いだった。
喪失の悲しみを抱えながら、
親分はようやく、“生きていく覚悟”を手に入れた。
娘の形見となった、小さな命。
それは今、鉄のような男の胸の中で、確かに生きていた。
 娘の形見となった、小さな命
娘の形見となった、小さな命
第5章:秘密の露見と喪失
その日も、夜明け前の路地をひとり歩く男の姿があった。
ジャージ姿に深めの帽子、背筋はぴんと伸びている。
右手には白い布に包まれた小さな命――コロが大人しく抱かれていた。
極道の親分が犬の散歩に出るなど、誰が信じるだろう。
だが、それが日課になっていた。
このひと月あまり、親分の生活は完全に変わっていた。
夜は早く眠り、朝は犬と共に起きる。
怒号の代わりに、静かな鼻歌が聞こえる日もあった。
だが、それを――“知られてはならなかった”。
ある日、親分がコロと裏道を歩いていると、
後ろから聞き慣れた足音が近づいてきた。
「……親分……?」
振り向いた瞬間、親分の表情が凍りついた。
そこには、子分頭のタカが立っていた。
片手に煙草を持ったまま、目をまるくしている。
そして、その視線は親分ではなく、
親分の腕の中にいる、丸まった子犬に注がれていた。
「それ……犬、ですよね……?」
しばしの沈黙のあと、親分は低く唸るように言った。
「……見たことは忘れろ」
「はいっ!」
子分は深々と頭を下げたが、その顔には驚きと戸惑いが残っていた。
その翌日から、子分たちの間に妙な噂が立ち始める。
「最近の親分、なんか丸くなったよな」
「犬を飼ってるって、ほんとっすか?」
誰かが漏らした小さなひと言が、あっという間に広まっていく。
数日後、親分は呼び止められた。
「親分、散歩……ワシに任せてもらえませんか」
申し出たのは、子分頭のタカだった。
真剣な表情で、頭を下げて言った。
「親分のお身体が気になってますし……この子のこと、大切にしますんで」
一瞬、親分は返事をためらった。
だが、無理を続けていたことは事実だった。
少し気を抜けば、足元もふらつくようになっていた。
「……わかった。ただし、乱暴にしたら……殺すぞ」
「もちろんでございます!」
こうして、コロの世話は子分に託された。
タカは毎朝、きちんと時間を守ってコロを連れ出した。
餌も自前で用意し、歩くときも速度を合わせ、
時折「よしよし」と頭をなでてやるようになっていた。
親分は口に出さなかったが、その姿を見て、どこか安心していた。
だが――
それは、ほんの束の間の“平和”だった。
その日、夕方になってもタカとコロは帰ってこなかった。
珍しいことだった。時間には厳しい男だ。
親分は少し胸騒ぎを覚えながらも、黙って座っていた。
30分、1時間……
やがて、玄関の引き戸が、ゆっくりと開いた。
そこには、肩を落とし、血の気の引いた顔で立つタカの姿。
「……親分……申し訳ありません……っ」
声が震えていた。
その手には、首輪とリードだけが握られていた。
「コロが……車に……急に飛び出して……!」
親分はその場に立ち上がり、何も言わずタカの胸ぐらを掴んだ。
「……何、だと……?」
「っ……ほんの一瞬でした……首輪から抜けて……っ、すぐ病院にも……でも……」
親分の手から、力が抜けていった。
目の前がぼやける。
心臓が、ぎゅうっと締めつけられる。
そして、次の瞬間、怒号ではなく、ただ一言。
「……おまえは悪くねぇ……俺の責任だ……」
タカは崩れ落ち、頭を地面につけて泣きながら謝り続けた。
だが、親分の耳には、もう何も届いていなかった。
その晩、親分はコロの小さな遺体を腕に抱え、
仏壇の前でひとり、朝まで座り続けていた。
何も言わず、何もせず、
ただ、小さくなった“娘の形見”を、胸に抱いたまま。
「……すまねぇ……守れなかった……」
それは、親分にとって、二度目の別れだった。
そして同時に、心にぽっかりと空いた穴が、
またひとつ、大きく広がった瞬間でもあった。
 心にぽっかりと空いた穴が・・
心にぽっかりと空いた穴が・・
第6章:もう一つの命
あれから、親分は変わった。
いや、“元に戻った”のかもしれない。
誰も近寄れない殺気を纏い、無口で、感情を見せない。
それは、コロと過ごす前の――あの頃の親分そのものだった。
朝も夜も、何も言わず、ただ煙草の煙をくゆらせている。
玄関の隅には、空になった犬小屋と、噛み跡のついたボールが寂しげに転がっていた。
「……全部、なくなっちまったな」
親分は、仏壇の前でぽつりと呟いた。
美咲も、コロも、もういない。
手元に残されたのは、思い出だけ。
守ると誓った命を、自らの手で守りきれなかった後悔だけ。
そして親分は、無意識に、あの日の場所へと足を向けていた。
――コロが事故に遭ったあの交差点。
小雨の降る歩道。
信号待ちのあいだ、親分はふと、目を凝らした。
道の向こう側に、小さな影が見えた。
犬だった。
コロよりもほんの少し大きく、
けれど、あの特徴的なクリーム色の毛並み顔立ち――どこか、見覚えがあった。
「……まさか……」
親分が立ち止まると、犬は一瞬こちらを見た。
目が合った。
その瞬間、親分の心がざわりと揺れた。
――似ている。あいつに、あまりにも。
けれどその犬は、しばらく見つめたあと、走り去っていった。
まるで幻だったかのように。
翌日も、親分はその場所に立っていた。
同じ時間、同じ信号。
まるで待ち合わせでもしているかのように。
そして、また現れた。
昨日の犬だった。
今度は、歩道の向こう側で親分を見つめ、しっぽを小さく振った。
呼びかけようとしたが、声が出なかった。
それが三日目、四日目と続いた。
雨の日も、風の日も、必ず同じ場所に、その犬は現れた。
声をかけても、手を差し伸べても、触れることはできなかった。
だが、ただ一つ――その犬は、親分を見ると、毎回しっぽを振った。
「……お前、なんなんだ……あいつの……生まれ変わりか……?」
親分はそう呟きながらも、心のどこかで確信していた。
あれは、偶然なんかじゃない。
あの子が、何かを繋げようとしている――そんな気がしてならなかった。
一週間目の朝。
親分は、ジャケットの中に小さな毛布を入れ、いつもの場所に向かった。
そして、やはりそこにいた。
「……今日は、連れて帰るぞ」
そう静かに言って、親分はしゃがみ込んだ。
犬は、最初こそためらったものの、ゆっくりと歩み寄り、親分の足元に座った。
「……そうか。お前も、待っててくれたんだな」
親分はそっとその子を抱き上げた。
その温もりは――あの時と同じだった。
家に戻ると、親分はまず、仏壇の前に座った。
「美咲、帰ってきたぞ。……いや、違うか。今度は“あいつの兄弟”らしい」
犬は、仏壇の前でおとなしく座り、美咲の遺影をじっと見つめていた。
しばらくして、しっぽを一度だけ、大きく振った。
「……お前、やっぱり“あっち側のやつ”か」
親分は苦笑しながら、頭を撫でた。
それからの日々は、不思議なほど穏やかだった。
犬には名前を付けなかった。
あえて、付けなかった。
「コロじゃねぇ。……けど、似てる。だから今は“おい”で十分だ」
散歩はまた、深夜の裏道を選んだ。
誰にも見られず、誰にも知られず。
けれど、かつてと違ったのは――
親分が、その歩みに、ほんの少し笑顔を見せていたこと。
人は、二度命を救われることがある。
ひとつは、誰かに助けられたとき。
もうひとつは――守るべき存在が、再び心に火を灯してくれたとき。
あの朝、交差点で出会った命は、
親分にとっての“もう一つの贈り物”だった。
 「……今日は、連れて帰るぞ」
「……今日は、連れて帰るぞ」
第7章:再び始まる日々
季節は、春の入口。
街の空気に少しずつ花の匂いが混じり始めた頃だった。
あの日の子犬――いや、“もうひとつの命”は、すっかり親分の生活に馴染んでいた。
相変わらず名前はない。
「おい」「そっち行くな」「こっち来い」が会話のすべて。
だが、言葉がなくても、その心は通じ合っていた。
親分が椅子に座れば、その足元にすっと寄り添い、
コーヒーを入れる間は、じっと待っている。
ときどき、仏壇に向かってしっぽを振るその姿に、
親分は思わず苦笑する。
「……ったく。お前まで“あっち側”か」
ある日、親分はふと思い立って、昼間に散歩へ出ることにした。
深夜の裏道ばかりじゃ、こいつも飽きるだろう。
そう思ったのだ。
帽子を深くかぶり、マスクもして、
なるべく人通りの少ない公園を選んだ。
犬は嬉しそうに歩き回り、時折くるっと振り返って、
「こっちで合ってるか?」とでも言いたげな顔をする。
「……勝手に歩けや。俺はついてくだけだ」
そう言いながらも、親分の足取りは軽かった。
そのときだった。
ベンチの向こう側、桜の若木の下に、一人の少女が座っていた。
10歳くらいだろうか。
ランドセルを脇に置き、何かノートに絵を描いている。
親分はその前を通りすぎようとした。
が、子犬がぴたりと足を止めた。
そして、その少女に向かって――しっぽを振った。
ぴくりと、少女が顔を上げる。
親分と目が合った。
数秒の沈黙。
少女は驚いたように目を丸くし、そっと口を開いた。
「……その子、コロ……に似てる……」
親分の心臓が、どくん、と鳴った。
「……なんで、その名前を知ってる?」
「……昔、飼ってたんです。小さな子犬……でも、ある日、いなくなっちゃって……」
親分は目を細めた。
この子は――まさか、コロの“兄弟”の飼い主だったのか。
いや、違うか。あの子犬は捨てられていた。
けれど、どこかで繋がっているような、不思議な感覚があった。
そして何より――
この少女の雰囲気が、どこか美咲に似ていた。
それからというもの、親分は自然と、同じ時間に同じ公園を訪れるようになった。
少女は絵を描くことが好きで、犬が大好きで、
そして、どこか寂しげな目をしていた。
親分は多くを語らなかったが、少女の前では自然と口数が増えた。
「おじさん、名前ないの?」
「あるわ。言わんだけだ」
「じゃあ、この子は?」
「……まだ、保留中だ」
そんなやりとりをしながら、少しずつ距離が縮まっていく。
子犬も、少女に会うと必ずしっぽを振り、
そのたびに少女は笑って言った。
「やっぱり、コロに似てるなぁ」
親分は、心の中でそっと呟いた。
――それは、美咲が初めてコロを拾ったときのセリフと、まったく同じだった。
季節は巡り、風が暖かさを含むようになった。
少女は、親分に名前を教えてくれた。
「私、“七海(ななみ)”っていいます。……変な名前でしょ?」
「変じゃねぇ。いい名前だ」
親分はそう言って、初めて自分から笑った。
犬はその隣で、満足そうにあくびをしていた。
それは、また始まった新しい日々だった。
喪失から、もう立ち上がれないと思っていたあの日。
けれど、命は繋がり、記憶は受け継がれ、
人と人とが、ふとした出会いのなかで、癒されていく。
それは奇跡ではない。
ただ、誰かが誰かを想った証――
それだけで、世界は少しだけ、優しくなる。
 親分は思わず苦笑する。
親分は思わず苦笑する。
第8章:公園で出会った少女
親分は、変わった。
強面はそのままでも、
公園では犬と戯れる子どもたちをぼんやりと眺め、
七海との会話ではときどき口元を緩ませるようになっていた。
「……人間ってのは、変わるもんだな」
そう、親分自身が最も驚いていた。
だがその変化は、決して“新しい人生”ではなかった。
むしろ、失った命の記憶に導かれて辿り着いた、新たな形の償いだった。
七海との交流は、週に数回、決まった時間に続いていた。
親分は「散歩のついで」と強がりながらも、
実は七海に会う時間を前提に、一日のスケジュールを組むようになっていた。
少女はいつも絵を描いていた。
動物や花、風景。
中でも、犬の絵を描くときだけ、特別に集中していた。
ある日、親分が近づくと、七海がこちらを振り返り、にこっと笑った。
「ねえ、この子、ほんとに不思議な子だよね」
「なんでだ」
「だって……ほら。人の心がわかってるみたいに、動くんだもん」
たしかに、親分もそれを感じていた。
仏壇の前でじっと座ったり、悲しみの夜には寄り添ってきたり、
そして、七海に会うたびに、しっぽを振る。
まるで、この子が自分の代わりに“何か”を感じ取ってくれているような――
そんな気さえしていた。
ある日、七海がぽつりと話し出した。
「おじさんってさ、なんで一人で住んでるの?」
「……一人じゃねぇ。こいつがいる」
「うん、でも……家族とかは?」
親分はしばし黙った。
やがて、仏壇の前で語った言葉を、ぽつりと口にした。
「昔な……娘がいた。……小さくて、明るくて……泣き虫で」
「……そっか……」
七海はうなずいたあと、少し黙ってから言った。
「ねぇ。なんとなくだけど……私、その子に似てるのかなって思ってた」
親分は驚いた。
「なんで、そう思った?」
「わかんない。……でも、この子がね、私を見るといつもしっぽを振るでしょ」
「……ああ」
「それって、“思い出してる”んじゃないかなって」
その言葉に、親分は返す言葉を失った。
たしかに、そうなのかもしれない。
この犬の中には、まだどこかに美咲の面影がある。
そして――この少女にも。
季節は再び巡り、初夏の風が吹くようになった。
親分は最近、疲れやすくなっていた。
歩くのが億劫になり、階段を上るのも息が切れる。
寝起きには胸の奥が痛み、立ち上がるまでに何分もかかるようになっていた。
「……歳かねぇ、俺も」
そう呟きながらも、親分は誰にも言わなかった。
七海にも、もちろん子分たちにも。
自分が病んでいることを知られることが、何よりも怖かったのだ。
ある日、いつもの公園に現れなかった親分のことを、
七海は不思議に思った。
「あれ……今日は来ないのかな?」
しっぽを振っていた犬も、その日は所在なげに公園をぐるぐる歩くだけだった。
次の日も、次の日も――親分は姿を見せなかった。
少女の不安は、日ごとに強くなっていった。
「……ねえ、この子。どこに帰ってるの?」
七海は犬の首輪に添えられた、古びた名札に気づいた。
そこには、小さな文字で――
“松永”という姓と、番地が手書きで書かれていた。
「松永……?」
七海は、放課後の帰り道、その住所を辿ってみることにした。
住宅街の外れ、古い木造の一軒家。
庭には雑草が伸び放題、門は半開きだった。
勇気を出してインターホンを押すが、応答はない。
少し迷ったあと、七海は小さく声をかけた。
「……あの……おじさん?」
静まり返った室内。
ふと玄関がゆっくり開いた。
そこには、痩せ細り、顔色の悪い親分が、
片手に犬のリードを持って立っていた。
「……ああ……お前、来たのか」
「……大丈夫?!」
七海は思わず駆け寄った。
親分は、少し笑った。
「……バレちまったな。……ちょっと、病院に行くのを、サボってただけだ」
「ウソだ。顔、真っ青だもん……!」
犬が心配そうに親分の足元に寄り添った。
そのとき、親分は決めた。
この子は、自分の手を離れるときが来たのだ――と。
その夜、親分は七海に話した。
この子が、美咲という娘の形見であること。
ひとりで命を抱えてきたこと。
そして――
「……お前に、頼みがある」
「……なに?」
親分は、目を伏せた。
「こいつを、お前に預けたい。……俺じゃ、もう……守りきれねぇかもしれねぇ」
七海はしばらく黙っていた。
けれど、やがて強く、まっすぐうなずいた。
「……わたし、大切にする。すっごく、大切にするから」
親分は、ふっと目を閉じた。
「……ありがとう。七海」
それは――再び命を託す、二度目の“贈り物”だった。
 七海に会う時間を前提に・・
七海に会う時間を前提に・・
第9章:最後の願い
雨上がりの朝、風に揺れる木々の音がやけに優しく聞こえた。
七海は、親分の家に通う日々を続けていた。
最初は心配だった。
だが、親分は思ったより元気そうに振る舞い、冗談さえ飛ばしていた。
「心配すんな。まだくたばっちゃいねぇよ」
「でも……顔、やっぱり白いよ」
「……男はな、歳とると白くなるもんだ」
笑ってごまかしていたけれど、七海にはわかっていた。
“その日”が、近づいているということを。
犬もそれを感じていたのか、
最近は親分の布団のそばから離れなくなっていた。
ご飯も控えめに、夜はぴったりと体を寄せて眠る。
親分は頭を撫でながら、ぽつりと呟いた。
「……お前は、ほんとにすげぇな。全部、わかってるんだろ」
その目は、すでに少し遠くを見ていた。
ある日、親分が七海に言った。
「今日は、話したいことがある」
いつもより、ゆっくりとした口調だった。
「俺はな……昔、誰よりも強くなりたかった。怖がられるのが嬉しかった。
でも……何も残らなかった。誰も寄りつかねぇ。
そんなときに、生まれてきたのが美咲だった」
七海は静かにうなずいた。
親分の語る声は、どこか懐かしいメロディのようだった。
「……俺の手は、人を殴るばっかだったけどよ、あいつを抱いたときだけは……震えた。
命ってのは、こんなに小さくて、こんなにあったかいんだって、あのとき初めて思ったんだ」
喉の奥が震え、しばらく言葉が止まる。
「でも……俺は、その命を守りきれなかった」
「……そんなことないよ」
七海が小さく口を挟んだ。
「あなたは、そのあともずっと、美咲ちゃんの命を守ってた。
この子を育てて、想いを繋いで……だから、私にまで届いた」
親分は、驚いたように七海を見つめた。
だがすぐに、ゆっくりと笑った。
「……そっか。そう、かもな」
そして、深く息を吐いたあと、
今にも消えそうな声で、こう言った。
「……七海。お前になら、託せる。俺の……全部を」
七海は何も答えなかった。
ただ、静かにうなずき、そっと親分の手を握った。
それは、言葉のいらない約束だった。
翌朝、七海が訪ねると、親分は布団の中で眠っていた。
顔には、静かな安らぎが浮かんでいた。
枕元には、犬がじっと寄り添っていた。
何も言わず、動かず、ただ目を閉じた親分のそばに、ぴったりと。
七海は、布団のそばに座り、そっと親分の手を取った。
その手は、少しだけ冷たかった。
庭に、小さな花を植えた。
親分が好きだった煙草を一本、横に添えた。
誰も知らない、静かな別れだった。
だがそこには、確かに“生きた証”があった。
犬は、七海の横にちょこんと座り、空を見上げていた。
その表情は、どこか晴れやかで、満ち足りていた。
七海は、そっとその頭を撫でた。
「……贈り物、ありがとう。私、ちゃんと受け取ったよ」
犬は、くるりとしっぽを一度だけ、大きく振った。
それは、ひとりの男の最後の願いだった。
命を守り、想いをつなぎ、そして託す。
ただ、それだけを胸に生き抜いた――静かで、確かな生き様だった。
 「心配すんな。まだくたばっちゃいねぇよ」
「心配すんな。まだくたばっちゃいねぇよ」
第10章:極道の贈り物
それからの日々は、驚くほど静かだった。
七海は、親分の家に残された小さな命――あの子犬を連れ、
毎朝、仏壇に手を合わせた。
「……おじさん、おはよう」
それが彼女の日課となった。
そして、散歩に出るときは、
親分と通った公園、交差点、あの桜の木の下――
思い出が残る場所を、ひとつずつ巡っていった。
犬は、まるで親分の足取りを覚えているかのように、
すっと道を選び、七海を導いていった。
しっぽを振りながら、静かに、誇らしく。
季節はまためぐり、夏の終わり。
蝉の声が遠のき、夕暮れが早くなってきたころ。
七海は、家の中のある引き出しを開けた。
そこには、古びた封筒と、白い布に包まれた首輪が入っていた。
封筒には、たった一言だけ。
「七海へ」
そこに書かれていたのは、たどたどしい文字で綴られた、親分からの手紙だった。
七海へ
お前が、この手紙を読んでるってことは、
俺はもう、こっちにはいねぇってことだな。
だけど、不思議と寂しくはねぇ。
お前がこの子をそばに置いてくれてること、ちゃんとわかってる。
俺は、何も誇れる人生を歩んできちゃいねぇ。
でもな、最後にやっと、
人に何かを“託す”って意味を知った。
命ってのは、握りしめるもんじゃねぇ。
渡すもんだ。繋げるもんだ。
この子は、美咲の形見であり、
俺の心そのものだ。
お前に預けられて、本当によかった。
七海、ありがとう。
この子と一緒に、笑って生きてくれ。
最後の一行は、墨が滲んでいた。
それは、震える手で書いた最後の言葉だったのかもしれない。
七海はその手紙を胸に抱き、涙を拭いた。
「うん……ちゃんと、笑って生きるよ。
この子と一緒に、あなたの分まで」
隣で犬が、小さく鳴いた。
しっぽを振りながら、七海の手をぺろりと舐めた。
まるで、ありがとうと伝えるかのように。
その日、七海は犬に新しい首輪をつけてあげた。
真っ白な布に、美咲のリボンが縫い込まれた手作りの首輪。
そして、ふと笑って言った。
「そろそろ、名前つけなきゃね」
犬は首をかしげた。
七海は、空を見上げて微笑んだ。
「コロ……って名前、今度は私が呼ぶ。
あなたたちの想い、全部まとめて、この子に込めるね」
コロは、まるでそれを理解したように、
大きくしっぽを振って、七海のまわりをぐるぐる回った。
それから数年――
七海は、中学生になった。
コロは少し大きくなり、落ち着いた表情で彼女の隣を歩く。
誰も知らない、でも確かにあった“贈り物”の物語。
それは今も、ひとりの少女と一匹の犬の中で、静かに生き続けている。
命をつないだ男。
想いを託された少女。
そして、すべてを覚えていた一匹の犬。
その出会いが教えてくれたのは――
たとえ不器用でも、
どんな過去があっても、
人は誰かに何かを“残す”ことができるということ。
それが、
この世でたったひとつの――
極道の贈り物。
 七海、ありがとう。
七海、ありがとう。
エピローグ:命は巡る
季節はまた巡り、春の陽射しがやわらかく街を包んでいた。
あの家には、今も小さな仏壇がある。
真ん中には、笑っている親分――松永の遺影。
その両側に、ふたつの小さな首輪が並んでいた。
ひとつは、娘・美咲が拾った子犬「コロ」のもの。
もうひとつは、親分が再び拾い、七海に託した“もう一つの命”のもの。
そのどちらにも、“家族のにおい”が、今も残っている気がした。
七海は、制服の胸元を整えながら、
リードを片手に玄関を出た。
その横には、すっかり成犬になった“コロ”が寄り添っていた。
「行こっか、コロ。おじさんの見てた風景、ちゃんと私も見ておくから」
しっぽをふりながら歩き出す犬。
その足取りは軽く、どこか誇らしげだった。
今日向かうのは、近所の保育園。
週に一度、七海がボランティアで「いのちの授業」をしている場所だった。
きっかけは、ある作文コンクールだった。
「私にとって、“命”とは何か」
――そのテーマに、彼女はこの物語を綴った。
美咲とコロ、親分の約束、そして託された命。
その文章は、多くの人の心を打ち、
やがて地域の子どもたちへ“命のつながり”を語る活動へとつながっていった。
教室に入ると、小さな子どもたちが一斉に駆け寄ってくる。
「コロー!」「今日も来た!」
「お姉ちゃん、話きかせてー!」
七海は笑いながらコロをなで、子どもたちを座らせた。
そして、静かに話し始める。
「ねえ、みんな。“命”ってね、目には見えないけど、ちゃんと繋がってるんだよ」
「この子のおかげで、私は大事な人と出会えたの。
そして、その人から、大切な“贈り物”をもらったの」
子どもたちは、じっと七海を見つめていた。
「その贈り物はね――“やさしさ”と、“思い出”と、そして“未来”だった」
その夜、七海はまた親分の仏壇に手を合わせた。
「……私、ちゃんと生きてるよ」
「あなたの言ってた“命は渡すもんだ”って言葉……やっと意味がわかった気がする」
「コロも、ちゃんと元気。今では、子どもたちの人気者だよ」
ローソクの火が、ゆらりと揺れた。
まるで、「よくやった」と言ってくれているようだった。
命はいつか終わる。
でも、想いは残る。
そして、それを“誰か”に託すことで、また新しい命が生まれる。
血のつながりではない。
形でもない。
ただ“心”が、次の誰かへと手渡されていく。
それがきっと――
“贈り物”という名前の、奇跡。
夜の窓の外、星がまたたいていた。
その光は、遠くで眠る親分の空へ、
そして、笑顔を遺した美咲の空へと、
まっすぐに届いていた。
 「……私、ちゃんと生きてるよ」
「……私、ちゃんと生きてるよ」


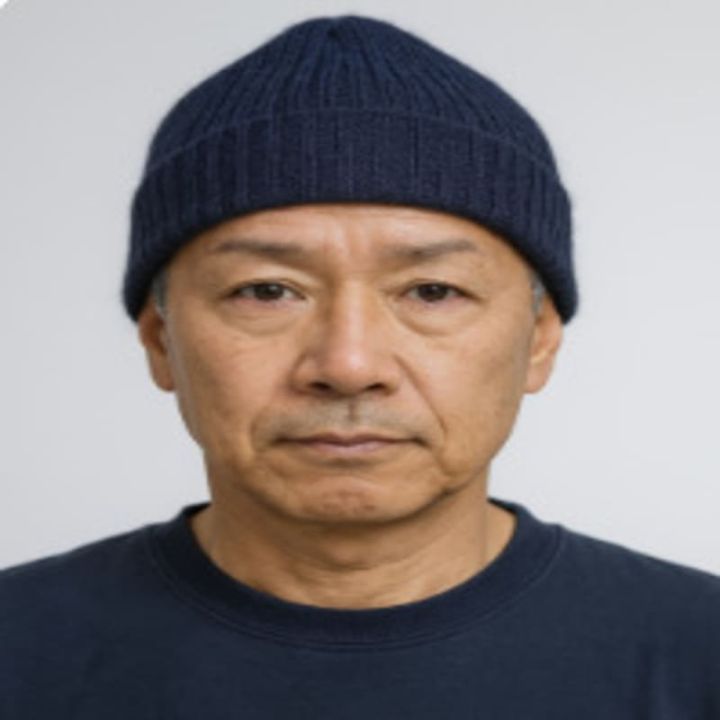



まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。