【総額いくら?】おひとりさまの終活費用、全内訳と賢い節約術
漠然としたお金の不安を「具体的な計画」へ
「おひとりさまの終活には、一体いくらかかるのだろう?」
この問いを胸に情報を集め始めると、多くの方がその数字の幅広さに戸惑い、不安を覚えるのではないでしょうか。ある調査では「平均約503万円」、別の資料では「600万円程」、中には「平均1,400万円」といった驚くような金額も目にします 。
なぜ、これほどまでに金額が錯綜するのでしょうか。その最大の理由は、「終活」という言葉が指し示す範囲が、情報源によって全く異なるからです。高額な試算には、老後の生活費の不足分や介護費用、さらには資産運用や自宅のリフォーム費用まで含まれていることがあります 。一方で、数百万円の試算は、主に亡くなった後の葬儀やお墓、各種手続きといった「死後」にかかる費用に焦点を当てている場合がほとんどです。
特に「おひとりさま」の場合、本来であれば家族が担うべき役割を、専門的なサービスで代替する必要があるため、その費用構造は家族のいる方とは根本的に異なります。頼れる親族がいないからこそ、入院時の身元保証や亡くなった後の事務手続きなどを、専門業者に有料で依頼する必要が出てくるのです。
この記事は、そんな情報の渦の中で途方に暮れているあなたのために、信頼できるデータに基づいた「自分だけの終活費用」を算出するための羅針盤となることを目指します。漠然とした不安を、具体的な計画へと変えていきましょう。
「生きているうち」にかかるお金:おひとりさま特有の5大費用
おひとりさまの終活で最も見えにくく、そして最も大きな不安の種となるのが、「生きているうち」にかかる費用です。特に、家族のサポートを外部サービスに頼らざるを得ない点が、おひとりさま特有の課題と言えます。
医療・介護費:公的保険だけでは足りない「自己負担」のリアル
高齢期の医療費や介護費は誰もが直面する大きな支出です。日本の公的保険制度は手厚く、75歳以上の方の医療費の窓口負担は原則1割または2割です 。さらに、1か月の自己負担額が上限を超えるとその分が払い戻される「高額療養費制度」もあります 。例えば、年収約370万円〜約770万円の方の場合、医療費が100万円かかっても自己負担は約87,430円に抑えられます 。
しかし、問題は公的保険の対象外となる「隙間」の費用です。入院時の差額ベッド代や食事代の一部は自己負担です 。そして最も大きな「見えざる出費」が、介護保険外サービスです。ペットの世話や庭の手入れ、長時間の見守りや話し相手といったサービスは全額自己負担となり、民間の事業者に依頼した場合の料金相場は、1時間あたり3,000円〜5,000円にもなります 。週に数回利用するだけで、月々の負担は数万円に膨れ上がります。介護にかかるトータルコストは、平均で約500万円というデータもあり、おひとりさまの場合は家族の無償のサポートが有料サービスに置き換わる可能性を念頭に置く必要があります 。
身元保証サービス:施設入居や入院に必須の「保証人」を確保する費用
おひとりさまが直面する大きな壁が「身元保証人」の問題です。病院への入院や介護施設への入居の際、ほとんどの施設で身元保証人が求められます。この役割を法人格で引き受けてくれるのが「身元保証サービス」ですが、その利便性の裏には高額な費用が伴います。
料金体系は複雑で、初期費用(1万円〜15万円)、契約金(30万円〜80万円以上)、月額費用(1,000円〜2万円)、そして預託金(20万円〜60万円)などで構成されています 。これらを合計すると、包括的なサービスを利用する場合の総額は100万円〜150万円に達することも一般的です 。これは、おひとりさまの終活において、最も特徴的で高額な支出の一つと言えるでしょう。
死後事務委任契約:自分の「死後の手続き」を託すための費用
身元保証が「生きている間の保証」なら、「死後事務委任契約」は「亡くなった後の手続き」を託す契約です。死亡届の提出、公共料金の解約、希望通りの葬儀の執行などを、生前の意思に基づき確実に実行してもらいます。
費用は依頼内容によって大きく変動し、契約書作成料(5万円〜30万円)、死後事務の報酬(30万円〜100万円以上)、そして葬儀費用などの実費を支払うための預託金(100万円〜200万円)などがかかります 。依頼内容を最低限に絞れば費用を抑えることも可能ですが、生前から死後まで一貫したサポートを求めると、身元保証と合わせて200万円、300万円を超える大きな出費となることを覚悟しておく必要があります 。
生前整理・住まい関連費
持ち物や住まいの整理も終活の一部です。自分で行えば粗大ごみの処分費用程度で済みますが、専門業者に依頼する場合、ワンルーム(1K)なら3万円〜8万円程度、3LDKのような広い家になると20万円〜50万円以上かかることもあります 。持ち家にお住まいの場合、自分が亡くなった後に家が「空き家」になるリスクも考慮し、生前の売却なども選択肢に入れる必要があります 。
遺言書作成・その他
おひとりさまにとって、財産の行先を明確にする遺言書は必須です 。法的な効力を確実にする「公正証書遺言」を専門家(司法書士や弁護士)に依頼した場合の費用は、5万円〜30万円以上が目安です 。また、ペットを飼っている方は、自分の死後にその子のお世話を託すペット信託などを検討する必要があり、1頭あたり100万円以上の費用がかかることもあります 。
「亡くなった後」にかかるお金:葬儀・お墓の賢い選択
「生きているうち」の費用とは対照的に、「亡くなった後」の費用はあなたの価値観や選択次第で大幅にコントロールすることが可能です。
葬儀費用:選択肢でここまで変わる
葬儀費用は、終活の中でも大きな割合を占めますが、その選択肢は驚くほど多様化しています。従来型の一般葬では150万円〜200万円が相場ですが、おひとりさま時代の新しい選択肢として注目されるのが「直葬(火葬式)」です 。これは通夜や告別式を行わず、火葬のみでシンプルにお別れする形式で、費用相場は10万円〜30万円程度と劇的に抑えられます 。近年は「小さなお葬式」や「よりそうお葬式」といった、インターネットで定額プランを提示する葬儀サービスも普及しており、明朗会計で費用を抑えることが可能です 。
お墓・納骨費用:もう「家のお墓」に縛られない
承継者を必要としないおひとりさまは、新しい供養の形を自由に選べます。従来型の一般墓を新しく建てるには120万円〜200万円以上かかりますが 、現代は多様な選択肢があります。
お寺や霊園が永代にわたって供養・管理してくれる「永代供養墓」は、他の方の遺骨と一緒に埋葬される合祀墓であれば5万円〜30万円程度から選べます 。墓石の代わりに樹木をシンボルとする「樹木葬」は30万円〜100万円程度 、屋内の施設に遺骨を安置する「納骨堂」は50万円〜150万円程度が目安です 。最も費用を抑えられる選択肢の一つとして、自治体が運営する「公営合葬墓」もあり、数万円程度で利用できる場合もあります 。
【実践編】終活費用を「準備する」&「削減する」ための全知識
ここまで見てきた費用を、具体的にどう準備し、どう削減するか。その実践的な知識を解説します。
費用の準備方法:貯金、保険、資産活用
将来必ず必要になるお金を確保するには、複数の方法を組み合わせるのが賢明です。計画的な貯蓄が基本ですが、おひとりさまにとって特に有効なのが「少額短期保険(葬儀保険)」です 。月々数千円という手頃な保険料で、亡くなった際に葬儀費用などに充てるための保険金を準備できます 。高齢でも加入しやすく、医師の診査が不要な商品が多いのが特徴です 。また、生命保険の受取人を、死後事務委任契約を結んだ法人などに指定することで、死後の手続き費用に充てることも可能です 。不動産などの資産を元気なうちに売却し、現金化しておくのも一つの方法です 。
費用の削減術:今すぐできる5つの鉄則
高額になりがちな終活費用ですが、いくつかのポイントを押さえることで賢く削減できます。
第一に、50代など心身ともに元気なうちから準備を始めることです 。じっくり情報を比較検討する時間が生まれ、焦って契約して後悔する事態を避けられます。
第二に、専門業者に依頼する際は、必ず複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を徹底することです 。
第三に、国や自治体のサービスを最大限活用することです。多くの市区町村で、エンディングノートの配布や終活の無料相談会が実施されています 。また、低所得の高齢者を対象に、入院や死後事務を支援する取り組みに補助金を出す動きも始まっています 。社会福祉協議会やシルバー人材センターでは、比較的安価(例:1時間1,000円〜数千円)で家事援助などのサービスを提供している場合もあります 。
第四に、自分にとって本当に必要なサービスだけを選ぶことです。「周りがやっているから」という理由で高額な葬儀やお墓を選ぶ必要はありません 。
最後に、全ての役割を一人で抱え込むのではなく、費用のかかる専門的な契約はプロに任せつつ、簡単な手伝いなどは信頼できる友人に頼ることも考えましょう 。
まとめ:不安を「具体的な計画」に変えて、自分らしい未来を
おひとりさまの終活費用は、時に数百万円、あるいはそれ以上の大きな金額となり、その数字だけを見ると圧倒されてしまうかもしれません。しかし、本記事で見てきたように、その費用は決してコントロール不可能なものではありません。
費用の内訳を正しく理解し、自分にとって何が大切かを見極め、合理的な選択を積み重ねていく。そのプロセスこそが、漠然としたお金の不安を、着実に実行可能な「具体的な計画」へと変えていきます。
- ポイント1:費用の全体像を把握する 「生きているうちの費用(医療・介護、身元保証など)」と「亡くなった後の費用(葬儀・お墓など)」に分けて考え、特に高額になりがちな専門サービスの内容と相場を理解しましょう。
- ポイント2:選択肢を知り、自分に合ったものを選ぶ 葬儀やお墓には、直葬や永代供養など、費用を抑えつつ自分らしい形を選べる多様な選択肢があります。伝統に縛られず、合理的な判断をすることが重要です。
- ポイント3:公的サービスと地域の支援を最大限活用する 高額な民間サービスを契約する前に、まずはお住まいの自治体や社会福祉協議会が提供する無料または安価な支援サービスがないか確認しましょう。これが費用削減の最大の鍵です。
- ポイント4:早めに着手し、情報を集める 元気なうちから準備を始めることで、冷静に情報を比較検討し、最適な選択をする時間が生まれます。
何から手をつけていいかわからないという方は、まず市販のエンディングノートを1冊買ってきて、自分の希望を書き出してみることから始めてみませんか 。不安の正体は、多くの場合「知らないこと」です。一つ一つ知識を身につけ、選択をしていくことが、誰にも気兼ねすることなく、自分らしく生き抜くための最も確かな力となるのです。
ソースと関連コンテンツ

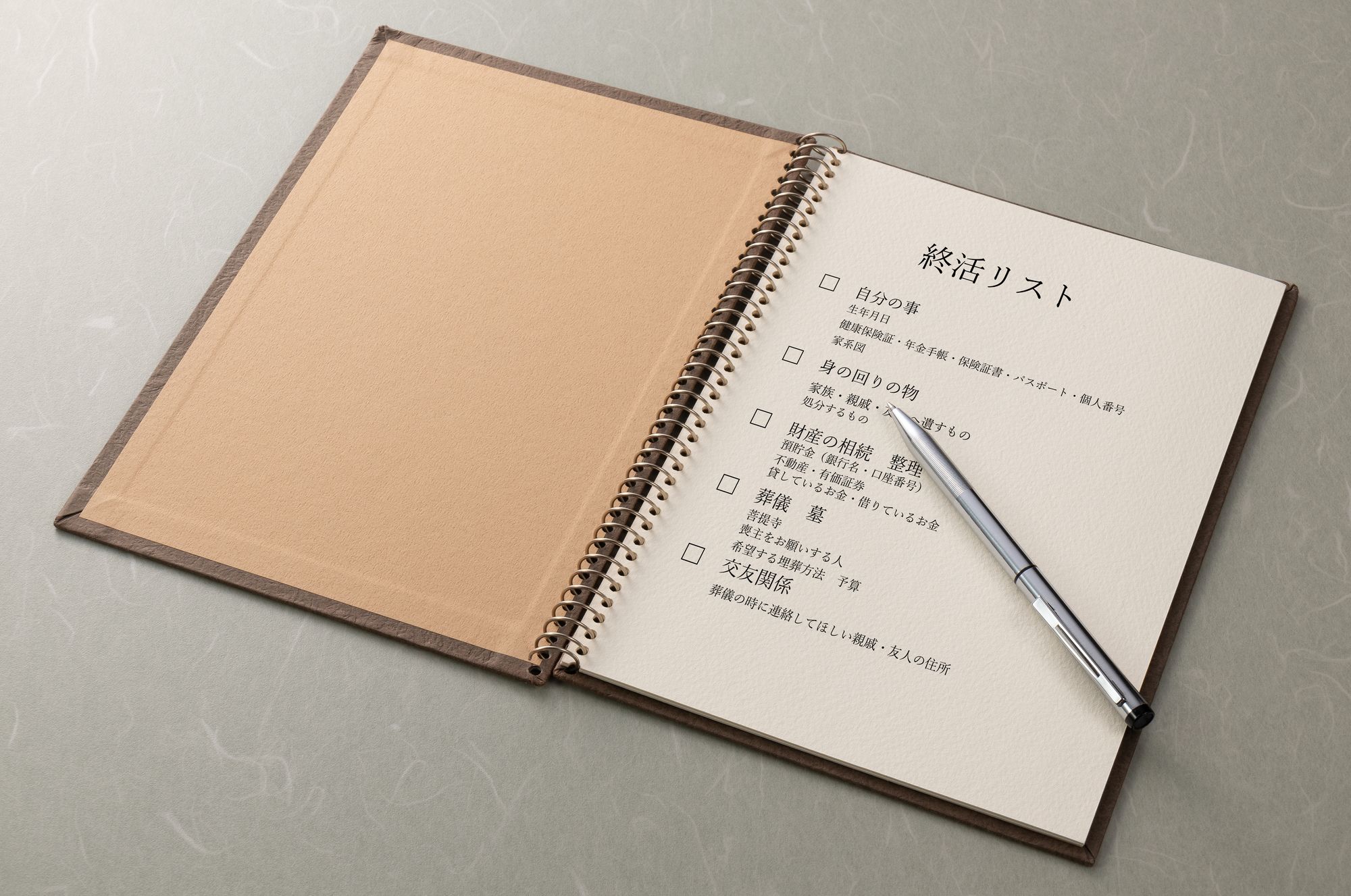

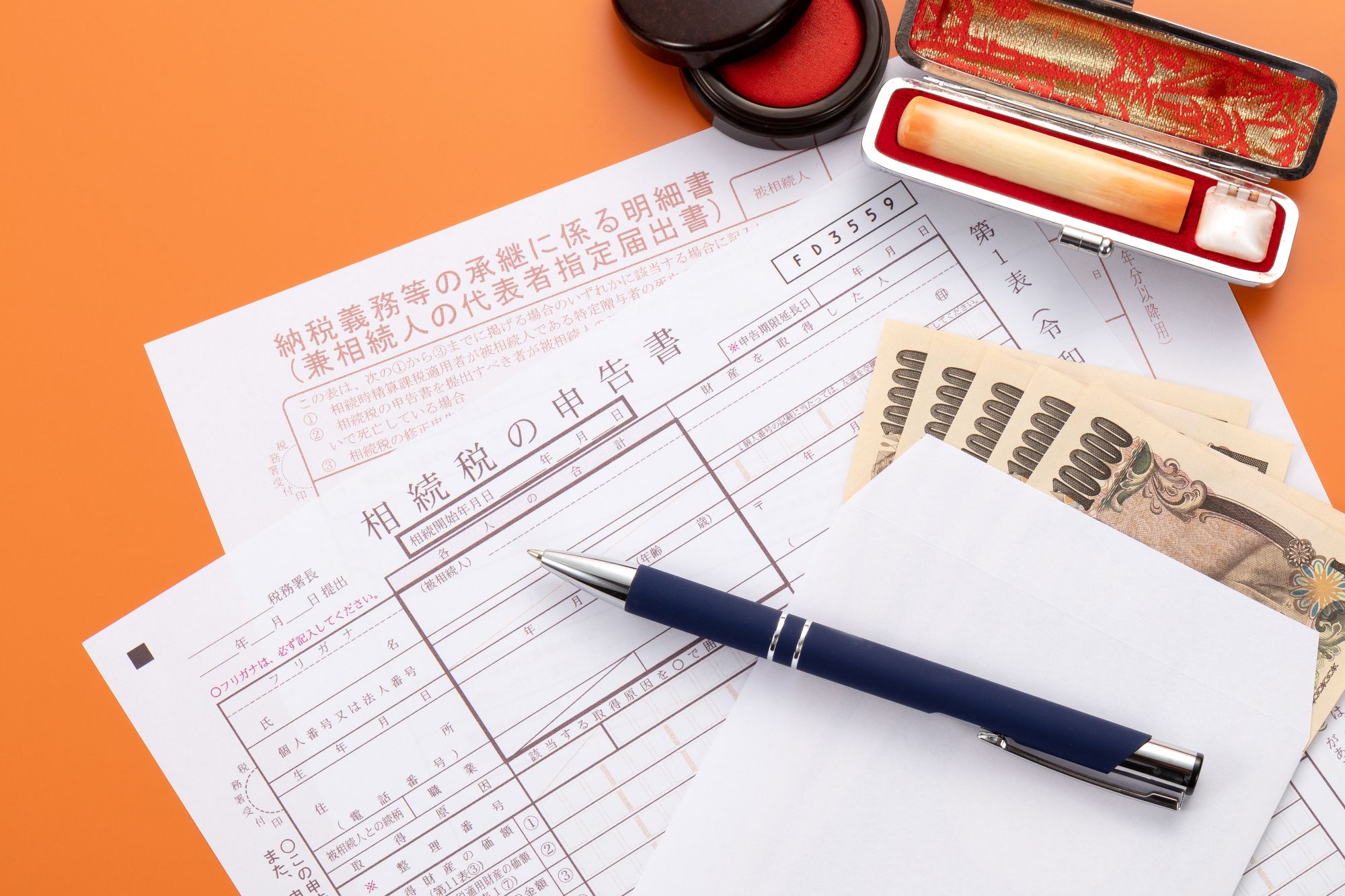


まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。