『コタローとサクラ──涙で結ばれた絆』
プロローグ:涙の始まり
山あいの小さな農場の朝。
静まり返った豚舎の前に、小さな雑種の子犬――コタローが座っていました。
その瞳には、大粒の涙が光っていました。
コタローの視線の先には、空っぽになった柵。
そこにいたはずの、大きな雌豚――サクラの姿はもうありません。
サクラはコタローにとって、ただの友ではありませんでした。
母を知らずに育った小さな命に、ぬくもりを与えてくれた唯一の存在。
寄り添えば、寂しさを忘れられる。
見上げれば、優しい目で応えてくれる。
サクラはコタローの母であり、親友でもあったのです。
けれど、そのサクラは……もう、いない。
農場主の苦渋の決断で、サクラは遠くへ連れて行かれてしまったのです。
「行かないで……置いていかないで……」
そう訴えるように鳴き叫んだあの日の声は、誰の耳にも焼き付いていました。
コタローは食べることをやめ、飲むことをやめ、ただ豚舎の扉の前で待ち続けます。
その小さな体からは、幼い命の喜びが消えかけていました。
動物にも感情があります。
喜びも、悲しみも、そして――涙も。
コタローの流した涙は、
サクラと過ごした日々がどれほど大切であったかを物語っていました。
これは、ひとりの子犬と、一頭の雌豚。
種を超えて結ばれた、深く、そして涙なしには語れない絆の物語です。
 寄り添えば、寂しさを忘れられる
寄り添えば、寂しさを忘れられる
第一章:孤独な子犬
最初にコタローを見つけたのは、霜の降りた早朝だった。
農道の外れ、空き箱の影で丸くなって震えていた。毛並みは土で濡れ、鼻先は冷たく、鳴く声も出ないほど小さかった。
通りかかった農場主は、ためらいもなく上着を脱いで包み込んだ。
「大丈夫だ。うちに来い」
それが、コタローの新しい暮らしの始まりだった。
納屋の隅に古い毛布が敷かれ、ぬるいミルクが小皿に注がれた。
最初、コタローは皿を見つめるだけで動かなかった。嗅いだことのない匂い、聞き慣れない道具の音、遠くで鳴く家畜たち――世界は広すぎて、怖すぎた。
農場主は急かさない。ただ膝を折り、呼吸の音を小さくして待った。
やがてコタローは鼻先をそっと近づけ、一口、また一口と舐め、飲み終える頃には小さな舌で自分の鼻をぺろりと舐めた。
その夜、風は強かった。板壁の隙間を抜ける空気が、毛布の端を揺らす。
コタローは毛布に体を埋めながら、どこかに置いてきたぬくもりを探した。
思い出そうとしても、はっきりした姿は浮かばない。温かい匂い、規則正しい鼓動、寄り添えば眠れた場所――それだけが、胸の奥の暗がりに残っている。
農場主は納屋の戸を閉める前に、そっと言った。
「名前をつけないとな。…コタロー、どうだ」
呼ばれた音に、コタローの耳がぴくりと動いた。
自分を呼ぶ声。世界のどこかに、自分を見つけてくれる人がいる。その事実が、まだ細い体に、かすかな力を灯した。
翌日から、コタローは農場の匂いを覚え始めた。乾いた藁、濡れた土、陽に温められた木の香り。
足元の世界は不安定で、時々空き缶が転がる音に飛び上がったりもしたが、夕暮れになると不思議と心が静まった。
遠くの舎から、低く柔らかな鳴き声が響く。
ふん、ふん――と、誰かが呼吸を整えるたびに、空気が丸くなる。
その音は、コタローの耳に心地よく触れ、胸の早鐘をゆっくりと鎮めていった。
三日目、農場主は小さな木箱を見つけて、毛布を厚く敷き詰めた。
「ここがおまえの場所だ。寒かったら奥へ潜れ」
コタローは鼻先で毛布を押し、体をくるりと丸める。木箱の壁は狭いが、囲まれている安心があった。
目を閉じると、風の音の奥で、またあの柔らかな鳴き声がする。
ふん、ふん――。
コタローは耳をそちらへ傾け、木箱から身をにゅっと伸ばした。匂いを確かめるように空気を吸い込み、足をちょん、と前へ出す。
豚舎の近くは、温かかった。地面に残る日のぬくもり、藁の湿った匂い、そして隔て板の隙間から漏れる、ゆったりした呼吸のリズム。
コタローはその板に体を寄せ、板の向こう側にいる「誰か」を想像した。
見えないのに、近い。知らないのに、懐かしい。
鼻先を板に押しつけると、向こうからもそっと息が返ってきた気がした。
夜が深くなるほど、孤独は鋭くなる。
木箱に戻っても、コタローは何度も身じろぎをした。
それでも、耳に残った呼吸のリズムが、やわらかな子守歌のように彼を包む。
眠りに落ちる直前、コタローは小さく鳴いた。
助けを求める声ではない。ただ、ここにいるよと世界に触れるための、小さな合図。
朝、納屋の戸が開く音で目覚めると、農場主が笑っていた。
「よく寝られたか、コタロー」
コタローは尻尾を一度だけ振った。まだ大きくは振れない。振り方も、喜びの出し方も、これから覚えていくのだろう。
小皿のミルクは昨日より早く空になり、彼は自分でも気づかないほど自然に、納屋の外へと歩き出していた。
豚舎の前で立ち止まる。
板の隙間から差す光が、細く床を切り取っている。
コタローはその線の上に前足を置き、静かに座った。
ふん、ふん――。
また、あの呼吸の音がした。
板の向こう側で、誰かがゆっくりと息をしている。確かに、ここにいる。
孤独は消えてはいない。けれど、形が少し変わった。
触れられないぬくもりの代わりに、寄り添う音がある。
名前を呼ぶ人の声と、壁一枚隔てた呼吸のリズム。
それだけで、世界は昨日より少しだけ、やわらかくなった。
コタローは鼻を上げ、そっと空気を吸い込む。
甘く温い、見知らぬ気配。
彼はまだ、その名を知らない。
やがて出会う――サクラという温もりに。
その予感だけが、朝の光の中で小さく震えていた。
 コタローの新しい暮らしの始まり
コタローの新しい暮らしの始まり
第二章:サクラとの出会い
ある昼下がり、農場主はコタローを抱き上げ、豚舎へと歩いていった。
陽射しはやわらかく、藁の匂いが風に混じって漂っていた。
仔犬のコタローにとって、農場はまだ見知らぬ世界。
目に映るものすべてが大きく、音は騒がしく、匂いは濃厚すぎて、ただただ小さな心を揺さぶった。
豚舎の扉がきしみを立てて開くと、そこには大きな影が横たわっていた。
雌豚のサクラ――農場の誰よりも大きく、ゆったりとした存在感をまとっている。
厚い体毛を持たないその姿は、柔らかい皮膚の下にたっぷりと温もりを抱え、ただ眠っているだけで空間を安心で満たしていた。
農場主は笑みを浮かべながら、コタローを床に降ろした。
「さあ、コタロー。おまえの仲間だよ」
その声に背中を押されるように、コタローは小さな足で一歩を踏み出した。
しかし、その先に横たわるサクラの巨体に圧倒され、足が止まった。
体の何十倍もある大きさ。小さな仔犬にとって、それは恐怖そのものだった。
だが、サクラはゆっくりと目を開けた。
黒く深い瞳が、まっすぐにコタローを見つめる。
そのまなざしは鋭さとは無縁で、湖面に広がる水のように穏やかだった。
ただひとつの眼差しで、「怖がらなくていい」と語りかけるようだった。
コタローは耳を伏せ、鼻をくんくんと動かした。
サクラの吐く息は、温かく湿り気を帯びて、仔犬の毛並みにふんわりと触れた。
その匂いは、藁と大地と母の体温が混ざったような、安心の匂いだった。
一歩。
また一歩。
小さな足が藁をかさりとかすかに鳴らすたび、サクラの耳がぴくりと揺れる。
そして、コタローが鼻先を近づけると、サクラは大きな鼻でそっと応えた。
ぬるりとした温もりが仔犬の額を撫で、コタローの体はびくりと震えたが、次の瞬間には尻尾がふるふると揺れ始めた。
――この大きな体は、怖いものじゃない。
むしろ、ずっと求めていたものなのかもしれない。
そう感じたのだろう。コタローは小さく鳴き声をあげ、そのままサクラの体に身を寄せた。
サクラは驚くこともなく、ただ静かに受け入れた。
大きな体を少しずらし、まるで「ここにおいで」と言わんばかりに空間を作った。
コタローはその柔らかな腹に鼻先を押しつけ、ぎゅっと体を丸めた。
そこには、探し続けていた温もりがあった。
母の鼓動に似た低いリズム。
皮膚越しに伝わる安堵の熱。
孤独に震えていた仔犬の心を、一瞬で包み込む不思議な力があった。
サクラは鼻先でコタローの背を軽く押した。
それはまるで「大丈夫、もうひとりじゃない」と告げるような仕草だった。
コタローは目を細め、尻尾を振りながら小さく鳴いた。
その声は助けを求める声ではなく、安心の中から漏れた「ありがとう」のように聞こえた。
その日から、コタローはサクラのそばを離れなくなった。
昼は大きな影に守られながら眠り、夜はサクラの低い呼吸を子守歌にして眠る。
時にはサクラの背に鼻先を乗せ、時にはその腹にすっぽりと潜り込む。
広い世界はまだ怖いけれど、この温もりがあれば大丈夫だと、幼い心が覚え始めていた。
農場主はその様子を遠くから見つめ、思わず笑みを浮かべた。
「おまえたちは、不思議な家族だな」
その言葉に、サクラは小さく鼻を鳴らし、コタローは尻尾を振った。
ふたりの間には言葉はいらなかった。ただ、確かに心が通い合っていた。
大きな体と小さな体――まるで不釣り合いな組み合わせ。
けれどその差こそが、ふたりの絆を強くした。
孤独だった子犬と、母性を秘めた雌豚。
出会うはずのなかったふたりが出会い、心を寄せ合ったその瞬間から、新しい物語が始まっていた。
それは種を超えた友情であり、母子のような愛情でもあった。
やがて、この絆がどれほど大きな試練に試されるかを、まだ誰も知らなかった。
 母の鼓動に似た低いリズム
母の鼓動に似た低いリズム
第三章:共に過ごす日々
季節の移ろいとともに描かれる、コタローとサクラの生活は、農場の風景そのものをやわらかく塗り替えていった。
出会ったばかりのぎこちなさは、いつの間にか寄り添う呼吸のリズムへと変わり、朝と昼と夜のあいだに、ふたりだけの小さな合図がいくつも生まれていく。
朝、鶏の声とともに納屋の扉が開くと、最初に動くのはコタローだった。
木箱から顔を出し、まだ眠たげな目のまま豚舎へ向かう。
サクラはすでに目を覚ましていて、コタローの足音が近づくと、ゆっくりと耳をふるわせた。
柵越しに鼻先が触れ合い、ふん、ふん――と低く短い息が交わる。
これが“おはよう”の合図。ふたりにしか通じないやり取りだった。
餌の時間になると、コタローは落ち穂や藁くずを追いかけて忙しなく動き回る。
サクラは大きな体を横たえながら、迷子にならないように視線で子犬を追い続けた。
コタローが遠くへ行き過ぎると、サクラはひと声だけ低く鳴く。
すると不思議とコタローは振り返り、尻尾をふって駆け戻ってくる。
呼べば応える――ただそれだけのことが、ふたりの世界の“約束”になっていった。
春。畑の端に名も知らぬ小さな花が咲いた日、コタローはそれを鼻先で転がし、風に乗せては追いかけた。
転んでは立ち、立ってはまた転ぶ。
そのたびにサクラは鼻でコタローの背をそっと押す。
押し戻すのでも、抱え込むのでもない。
ただ「ここにいるよ」と知らせる、やわらかなタッチだった。
母を知らない子犬が、はじめて“安心”という名前の感情を体で覚えたのは、そんなふうにしてだった。
昼下がり、農場主が長靴の泥を落としているころ、コタローはサクラの腹の下にもぐりこみ、日だまりの匂いを吸い込んだ。
皮膚越しの体温は炉のように温かく、低い呼吸は子守歌のように等間隔で繰り返される。
ウトウトとまぶたが落ちてくると、コタローは前足で藁をかいて、自分の輪郭より少し大きいベッドを整える。
そこに丸くなって眠る姿は、見ているこちらまで眠気を誘うほど穏やかだった。
夏が来ると、容赦のない日差しが農場を白く照らした。
コタローは水桶の縁に前足をかけて、ぴょん、と身を投げ出す。
水しぶきが上がると同時に、サクラの影がコタローにかかった。
大きな体が作る影は、動く日傘のようだった。
コタローが疲れて横たわると、サクラは体を少し傾け、風の通り道を作る。
耳をぱたぱたと動かし、うちわのように風を送ってやると、コタローは目を細めて尻尾をふった。
夕方、農場主が見回りに来ると、ふたりの姿に思わず笑ってしまうことがあった。
豚舎の柵のすぐ外、コタローがちょこんと座り、サクラは柵の内側で同じ方向を見ている。
遠くの入道雲、沈みかけの太陽、帰っていくトラクター――見えるものは違っても、見つめる“先”だけは同じだった。
農場主が「まるで親子だな」と呟くと、サクラは低く鼻を鳴らし、コタローは小さく吠えて応えた。
ある夜、雷が近づいた。
空が裂けるような光のあと、大地を揺らす音が遅れてやってくる。
コタローはびくりと身を縮め、木箱へ逃げ込んだが、すぐに踵を返して豚舎へ走った。
サクラのもとへ――。
柵に鼻を押しつけると、向こう側から大きな鼻面がそっと重なる。
ふん、ふん――雷の間を縫うように落ち着いた呼吸が戻ってくる。
コタローはそのリズムに合わせて呼吸を整え、やがて震えが止まった。
嵐の夜の“合図”もまた、ここでひとつ増えた。
初めての小さな試練もあった。
コタローが畑の端で棘を踏んだのだ。
前足を持ち上げ、情けない顔で鳴く。
農場主が駆け寄って棘を抜いてやると、サクラはそっと鼻を近づけ、コタローの足先に温い息をかけた。
痛みはすぐには消えないが、心細さはその場で消えた。
コタローはサクラの腹の下に潜り、片足をかばいながらもしっかりと眠った。
目覚めたとき、彼はまた走れるようになっていて、サクラの前でぎこちない跳ねを繰り返して見せた。
秋、畑が黄金色に変わる頃、ふたりは収穫のあとの畦道を並んで歩いた。
小さな影と大きな影が夕日に長く伸び、風に揺れる稲の音が、さらさらと耳の奥に積もっていく。
サクラが立ち止まると、コタローも立ち止まり、サクラが右を向くと、コタローも右を向く。
まるで鏡のように動作が重なるのが面白くて、農場主はポケットから古い携帯を取り出し、何枚か写真を撮っては照れたように咳払いをした。
夜には、ふたりだけの遊びがあった。
コタローが藁をひと束くわえて、サクラの鼻先の前で落とす。
サクラが鼻でそっと押し返す。
コタローがまた拾って別の場所へ運ぶ。
言葉にできないキャッチボール。
どちらも本気ではなく、どちらも退屈を忘れるのに充分だった。
遊び疲れて眠る前、コタローはサクラの耳の付け根をぺろりと舐める。
サクラは目を閉じ、ほんの少しだけ喉の奥で鳴った。
ありがとう――そんな意味のない言葉が、確かに交わされた気がした。
冬のはじめ、風が鋭くなった。
コタローは木箱の毛布だけでは寒くて、夜半に何度も目を覚ました。
すると、豚舎の扉の近くにサクラの影が寄ってくるのが見える。
柵越しに体を横たえ、隙間からあふれる熱でコタローを温めるのだ。
コタローは柵のこちら側で丸くなり、ふたりの体温が板一枚をはさんでゆっくり混ざり合った。
呼吸と呼吸が同期し、眠りと眠りが重なっていく。
冬の夜を越えるたび、絆は目に見えないところで太くなった。
日課も増えた。
朝は“ふん、ふん”の合図、昼は日陰の共有、夕方は影の散歩、夜は鼻先のキャッチボール。
コタローはそれぞれの時間に自分の居場所を覚え、サクラはその居場所を黙って空けておく。
互いに相手の輪郭を尊重しながら、重なり合う部分を少しずつ広げていった。
どちらかが一方的に与えるのではない。
小さな貸し借りを積み重ねていくうちに、“家族”という形が自然にできあがっていった。
農場主は帳面に売上や飼料の量を書きつけながら、ときどき顔を上げてふたりを眺めた。
数字の行間に、コタローとサクラの穏やかな光景を挟みこむことが、いつしか癖になっていた。
疲れた日ほど、その一枚の景色に救われた。
大きな体と小さな体が、互いの弱さを隠さず寄り添っている――それは、人間がしばし忘れがちな“正しさ”を、静かに思い出させてくれるものだった。
やがて、空の色がまた春に近づく頃、コタローは少しだけ大きくなっていた。
とはいえ、サクラの腹の下に潜りこむ癖は直らない。
サクラのほうも、コタローがそうする前提で体をずらす。
ふたりの間に、言わずもがなの段取りが増えていく。
段取りの数は、そのまま信頼の数だった。
この頃になると、コタローはサクラの目の動きで気持ちが読めるようになっていた。
眠いのか、用心しているのか、退屈しているのか。
サクラはコタローの足音で同じことが分かった。
駆けるときの弾み、迷うときのためらい、戻ってくるときの安心。
互いの“音”を聴き分けられることは、言葉を持たないふたりの、何より確かな会話だった。
コタローにとって、サクラは母親であり、親友であり、世界そのものだった。
サクラにとってコタローは、守る対象であり、日々に張りを与える小さな光だった。
ふたりの輪郭は違っても、重なる中心はひとつ。
そこには名前のないやさしさが、静かにたしかに灯っていた。
そして――季節がもう一度巡る少し手前、農場の空気に、ゆっくりと別の匂いが混じり始めた。
飼料の値段、修理の見積もり、帳面のため息。
コタローもサクラも、まだその意味を知らない。
ただ、夕暮れの影がいつもより長いことだけを、ふたりは同時に感じ取っていた。
温かな日々は続いている。
だが、その温もりがどれほど尊いものかを教える出来事が、遠くの地平線で小さく瞬き始めていた。
 コタローはサクラの腹の下にもぐりこむ
コタローはサクラの腹の下にもぐりこむ
第四章:農場主の苦悩
朝の光は、今日も変わらず農場を照らしていた。
けれど、その光を浴びる農場主の顔には、晴れやかさよりも深い影が漂っていた。
鶏が鳴き、風が麦を揺らし、遠くで犬の声がする。
一見すれば何の変哲もない農村の朝。だが、胸の奥には静かに沈殿する不安が、じわじわと農場主を締めつけていた。
コタローとサクラは寄り添っていた。
柵越しに並ぶその姿は、まるで母と子のようで、農場主の心を温める宝物のような光景だった。
だが同時に、その光景を見るたびに「この時間を壊したくはない」という願いと、「現実はもう待ってはくれない」という冷酷な声がせめぎ合った。
帳面を開くと、冷たい数字が並んでいた。
飼料代は去年よりさらに高騰し、燃料費や修理代も膨らむ一方。
収穫を出荷しても得られる利益はほんのわずかで、むしろ働けば働くほど減っていくようにさえ感じられる。
農場主は鉛筆を転がし、何度も同じ計算を繰り返す。
答えは変わらない。赤字は確実に膨らみ、未来はじわじわと削られていった。
「これ以上は……持たないかもしれない」
独り言のように漏れた声は、静かな納屋に吸い込まれ、埃をかぶった梁に溶けて消えた。
サクラは立派に育った雌豚だった。
もし市場に出せば、まとまった金になることはわかっている。
農場主も家族も、その価値を知っていた。
だからこそ、何度も「サクラを手放す」という選択肢が頭をよぎる。
だが、そのたびに豚舎の隅で眠る小さな影――コタローの姿が目に浮かんだ。
母を知らずに育った子犬が、サクラの体温に包まれてようやく安心を得ている姿を思い出すと、胸の奥が痛んでならなかった。
サクラとコタローは、ただの動物ではなかった。
互いの孤独を埋め、支え合う、かけがえのない存在だ。
「金になる」という言葉で片付けることなど、到底できなかった。
夜、農場主は囲炉裏の前に座り、黙って火を見つめた。
薪がはぜる音がやけに大きく響く。
火の赤さは温かいのに、胸の奥は冷たいままだった。
「家計を守るためにサクラを売るべきか。それとも……」
答えの出ない問いを、何度も心の中で繰り返す。
「俺が本当に守りたいものは、いったい何なんだろうな……」
声に出すと、かすかに震えていた。
煙が立ちのぼり、言葉は闇の天井へ吸い込まれていく。
翌朝。サクラが柵越しに鼻を鳴らし、コタローが尻尾を振って飛びついた。
その光景は、あまりにも当たり前で、あまりにも美しかった。
無邪気な二匹を前に、農場主の胸はまた締めつけられる。
「こんなに寄り添って生きているのに……」
呟いた声は小さく、しかし痛みを含んでいた。
昼下がり、農場主は畦道に腰を下ろし、遠くで遊ぶ二匹の影を見つめた。
サクラの大きな影とコタローの小さな影が、夕陽に重なり合って長く伸びていく。
その姿はまるで本物の親子のようで、農場主の心を温めながらも、同時に深く苦しめた。
夜になり、布団に入っても眠れなかった。
窓の外、月明かりに照らされた豚舎の屋根が白く光る。
その屋根の下で眠る二匹の姿を思い浮かべながら、農場主は自分に問い続けた。
「守りたいものと、守らなければならないもの……」
目を閉じても、その答えは見つからなかった。
ただひとつ確かなのは、避けられない決断が刻一刻と迫っているということだった。
愛情と責任、その板挟みの中で、農場主は日ごとに削られていった。
こうして農場主の胸には、言葉にならない苦悩が積もっていった。
それはやがて、コタローとサクラの運命を揺さぶる大きな波となり、避けられない未来へと導いていくのだった。
 「これ以上は……持たないかもしれない」
「これ以上は……持たないかもしれない」
第五章:別れの日
朝の空はどこか落ち着かない色をしていた。
薄雲に隠れた太陽は柔らかなはずなのに、光はどこか鈍く、農場主の胸には鉛のような重みを落としていた。
今日――サクラを手放す日が来てしまったのである。
帳面の中で並ぶ赤い数字が、昨夜から何度もまぶたの裏に浮かんでいた。
どれほど計算し直しても、答えは変わらなかった。
飼料の高騰、農機具の修理費、生活費。
農場を守るためには、サクラを売るしか道は残されていない。
農場主は胸の奥で何度も「すまない」と繰り返し、火の消えかけた囲炉裏に向かってひとり小さく頭を垂れた。
思い浮かぶのは、昨日までの温かな光景だった。
大きな体を横たえるサクラに寄り添い、安心しきった顔で眠るコタロー。
小さな鼻先をサクラの体毛にうずめ、耳をぴくぴく動かしながら夢を見ている子犬の姿は、農場主にとって癒しであり誇りでもあった。
その光景を思い出すたび、胸の奥に鋭い痛みが走った。
その朝も、コタローは無邪気だった。
朝露に濡れた草の上を駆け回り、しっぽを千切れるほど振りながらサクラのもとへ駆け寄る。
サクラは低く鼻を鳴らし、柵越しに鼻先を合わせてやる。
ふたりだけの挨拶。
農場主の目には、その一瞬が永遠に続いてほしいと願うほどに美しく映った。
だが、その光景を見守る彼の心は沈んでいた。
「今日で、この景色ともお別れかもしれない……」
そう思った瞬間、視界が揺れて帳面の数字が霞んだ。
男の喉奥に詰まった塊は、簡単に飲み込めるものではなかった。
昼前、遠くから荷馬車の音が近づいてきた。
鉄の車輪が石を弾くガラガラという音に、サクラは敏感に耳を動かす。
コタローも異変を感じ取ったのか、首をかしげ、小さく吠えた。
その声は、かすかに震えていた。
農場主は深く息を吸い込み、荷馬車を引いてきた商人に頭を下げた。
その動作ひとつで胸が焼けつくように痛む。
「本当に……これでいいのか」
心の奥で叫ぶ声は、答えを待たずに風へと溶けていった。
商人が差し出した綱がサクラの首元にかけられる。
サクラは抵抗せず、ただ静かに鼻を鳴らした。
その声は「仕方がない」とも「大丈夫」とも聞こえ、農場主の心をさらに締めつけた。
だが、コタローは違った。
サクラの周りを必死に駆け回り、吠え、飛びつき、足にまとわりついた。
「行かないで! 僕を置いて行かないで!」
声にならぬ声が、確かにそう訴えていた。
サクラが一歩を踏み出すと、コタローも吠えながら追いかけた。
小さな足では追いつけないと分かっていても、止まることなどできなかった。
必死に走り、尻尾を振り、涙でにじんだ瞳でその背中を追い続ける。
やがて荷馬車はゆっくりと遠ざかり、サクラの姿は影となり、やがて霞の中に溶けていった。
その瞬間、コタローの足が止まった。
目から大粒の涙がこぼれ、地面に小さな濡れ跡をいくつもつくった。
喉の奥から絞り出された声は嗚咽となり、空気を震わせては消えていった。
農場主はその光景を目の当たりにし、胸が裂けそうになった。
「すまない……コタロー」
声にならぬ謝罪は唇で震えただけで、誰に届くこともなく、風にさらわれて消えた。
その後、コタローは豚舎の前から動かなかった。
藁の上に体を伏せ、扉の向こうをじっと見つめ続ける。
差し出された餌にも口をつけず、水桶にも近づかない。
ただ、サクラが戻ってくるのを待ち続けるかのように、耳を立て、目を凝らした。
日が傾き、空が茜色に染まる頃も、コタローは動かなかった。
農場主が藁を抱えて戻ると、小さな子犬の体は震えていた。
それでも目は扉を見つめ続けている。
「もう二度と戻らないかもしれない」――その恐怖と悲しみが、小さな体を覆い尽くしていた。
夕暮れの雲は美しいはずだった。
だが農場主の胸に広がったのは、深い暗さだけだった。
茜色の光は涙の膜に滲み、まるで血の色のように見えた。
「この子から、大切な光を奪ってしまったのかもしれない……」
農場主のつぶやきは、夜風にかき消されていった。
その夜、農場は静まり返った。
虫の声も遠く、ただ子犬のかすかなすすり泣きだけが、闇に染み込んでいた。
こうして農場からサクラの姿は消えた。
残されたのは、小さな子犬と、深い孤独だけ。
けれどその孤独の先には、思いがけない奇跡が待っていた。
その奇跡が訪れることを、このときの誰もまだ知らなかった。
 コタローは異変を感じ取った
コタローは異変を感じ取った
第六章:涙の夜
サクラが荷馬車に揺られて去っていったその日の夜、農場は不自然なほどの静けさに包まれていた。
風の音すら遠く、虫の声もまばらで、広い農場全体が深い眠りに落ちているようだった。
しかし、その眠りの外に取り残された小さな影がひとつ――コタローだった。
豚舎の前に座り込んだコタローは、昼間からほとんど動いていない。
いつもなら藁の上を跳ね回り、農場主の足元にまとわりついていた子犬の姿はそこになかった。
ただ、じっと扉を見つめ続けている。
まるでその扉から、もう一度サクラが現れると信じているかのように。
農場主は心配して、ご飯を器に入れてやった。
けれど、コタローは鼻先を少し近づけただけで背を向けた。
喉が渇いていないはずはない。
しかし、彼の小さな体を支配していたのは空腹ではなく、深い喪失感だった。
やがて夜の帳が降り、星が瞬き始める。
それでもコタローは豚舎の前から離れなかった。
冷え込む風が毛並みを逆立てても、目の奥に涙を浮かべながらじっと動かずにいた。
時折、遠くの牛舎から別の牛の鳴き声が聞こえると、そのたびにコタローは耳をぴんと立て、扉の方へ駆け寄った。
「サクラ!」――そう呼びかけるように小さく吠える。
しかし、返ってくるのは冷たい沈黙だけ。
その沈黙が深まるたびに、子犬の胸はきゅうっと縮み、瞳から大粒の雫がこぼれ落ちた。
犬が涙を流すのを見たことがある人は少ないかもしれない。
だがその夜のコタローは、紛れもなく泣いていた。
サクラの匂いがまだ残る豚舎の柵に顔を押しつけ、小さく鳴きながら涙を流す。
その表情には「行かないで」「戻ってきて」という叫びが刻まれていた。
農場主は納屋の影からその姿を見ていた。
胸の奥を鋭い刃で裂かれるような思いだった。
「すまない……コタロー……」
声を出そうとしても、かすれた息しか出なかった。
夜半、雷鳴が遠くで轟いた。
空を裂く稲妻が一瞬農場を白く照らし、その後に大地を揺らす轟音が続く。
コタローはびくりと身を縮め、震える足で必死に立ち上がった。
怖さに耐えきれず木箱へ逃げ込むが、すぐに踵を返し、また豚舎の扉へ走った。
「サクラ……助けて……」
言葉にならない声を必死に重ねる。
扉の隙間に鼻先を押し込み、向こう側に温もりを探した。
だが、そこにはもう誰もいない。
時間が経つごとに、コタローの体力は奪われていった。
足を投げ出すように座り込み、声も出せなくなる。
ただ時折、体を震わせて嗚咽のような息を吐くばかりだった。
やがて瞼が重くなり、眠りに落ちそうになる。
しかし、眠りに落ちることが怖かった。
目を閉じてしまえば、サクラとの日々までもが遠ざかってしまいそうだった。
だから必死に目を開け続け、扉を見つめ続けた。
夢うつつの中で、コタローは何度もサクラの姿を幻のように見た。
夏の日差しを遮ってくれた大きな影。
秋の夕暮れに並んで歩いた長い影。
冬の夜、板一枚を隔てて伝わってきた温もり。
幻が鮮やかであるほど、現実の冷たさが痛烈に突き刺さった。
コタローは小さな前足で地面をかき、声にならない声を吐き出した。
「どうして……いないの?」
その頃、農場主もまた眠れない夜を過ごしていた。
囲炉裏の前で煙草に火をつけるが、ひと口吸うたびに咳がこみ上げる。
胸を満たすのは煙ではなく、後悔と罪悪感だった。
「俺は……あの子から何を奪ったんだ……」
ぶつぶつと呟く声が震え、涙が視界を曇らせた。
大人の男が泣くことなど滅多にない。
だが、コタローの涙を見てしまった以上、心を保つことはできなかった。
夜明け前、東の空が白み始めたころ、コタローは力尽きたように藁の上に倒れ込んだ。
それでも扉から目を逸らさず、最後の力で視線を送り続けた。
まるで「帰ってくるよね」と信じ込むように。
朝日が昇っても、サクラの姿は戻らない。
それでも、コタローの小さな胸の奥には、まだかすかな灯が残っていた。
それは希望という名の灯火。
失われた温もりを求める強い祈りが、消えかけた心を辛うじて支えていた。
こうして「涙の夜」は過ぎていった。
それはただの悲しみの時間ではなかった。
コタローにとって、サクラがどれほど大きな存在だったかを知る夜であり、同時に、その想いが奇跡を呼ぶ夜でもあった。
やがて――この祈りにも似た涙が、信じられない未来を引き寄せることになるのだった。
 農場主は心配して、ご飯を器に入れた
農場主は心配して、ご飯を器に入れた
第7章:農場主の後悔
朝の光が差し込むころ、農場主は重い足取りで納屋へ向かった。
扉を開けた瞬間、彼の目に映ったのは豚舎の前に小さく座り込むコタローの姿だった。
夜を徹して待ち続けたのだろう。瞳は赤く腫れ、毛並みには露が張りついたように濡れた跡が残っていた。
それでも子犬は、動こうとはせず、ただ扉を見つめていた。
農場主の胸は鋭く痛んだ。
サクラを売ることが家計のためだと信じて下した判断。
だが、その結果が、目の前の小さな命をこれほど苦しめている。
「俺は……間違ったのかもしれない」
心の奥底から絞り出すように、農場主は呟いた。
コタローは農場主の気配に気づくと、ゆっくり顔を上げた。
その瞳には怒りも責める色もなかった。
ただ「待っている」という、ひたむきな意思だけが宿っていた。
その純粋さがかえって農場主の心をえぐった。
「お前は……まだ信じてるんだな」
その言葉を飲み込みながら、農場主は視線を逸らすしかなかった。
日常の作業は待ってくれない。
畑の見回り、鶏の世話、飼料の仕入れ。
だがどんな仕事をしても、心の奥に貼りついて離れないのは、豚舎の前でじっと動かないコタローの姿だった。
帳面に数字を書き込むとき、目に浮かぶのはサクラの横で眠るコタロー。
畑を耕す音に重なるのは、夜に聞いた子犬の嗚咽。
現実の仕事に手を動かしても、心は常に「後悔」という影に絡め取られていた。
「家計を守らなければ、この農場は続けられない」
そう自分に言い聞かせてきた。
しかし、コタローの涙を目にして以来、その言葉はもはや力を持たなくなっていた。
家畜を「数」として扱うことで必死に暮らしを維持してきた自分。
だが、コタローとサクラの絆を前にして、その考え方の浅さに気づかされた。
動物はただの生き物ではない。
「心を持ち、愛し、悲しみ、そして涙を流す存在だ」――その当たり前を、農場主は帳面の数字に追われるうちに忘れていた。
夜、囲炉裏の前に座った農場主は、煙の向こうにサクラの姿を思い出していた。
あの日、子豚を産んでからも健気に育ててきた雌豚の姿。
コタローに寄り添い、まるで母親のように守り続けていた姿。
「俺は……あの温もりを金に変えてしまったのか」
苦い煙が喉を刺し、目尻から涙がにじんだ。
その夜もコタローは豚舎の前に身を丸めて眠らなかった。
扉が開くことを信じ、ひたすらに待ち続けている。
農場主は納屋の影からその背中を見つめ、胸の奥が締めつけられた。
「すまない……コタロー。お前にこんな思いをさせるつもりじゃなかった」
言葉は夜風にかき消され、届くことはなかった。
しかし、その瞬間、農場主の心に小さな火がともった。
「もう一度、取り戻さなければならない」
それは償いであり、同時に新たな覚悟でもあった。
後悔だけでは何も変わらない。
行動しなければ、この涙は永遠に消えない。
農場主は固く拳を握った。
自分の選択を悔い、何度も迷った末に、ようやく心の中で答えを見出しつつあった。
こうして農場主の胸に宿った後悔は、やがて彼を動かす原動力となっていく。
それは、コタローとサクラを再び結び合わせる「奇跡」の始まりでもあった。
 農場主の胸は鋭く痛んだ
農場主の胸は鋭く痛んだ
第八章:奇跡の再会
サクラが去って三日目の朝、農場主は帳面を閉じ、静かに深呼吸をした。
数字の列は冷たく整っているのに、胸の中だけがざわついて落ち着かない。
コタローは相変わらず豚舎の前から離れず、夜明け前の冷え込みに震えながら、扉の向こうを見つめ続けていた。
「このままでは、あの子の心まで痩せてしまう」――その思いが、ついに背中を押した。
農場主は家の引き出しをひとつずつ開け、ため込んだ小銭や古い封筒を机に並べた。
壊れかけのラジオを質屋に持ち込み、納屋の奥に眠っていた使わない部品をまとめて鉄くず屋に引き取ってもらう。
八百屋の主人には「次の出荷分で返す」と頭を下げ、わずかばかりの前借りを頼んだ。
それでも足りない分は、妻の形見の指輪を布で丁寧に包み、胸ポケットに忍ばせた。
「もしものときは、これも差し出す」――覚悟は決まっていた。
午前、農場主は町外れの市場へ向かった。
サクラを連れ出していった仲買人がよく出入りする場所だ。
土埃の舞う道を歩きながら、胸の中で何度も言葉を練った。
「返してほしい」と頼むだけでは足りない。
なぜ戻してほしいのか、どんな意味があるのか、すべてを伝えなければならないと分かっていた。
市場はいつも通りの喧噪に満ちていた。
荷車の軋む音、値段を叫ぶ声、獣の鳴き声。
その真ん中で、農場主は仲買人を見つけ、深々と頭を下げた。
「サクラを……買い戻したい」
仲買人は少し驚いた顔をしたが、すぐに現実的な表情へ戻った。
「運搬費と手数料がかかる。それに、向こうにも話を通さなきゃならん」
農場主はうなずき、包みを差し出した。
布を開くと、きちんと数えた小銭と札、それから形見の指輪。
仲買人は指輪を見て目を細めた。
「そこまでしてか」
農場主は短く答えた。
「一匹の豚じゃない。あの子は、うちの子犬の“家族”なんだ」
しばらくの沈黙の後、仲買人は息を吐いて肩をすくめた。
「分かった。俺も鬼じゃない。向こうへ話をつける。費用はこっちでなんとかする。指輪はしまっておきなさい」
農場主は思わず頭を下げ続け、額が土に触れた。
背中に、少しだけ重かった空が軽くなるのを感じた。
手続きと連絡に半日を要した。
夕方、仲買人の荷馬車にサクラの姿が戻ることが決まると、農場主は一刻も早く家路についた。
道すがら、どの角を曲がってもコタローの顔が浮かぶ。
「もうすぐだ、もう少しだけ待ってくれ」
そう心の中で繰り返すうち、足取りは知らず速くなっていた。
そのころ農場では、コタローがいつものように扉の前で風の匂いを嗅いでいた。
夕方の風は畑の土と藁の香りを運ぶ。
しかしその日、風はもうひとつの匂いを連れてきた。
懐かしく、胸の奥があたたかくなる匂い。
コタローは顔を上げ、耳をぴんと立てた。
遠くで車輪が石を弾く音がした。
カラララ――。
音が近づくにつれ、コタローの尻尾は勝手に揺れ始める。
足が震え、爪が地面に小さな跡を刻む。
何度も裏切られた耳と鼻が、それでも確信へと近づいていく。
荷馬車が門をくぐった。
夕陽の逆光の中、ゆっくりと大きな影が立ち上がる。
サクラだ。
コタローは弾かれたように走り出した。
小さな体が土の上を飛ぶ。
泣き声とも笑い声ともつかない高い声が、夕暮れの空に跳ねた。
柵にぶつかりそうになりながら止まり、前足をかけて背伸びする。
サクラはその鼻先に自分の鼻を寄せた。
ふん、ふん――。
ふたりだけの“おかえり”の合図が、やさしく重なる。
その瞬間、コタローの目から溢れた涙が、柵の影に落ちた。
農場主は荷台の縄を外しながら、そっとサクラの首を撫でた。
長旅の疲れはあるが、瞳は澄んでいる。
「すまなかった。戻ってきてくれて、ありがとう」
サクラは短く鼻を鳴らし、答えるようにコタローへ顔を向けた。
柵の扉を開けると、コタローは待ちきれずサクラの腹の下へ潜り込んだ。
小さな体をすり寄せ、全身で“ここが自分の場所だ”と確かめる。
サクラは大きな体を少しだけ傾け、いつもの風の通り道を作った。
あの日々と同じ仕草に、農場主は目頭を押さえた。
失ったと思った景色が、音もなく元に戻っていく。
しばらくして、コタローはサクラの耳の付け根をぺろりと舐めた。
涙で濡れた舌先が触れるたび、サクラは目を細めて喉の奥で小さく鳴く。
二匹のまわりだけ、時間がゆっくり流れる。
夕陽は柵の影を長く伸ばし、畑の端までふたりの影を連れていった。
農場主は荷馬車を見送ったあと、豚舎の前に腰を下ろした。
コタローとサクラの様子を眺めながら、静かに誓う。
「数字だけを見て心を見失うのは、もうやめよう」
帳面には売上と支出だけでなく、“守りたい光景”を書き留める欄を作ろう――そんなことまで思いついた。
それは経営の計算にはならないかもしれない。
だが、ここで生きる者たちの心を守るための、小さな羅針盤にはなる。
日が暮れきる前、農場主は桶にぬるま湯を用意し、サクラの体を布で拭った。
コタローは横でじっと見守り、ときどき鼻先で布をつついて手伝う真似をする。
拭き終えると、サクラは満足そうに鼻を鳴らし、コタローは再び腹の下で丸くなった。
その姿は、離れ離れになる前の、あの穏やかな日々とまるで同じだった。
やがて夜が降りてきた。
吹き込む風は少し冷たい。
サクラは体を寄せ、柵の隙間からあふれる熱でコタローを包む。
コタローは安心しきった表情で、ふう、と小さな息をもらした。
その音を聞いた農場主は、胸の底まで温かさが染み込んでいくのを感じた。
「おかえり、サクラ。よかったな、コタロー」
農場主がそう言うと、コタローは顔だけ出して尻尾を振った。
サクラも短く鼻を鳴らす。
言葉は少しも交わされないのに、三つの心は確かに結び直されていた。
その夜、農場主は珍しく深い眠りについた。
耳の奥に残るのは、サクラの落ち着いた呼吸と、コタローの寝息。
ふたりの呼吸が重なり、家全体が静かに整っていくような、そんな音色だった。
翌朝、鶏の声とともに納屋の扉を開けると、最初に動いたのはコタローだった。
いつものようにサクラへ寄り、鼻先を触れ合わせる“おはよう”。
それを見届けた農場主は、誰にともなく微笑んだ。
「これが、守りたかった朝だ」
涙と歓喜の再会は、奇跡と呼ぶには静かすぎた。
だが、静けさの中に確かな力があった。
失われかけた絆が戻るとき、世界は大きな音を立てない。
ただ、ふたりの呼吸が重なり、ひとつの生活が再び動き始めるだけだ。
その確かさこそが、奇跡の正体だった。
こうしてサクラは農場に戻り、コタローはふたたび笑顔を取り戻した。
数字よりも大切なものを選んだ農場主の決断は、三つの命をもう一度同じ光の下へ集めた。
これからの毎日は、以前よりも少し静かで、少し強い。
そして――その静かな強さは、次の章で新しい“約束”へと育っていく。
 コタローは弾かれたように走り出した
コタローは弾かれたように走り出した
第九章:二度と離れない
サクラが再び農場に戻ってきたあの日から、コタローの世界は色を取り戻した。
けれど、それは単なる「日常の回復」ではなかった。
失った恐怖を知った子犬は、以前よりもさらに強く、サクラに心を縛りつけられるように寄り添った。
まるで「少しでも離れれば、また連れて行かれてしまう」と本能で悟っているかのように。
朝が来るたび、コタローは真っ先に豚舎へ駆けていった。
サクラの姿を見つけると、尻尾を激しく振りながら、鼻先を押し当てる。
その仕草には「おはよう」だけではなく、「まだここにいてくれてありがとう」という思いが詰まっていた。
サクラは低く穏やかな鼻音を返し、コタローの頭を鼻面でそっと撫でる。
その一瞬のやり取りだけで、コタローの小さな胸は安堵で満たされた。
日中も、コタローは片時もサクラのそばを離れなかった。
畑の隅で風に舞う枯れ葉を追いかけるときも、豚舎の中でサクラが藁に体を沈めるときも、必ずそのすぐそばにいた。
ときにはサクラの大きな腹の下に潜り込み、そこから外の景色を覗いては尻尾を揺らす。
サクラはそんな子犬の行動を決して邪魔しなかった。
むしろ、「好きなだけここにいなさい」と言わんばかりに、大きな体を少し傾けて居場所を作ってやった。
農場主は、その姿を何度も目にした。
仕事の合間にふと顔を上げると、必ず視界のどこかで寄り添う二つの影があった。
小さな影と大きな影――。
まるでそれぞれの輪郭が一つに溶け合うように重なり、農場主の胸に静かな温もりを残した。
「もう二度と、こんな光景を壊すわけにはいかない」
そう思うたびに、後悔と決意が新たに胸に刻まれていった。
時には、コタローの執着が強すぎるように見えることもあった。
農場主が柵の扉を開けてサクラを外に出そうとすると、コタローは不安げに鳴き、足元にまとわりついた。
少しでも距離が開くと、尻尾を下げて必死に追いかける。
それは「置いていかないで」という叫びそのものだった。
その切実な姿に、農場主の胸は何度も締めつけられた。
しかしサクラは、そんな子犬を拒まなかった。
餌を食べるときも、水を飲むときも、いつもコタローを傍らに受け入れた。
時に大きな鼻先で毛並みを整えてやり、時にただ静かに寄り添う。
その穏やかな態度は、母親にも似た大きな包容力に満ちていた。
「この子を二度と孤独にさせない」――そんな意志さえ感じられるほどだった。
ある日の夕暮れ。
畑の端で、コタローが小さな影を引き、サクラは大きな影を並べた。
夕陽は二つの影をひとつに重ね、黄金色の稲の波を照らした。
農場主は遠くからその光景を見て、思わず携帯を取り出し、シャッターを切った。
写真には、ただ静かに寄り添う二つの影が写っているだけだった。
だが、その一枚には「失って、取り戻して、それでもまだ一緒にいる」という物語すべてが凝縮されていた。
夜になると、コタローは必ず豚舎の扉の前に丸くなった。
冷たい風が吹いても、板一枚を隔ててサクラの熱を感じることができれば、それで眠れた。
サクラは柵の内側で横たわり、体温を隙間からあふれさせていた。
呼吸と呼吸が重なり、眠りと眠りが重なっていく。
その穏やかなリズムが、ふたりの「二度と離れない」という無言の誓いになっていた。
季節が進み、風の匂いも空の色も変わっていった。
けれど、コタローがサクラのそばを離れないという事実だけは変わらなかった。
それは恐怖から始まった執着だったかもしれない。
だがやがて、それは強固な絆へと形を変えた。
小さな命と大きな命が支え合い、互いの存在そのものを必要としている――その姿は、農場で働く誰の心にも深い感動を残した。
コタローにとって、サクラは母であり友であり、世界そのものだった。
そしてサクラにとっても、コタローは守るべき存在であり、日々を明るくする光だった。
二つの命が重ねた時間は、言葉も約束もいらない。
ただ「共にいる」という事実が、何より確かな証だった。
こうしてふたりは、もう二度と離れることのない日々を、確かに刻み始めていた。
その光景を見守る農場主の胸には、やがて「未来」への小さな祈りが芽生えていた。
 コタローは片時もサクラのそばを離れなかった
コタローは片時もサクラのそばを離れなかった
第十章:新しい仲間
サクラが戻ってきてからの農場には、確かに平穏が戻っていた。
けれど農場主の胸の奥では、まだ小さな不安が燻っていた。
「いつかまた、あの子が一人きりの夜を迎えることがないように」――その思いから、彼は“仲間づくり”を静かに始めた。
最初に用意したのは、匂いからの挨拶だった。
知り合いの牧場から借りたタオルをサクラの身体に軽くこすり、同じように向こうの子犬たちの匂いを移した布を受け取る。
コタローは慎重に鼻を鳴らし、布をつついてはサクラの顔を見上げる。
「大丈夫だよ」と言わんばかりに、サクラは低く短く鼻音を返した。
はじめての顔合わせは、土曜の午後。
隣の田中さんが、耳の大きなミックス犬「ミミ」と、茶色の若犬「ラン」を連れてきた。
コタローは最初、サクラの影に身を隠し、来客を横目でちらちらと観察する。
ミミが一歩近づくたび、コタローは半歩だけ前へ出て、また下がる。
そのたびにサクラが鼻面で背をそっと押し、「あいさつをしてごらん」と背中を支えた。
十分もしないうちに、追いかけっこが始まった。
枯れ葉が風に舞い、ミミが先に葉を捕まえる。
悔しそうに見えたコタローだったが、次の瞬間には尻尾を大きく振っていた。
遊びの輪が広がるほど、コタローの足取りは軽く、地面に刻まれる足跡も弾んでいく。
それでも、休む場所は変わらない。
走り疲れると、コタローは必ずサクラの腹の下へもぐり込み、そこから世界を覗いた。
サクラは体を少し傾け、影を作り、鼻先で背中の土を払ってやる。
「ここが家だ」と全身で教えるように。
翌週から、農場主は“土曜放牧場タイム”を続けた。
時間は十五分から始め、二十分、三十分と少しずつ延ばす。
遊びの後は必ず水と休憩、そして「おしまい」の合図。
決まりが増えるほど、コタローは安心して世界を広げられるようになった。
三回目の集まりには、年上の牧羊犬「玄(げん)」が加わった。
白い眉が凛々しい老犬は、群れの距離感を体で教える達人だった。
玄が静かに横を通り過ぎると、若犬たちは自然と道を空ける。
コタローもその流れを真似し、相手の目を見すぎないこと、匂いの順番を守ることを覚えた。
「うまいぞ」と農場主が声をかけると、サクラが誇らしげに鼻を鳴らした。
雨の日は屋内で合図の練習をした。
「待て」「おいで」「離れて」の三つだけ。
農場主が短く言い、手の形で示す。
サクラは少し離れたところで見守り、合図のたびに喉の奥で低く鳴いて、まるで伴奏のようにリズムをとった。
コタローが成功すると、サクラの方へ一直線。
ごほうびの一口と、母の匂い――それが一番の報酬だった。
ある日、小さな嫉妬が起きた。
ランがサクラに甘えようと近づいた瞬間、コタローが思わず前へ出て低く唸ったのだ。
農場主はすぐにコタローを抱え、「大丈夫だ」と耳元で囁き、距離を置かせた。
サクラは一歩だけ前に出て、短く「ふん」。
その一音で空気がすっとほどけ、ランは尻尾を下げて別の方向へ駆けていった。
コタローはしばらくしてからサクラの腹の下へ戻り、鼻先をくいっと押し付ける。
「ごめん」と「好き」が一度に混ざった仕草だった。
季節はゆっくりと進む。
春先のやわらかな風の日、地域の子どもたちが社会科見学で農場を訪れた。
コタローは最初こそ緊張していたが、玄の後ろにぴたりとついて歩き、落ち着いた挨拶を見せた。
子どもが差し出す小さな掌の匂いを確かめ、ぺろりと舐める。
拍手が起きたとき、コタローは反射的にサクラのもとへ走り、影に潜ってから、もう一度ゆっくり出てきた。
新しい世界は広い。
けれど、その広さを受け止めるための“基地”がちゃんとある――コタローはそれを体で学んでいった。
月に一度、移動診療の獣医がやってくる。
アルコールの匂いに耳を伏せるコタローの首元へ、サクラが鼻先を寄せる。
ぬくい息がかかると、コタローは小さく頷くように顎を引き、注射を受けた。
終わるやいなや、腹の下へ潜って深呼吸。
獣医は笑って言った。
いいチームだね。強い子に育つよ。
農場主は小さく会釈し、胸の内で何度も同じ言葉を繰り返した。
夏の入口には、近隣の農家が集まって小さなピクニックを開いた。
木陰で敷いたシートの上、コタローはミミと走り、ランと転がり、玄の周りを回って遊ぶ。
ときどき、ふっと立ち止まって振り返る。
視線の先には、こちらを見守るサクラの姿。
そのたびにコタローの尻尾が大きく弧を描き、また仲間の輪へと戻っていった。
新しい仲間が増えるにつれ、別れの練習も少しだけした。
放牧場タイムの終わり、ミミやランが帰る前に、農場主はコタローを抱え、サクラから数歩離れる。
十秒、二十秒、三十秒――短い距離と短い時間。
コタローは不安げに鳴くが、合図で戻ると、サクラの影はいつも同じ場所にあった。
「離れても、戻れる」
その経験が、コタローの小さな胸に静かな自信を灯した。
それでも、一番の母はサクラであることに、揺らぎはない。
走り回った日の夕暮れ、コタローは決まってサクラの耳の付け根をぺろりと舐める。
サクラは目を細め、喉の奥で低く鳴く。
そのたった一往復で、一日の出来事がすべて「よかったね」に変わる。
農場主はその仕草が好きだった。
どんな励ましの言葉より、確かにふたりをつないでいるからだ。
こうしてコタローの世界は、サクラを中心に同心円状に広がっていった。
円の外側にはミミやラン、静かな先生の玄、見学に来る子どもたち、巡回の獣医、そして農場主。
円の一番内側には、いつだってサクラの温もりがある。
そこへ戻れる限り、コタローはどこへでも行ける。
戻り方を知っている者は、遠くまで歩けるのだ。
夜、星が冴える。
柵のこちらと向こうで、ふたりの体温が板一枚を隔てて混ざり合う。
コタローの寝息は前よりも深く、サクラの呼吸は前よりもゆっくりだ。
農場主はその音を聞きながら、そっと目を閉じた。
「もう大丈夫だ」
胸の奥で響くその言葉は、数字で測れない豊かさを、はっきりと告げていた。
そして翌朝。
納屋の扉が開くと、いつものようにコタローはサクラのもとへ。
鼻先が触れ合い、ふん、ふん――。
短い合図のあと、コタローはミミを探しに走り、ランを追いかけ、玄に会釈するみたいに尻尾を振った。
世界は広がった。
けれど、帰る場所はひとつだけ。
それがコタローの強さであり、サクラの誇りだった。
 はじめての顔合わせは、土曜の午後
はじめての顔合わせは、土曜の午後
エピローグ:涙で結ばれた絆
農場に再び静かな季節が流れていた。
朝露に濡れた草が陽の光を受けてきらめき、遠くで風車がゆっくりと回っている。
その風景の中に、小さな子犬コタローと、大きな雌豚サクラの姿があった。
コタローは仲間と遊ぶ術を覚え、少しずつ世界を広げていった。
けれど、日が暮れると必ずサクラのもとへ戻り、その影に身を寄せる。
サクラもまた、母であり友であるその子犬を、何も言わずに受け止め続けていた。
農場主は二匹の姿を見つめながら、胸の奥で何度も同じ言葉を反芻した。
動物にも心がある。愛があり、そして涙がある。
その絆は、人間のそれと何ひとつ変わらない――
サクラとコタローが交わした日々は、ただの「動物の習性」ではなかった。
そこには、言葉を超えた信頼があり、孤独を埋め合う温もりがあった。
そして別れの涙を乗り越え、再び巡り合えた奇跡が、彼らをより強く結びつけていた。
農場を歩く人々も、その姿を目にすると自然と微笑みを浮かべ、時には涙をぬぐった。
大きな影と小さな影が並んで伸びていく光景は、誰の心にも「そうだよね」と温かい共感を呼び起こした。
動物も人間も、命あるものすべてが涙を流す。
その涙は悲しみだけでなく、愛と感謝を語るものでもある。
サクラとコタローの絆は、そのことを静かに、しかし力強く教えてくれていた。
そして今日も、農場には穏やかな時間が流れていく。
涙で結ばれた絆は、やさしい風に乗って、未来へと静かに受け継がれていくのだった。
 農場に再び静かな季節が流れていた
農場に再び静かな季節が流れていた


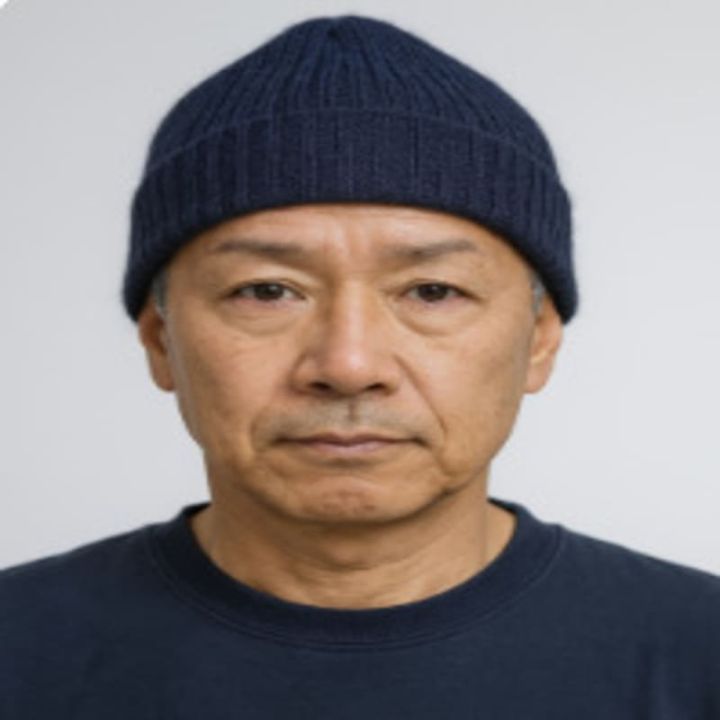



まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。