「評価はしてるよ?」に社員が心を閉ざす理由とは
「ちゃんと評価はしてるよ?」
そう胸を張って言う社長に限って、社員の離職が止まらなかったりする。
皮肉でもなんでもなく、これは中小零細企業でよくある現実だ。
評価制度も作った。
昇給の仕組みも明確にした。
面談だって年に1回はしている。
なのに、社員がどこか冷めている。
むしろ、できる社員ほど辞めていく。
……いったい、何が間違っているんだろう?
それ、伝わってないだけかも?
ちょっと想像してみてほしい。
あなたがプレゼントを渡したとして、相手にこう言われたらどう思う?
「え?それ、いつくれたっけ?」
「いやいや、ちゃんと渡したじゃん!」
って言いたくなるよね。でも、相手の記憶にないなら、渡したことにはなってないのと同じだ。
実は、人事評価もこれとそっくりなんだ。
「ちゃんと評価した」と思ってるのは、評価を“した側”の社長だけ。
“された側”の社員が、「評価された」と感じなければ、それは評価にならない。
これが、評価が空回りする一番の落とし穴。
社長が気づいてない「ズレ」
社長と社員との間にある“温度差”って、けっこう深刻だ。
特に人事評価に関しては、そのズレが大きければ大きいほど、社員の信頼はスッと冷えていく。
たとえばこんな感じ。
- 社長「Aさんは売上も出してるし、頑張ってる。だからちゃんと評価してるよ」
- 社員「売上出しても給料はほとんど変わらないし、上司からも何も言われない…評価されてないんだと思う」
この会話、どこかですれ違ってるの、気づいただろうか?
ポイントは、「伝えたつもり」と「伝わってない現実」。
評価って、“想い”じゃない。
数字でも、制度でもない。
「伝わって、はじめて意味がある」ものなんだ。
よくある“社長の勘違い”3選
では、なぜこのズレが生まれてしまうのか?
僕が実際に現場で見てきた「やりがちだけど効果ゼロ」の例をいくつか紹介しよう。
① 上から目線の「してやってる評価」
評価の場で、ついつい出てしまう“上から目線”。
「ちゃんと評価してあげたんだから感謝しろよ」的な空気、出てないだろうか?
社員は敏感だ。
「いや、評価って恩着せがましく言われるもんじゃないでしょ?」って、心のシャッターをガラガラ閉めてるかもしれない。
② タイミングがバラバラすぎる
評価の言葉をかけるタイミングって、実はめちゃくちゃ重要だ。
たとえば、成果を出した“その時”に「ナイスプレイ!」と声をかけるのと、
半年後に「そういえば、あの時のアレ、よかったよね」と言うのでは、社員の受け取り方がまったく違う。
フィードバックは、鮮度が命。
「あとで言おう」と思っている間に、社員の気持ちは次の目標にいってたり、すでに冷めてたりする。
③ 給料UP=評価だと思ってる
これ、めちゃくちゃ多い誤解。
「評価した=給料を上げた」って思ってる社長、ほんとに多い。
でもね、給料って“結果”であって、“フィードバック”ではないんだ。
社員が求めてるのは「見てくれてる」「認めてくれてる」っていう実感。
これがないと、いくら昇給しても、心は満たされない。
そして、その結果…
「うちの会社、なんか評価されてる気がしないっす」
と、転職サイトを開かれてしまう。
評価って、ただの“ジャッジ”じゃない
そもそも評価って何のためにあるのか?
その本質を見失ってる社長も多い。
評価って、社員を裁くための“ジャッジ”じゃない。
信頼関係を築くための“コミュニケーション”ツールなんだ。
「君の頑張り、ちゃんと見てるよ」
「この部分はすごく良かった。さらにこうなるともっといいね」
こんな一言が、社員にとっては何よりのモチベーションになる。
逆に言えば、そこがない評価はただの「点数つけ」だ。
社員からしたら、それって通知表と同じ。しかも、中身の説明がないタイプのやつ。
じゃあ、どうすれば伝わるのか?
じゃあ、どうすれば「評価してるのに伝わらない」状態を防げるのか?
僕がオススメするのは、この3つ。
1. 評価は“言語化”して伝える
「評価してる」はNGワード。
「何を」「どう頑張って」「どんな成果を出したのか」を言葉で具体的に伝えること。
人は抽象的な言葉には反応しにくい。
「頑張ってたね」よりも「クレーム対応のスピードと丁寧さ、あれはお客様満足度上がったと思うよ」のほうが100倍伝わる。
2. フィードバックの“間隔”を短くする
年1回の評価面談だけじゃ足りない。
もっとフランクに、月1回でも、週1回でもいい。
小さなフィードバックをこまめに挟むだけで、社員の「ちゃんと見てもらってる感」はグンと上がる。
3. 評価と“対話”をセットにする
一方的に評価を伝えるだけでは不十分。
社員の話を聞いて、思ってること、感じてることに耳を傾ける。
「どう感じた?」
「最近どう?やりにくいことない?」
こんな声かけがあるだけで、社員の心の扉は開きやすくなる。
伝わらなければ「ない」のと同じ
せっかく評価してるのに、社員がそれを感じていなければ意味がない。
逆に、伝え方をちょっと変えるだけで、
「評価されてる感」がグッと増して、社員はやる気になるし、辞めにくくもなる。
これは、制度の問題じゃない。
社長自身の“関わり方”の問題だ。
評価って、特別な何かじゃない。
もっと日常的に、カジュアルに、コミュニケーションの一部として使っていくべきもの。
「ちゃんと評価してるのに…」と感じたときこそ、
それが「伝わってるか?」を見直すチャンスだ。
最後に:評価は“愛”の形のひとつ
ちょっとキザな言い方だけど、評価って愛情の表現方法のひとつだと思う。
社員に長く働いてほしいなら、
「評価してるよ?」じゃなくて、
「君のこと、ちゃんと見てるよ」を伝えよう。
見てるだけじゃダメだ。
ちゃんと、伝えよう。届けよう。
その一歩が、会社をもっと良くするはずだから。

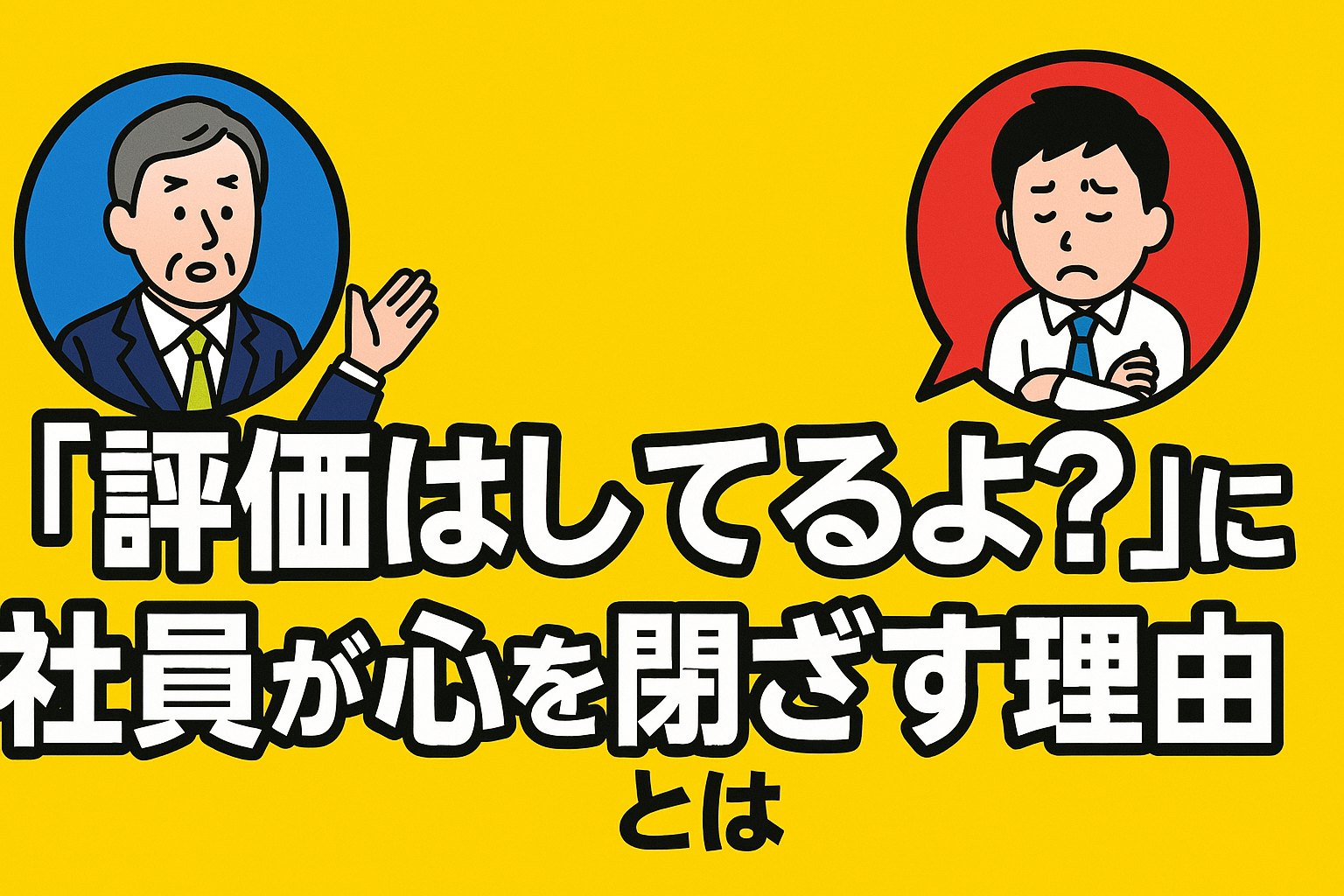

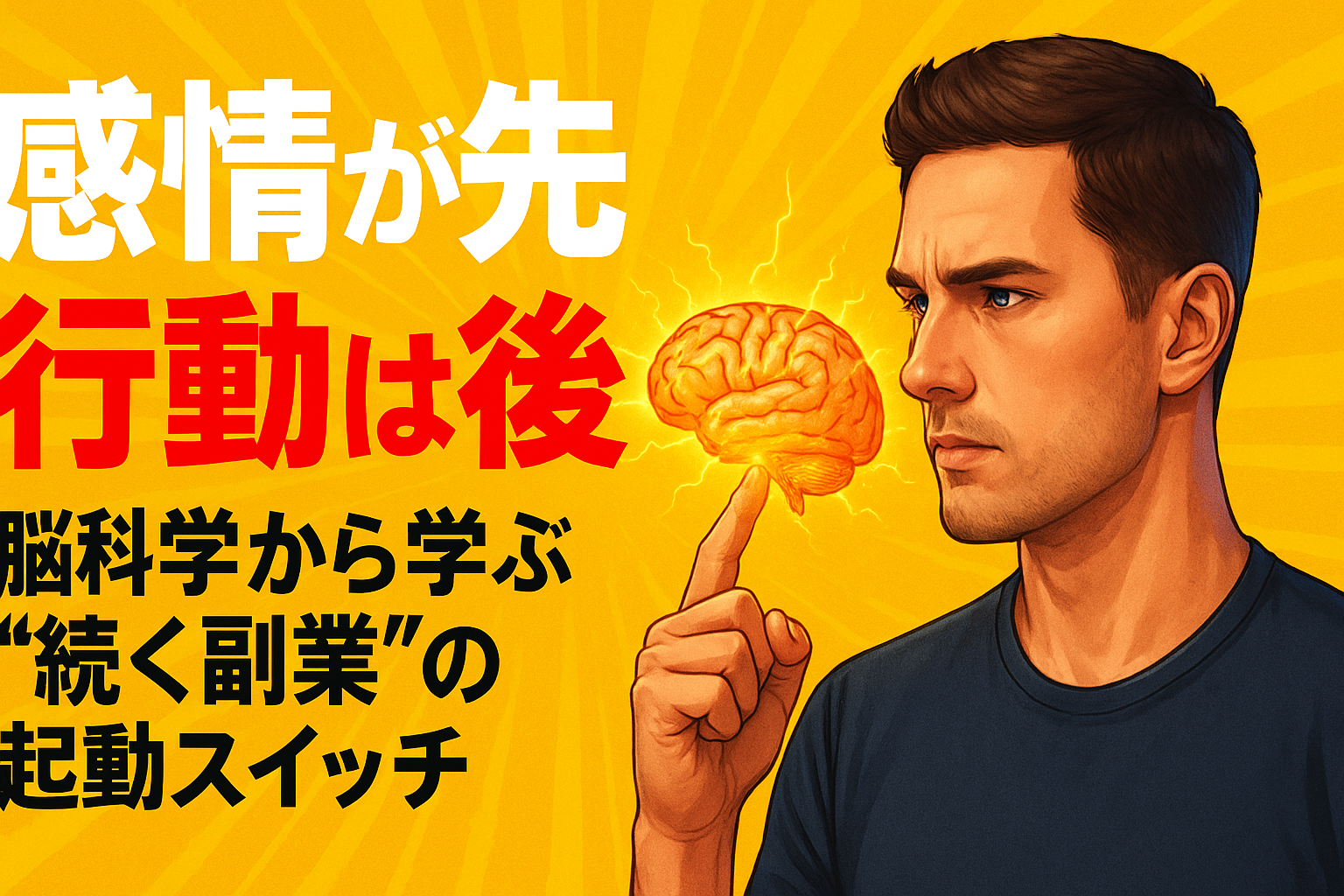
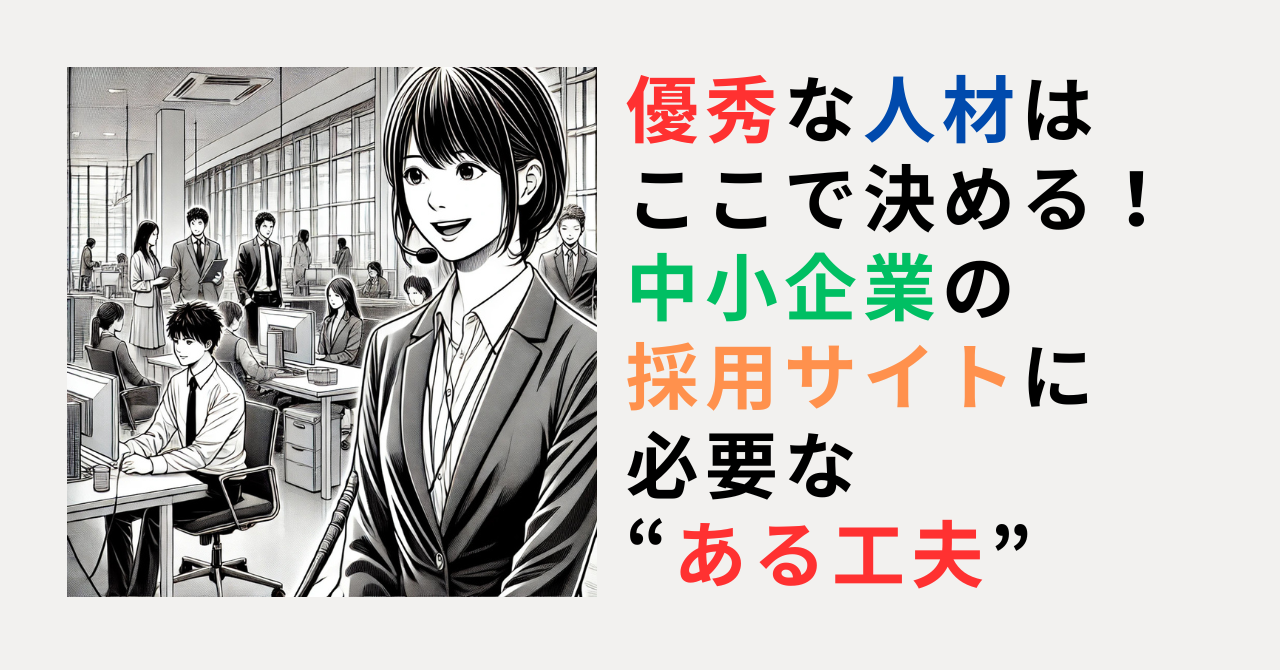

まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。