『僕は違う』という顔でニュースを消費する、その清潔な残酷さについて
ランチタイムのオフィス街は、奇妙なほど平和な喧騒に包まれている。
ガラス張りのカフェの奥、モニターにはまた、どこかの誰かが奪われたニュースが流れている。若い女性が殺されたとか、性被害の告発がどうだとか、そんな、私たちにとっては日常の地続きにある恐怖の映像。
向かいの席でパスタを巻き取っている彼は、私の「先輩」にあたる人だ。
仕事ができて、物腰が柔らかく、部下のミスも声を荒らげずに指摘する。社内でも評判の「良い人」で、おそらく家庭でも良き夫であり、良き父なのだろうと思う。
彼はモニターを一瞥し、眉を少し下げて、こう言った。
「本当にひどいね。男として情けないよ。こういうニュースを見ると、同じ男だと思われるのが恥ずかしくなる」
その声はあまりに滑らかで、あまりに清潔だった。
彼は本心からそう言っている。悲劇を憂い、被害者に同情し、加害者を軽蔑している。その感情に嘘はないのだろう。けれど、その純度100%の「善意」こそが、私の中で冷たく濁った何かを逆流させる。
吐き気がする。
彼が引いた、あまりにも鮮やかな境界線が見えるからだ。「あちら側」の野蛮な男たちと、「こちら側」の理性的な僕。その線を、彼は一切の疑いもなく、当然の権利として引いている。
なぜ、自分が「あちら側」ではないと、そんなに無防備に信じられるのだろう。
統計を見てほしい。
加害者の多くは、額に「犯罪者」と書いて歩いているわけではない。彼らは、昼間はスーツを着て、誰かの同僚として働き、誰かの息子として愛され、誰かのパートナーとして微笑んでいる「普通の人」たちだ。
痴漢の4割、性暴力の多くが、顔見知りや「信頼していた人」によって行われているという事実。それはつまり、私たちの隣でパスタを食べている「善良な市民」の皮を被った誰かが、夜には、あるいは密室では、牙を剥いているということだ。
それなのに、彼はあまりにも無邪気に、自分を「安全地帯」に置いている。
「僕は違うよ」
「僕は君を傷つけないよ」
「僕は理解者だよ」
その暗黙のメッセージは、私たちに対する「信頼の強要」という暴力だ。
私たちは、常に警戒しなければならない。夜道で背後を気にするように、エレベーターで二人きりになるのを避けるように、社会というジャングルの中で、常に「捕食者」の気配に神経を尖らせて生きている。それは個人の性格の問題ではなく、生存戦略としての必然だ。
それなのに、彼はその緊張感を「君の考えすぎだ」と笑う権利を持っていると錯覚している。
自分が「捕食者」の属性を持っていること、その強者の身体性を持っていること、その構造的優位性の上に胡座をかいていることに、あまりにも無自覚だ。
野生動物の群れの中で、たまたま今は腹が満たされている猛獣が、獲物を襲っている別の個体を眺めながら、草食動物に向かって「あいつは野蛮だね、僕はあんなことしないよ」と話しかけている。
そのグロテスクさに、彼は気づかない。
彼がその牙を使わないのは、単に「今はその必要がないから」か、あるいは「リスクとリターンを計算できる知能があるから」に過ぎないかもしれないのに。本能のレベルで、構造のレベルで、彼が私を圧倒できる力を持っている事実は変わらないのに。
「本当に、嫌な世の中ですね」
私は微笑んで、彼の言葉を繰り返す。
この笑顔は、処世術だ。彼を刺激せず、彼の「善良な自尊心」を傷つけず、このランチタイムを平穏に終わらせるための、女性にだけ課せられた感情労働だ。
彼は満足そうに頷き、アイスコーヒーに口をつける。
彼はおそらく、自分が私に「寄り添った」と思っている。私の不安を共有し、正義を示したことで、自分のポイントが加算されたと思っているかもしれない。
その浅ましさが、どうしようもなく虚しい。
彼に必要なのは、安っぽい共感の言葉ではない。
「自分もまた、加害の構造の一部である」という、痛みを伴う自覚だ。
自分が享受している「夜道を怖がらずに歩ける自由」や「性的な視線に晒されずに仕事ができる特権」が、誰かの犠牲の上に成り立っていることへの想像力だ。
けれど、それを彼に求めるのは、あまりにも酷なのだろうか。
彼は「普通」に生きているだけなのだから。この狂った社会が設定した「普通」のレールの上を、疑いもなく歩いているだけなのだから。
だから私は、沈黙する。
言葉を飲み込み、パスタを飲み込む。
言葉にすれば「過激だ」とレッテルを貼られ、「これだから女は」と嘲笑されるのが目に見えているから。
私たちはただ、静かに採点を続けるだけだ。
目の前の彼が、ニュースの中の加害者とどれほど似通っているか。その無自覚な傲慢さが、いかにして歴史的な差別を温存させてきたか。
その罪の深さを、彼は一生知ることはない。
彼はきっと、家に帰れば妻に今日のニュースの話をするのだろう。「ひどい事件があったね」と。そして、自分がいかに家族を大切にしているかを再確認し、健やかな眠りにつくのだろう。
その安眠こそが、私たちが奪われ続けてきたものであるとも知らずに。
外は眩しいほどの晴天で、ビル風が私のスカートを揺らす。
私はまた、見えない鎧を着直して、彼らの作った社会へと戻っていく。
理解されない言葉は、私の喉の奥で、静かに、けれど熱く、黒い澱のように積もっていく。

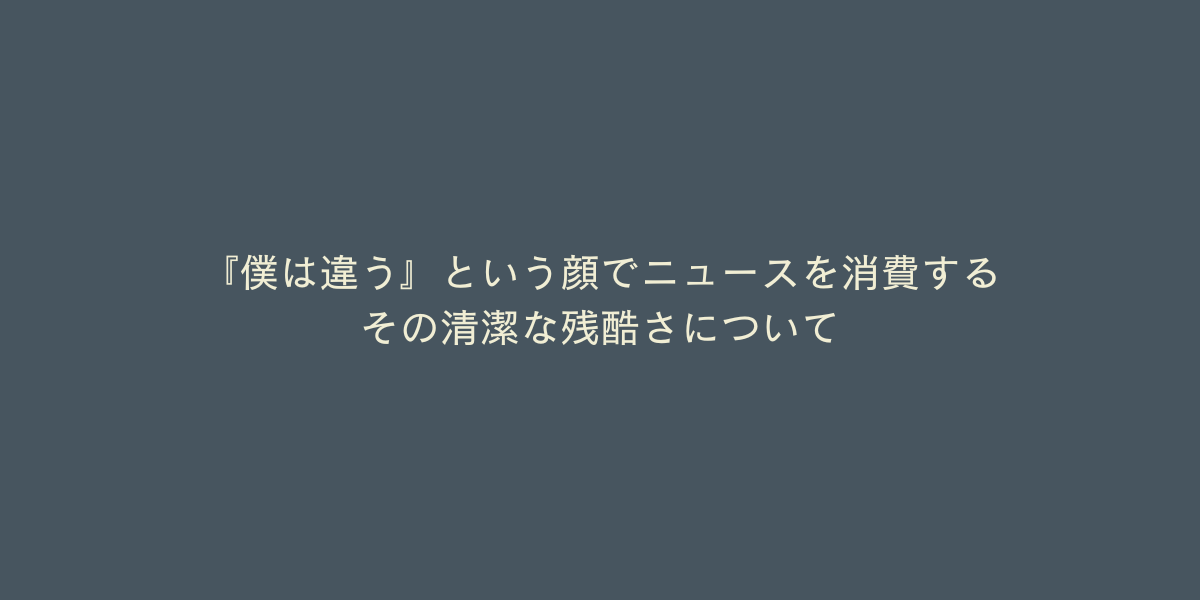

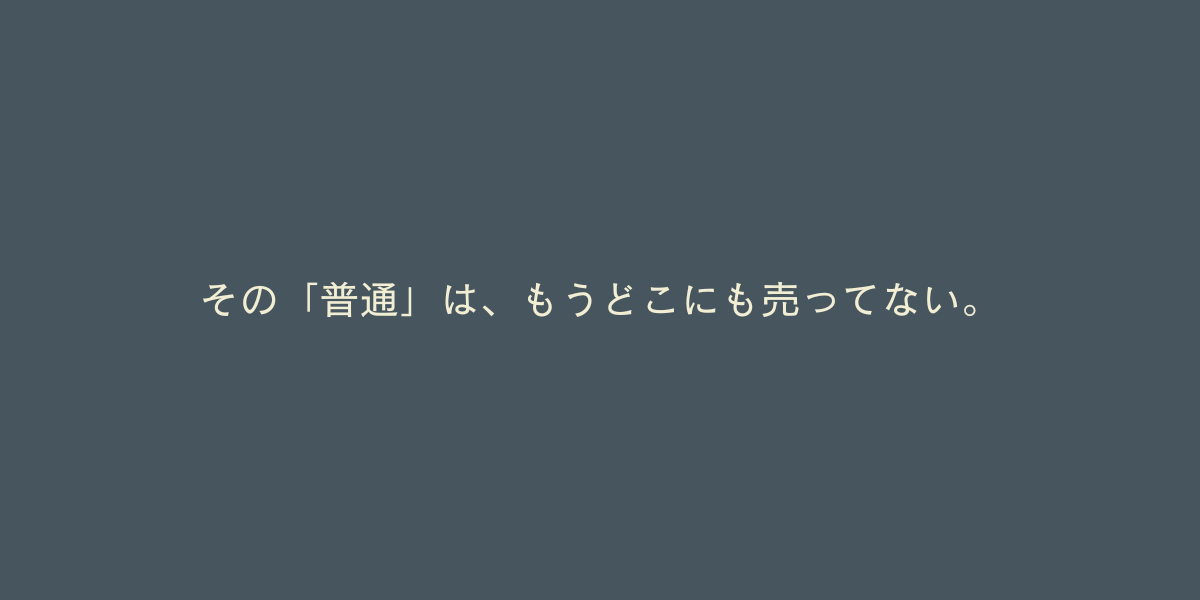
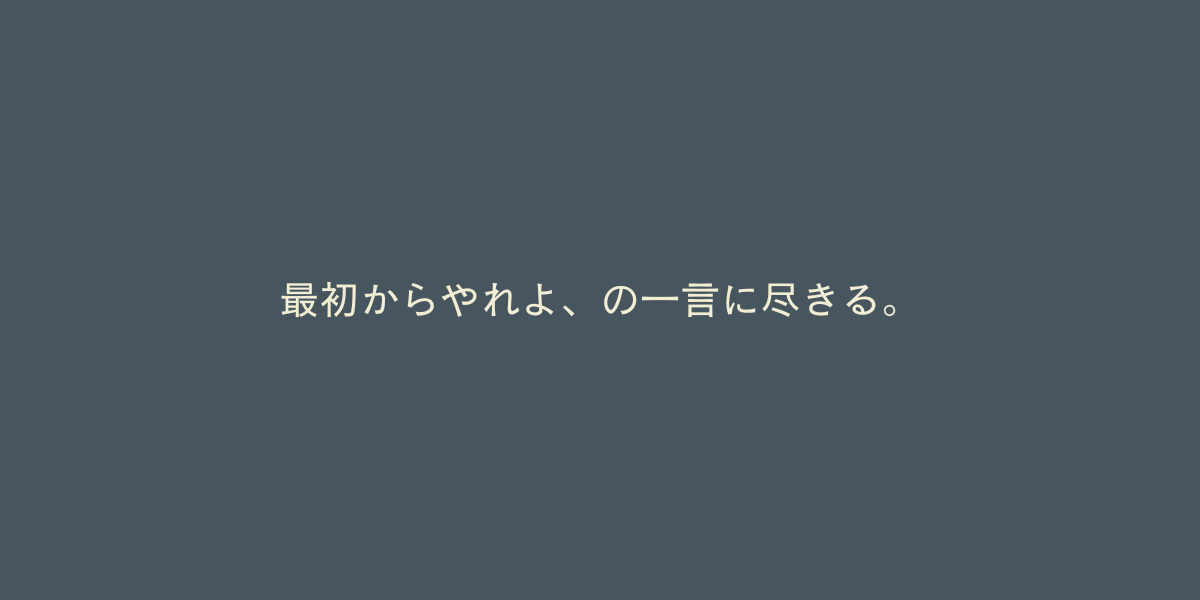
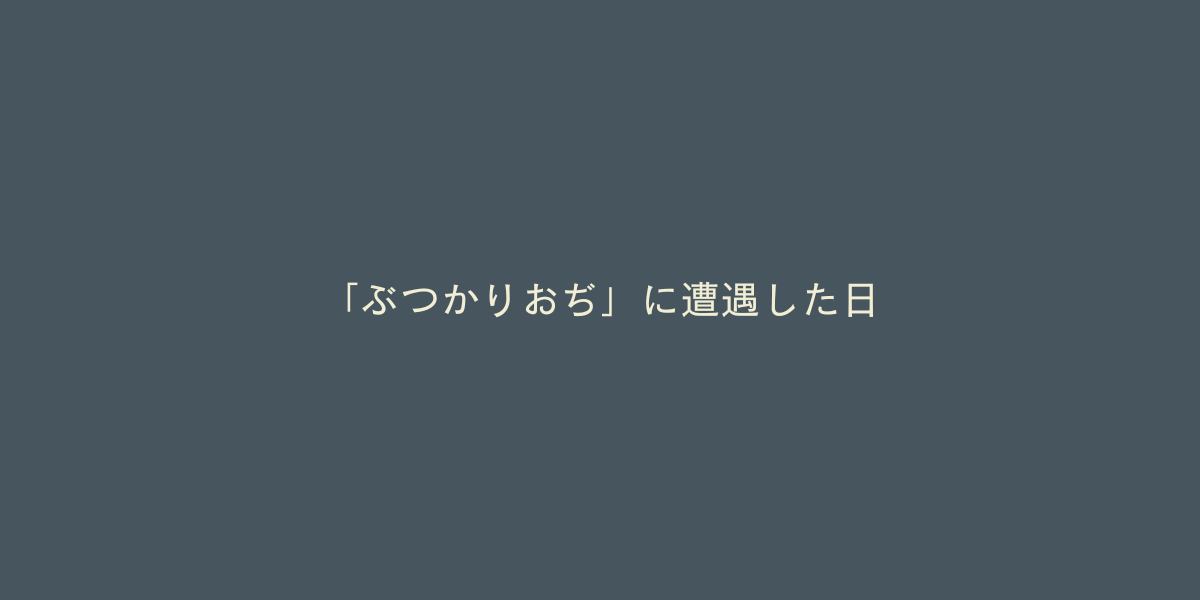
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
コメントを投稿するには、ログインする必要があります。